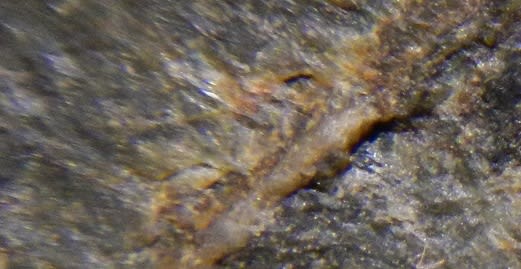削り続けること半年、そろそろ2ミリに達する。
やっと変化が起きました。
グラファイトとカーボンのミルフィーユ層が多結晶に変わりました。
これからは更に硬くなるでしょう。
透明のダイヤモンドになるのは、いつの日か。
腰が曲がるぞー。 . . . 本文を読む
海底火山では大きな山を残すことはないのではないか。
実際、見つかっている海底火山は高さ100メートルほど。
しかし、火口はしっかり残っている。
地図からは想像できないが、非常に切り立った谷間だ。
溶岩は焼き入れをした鉄のように硬い石になる。
地図上bにそんな石があった。
地図上aの落石。
粘板岩に熱水が通ったとみえる。粘板岩は海底にたまった泥、矛盾なし。
原生代のプルームが黒一色なのに対 . . . 本文を読む
石は灰鉄輝石と思う。
石炭紀、モーリー一帯は沼地だった。
シンズークから流れ出した溶岩はモーリーにたどり着き、
沼の泥にポタリポタリと落ち、コケ類を焼き付けて一つの石になった。
絶妙な条件下で珪化した珍しい化石と思います。
Wikiにフズリナの化石の写真がある。オレンジ色の土はP-T境界の火山灰だろうか。
泥に埋まっている所にポタリと落ちても化石化は難しいような。
火山灰に埋まっている所に . . . 本文を読む
水を弾く。見た感じからカーボナードかと思ったが、
固いが、硬さは無く削りやすい。琥珀程度。
黒い琥珀かと、しかし、強磁性体である。更に分けると軟磁性体。
ダイヤモンドの特性に
≪耐食性、ただし溶融した鉄に不可逆的に溶解。≫
1500度なら鉄でなくたって溶けちまうぜ。
解けて混ざるということかな。
≪2004年に炭素同素体でカーボンナノフォームの強磁性体が発表された。室温では数時間後にはその現 . . . 本文を読む
あるいは4億年か、パンゲアが出来つつあった頃、海は次第に浅くなり、
この頃には淡水化していたようだ。藻類の化石と見られる。
ネットで探したが化石では見つからなかった。今の藻類に良く似ている。
石は石英質で硬く、叩くとセラミックのような音がする。
厚さは2センチ、四角い和皿のように平らだ。
両面に藻類が張り付いていることから、雨季と乾季があったのかもしれない。
放散虫が堆積した丘が近くにあった . . . 本文を読む
この石をハイアロクラスタイトとしたのは、
割れ方、鉄を含む、重い、直感など。
しかし、
陸生植物の化石と見える。石炭紀か。
となると、泥岩。
ヒツトリーを海底噴火としたのは、この石。
根拠がなくなってヒツトリーは消滅。
火山活動があったこと、隆起は事実。
海底火山が残るとすれば、どんな地形?
陸生植物はシルル紀から。 . . . 本文を読む
ちょっと一休み。カーボナードです。
黒ダイヤで削ってみました。
産地は極秘。
ここまで結晶が大きいと、多結晶というよりは粗粒。
等倍
結晶の間隔からすると結晶は立体。
ルーペでは正六面体に見えるが八面体か。
硬さは黒ダイヤと同じ。
この石は珍しく裸で転がっていました。
カーボナタイトのような柔らかい火山弾の中に入っていたのかもしれません。
通常は割れやすい輝緑岩や蛇紋岩を割って取り出 . . . 本文を読む
中央右上にスチュワータイトか。
謎は、モーリーの回りに洪水玄武岩の溶岩が飛び散ったと思われる石があるのに
火口が見当たらない。西側に緑色の玄武岩が多いことから、西を見回した。
西へ20Km、シンズーク火口。
シベリアトラップから推測すると小さいが、雰囲気は火口だ。(沼森隕石クレータ)
となると、ヒーノ火口は消滅するしかなさぞうだ。(ヒーノは沼森から分裂した隕石によるクレータ)
2.5億年前 . . . 本文を読む
今日は岩手地学教育研究会の研究発表会から2件。
1)花巻市小舟渡上澤層の年代測定で1.5億年前
写真英海岸の地層の上の部分
ここのことらしい。軽石凝灰岩というそうだ。
1.5億年前と聞いたので、もしやモーリーからの灰かと思ったが類似性はあるかも。
残念ながら採れない。
2)「ちきゅう」による311掘削の成果
当初、跳ね上がりによる津波と報道されていたが、
断層が滑ったことにより大きな . . . 本文を読む
昨夜はどんだけの豆が外に向かって投げられたのだろう。
一夜明け、福を得たのはカラスだった。
カラスが何かをくわえて飛んできて、
草むらに隠して飛び去った。
何だろうと掘り出したら、落花生。
お節介にも、殻を割って置いた。
早く帰ってこないと食われるぞ。
. . . 本文を読む