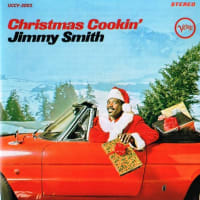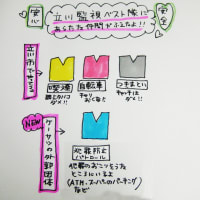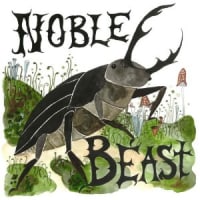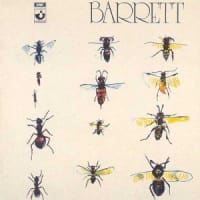今日、うらわ美術館でやってる
「氾濫するイメージ-反芸術以後の印刷メディアと美術1960’s-1970’s」
を思い立って見に行く。浦和、とおい~。
埼玉って、さいたま芸術劇場に何か見に行くときくらいしか
関わりがない。
展覧会の説明:
1960年代の美術界では前衛的な動向が様々に展開し、
70年代に入ると禁欲的で内省的なコンセプチュアル・アートや
もの派などが台頭しました。一方で、雑誌・漫画・広告など
印刷メディアの世界では奔放なビジュアル・イメージが
氾濫していた時代でした。本展の出品作家は
横尾忠則、赤瀬川原平、粟津潔、宇野亜喜良、木村恒久、タイガー立石、
中村宏、つげ義春。
彼らが時代と切り結んだ豊かなイメージのポスターや装丁、挿絵、
そして関連する絵画や版画、オブジェ等約650点を紹介します。
うらわ美術館 2008年11月15日(土)~ 2009年1月25日(日)
なぜだか、うらわ美術館のサイトは、夏にやってたらしい
「ぐりとぐら」の展示から更新されてない。不安だ。
でもちゃんとやってたよ。
閉館一時間前の到着。
・最初の赤瀬川さんスペースの情報量の多さについつい
30分くらいかけてじっくり見てしまう/笑ってしまう/唸ってしまう。
(おかげで他が急ぎ足で見ることになったけど、まあしょうがない)
・木村恒久かっこいい。
この時代のフォトモンタージュってどうやってやってたんだろう?
写真の修正みたいな感じでコツコツやってたのかなぁ…
・中村宏は好きだけど、去年あたりに東京現代美術館でじっくり回顧展をみてたのでさらり。
・つげ義春の展示はほぼマンガが並べてあるだけ。必要あったのかな。
・横尾さんの展示は結構大きめ。とはいえ夏の世田谷美術館で
たっぷり見ていたので、これもさらり。
しかし、うろつき夜太の極細ペン画の美しさは、何度見てもためいき。
あと、週刊アンポにはびっくり。
(しかも週刊と書いてあるのに隔週刊だったらしい)
すごいネーミングだし、関わってたメンツも超豪華。

平日閉館間際というのもあったけど客は自分ひとり。
追い出しアナウンスが鳴っても粘って見てたので
膝掛け毛布部隊に「早く出ろ」と念を送られる。
なんとなくあせって図録も購入。(アンポ写真は図録より)
印刷メディアと特筆してるくらいなので「印刷物」の展示も多かったけど
図録では、蛍光色や特色のものやシルクで刷ってるのなんかは
全然美しさが再現されてないからやはり本物を見れてよかった。
同時開催していた「郵便がつなぐ美術」というのも
すごく興味深かったので、これは、もう一回行くしかないかも。
同フロアのスタジオDで開催していて、こちらは無料。
郵便がつなぐ美術 :
このテーマ展ではコレクションを中心に、郵便に関わる作品約30点を展示します。
マルチプル(複雑芸術作品)として大きな役割を担ったヨーゼフ・ボイスの
ポストカードや、展覧会の招待状であると同時にそれ自体が作品として郵送された
「アート&プロジェクト会報」、世界同時多発的なイヴェントを手紙で促した
塩見允枝子の「スペイシャル・ポエム」のほか、
郵便によるアート・ネットワークをいち早く確立したレイ・ジョンソンや、
イタリアの作家カヴェリーニによる手紙を用いた作品を紹介します。

ちなみに浦和はレッズの本拠地だけあって
サッカーボールの電飾(ロータリーは真っ赤でサッカーボールの飾りつき)、
レッズの店「レッドボルテージ」に掲げられた「速く、激しく、外連味なく」
という分かるような分からないようなスローガン。

駅前で大判焼き(黒ゴマあん)をほおばって浦和をあとにしました。
「氾濫するイメージ-反芸術以後の印刷メディアと美術1960’s-1970’s」
を思い立って見に行く。浦和、とおい~。
埼玉って、さいたま芸術劇場に何か見に行くときくらいしか
関わりがない。
展覧会の説明:
1960年代の美術界では前衛的な動向が様々に展開し、
70年代に入ると禁欲的で内省的なコンセプチュアル・アートや
もの派などが台頭しました。一方で、雑誌・漫画・広告など
印刷メディアの世界では奔放なビジュアル・イメージが
氾濫していた時代でした。本展の出品作家は
横尾忠則、赤瀬川原平、粟津潔、宇野亜喜良、木村恒久、タイガー立石、
中村宏、つげ義春。
彼らが時代と切り結んだ豊かなイメージのポスターや装丁、挿絵、
そして関連する絵画や版画、オブジェ等約650点を紹介します。
うらわ美術館 2008年11月15日(土)~ 2009年1月25日(日)
なぜだか、うらわ美術館のサイトは、夏にやってたらしい
「ぐりとぐら」の展示から更新されてない。不安だ。
でもちゃんとやってたよ。
閉館一時間前の到着。
・最初の赤瀬川さんスペースの情報量の多さについつい
30分くらいかけてじっくり見てしまう/笑ってしまう/唸ってしまう。
(おかげで他が急ぎ足で見ることになったけど、まあしょうがない)
・木村恒久かっこいい。
この時代のフォトモンタージュってどうやってやってたんだろう?
写真の修正みたいな感じでコツコツやってたのかなぁ…
・中村宏は好きだけど、去年あたりに東京現代美術館でじっくり回顧展をみてたのでさらり。
・つげ義春の展示はほぼマンガが並べてあるだけ。必要あったのかな。
・横尾さんの展示は結構大きめ。とはいえ夏の世田谷美術館で
たっぷり見ていたので、これもさらり。
しかし、うろつき夜太の極細ペン画の美しさは、何度見てもためいき。
あと、週刊アンポにはびっくり。
(しかも週刊と書いてあるのに隔週刊だったらしい)
すごいネーミングだし、関わってたメンツも超豪華。

平日閉館間際というのもあったけど客は自分ひとり。
追い出しアナウンスが鳴っても粘って見てたので
膝掛け毛布部隊に「早く出ろ」と念を送られる。
なんとなくあせって図録も購入。(アンポ写真は図録より)
印刷メディアと特筆してるくらいなので「印刷物」の展示も多かったけど
図録では、蛍光色や特色のものやシルクで刷ってるのなんかは
全然美しさが再現されてないからやはり本物を見れてよかった。
同時開催していた「郵便がつなぐ美術」というのも
すごく興味深かったので、これは、もう一回行くしかないかも。
同フロアのスタジオDで開催していて、こちらは無料。
郵便がつなぐ美術 :
このテーマ展ではコレクションを中心に、郵便に関わる作品約30点を展示します。
マルチプル(複雑芸術作品)として大きな役割を担ったヨーゼフ・ボイスの
ポストカードや、展覧会の招待状であると同時にそれ自体が作品として郵送された
「アート&プロジェクト会報」、世界同時多発的なイヴェントを手紙で促した
塩見允枝子の「スペイシャル・ポエム」のほか、
郵便によるアート・ネットワークをいち早く確立したレイ・ジョンソンや、
イタリアの作家カヴェリーニによる手紙を用いた作品を紹介します。

ちなみに浦和はレッズの本拠地だけあって
サッカーボールの電飾(ロータリーは真っ赤でサッカーボールの飾りつき)、
レッズの店「レッドボルテージ」に掲げられた「速く、激しく、外連味なく」
という分かるような分からないようなスローガン。

駅前で大判焼き(黒ゴマあん)をほおばって浦和をあとにしました。