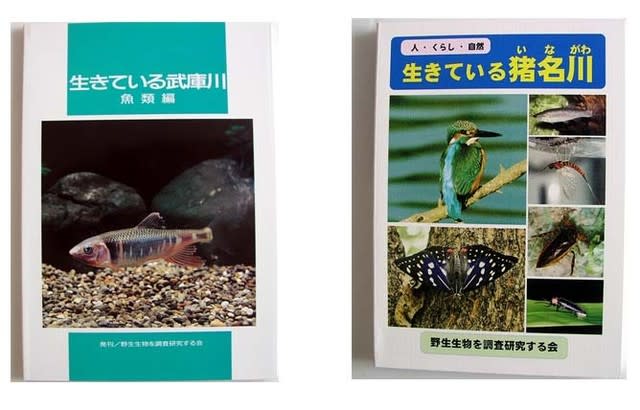国際協力の歴史
2001年
ブラジル、当会の有志がトメアスを訪れる機会を得ました。
破壊の進む熱帯林の現状をみてどうしたら
保全することができるだろうかと考えました。
2003年~2006年
(JICAの草の根支援)環境を守る人材を育てる事業の実施。
「アマゾン自然学校」を実施しました。
日本からエコツアーをおこない、アマゾン自然学校の見学。
我々に活動が少しでも日本の皆さんに理解していただいたはずです
https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry#
2007~2008年
「アマゾン自然学校」の事業終了後、どのようにトメアスでの活動をつづけるか、
日本国内で多くの人に協力をもとめました。
自然学校の様子をJICA神戸で展示 活動を紹介しました。
2009年~2012年
小農家へのアグロフォレストリー推進支援による森林回復と荒廃地回復植林事業(国土緑化助成活動)開始(2009年~)
小規模・零細農家が自立的に苗作りができるようにすることを目的に、苗畑を設置した。
2009年:マサランドゥーバ生産者協会と、同じく車で約 30 分程度の距離にあるブレジーニョ生産者協会の2つ。


ブラジルアマゾンにおけるアグロフォレストリーによる河畔林再生植林活動と産学官ネットワーク化事業(三井物産環境基金助成活動)(2009年~2012年)
河畔地帯の植生回復を回復しながら残された天然林とアグロフォレストリーを有機的に結びつけ、天然林のネットワーク化をはかる。
各年 10ha の植林を実施する
2013年以降
ネットワーク化活動におけるワークショップの開催を続け現在に至る
2001年
ブラジル、当会の有志がトメアスを訪れる機会を得ました。
破壊の進む熱帯林の現状をみてどうしたら
保全することができるだろうかと考えました。
2003年~2006年
(JICAの草の根支援)環境を守る人材を育てる事業の実施。
「アマゾン自然学校」を実施しました。
日本からエコツアーをおこない、アマゾン自然学校の見学。
我々に活動が少しでも日本の皆さんに理解していただいたはずです
https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry#
2007~2008年
「アマゾン自然学校」の事業終了後、どのようにトメアスでの活動をつづけるか、
日本国内で多くの人に協力をもとめました。
自然学校の様子をJICA神戸で展示 活動を紹介しました。
2009年~2012年
小農家へのアグロフォレストリー推進支援による森林回復と荒廃地回復植林事業(国土緑化助成活動)開始(2009年~)
小規模・零細農家が自立的に苗作りができるようにすることを目的に、苗畑を設置した。
2009年:マサランドゥーバ生産者協会と、同じく車で約 30 分程度の距離にあるブレジーニョ生産者協会の2つ。


ブラジルアマゾンにおけるアグロフォレストリーによる河畔林再生植林活動と産学官ネットワーク化事業(三井物産環境基金助成活動)(2009年~2012年)
河畔地帯の植生回復を回復しながら残された天然林とアグロフォレストリーを有機的に結びつけ、天然林のネットワーク化をはかる。
各年 10ha の植林を実施する
2013年以降
ネットワーク化活動におけるワークショップの開催を続け現在に至る