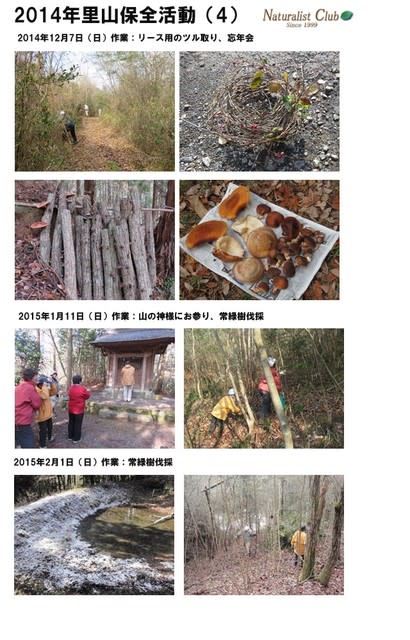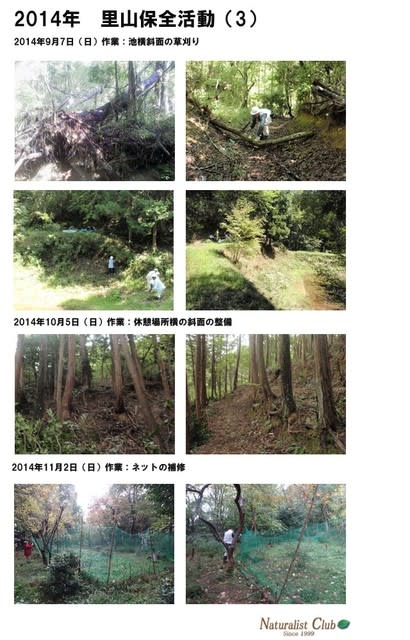年に1度は遠くのフィールドでの観察会を計画しています
●2011年11月20日(日) 「水辺の野鳥観察」
今月はミニバスで湖北野鳥センターに野鳥の観察に行きました。
長浜市湖北町の琵琶湖岸は1988年に今月はミニバスで湖北野鳥センターに野鳥の観察に行きました。
長浜市湖北町の琵琶湖岸は1988年に「湖北水鳥センター」として整備され「湖北水鳥センター」が併設されました。
1993年に琵琶湖がラムサール条約に登録され、1997年には環境省により「琵琶湖水鳥・湿地センター」が開設されました。
ここはコハクチョウや天然記念物のオオヒシクイの越冬地となっています。
7:30阪急宝塚駅集合、一路湖北へ。琵琶湖といっても長浜市は東側にあり、結構時間がかかります。到着予定は11時。途中菩提寺パーキングエリアで休憩。タヌキがお出迎え、早速なりきる人が。ここのパーキングエリアは最近改装されたのか、トイレがとてもきれいです!
渋滞もなく予定通り到着。まずは湖の東側の池周辺と田んぼを散策。この田んぼは水を引き込んであり、実験的にビオトープが作られています。さらに奥の田んぼはコハクチョウのエサ場となっています。池にはマガモ、コガモ、オナガガモなどがたくさんいました。
池の向こう側にたくさんのコハクチョウが見えます。田んぼにエサをまいてエサ場にしているそうです。早速行ってみましょう!
この日は雨が降ったりやんだり日が射したりで何度も虹が見えました。なんと二重の虹も!移動するメンバーの上にも虹がかかっているのが見えますか
いました、いました。たくさんのコハクチョウがエサをついばんでいます。器用に片足で立っている鳥もいました。後ろの方に足を伸ばしているんですがバランスを上手にとって結構長い間このままでの恰好で立っていました。
左の写真、後ろにいる顔がグレーの鳥が幼鳥。くちばしもまだ黄色い部分がありません。体にもグレーの色が残っています。みにくいアヒルの子のお話が思い出されますね。
マガンが一緒にエサを食べていました。右が成鳥で顔の部分が白く胸に黒班があります。左は幼鳥でまだ特徴が現れていません。マガンが飛ぶ時はI字型やV字型のきれいな編隊を組んで飛びます。
水鳥センターに到着。マルチビジョンに映し出される水鳥の自動撮影カメラで観察。下の写真はヒシの実。オオヒシクイはこんな硬くて大きい実を砕いて飲み込みます。大きい実を飲み込んで喉がプックリ膨らんでいる面白い映像も見せてい頂きました。
水鳥センターにはフィールドスコープが20台備え付けられています。これで見ると対岸の鳥が間近にいるようにはっきりと見えます。右の写真の木が生えている辺りが鳥のねぐらです。
フィールドスコープにコンパクトデジカメを押し当てて撮影してみました。遠くにある木がこんなにはっきりと見えます。白い鳥はコハクチョウで多分体調が悪いのでエサ場に行かなかったのでしょう、と言うことでした。コハクチョウは仲間意識が強く一羽が残ると必ず連れも残るそうです。はっきり見えませんが、2羽寄り添っています。
レクチャールームを借りて昼食を食べた後は各自で近くを散策。近くの川にオオバンがいました。とても用心深くて人が近寄ってくる気配がするとすっとヨシの中に隠れてしまい、なかなか写真がとれませんでした。やっと出てきたところをパチリ。
さらにここには天然記念物のオオワシが毎年訪れています。普通は北海道で越冬するのですがなぜか彼女は琵琶湖が気に入って毎年やってくるそうです。ただしかなりの高齢(?)とかで毎年その時期になると「今年は来るかな?」と空を見上げる日が続くそうです。今年はまだ来ていないとのことで残念。写真は実物大の模型です。羽根を広げると2.4mあります。
たくさんの水鳥を観察して2時半過ぎに帰路に。車内で手作りのガマズミ酒をいただきました。とってもきれいな色です。ガマズミの赤がそのまま出てますね!今回は焼酎ではなくいいちこに漬けこんだとのこと、そのせいか色が出るのが早かったそうです。ごちそうさまでした!として整備され「湖北水鳥センター」が併設されました。1993年に琵琶湖がラムサール条約に登録され、1997年には環境省により「琵琶湖水鳥・湿地センター」が開設されました。ここはコハクチョウや天然記念物のオオヒシクイの越冬地となっています。
2011年度ナチュラリストクラブhpより