
(1)
9月3日。
川崎市に<藤子・F・不二雄ミュージアム>がオープンするんですね。全部予約制みたい。フラッと行ったら断られます。
行きたいなー。
きっとマンガ好きにとっては、行くだけで幸せな気持ちになれると思う。
京都で散々お寺巡りをした後、<京都国際マンガミュージアム>に行った時も幸せな気持ちになったものです。漫画を読みまくりました。
<藤子・F・不二雄ミュージアム>は、登戸や向ヶ丘遊園駅から徒歩15分くらいのところにあります。
この近くには、なんと川崎市岡本太郎美術館もあるんですよねー。
いい気に満ちてそうです。
ちなみに、自分の高校の卒業旅行は宝塚市の手塚治虫記念館に親友と二人で行ったのです。丸二日間、手塚先生漬けの日々。
楽しかったなー。藤子・F・不二雄ミュージアムから、そういうことをふと思いだします。(しばし回想)
(2)
平凡社の企画でやっている、漫画家こうの史代さんの「ぼおるぺん 古事記」が面白い。
日本の神話の『古事記』。
実は相当におもしろいんですよね。
自分もつい最近知りました。
日本人なら色んなバリエーションで読んでみる価値アリです。
文字で読むなら「古事記(ビギナーズ・クラシックス) 」角川ソフィア文庫(2002/08) なんて読みやすかった。このシリーズは大好きです。
ちなみに、こうの史代さんは「夕凪の街 桜の国」双葉社 (2004/10/12) という原爆を描いた漫画が超名作として有名。
漫画好きなら、読まずに死んだらきっと損します。
ひさしぶりにAmazonを見てみたら、レビュー数が315もあって驚いた!
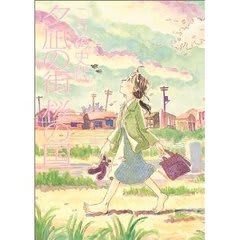
===========
<出版社/著者からの内容紹介>
昭和30年、灼熱の閃光が放たれた時から10年。
ヒロシマを舞台に、一人の女性の小さな魂が大きく揺れる。
最もか弱き者たちにとって、戦争とは何だったのか……、原爆とは何だったのか……。
漫画アクション掲載時に大反響を呼んだ気鋭、こうの史代が描く渾身の問題作。
===========
(3)
古事記で、思い出しました。
シュールな漫画家、五月女ケイ子さん。
彼女が描く「五月女ケイ子のレッツ!!古事記」講談社 (2008/8/1) ってのも笑えておもしろい。
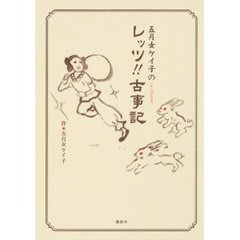
漫画家の方ってほんとにすごいですよね。
描く対象の急所を完全に掴んだうえで、それをイメージに変換させるわけだから。
映画を、監督・脚本・俳優・美術・・・全て自分でやるようなもので。
日本の漫画家の先生方には、どんな方にも深い敬意を感じずにはおれません。
(4)
古事記で、最後にひと言付け加えたくなってきました。
河合隼雄大先生の「神話と日本人の心」岩波書店 (2003/7/19) ってのはすごい本です。

===========
<内容>
日本を代表するユング派心理学者であり、『昔話と日本人の心』などの著作で独自の物語論を展開する著者が、日本神話の意味とその魅力をわかりやすく語る。
他世界の多くの神話と異なり、太陽神はなぜ男性ではなく「日の女神」アマテラスなのか?
繰り返し現れる神々の「トライアッド」構造とは何か?
母との一体性、トリックスター、英雄…さまざまな顔をもつスサノヲとはいかなる神か?
「見畏む」男神たち、流し棄てられた神ヒルコは何を意味するのか…。
『古事記』『日本書紀』の世界を独自の観点から、また世界の神話・物語との比較をまじえた広い視野からよみとき、日本人の心性と現代社会の課題をさぐる。
===========
この本を読むと、河合先生の偉大さや懐の広さを改めて感じたのです。
それと共に、人間の心の深さ、そんな人間の長い歴史。
言葉にできない色んなものを衝撃と共に感じました。ああ、自分は日本をなにも知らない。と思いつつ。
河合隼雄先生は、1965年に37歳で日本人初のユング派分析家の資格をとります。そのときの審査論文が、ここで書かれている日本神話の心理学的な研究なのです。
伊勢神宮もそうですが、日本のアマテラス(天照皇大神)は「太陽の女神」です。
海外では太陽神が男性、月が女性で表現されることが多いのですが、日本は「女性の太陽神」なのです。
「女性の太陽神」は世界的な神話で見てもかなり珍しいとのこと。北欧神話と日本神話くらいみたいです。
そんな女性の太陽神を母体とする、日本の母性社会、その日本人の心の光と影を壮大なテーマで書いてます。
古事記の深い解釈に思わずうならされます。
あと、河合先生が注目されている神様の「ヒルコ」。
国産みの時に、イザナギ(伊耶那岐命)とイザナミ(伊耶那美命)との間に生まれた最初の神様がヒルコなのですが、子作りの際に女神のイザナミが最初に声をかけたという順番がよろしくないとのことで、ヒルコという神様は葦の舟に入れられてオノゴロ島から流されてしまうのです。
神々のなかから捨てられた「ヒルコ」。
そのヒルコは、日本が失った強い男性性の象徴と河合先生は考えます。それは一神教を産み出す強い男性原理の神様。
その強い男性性を捨ててしまった日本は、改めて男性性と女性性を調和させることで、新しい日本の旅立ちになると、河合先生は書いています。
・・・・この辺は、あまり表面的には書けないほどの壮大なテーマなので、書いてて中途半端になるので、是非読んでみてほしい。
いつか、元気があればブログにも書いてみたい気もする。でも、恐れ多い気もする。
・・・・・・・・
なんか脱線してキリがないのでこの辺で。
もともと、書きたかったのは<藤子・F・不二雄ミュージアム>オープン!っていうのと、あとひとつ別のことだったんですが、ダラダラ書いてたら忘れてしまいました。
また、思い出したら書きます。
9月3日。
川崎市に<藤子・F・不二雄ミュージアム>がオープンするんですね。全部予約制みたい。フラッと行ったら断られます。
行きたいなー。
きっとマンガ好きにとっては、行くだけで幸せな気持ちになれると思う。
京都で散々お寺巡りをした後、<京都国際マンガミュージアム>に行った時も幸せな気持ちになったものです。漫画を読みまくりました。
<藤子・F・不二雄ミュージアム>は、登戸や向ヶ丘遊園駅から徒歩15分くらいのところにあります。
この近くには、なんと川崎市岡本太郎美術館もあるんですよねー。
いい気に満ちてそうです。
ちなみに、自分の高校の卒業旅行は宝塚市の手塚治虫記念館に親友と二人で行ったのです。丸二日間、手塚先生漬けの日々。
楽しかったなー。藤子・F・不二雄ミュージアムから、そういうことをふと思いだします。(しばし回想)
(2)
平凡社の企画でやっている、漫画家こうの史代さんの「ぼおるぺん 古事記」が面白い。
日本の神話の『古事記』。
実は相当におもしろいんですよね。
自分もつい最近知りました。
日本人なら色んなバリエーションで読んでみる価値アリです。
文字で読むなら「古事記(ビギナーズ・クラシックス) 」角川ソフィア文庫(2002/08) なんて読みやすかった。このシリーズは大好きです。
ちなみに、こうの史代さんは「夕凪の街 桜の国」双葉社 (2004/10/12) という原爆を描いた漫画が超名作として有名。
漫画好きなら、読まずに死んだらきっと損します。
ひさしぶりにAmazonを見てみたら、レビュー数が315もあって驚いた!
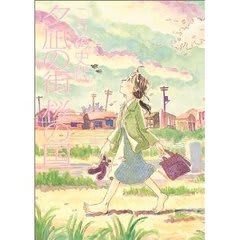
===========
<出版社/著者からの内容紹介>
昭和30年、灼熱の閃光が放たれた時から10年。
ヒロシマを舞台に、一人の女性の小さな魂が大きく揺れる。
最もか弱き者たちにとって、戦争とは何だったのか……、原爆とは何だったのか……。
漫画アクション掲載時に大反響を呼んだ気鋭、こうの史代が描く渾身の問題作。
===========
(3)
古事記で、思い出しました。
シュールな漫画家、五月女ケイ子さん。
彼女が描く「五月女ケイ子のレッツ!!古事記」講談社 (2008/8/1) ってのも笑えておもしろい。
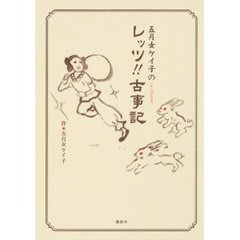
漫画家の方ってほんとにすごいですよね。
描く対象の急所を完全に掴んだうえで、それをイメージに変換させるわけだから。
映画を、監督・脚本・俳優・美術・・・全て自分でやるようなもので。
日本の漫画家の先生方には、どんな方にも深い敬意を感じずにはおれません。
(4)
古事記で、最後にひと言付け加えたくなってきました。
河合隼雄大先生の「神話と日本人の心」岩波書店 (2003/7/19) ってのはすごい本です。

===========
<内容>
日本を代表するユング派心理学者であり、『昔話と日本人の心』などの著作で独自の物語論を展開する著者が、日本神話の意味とその魅力をわかりやすく語る。
他世界の多くの神話と異なり、太陽神はなぜ男性ではなく「日の女神」アマテラスなのか?
繰り返し現れる神々の「トライアッド」構造とは何か?
母との一体性、トリックスター、英雄…さまざまな顔をもつスサノヲとはいかなる神か?
「見畏む」男神たち、流し棄てられた神ヒルコは何を意味するのか…。
『古事記』『日本書紀』の世界を独自の観点から、また世界の神話・物語との比較をまじえた広い視野からよみとき、日本人の心性と現代社会の課題をさぐる。
===========
この本を読むと、河合先生の偉大さや懐の広さを改めて感じたのです。
それと共に、人間の心の深さ、そんな人間の長い歴史。
言葉にできない色んなものを衝撃と共に感じました。ああ、自分は日本をなにも知らない。と思いつつ。
河合隼雄先生は、1965年に37歳で日本人初のユング派分析家の資格をとります。そのときの審査論文が、ここで書かれている日本神話の心理学的な研究なのです。
伊勢神宮もそうですが、日本のアマテラス(天照皇大神)は「太陽の女神」です。
海外では太陽神が男性、月が女性で表現されることが多いのですが、日本は「女性の太陽神」なのです。
「女性の太陽神」は世界的な神話で見てもかなり珍しいとのこと。北欧神話と日本神話くらいみたいです。
そんな女性の太陽神を母体とする、日本の母性社会、その日本人の心の光と影を壮大なテーマで書いてます。
古事記の深い解釈に思わずうならされます。
あと、河合先生が注目されている神様の「ヒルコ」。
国産みの時に、イザナギ(伊耶那岐命)とイザナミ(伊耶那美命)との間に生まれた最初の神様がヒルコなのですが、子作りの際に女神のイザナミが最初に声をかけたという順番がよろしくないとのことで、ヒルコという神様は葦の舟に入れられてオノゴロ島から流されてしまうのです。
神々のなかから捨てられた「ヒルコ」。
そのヒルコは、日本が失った強い男性性の象徴と河合先生は考えます。それは一神教を産み出す強い男性原理の神様。
その強い男性性を捨ててしまった日本は、改めて男性性と女性性を調和させることで、新しい日本の旅立ちになると、河合先生は書いています。
・・・・この辺は、あまり表面的には書けないほどの壮大なテーマなので、書いてて中途半端になるので、是非読んでみてほしい。
いつか、元気があればブログにも書いてみたい気もする。でも、恐れ多い気もする。
・・・・・・・・
なんか脱線してキリがないのでこの辺で。
もともと、書きたかったのは<藤子・F・不二雄ミュージアム>オープン!っていうのと、あとひとつ別のことだったんですが、ダラダラ書いてたら忘れてしまいました。
また、思い出したら書きます。










そのことを聞いて、あらためて日本神話の舞台である島根県に一度行ってみたいと思いました。
出雲大社にも来年こそは行こうと思っています。
とても面白そうな行程ですね。
知らない場所にいると、その土地の伝説や神話や伝承が色濃く残り、誰かに見つけられるのを待つように静かに黙想するように佇んでいるのに感動することがあります。神社や石碑やいろんなもの。それは過去にそれを作った人がいて、願いや祈りを刻み込み封印した人がいる。
そういうことに思いをはせるだけでも旅は楽しいものです。
赤猪岩神社はすごく興味あります。自分も因幡の白ウサギと同じ、いなば姓でもありますから。
根之堅洲国は須賀神社、黄泉比良坂の揖夜神社・・・すごいですね。その土地土地に神社があり、カミの依り代があるんですね。ゆっくり時間をとって散策しに行きます。そのときはまたブログに書いてみようかな、と思います。ありがとうございました。