2007/2/7(水) 午後 6:38
参議院選挙を意識した与野党の鞘あてが激しさを増している。
郵政解散選挙で、衆議院では、自民・公明の与党が圧倒的多数を確保した。しかし、参議院では与野党拮抗している。今年の参議院選挙で野党が勝利すれば、野党支配の参議院で、衆議院から送付される法案を次々と葬り、安部政権を退陣に追い込めるという。民主党の小沢代表は、自らの主義主張をかなぐりすて、野党連携に邁進している。
こういう事態に、国民は何の疑問もいだいていないようだ。メディアも、高みの見物の態度です。
しかし、これでいいのだろうか。
衆参のねじれによって国会が機能不全に陥る、つまり、国の意思決定が不能になるということです。小沢代表は、これを目指すという。しかし、これと同じことは、政権与党となった民主党に対しても生じうることです。同じことをされれば、民主党の政策も実施できない状況が現出することになります。
もともと、国会の機能は、国の意思(政策)を一義的に決定し、行政に対して実行を命じることです。身体であれば、頭脳が国会、筋肉が行政です。変化する環境に対し、国は的確に対処していかなければなりません。これは、企業も個人も同じです。先を見据えた国家経営ができなければ、結局国民が災厄をこうむります。衆参のねじれは、意思決定機能を破壊するもので、身体でいえば脳梗塞にかかった状態でしょう。人間なら、ICUにはいって絶対安静事態です。
問題は、衆参のねじれ事態を引き起こす国会制度にあります。二院制自体は、意思決定に慎重さを確保するための設計ですが、程度が過ぎ機能不全を引き起こすのであれば、欠陥商品として、再設計が必要でしょう。
では、どのように再設計すればいいでしょうか。
かつて、政治改革が熱く議論された時代がありました。政権交代可能な選挙制度改革をめぐり、小沢氏は自民党を脱退し、新制度による選挙を経て、自民党は野にくだり、細川政権が誕生しました。当時の議論をおさらいしましょう。
1選挙区区から5名前後の議員を選出する中選挙区制では、有効票の5分の1の得票で当選可能です。これは、少数の利益団体の支持があれば当選できる制度です。仮に投票率が50%とすれば、5%の組織票があれば、あと5%の上乗せでらくらく当選です。また、同一政党から、複数の候補が出馬することから、政策を選択する政党選挙ではなく個人選挙となりました。選挙区で対立する同一政党個人候補は、政党内で派閥を結成し、政策選択をさらに不透明にしました。派閥の領袖が、派閥を維持するための資金集めをし、腐敗の温床ともなりました。
この、反省にたち政策本位の選挙をするための小選挙区制に移行しようとしたのが、「政治改革」でした。現在の、自民、民主の2大政党は、こうして生まれました。社会は、これで欧米型の2大政党が現出し、政権交代がスムーズに行われると考え、政治改革の熱意はさめました。
しかし、この改革は、2つの点で大きな欠陥がありました。その1は、衆議院で、比例代表並立という妥協制度を採用したことです。その2は、改革が衆議院にとまり、参議院が改革を間苦れたことです。
その結果、何が起きたか。2大政党が拮抗するも完全多数がどちらもとれず、公明党という国民の5%以下の支持しかない政党が支配することになりました。安部政権いやどんな自民党党首が独自性を発揮しようとしてもできない仕組みです(民主に言い換えても同じ)。また、参議院は、もともと都道府県選挙区と比例が混在し、これに定数調整を重ねたため選出原理がまったく不明の代物となっている。
選挙制度と政党数には、明快な対応関係がある。米国で、テレビジョン経済学という本を読んだことがあります。地域のTVのチャンネル数と番組編成方針との関係を考察した論です。地域住民の選好が均等に分布しているとすれば、番組編成は、チャンネル数で割った視聴率を確保する番組編成方針が合理的というものです。チャンネル数は、政党数、番組編成は政策セットとすれば、この分析は、そのまま選挙分析に適用可能です。
2TV局の場合、それぞれが50%以上の視聴率をめざし、2局の番組編成は中道よりとなります。小選挙区制は、選択肢を2つに絞ることにより、政権交代可能な中道寄り2大政党を形成する原理です。(逆に、中選挙区制の下では、5つの派閥ができました)
さらに、小選挙区制は、選挙民にイエスかノーかいう形で争点を明確化してしめしし、選択を容易にする効果がありあます。マニフェストも、小選挙区制がなければ意味がないでしょう。あらゆる意思決定は、一義的な行動を指定する必要があります。妥協した一つの行動はとれても、相反する2つの行動をとることは、原理上不可能です。政治過程とは、無限に多様な個人の見解を単純化し、一義的なの社会的意思決定に収斂する過程です。小選挙区制は、もっとも効率的な収斂制度でしょう。
これに対し、比例代表は多様性が多様なまま選挙結果に反映され、政策決定は議員間の妥協にまかされます。妥協結果は誰にも予測できず、妥協の継続期間も不明です。つまり、政治過程における意思収斂機能がまったくない。当然、マニフェストも無意味となります。
現在の小選挙区比例並立制のもとにおける衆議院の少数第3党の支配は、現行制度の必然として生み出されているということです。これは、はたして、これは政治改革で望んだことだったのだろうか。
国会改革は、まず、民主と自民が共同で衆議院の完全小選挙区制を実現することです。そうすれば、政権交代可能な2大政党が出現する。
参議院は、どう改革すればいいでしょうか。まず、国会の機能不全を回避するため、ねじれが生じない制度にするか、ねじれが生じても実害が生まれない制度にすることが、最小限必要です。参議院廃止論もありますが、日本の民主主義の熟度を考慮すれば、衆議院の意思決定に慎重さを促す牽制作用に期待するのも一理あるかもしれません。さらに、切り捨てられた少数意見の主張を考慮する場としての機能も必要かもしれません。そういう観点からは、梶山静六氏が唱えた衆議院完全小選挙区とセットのした参議院完全比例代表制もいいでしょう。ただし、国会の機能不全を避けるため、憲法改正により、参議院否決案の衆議院再議決要件を過半数に緩めること等が考慮されるべきでしょう。
今回の参議院選挙を機に、自民・民主両党の政治家に、根本に戻って、あらためて日本の行く末を考えてもらいたい。小沢党首には、当面の選挙戦の勝利者ではなく、元の志にそって政治改革の勝利者になり歴史に名を残してもらいたい。
参議院選挙を意識した与野党の鞘あてが激しさを増している。
郵政解散選挙で、衆議院では、自民・公明の与党が圧倒的多数を確保した。しかし、参議院では与野党拮抗している。今年の参議院選挙で野党が勝利すれば、野党支配の参議院で、衆議院から送付される法案を次々と葬り、安部政権を退陣に追い込めるという。民主党の小沢代表は、自らの主義主張をかなぐりすて、野党連携に邁進している。
こういう事態に、国民は何の疑問もいだいていないようだ。メディアも、高みの見物の態度です。
しかし、これでいいのだろうか。
衆参のねじれによって国会が機能不全に陥る、つまり、国の意思決定が不能になるということです。小沢代表は、これを目指すという。しかし、これと同じことは、政権与党となった民主党に対しても生じうることです。同じことをされれば、民主党の政策も実施できない状況が現出することになります。
もともと、国会の機能は、国の意思(政策)を一義的に決定し、行政に対して実行を命じることです。身体であれば、頭脳が国会、筋肉が行政です。変化する環境に対し、国は的確に対処していかなければなりません。これは、企業も個人も同じです。先を見据えた国家経営ができなければ、結局国民が災厄をこうむります。衆参のねじれは、意思決定機能を破壊するもので、身体でいえば脳梗塞にかかった状態でしょう。人間なら、ICUにはいって絶対安静事態です。
問題は、衆参のねじれ事態を引き起こす国会制度にあります。二院制自体は、意思決定に慎重さを確保するための設計ですが、程度が過ぎ機能不全を引き起こすのであれば、欠陥商品として、再設計が必要でしょう。
では、どのように再設計すればいいでしょうか。
かつて、政治改革が熱く議論された時代がありました。政権交代可能な選挙制度改革をめぐり、小沢氏は自民党を脱退し、新制度による選挙を経て、自民党は野にくだり、細川政権が誕生しました。当時の議論をおさらいしましょう。
1選挙区区から5名前後の議員を選出する中選挙区制では、有効票の5分の1の得票で当選可能です。これは、少数の利益団体の支持があれば当選できる制度です。仮に投票率が50%とすれば、5%の組織票があれば、あと5%の上乗せでらくらく当選です。また、同一政党から、複数の候補が出馬することから、政策を選択する政党選挙ではなく個人選挙となりました。選挙区で対立する同一政党個人候補は、政党内で派閥を結成し、政策選択をさらに不透明にしました。派閥の領袖が、派閥を維持するための資金集めをし、腐敗の温床ともなりました。
この、反省にたち政策本位の選挙をするための小選挙区制に移行しようとしたのが、「政治改革」でした。現在の、自民、民主の2大政党は、こうして生まれました。社会は、これで欧米型の2大政党が現出し、政権交代がスムーズに行われると考え、政治改革の熱意はさめました。
しかし、この改革は、2つの点で大きな欠陥がありました。その1は、衆議院で、比例代表並立という妥協制度を採用したことです。その2は、改革が衆議院にとまり、参議院が改革を間苦れたことです。
その結果、何が起きたか。2大政党が拮抗するも完全多数がどちらもとれず、公明党という国民の5%以下の支持しかない政党が支配することになりました。安部政権いやどんな自民党党首が独自性を発揮しようとしてもできない仕組みです(民主に言い換えても同じ)。また、参議院は、もともと都道府県選挙区と比例が混在し、これに定数調整を重ねたため選出原理がまったく不明の代物となっている。
選挙制度と政党数には、明快な対応関係がある。米国で、テレビジョン経済学という本を読んだことがあります。地域のTVのチャンネル数と番組編成方針との関係を考察した論です。地域住民の選好が均等に分布しているとすれば、番組編成は、チャンネル数で割った視聴率を確保する番組編成方針が合理的というものです。チャンネル数は、政党数、番組編成は政策セットとすれば、この分析は、そのまま選挙分析に適用可能です。
2TV局の場合、それぞれが50%以上の視聴率をめざし、2局の番組編成は中道よりとなります。小選挙区制は、選択肢を2つに絞ることにより、政権交代可能な中道寄り2大政党を形成する原理です。(逆に、中選挙区制の下では、5つの派閥ができました)
さらに、小選挙区制は、選挙民にイエスかノーかいう形で争点を明確化してしめしし、選択を容易にする効果がありあます。マニフェストも、小選挙区制がなければ意味がないでしょう。あらゆる意思決定は、一義的な行動を指定する必要があります。妥協した一つの行動はとれても、相反する2つの行動をとることは、原理上不可能です。政治過程とは、無限に多様な個人の見解を単純化し、一義的なの社会的意思決定に収斂する過程です。小選挙区制は、もっとも効率的な収斂制度でしょう。
これに対し、比例代表は多様性が多様なまま選挙結果に反映され、政策決定は議員間の妥協にまかされます。妥協結果は誰にも予測できず、妥協の継続期間も不明です。つまり、政治過程における意思収斂機能がまったくない。当然、マニフェストも無意味となります。
現在の小選挙区比例並立制のもとにおける衆議院の少数第3党の支配は、現行制度の必然として生み出されているということです。これは、はたして、これは政治改革で望んだことだったのだろうか。
国会改革は、まず、民主と自民が共同で衆議院の完全小選挙区制を実現することです。そうすれば、政権交代可能な2大政党が出現する。
参議院は、どう改革すればいいでしょうか。まず、国会の機能不全を回避するため、ねじれが生じない制度にするか、ねじれが生じても実害が生まれない制度にすることが、最小限必要です。参議院廃止論もありますが、日本の民主主義の熟度を考慮すれば、衆議院の意思決定に慎重さを促す牽制作用に期待するのも一理あるかもしれません。さらに、切り捨てられた少数意見の主張を考慮する場としての機能も必要かもしれません。そういう観点からは、梶山静六氏が唱えた衆議院完全小選挙区とセットのした参議院完全比例代表制もいいでしょう。ただし、国会の機能不全を避けるため、憲法改正により、参議院否決案の衆議院再議決要件を過半数に緩めること等が考慮されるべきでしょう。
今回の参議院選挙を機に、自民・民主両党の政治家に、根本に戻って、あらためて日本の行く末を考えてもらいたい。小沢党首には、当面の選挙戦の勝利者ではなく、元の志にそって政治改革の勝利者になり歴史に名を残してもらいたい。















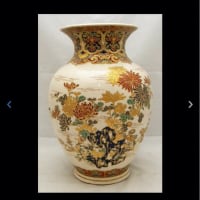



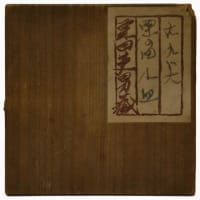
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます