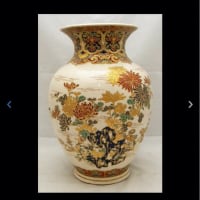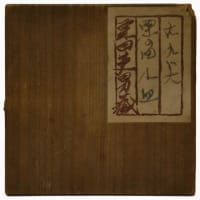沖縄はゆすりたかりの名人とは、アメリカ国務省のメア前日本部長の発言だ。もっとも、本人は発言を否定している。反基地運動家に乗せられたのだという。まあ、事態収拾のため否定せざるをえなかったのだろうが、乗せられたのは事実のようだ。
反基地運動家の狙いどおり、沖縄住民は、これに猛反発した。なぜか。痛いところを突かれたからだ。本人達が、自らをゆすりと認識しているからこそ、反発する。客観的に誰から見てもゆすりとされない行動をとっていれば、一笑に付すことができる。猛反発によって、自らがゆすりの名人であることを明白にしてしまった。果たして、これが、反基地運動家の狙いだったか否かについては不明であるが。
振り返って考えると、ゆすりたかりの名人は沖縄に限らない。日本のほとんどの地方自治体は、ゆすりたかり精神にどっぷりとつかっている。
震災被災地の岩手・宮城は、中央の復興予算の獲得をめざして、あの手この手。その獲得を地方住民が後押しする。それに、悪知恵をつけるのは、復興予算に群がる企業だ。復興自体より、如何に予算額を増やすかが関心事となっている。そこに、政治家がからむ。まさに、眼を覆う惨状だ。
被災者の救済は後回しで、予算確保のための人質になっている。被災者のことを思うと胸が痛む。しかし、被災者の名を借りて、都合よく金を巻き上げようとする人間がいると思うとより胸が痛む。
問題は、関係者が、それぞれ合理的な行動をとっていることだろう。自治体が予算をとるために方便を使うのは、当たり前。予算関係住民がそれを支援するのも当たり前。企業が営業目的で知恵をつけるのも、当然。そして、真の支援は無視される。
これは、コモンズの悲劇といわれる現象と類似の構造だ。猟場で、参加者が個々に合理的な行動を取ることにより、猟場の資源は枯渇する。解決は、個々人の行動全体を、新たなルールで規制し、そのもとで、資源管理を行なうことだ。
日本の地方自治にも新たなルールが必要だろう。今の制度は、ゆすりたかり精神のビルトイン・システムといってよい。これは、明治政府が、近代化を進めるために、中央が遅れた地方を改革指導するために作ったものだ。当時意義のあった制度が、今や国民の活力を削ぐ制度に転化してしまった。
明治の初め、日本の地方はみすぼらしかったが輝いていた。地方には、天下国家を論ずる有志が溢れ、自ら行動した。文化程度も、中央と遜色なかった。自主独立の精神を失い、ゆすり根性に蝕まれ、その必然としての凋落と疲弊のさなかにある今の地方とは大違いだ。
地方の再生は、中央の金をつぎ込むことによっては解決できない。それは、依存を更に深める死に至る病そのものだ。
地方分権の推進が叫ばれて久しい。政府の委員会の報告書を見ると、おっしゃるとおりという立派なことが書いてある。しかし、現実は、はるかに遠いところにある。地方の真の自立を実現するために何が必要か。これは、明治以来の仕組みを根本から改める以外にない。
具体的には、政府の事務を国と地方に完全分離し、それぞれがお互いのことに口を挟まず完全独立で事務を執行することだ。当然、地方は独自に自由に課税する。
現在の地方制度の根本問題は、制度上、地方政府は何でもできることになっていることだ。明治政府は、この制度で地方を中央の手足として使った。その総本山が旧内務省だ。その制度のもとでは、国と地方は一体で役割分担がない。戦後、地方自治制度が施行されたが、霞ヶ関は、作業の地方に押し付け、自らはそれを監督する形で旧体制が温存された。戦後は、悪いことに、地方は、無限定権限を逆手にとり、安全保障など国に事務に口を挟むようになった。その典型が、沖縄の安全保障を人質にとったゆすりたかりだろう。
改革の基本は、地方と中央の役割分担確定と役割遂行の完全独立だろう。中央の仕事は、地方にあっても、税務署のような中央の地方組織が実施する。戸籍事務のように、一部国と地方の共同事務が残るが、共同事務は、国が制度を定め、地方が受益に応じて費用負担すべきだろう。基地問題は、防衛施設庁だけの判断で実施すべきだろう。地域の人間には、自治体を絡ませず、国に対して直接問題を提起させるべきだ。
改革原理は、簡単だ。まさにアメリカ下賜憲法が言う地方自治の本旨を実現するだけだ。憲法施行後60年以上。この理念を全く理解しない日本の学界・言論界はあまりに異常であり、あまりにお粗末だ。
反基地運動家の狙いどおり、沖縄住民は、これに猛反発した。なぜか。痛いところを突かれたからだ。本人達が、自らをゆすりと認識しているからこそ、反発する。客観的に誰から見てもゆすりとされない行動をとっていれば、一笑に付すことができる。猛反発によって、自らがゆすりの名人であることを明白にしてしまった。果たして、これが、反基地運動家の狙いだったか否かについては不明であるが。
振り返って考えると、ゆすりたかりの名人は沖縄に限らない。日本のほとんどの地方自治体は、ゆすりたかり精神にどっぷりとつかっている。
震災被災地の岩手・宮城は、中央の復興予算の獲得をめざして、あの手この手。その獲得を地方住民が後押しする。それに、悪知恵をつけるのは、復興予算に群がる企業だ。復興自体より、如何に予算額を増やすかが関心事となっている。そこに、政治家がからむ。まさに、眼を覆う惨状だ。
被災者の救済は後回しで、予算確保のための人質になっている。被災者のことを思うと胸が痛む。しかし、被災者の名を借りて、都合よく金を巻き上げようとする人間がいると思うとより胸が痛む。
問題は、関係者が、それぞれ合理的な行動をとっていることだろう。自治体が予算をとるために方便を使うのは、当たり前。予算関係住民がそれを支援するのも当たり前。企業が営業目的で知恵をつけるのも、当然。そして、真の支援は無視される。
これは、コモンズの悲劇といわれる現象と類似の構造だ。猟場で、参加者が個々に合理的な行動を取ることにより、猟場の資源は枯渇する。解決は、個々人の行動全体を、新たなルールで規制し、そのもとで、資源管理を行なうことだ。
日本の地方自治にも新たなルールが必要だろう。今の制度は、ゆすりたかり精神のビルトイン・システムといってよい。これは、明治政府が、近代化を進めるために、中央が遅れた地方を改革指導するために作ったものだ。当時意義のあった制度が、今や国民の活力を削ぐ制度に転化してしまった。
明治の初め、日本の地方はみすぼらしかったが輝いていた。地方には、天下国家を論ずる有志が溢れ、自ら行動した。文化程度も、中央と遜色なかった。自主独立の精神を失い、ゆすり根性に蝕まれ、その必然としての凋落と疲弊のさなかにある今の地方とは大違いだ。
地方の再生は、中央の金をつぎ込むことによっては解決できない。それは、依存を更に深める死に至る病そのものだ。
地方分権の推進が叫ばれて久しい。政府の委員会の報告書を見ると、おっしゃるとおりという立派なことが書いてある。しかし、現実は、はるかに遠いところにある。地方の真の自立を実現するために何が必要か。これは、明治以来の仕組みを根本から改める以外にない。
具体的には、政府の事務を国と地方に完全分離し、それぞれがお互いのことに口を挟まず完全独立で事務を執行することだ。当然、地方は独自に自由に課税する。
現在の地方制度の根本問題は、制度上、地方政府は何でもできることになっていることだ。明治政府は、この制度で地方を中央の手足として使った。その総本山が旧内務省だ。その制度のもとでは、国と地方は一体で役割分担がない。戦後、地方自治制度が施行されたが、霞ヶ関は、作業の地方に押し付け、自らはそれを監督する形で旧体制が温存された。戦後は、悪いことに、地方は、無限定権限を逆手にとり、安全保障など国に事務に口を挟むようになった。その典型が、沖縄の安全保障を人質にとったゆすりたかりだろう。
改革の基本は、地方と中央の役割分担確定と役割遂行の完全独立だろう。中央の仕事は、地方にあっても、税務署のような中央の地方組織が実施する。戸籍事務のように、一部国と地方の共同事務が残るが、共同事務は、国が制度を定め、地方が受益に応じて費用負担すべきだろう。基地問題は、防衛施設庁だけの判断で実施すべきだろう。地域の人間には、自治体を絡ませず、国に対して直接問題を提起させるべきだ。
改革原理は、簡単だ。まさにアメリカ下賜憲法が言う地方自治の本旨を実現するだけだ。憲法施行後60年以上。この理念を全く理解しない日本の学界・言論界はあまりに異常であり、あまりにお粗末だ。