
 一時期積もっていた雪も消え、今のところは「暖かい初冬」となっています。
一時期積もっていた雪も消え、今のところは「暖かい初冬」となっています。このままいけばいいのですが、そうはならないでしょうね。今年も、残すところあと1か月。
早いですね。ともすれば大震災の記憶が遠くなりがちですが、できることはしっかり継続
していかねばなりません、微力でも。宇野ゆかりの皆さま、お元気でしょうか?
築山順子さんの著作「最新和洋料理」の内容をチェックしていると、地域独特の用語・食材
などが登場して、興味深いものです。その中の一つで次のようなものがありました。
「かば焼き豆腐」を作る時の食材に「阿蘇のり・水前寺のり」を使用するのが最も適当である、
というのです。これらの「のり」の名前を目にするのは初めてでした。熊本の地名が入った
「のり」ですから、近くの海で採れた「海苔」の名前だろうと思っていましたが、「阿蘇」
「水前寺」に引っかかっていました。どちらも「海」ではなく、むしろ「山」だったからです。
少し調べていくうちに、意外なことが分かりました。「水前寺のり」は、いわゆる海で採れる
「海苔」ではなく、川で採れる「藍藻」だというのです。しかも、今は絶滅が危惧され、国の
天然記念物。水前寺の江津湖(えづこ)ではすでに絶滅したものとされ、福岡県朝倉市の
黄金川でも天然のものは少なくなっているといいます。養殖はされているようですが。
本が出された明治の末期、この頃は「水前寺のり」は熊本では珍しい食材ではなかったの
でしょうね。国の天然記念物に指定されたのが大正14年ですから、明治以後の環境の変化
などで稀少になったのかもしれません。
一方、「阿蘇のり」も調べてみましたが、こちらは有用な資料は見つけられませんでした。
阿蘇山中のどこかの清流で「藍藻」が育っていたのでしょうか? 今でもあるのでしょうか?
ご存じの方がいましたら、情報をお知らせいただければ、と思います。それにしても、どんな
味、食感なのでしょうね。この「のり」を使った「かば焼き豆腐」を食べてみたいものです。
 イチョウの落ち葉に積もった雪が融け残っていました。いずれ雪の下になってしまう
イチョウの落ち葉に積もった雪が融け残っていました。いずれ雪の下になってしまうものと思います。清源院の旅日記、やっと完結。最終日に、宇野甚五郎さんが登場して
いました。遅くなりましたが、来週にはお届けできるものと思います。












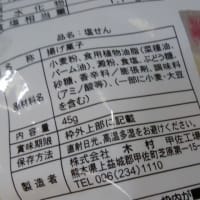








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます