この先、大館・弘前・青森の各駅で乗り継ぎしますが、まずは大館駅まで。
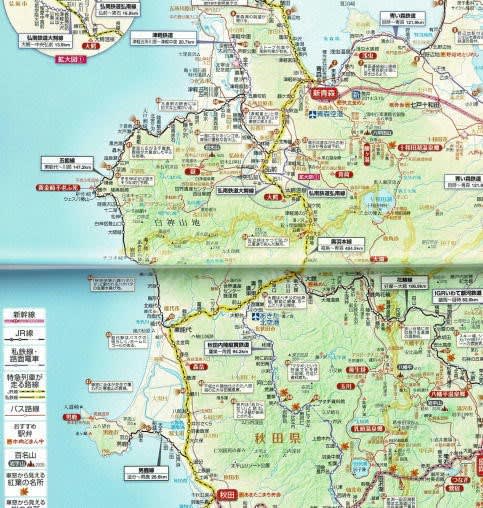
大館・弘前駅では7~8分の乗り継ぎ時間なので、ここで水分を確保します。
最近は、スープや味噌汁系の種類が多くなってきました。
「具たっぷり とん汁」、飲み物の域を超えています。

奥羽本線下り 普通 大館行
始発 秋田09:46
追分 09:59着 10:00発
1分程遅れての到着です。

大久保 10:06着 10:06発
この辺りは、男鹿半島が陸とつながるまでは海だったそうです。
田んぼを餌場にしているのは鷺でしょうか。

羽後飯塚 10:09着 10:10発
羽後飯塚駅のある旧飯田川町は、2005年(平成17年)の平成の大合併により昭和町、天王町と合併し潟上市となるまでは秋田県で一番小さな町で、二代秋田藩主佐竹義隆が神明社を建立した際に、御前で舞われた鷺舞が伝統芸能として伝わることからか、町の鳥は鷺だったそうです。

井川さくら 10:12着 10:12発
「芸名・人名だと勘違いしそうな実在の駅名ランキング」で第1位になったことがある駅です。
駅名は、駅から徒歩20分程の所にある桜の名所「日本国花苑」に由来するそうです。
「日本国花苑」は、1972年(昭和47年)4月に昭和天皇・皇后両陛下の御訪欧、秋田県立県百年、井川小学校統合校舎の建設を記念し、日本各地から集められた桜200種2,000本が2年がかりで植樹された公園だそうです。

八郎潟に注ぐ馬場目川を渡ると八郎潟駅に着きます。

八郎潟 10:16着 10:17発
五城目駅・一日市駅・八郎潟駅と名前を変えてきた駅。
話せば長くなる「八郎太郎伝説」が残るところでもあります。

八郎潟に沿ってきたに進んでいるのですが、見えているのは八郎潟の干拓地ではありません。

鯉川駅の手前で、八郎潟干拓事業によって残された3つの水域の一つ東部承水路が見えてきました。

鯉川 10:21着 10:22発
駅のフェンスに「橋本五郎文庫」の看板が見えます。
駅から徒歩15分程の所にある、みたね鯉川地区交流センター(旧鯉川小学校)に2011年(平成23年)4月29日に、三種町鯉川出身の読売新聞東京本社特別編集委員であり、テレビなどで御存知のジャーナリスト橋本五郎さんから寄贈された約2万冊の書籍と、地域の方々から提供された書籍によってオープンしたそうです。

次の鹿渡駅の位置は北緯40度2分40.69秒、東経140度4分57.25秒。
日本列島には緯度・経度線の分、秒以下の数値が0となる交差ポイントが陸上に39箇所存在し、これを「ポイントゼロ」と呼ぶそうです。
中でも、10度単位で交差する交点は1ヶ所。北緯40度0分0秒、東経140度0分0秒。場所は大潟村の中にあります。
北緯40度0分はこの辺りと思われます。

鹿渡 10:26着 10:27発
鹿渡駅を過ぎると八郎潟と離れます。
左手に見えるのは八郎潟ではありません。「角助沼」です。
周囲3.5kmの大きな池で、昔、ここに住んでいたカッパがいたずらをするので、角助という者が懲らしめたという伝説が残っているそうです。
「森岳ジュンサイの発祥の地」で、かつては「角助沼」にもジュンサイが自生していましたが、現在自生のジュンサイはなく、ハスの花が一面に咲くそうです。

森岳 10:32着 10:33発
北金岡 10:37着 10:37発
秋田自動車道をアンダーパスします。

東北電力の城火力発電所の煙突が見えると東能代駅に到着します。
発電所の煙突は赤白塗装と決まっていたのですが、なんでも航空法の改正でを受けて、高輝度障害灯を付けていれば、塗装色は自由に出来るようになりました。

東能代 10:43着 10:43発
東能代駅の能代市は、秋田県立能代工業高等高校のバスケットボールでの活躍が有名で、旧能代市時代の1989年度(平成元年度)からバスケットボールによる街づくり事業に取り組んでいます。東能代駅・能代駅のホームにはバスケットボードもあるのですが、歓迎の横断幕には「北限の茶畑」の文字が見えます。
日本茶の栽培の南限は沖縄県。北限は秋田県。栽培しているところは「秋田名物 八森ハタハタ 男鹿で男鹿ブリコ 能代春慶 桧山納豆 大館曲げわっぱ…」に出てくる、現在の能代市檜山町です。

東能代駅発車時点で、遅れが5分に広がっています。
東能代駅から進路を東に変えます。
白神の山々が見えます。

鶴形 10:48着 10:48発
戦後、仮乗降場を経て開業した駅です。
駅建設を想定していない、築堤のようなところに設けられたホームの高さに合わせるため、駅舎は鉄骨で組まれた高床の上に建てられています。

そんなに遠くないところを米代川が流れていますが見ることはできません。

富根 10:53着 10:53発
駅前にあるのは…。ロダンではないようです。
「考える少年の像」(昭和42年度富根中学校卒業記念制作作品)とのことです。
昭和44年4月1日に二ツ井町内6中学校が統合し、二ッ井中学校となっていますから、統合1年前の卒業制作のようです。

ここで、米代川を渡ります。

二ツ井 10:58着 10:59発
奥羽本線の前身、奥羽北線と同時の1901年(明治34年)11月1日に開業した駅です。
1922年(大正11年)から1936年(昭和11年)まで(正式には、1940年(昭和15年)3月1日に廃止。)は、駅前から米代川の川岸までの0.78kmに、中西徳五郎さんが敷設した軌間610mmの手押しトロッコ軌道「中西徳五郎経営二ツ井軌道」(個人経営であったため、正式名称が無かったとも言われています。)が荷物専用で、それまでの米代川水運と二ツ井駅との中継交通機関としての役を果たしていたそうです。
「食堂前田屋」。かつての駅前の賑わいを感じさせます。

明治天皇によって「徯后阪(きみまち阪)」と命名されたのは1882年(明治15年)。「きみまち阪」は県立自然公園に指定されている、サクラと紅葉の名所です。

二ツ井駅を出て藤琴川を渡ると徯后阪トンネルに入るため、「きみまち阪」は見えません。電車は、「恋文神社」の下を通っているようです。

前山 11:04着 11:05発
前山駅で、関係箇所への業務連絡のため少々停車というアナウンス。
そんなに時間も掛からず、5分遅れた発車。

至る所で白鳥を目にするようになりました。

右手に、本間様の「マルホン」の看板が見えてくると、秋田内陸鉄道線が合流して鷹ノ巣駅に着きます。


鷹ノ巣 11:09着 11:10発
JRは「鷹ノ巣駅」、秋田内陸鉄道は「鷹巣駅」。


第三セクターに転換される前の秋田内陸縦貫鉄道はもともと国鉄阿仁合線で、駅名は「鷹ノ巣」駅でしたが、第三セクターになった際に「鷹ノ巣」から「鷹巣」に変更になりました。当時の町名であった「鷹巣町」にあわせたものと思われます。
しかし、「鷹巣町」は平成の大合併で2005年(平成17年)3月22日、森吉町・合川町・阿仁町と合併し北秋田市となりました。
北秋田市には世界各国の太鼓を展示している「大太鼓の館」があり、最も大きいものは直径3.80m、二番目に大きいものでも直径が3.71mあり、二番目に大きい太鼓は1989年(平成元年)に、「牛の一枚皮を使った世界一の和太鼓」(綴子大太鼓)ということでギネスブックに認定されているそうです。

糠沢 レ
糠沢駅は、綴子大太鼓が伝わる秋田県北秋田市綴子集落にある無人駅で、かつては貨車を改造した駅舎が利用されていましたが、2009年(平成21年)から綴子大太鼓の形を取り入れた新駅舎に生まれ変わりました。しかし、特急・快速列車は勿論、日中の上下合わせて6本と下り最終の普通列車が通過します。

早口 11:17着 11:17発
早口駅を出ると平地が広がり、左手に青森県八戸市に本社を置く、1921年(大正10年)創業の「吉田金物店」を前身とするとする「吉田産業」大館支店が見えます。

下川沿 11:21着 11:21発
雪の「大」の文字が浮かび上がる鳳凰山。かつて山嶺に鳳凰山玉林寺あったことにちなんで命名された大館市のシンボルとされる山です。
1968年(昭和43年)、当時の大館市長の発案により大文字の送り火を実施したことが始まりの大文字まつりは毎年8月16日に行われているそうです。
間もなく、大館駅に到着します。

大館 11:27着
定刻より7分遅れての到着。次の列車の発車時刻となっています。


急いで跨線橋を渡ります。
つづく。
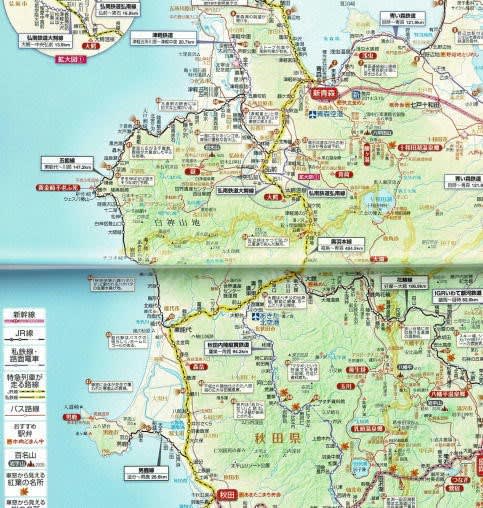
大館・弘前駅では7~8分の乗り継ぎ時間なので、ここで水分を確保します。
最近は、スープや味噌汁系の種類が多くなってきました。
「具たっぷり とん汁」、飲み物の域を超えています。

奥羽本線下り 普通 大館行
始発 秋田09:46
追分 09:59着 10:00発
1分程遅れての到着です。

大久保 10:06着 10:06発
この辺りは、男鹿半島が陸とつながるまでは海だったそうです。
田んぼを餌場にしているのは鷺でしょうか。

羽後飯塚 10:09着 10:10発
羽後飯塚駅のある旧飯田川町は、2005年(平成17年)の平成の大合併により昭和町、天王町と合併し潟上市となるまでは秋田県で一番小さな町で、二代秋田藩主佐竹義隆が神明社を建立した際に、御前で舞われた鷺舞が伝統芸能として伝わることからか、町の鳥は鷺だったそうです。

井川さくら 10:12着 10:12発
「芸名・人名だと勘違いしそうな実在の駅名ランキング」で第1位になったことがある駅です。
駅名は、駅から徒歩20分程の所にある桜の名所「日本国花苑」に由来するそうです。
「日本国花苑」は、1972年(昭和47年)4月に昭和天皇・皇后両陛下の御訪欧、秋田県立県百年、井川小学校統合校舎の建設を記念し、日本各地から集められた桜200種2,000本が2年がかりで植樹された公園だそうです。

八郎潟に注ぐ馬場目川を渡ると八郎潟駅に着きます。

八郎潟 10:16着 10:17発
五城目駅・一日市駅・八郎潟駅と名前を変えてきた駅。
話せば長くなる「八郎太郎伝説」が残るところでもあります。

八郎潟に沿ってきたに進んでいるのですが、見えているのは八郎潟の干拓地ではありません。

鯉川駅の手前で、八郎潟干拓事業によって残された3つの水域の一つ東部承水路が見えてきました。

鯉川 10:21着 10:22発
駅のフェンスに「橋本五郎文庫」の看板が見えます。
駅から徒歩15分程の所にある、みたね鯉川地区交流センター(旧鯉川小学校)に2011年(平成23年)4月29日に、三種町鯉川出身の読売新聞東京本社特別編集委員であり、テレビなどで御存知のジャーナリスト橋本五郎さんから寄贈された約2万冊の書籍と、地域の方々から提供された書籍によってオープンしたそうです。

次の鹿渡駅の位置は北緯40度2分40.69秒、東経140度4分57.25秒。
日本列島には緯度・経度線の分、秒以下の数値が0となる交差ポイントが陸上に39箇所存在し、これを「ポイントゼロ」と呼ぶそうです。
中でも、10度単位で交差する交点は1ヶ所。北緯40度0分0秒、東経140度0分0秒。場所は大潟村の中にあります。
北緯40度0分はこの辺りと思われます。

鹿渡 10:26着 10:27発
鹿渡駅を過ぎると八郎潟と離れます。
左手に見えるのは八郎潟ではありません。「角助沼」です。
周囲3.5kmの大きな池で、昔、ここに住んでいたカッパがいたずらをするので、角助という者が懲らしめたという伝説が残っているそうです。
「森岳ジュンサイの発祥の地」で、かつては「角助沼」にもジュンサイが自生していましたが、現在自生のジュンサイはなく、ハスの花が一面に咲くそうです。

森岳 10:32着 10:33発
北金岡 10:37着 10:37発
秋田自動車道をアンダーパスします。

東北電力の城火力発電所の煙突が見えると東能代駅に到着します。
発電所の煙突は赤白塗装と決まっていたのですが、なんでも航空法の改正でを受けて、高輝度障害灯を付けていれば、塗装色は自由に出来るようになりました。

東能代 10:43着 10:43発
東能代駅の能代市は、秋田県立能代工業高等高校のバスケットボールでの活躍が有名で、旧能代市時代の1989年度(平成元年度)からバスケットボールによる街づくり事業に取り組んでいます。東能代駅・能代駅のホームにはバスケットボードもあるのですが、歓迎の横断幕には「北限の茶畑」の文字が見えます。
日本茶の栽培の南限は沖縄県。北限は秋田県。栽培しているところは「秋田名物 八森ハタハタ 男鹿で男鹿ブリコ 能代春慶 桧山納豆 大館曲げわっぱ…」に出てくる、現在の能代市檜山町です。

東能代駅発車時点で、遅れが5分に広がっています。
東能代駅から進路を東に変えます。
白神の山々が見えます。

鶴形 10:48着 10:48発
戦後、仮乗降場を経て開業した駅です。
駅建設を想定していない、築堤のようなところに設けられたホームの高さに合わせるため、駅舎は鉄骨で組まれた高床の上に建てられています。

そんなに遠くないところを米代川が流れていますが見ることはできません。

富根 10:53着 10:53発
駅前にあるのは…。ロダンではないようです。
「考える少年の像」(昭和42年度富根中学校卒業記念制作作品)とのことです。
昭和44年4月1日に二ツ井町内6中学校が統合し、二ッ井中学校となっていますから、統合1年前の卒業制作のようです。

ここで、米代川を渡ります。

二ツ井 10:58着 10:59発
奥羽本線の前身、奥羽北線と同時の1901年(明治34年)11月1日に開業した駅です。
1922年(大正11年)から1936年(昭和11年)まで(正式には、1940年(昭和15年)3月1日に廃止。)は、駅前から米代川の川岸までの0.78kmに、中西徳五郎さんが敷設した軌間610mmの手押しトロッコ軌道「中西徳五郎経営二ツ井軌道」(個人経営であったため、正式名称が無かったとも言われています。)が荷物専用で、それまでの米代川水運と二ツ井駅との中継交通機関としての役を果たしていたそうです。
「食堂前田屋」。かつての駅前の賑わいを感じさせます。

明治天皇によって「徯后阪(きみまち阪)」と命名されたのは1882年(明治15年)。「きみまち阪」は県立自然公園に指定されている、サクラと紅葉の名所です。

二ツ井駅を出て藤琴川を渡ると徯后阪トンネルに入るため、「きみまち阪」は見えません。電車は、「恋文神社」の下を通っているようです。

前山 11:04着 11:05発
前山駅で、関係箇所への業務連絡のため少々停車というアナウンス。
そんなに時間も掛からず、5分遅れた発車。

至る所で白鳥を目にするようになりました。

右手に、本間様の「マルホン」の看板が見えてくると、秋田内陸鉄道線が合流して鷹ノ巣駅に着きます。


鷹ノ巣 11:09着 11:10発
JRは「鷹ノ巣駅」、秋田内陸鉄道は「鷹巣駅」。


第三セクターに転換される前の秋田内陸縦貫鉄道はもともと国鉄阿仁合線で、駅名は「鷹ノ巣」駅でしたが、第三セクターになった際に「鷹ノ巣」から「鷹巣」に変更になりました。当時の町名であった「鷹巣町」にあわせたものと思われます。
しかし、「鷹巣町」は平成の大合併で2005年(平成17年)3月22日、森吉町・合川町・阿仁町と合併し北秋田市となりました。
北秋田市には世界各国の太鼓を展示している「大太鼓の館」があり、最も大きいものは直径3.80m、二番目に大きいものでも直径が3.71mあり、二番目に大きい太鼓は1989年(平成元年)に、「牛の一枚皮を使った世界一の和太鼓」(綴子大太鼓)ということでギネスブックに認定されているそうです。

糠沢 レ
糠沢駅は、綴子大太鼓が伝わる秋田県北秋田市綴子集落にある無人駅で、かつては貨車を改造した駅舎が利用されていましたが、2009年(平成21年)から綴子大太鼓の形を取り入れた新駅舎に生まれ変わりました。しかし、特急・快速列車は勿論、日中の上下合わせて6本と下り最終の普通列車が通過します。

早口 11:17着 11:17発
早口駅を出ると平地が広がり、左手に青森県八戸市に本社を置く、1921年(大正10年)創業の「吉田金物店」を前身とするとする「吉田産業」大館支店が見えます。

下川沿 11:21着 11:21発
雪の「大」の文字が浮かび上がる鳳凰山。かつて山嶺に鳳凰山玉林寺あったことにちなんで命名された大館市のシンボルとされる山です。
1968年(昭和43年)、当時の大館市長の発案により大文字の送り火を実施したことが始まりの大文字まつりは毎年8月16日に行われているそうです。
間もなく、大館駅に到着します。

大館 11:27着
定刻より7分遅れての到着。次の列車の発車時刻となっています。


急いで跨線橋を渡ります。
つづく。









