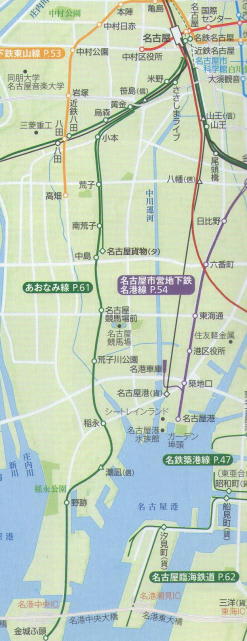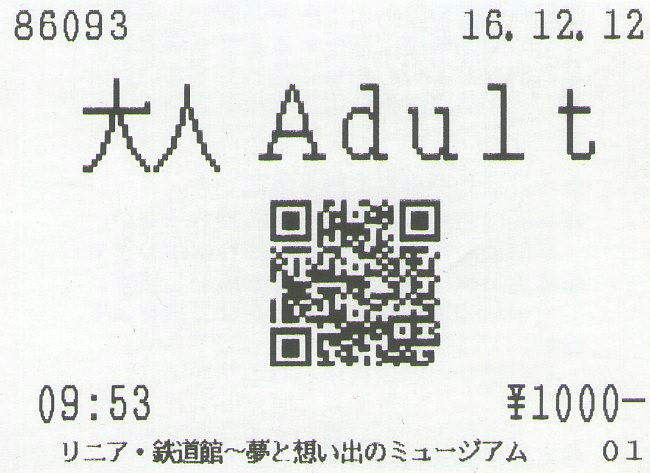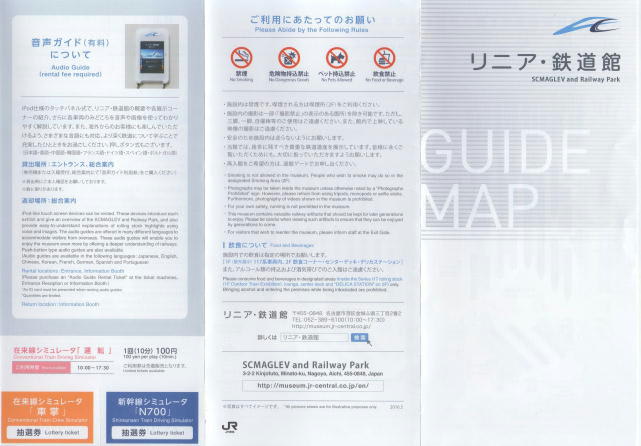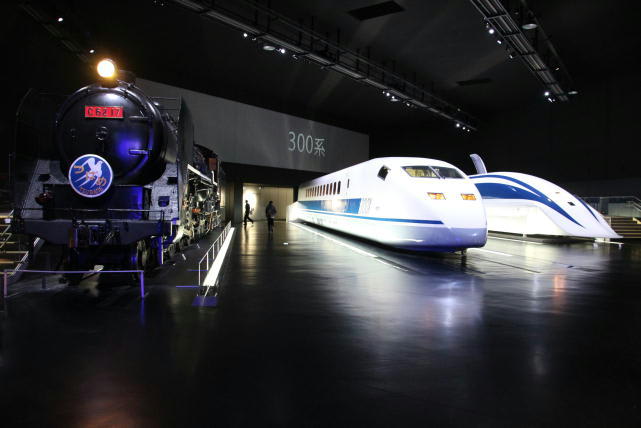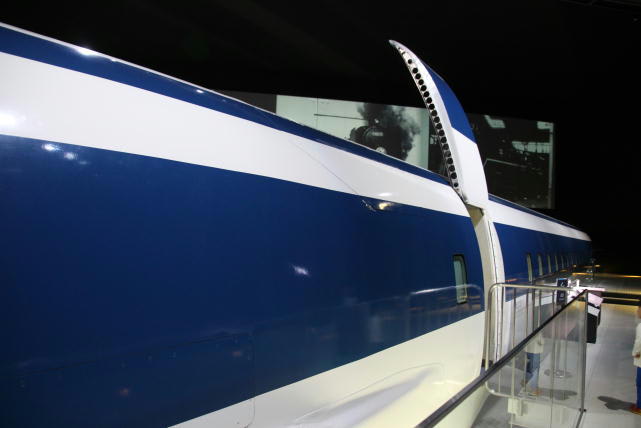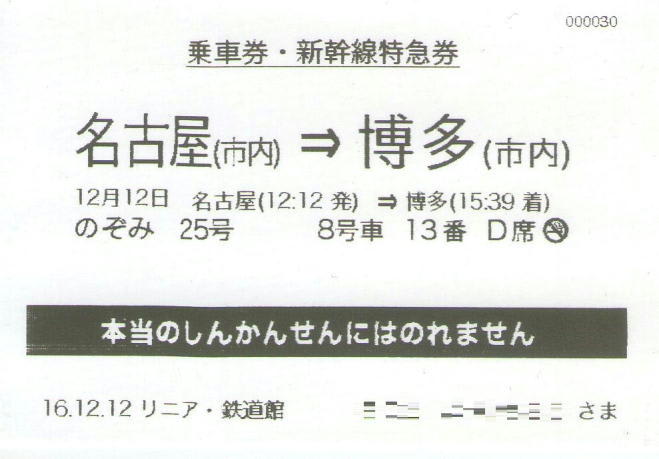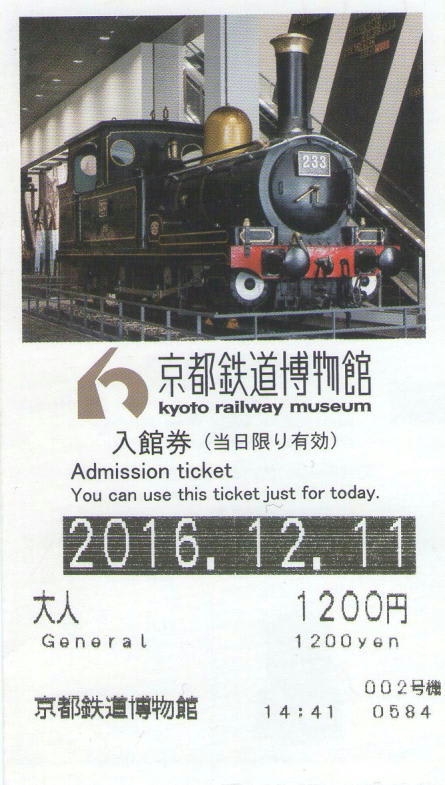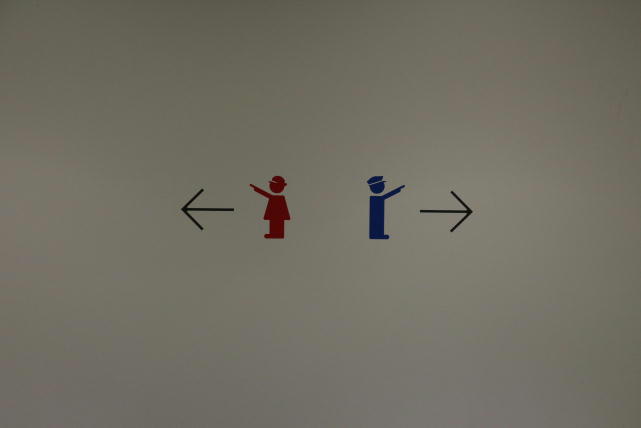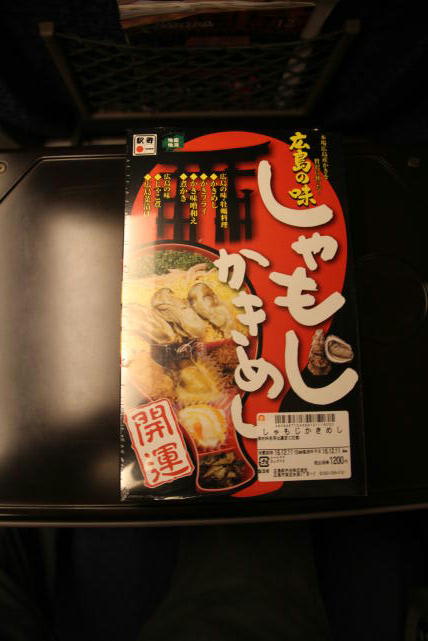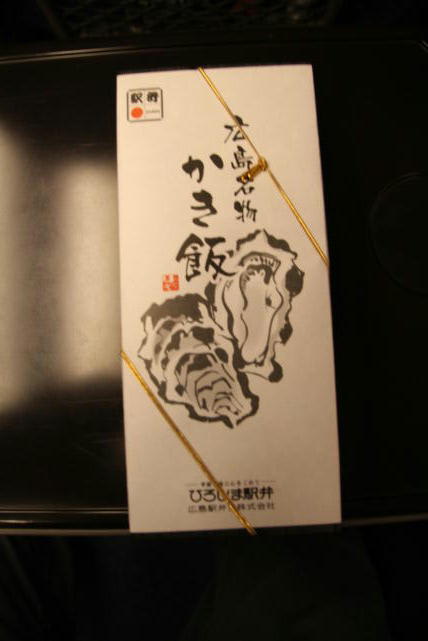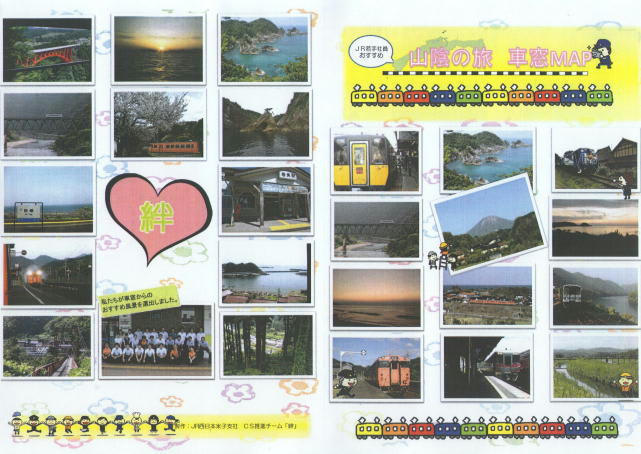浜原 07:47発
浜原駅までの最高速度は時速65kmでしたが、40~50kmぐらいのゆっくりしたスピードでした。浜原駅・口羽駅間の最高速度は時速85kmで、それに近いスピードで運転を始めました。

浜原駅の手前から潮駅の手前まで、江の川にある浜原ダム湖を避けるかのように、江の川から離れます。
 沢谷 07:51着 07:52発
沢谷 07:51着 07:52発

沢谷駅は「猿丸太夫」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。 「天武天皇に仕える猿丸太夫は、石見の国司として下ってきますが、途中、娘の秋姫を盗賊に奪われてしまいます。秋姫を取り戻すため盗賊と闘いますが、その闘いの中で過って太夫自らの手で秋姫の命を奪ってしまいます。秋姫の無念を晴らすため険しい山中をさまよい歩き、盗賊の岩屋を見つけ、見事盗賊を討ち滅ぼします。
地元の伝説をもとに創作された新作演目です。」
潮駅の手前で、進行方向右側に江の川が姿を現します。
 潮 07:57着 07:58発
潮 07:57着 07:58発

潮駅は「潮払い」。
「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「神楽を奉納するにあたり、舞台である「舞殿」を浄め、神々の降臨を願う舞です。幣と扇を持って舞う一人舞いで、基本的な舞の型が込められています。
二人での連舞の場合も増えてきました。」

三江線には大小いくつものトンネルがあります。
 石見松原 08:03着 08:03発
石見松原 08:03着 08:03発

石見松原駅は「戻り橋」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「平安時代、京の都において、戻り橋や羅生門に夜な夜な鬼が出没し、人々を苦しめていました。
そんな中、傘売りの善兵衛が商いをしますがなかなか売れず、あきらめたとき、一人の老婆が傘を求めてきます。快く傘を受け渡しますが、その正体は茨木童子という鬼でした。危うく襲われかけたとき、渡辺綱という武士が登場、茨木童子に戦いを挑みます。すると茨木童子は親分の酒呑童子を呼び出し大ピンチに。しかしそこへ坂田金時が加勢に来て、壮絶な戦いを繰り広げます。最後に綱が茨木童子の左腕を切り落とすと、鬼たちは虚空
飛天の妖術で住処の大江山に逃げていきます。」
江の川には鉄道橋も含めて100以上の橋がありますが、高梨大橋は唯一の斜張橋です。

「江の川鉄道」との愛称が付いているだけあって、常に江の川を見ながら進んでいる感じです。
 石見都賀 08:09着 08:10発
石見都賀 08:09着 08:10発

岩見都賀駅は「髪掛けの松」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「この物語は美郷町・蟠龍峡に伝わる伝説を神楽化したものです。鎌倉時代末期、石見初代小笠原四郎三河の守長親は足利の軍勢との合戦で功績のあった重臣、玄太夫宗利に恩賞として明日香姫を妻と与えます。しかし、宗利に好意を抱いていた小間使の水無月は、明日香姫を妬んで毒を盛ったため、明日香姫は醜い姿に。宗利は次第に妻を疎み、水無月に心惹かれていきます。明日香姫は水無月に恨みを晴らすべく、水無月を蟠龍峡へ誘い出し、激しい争いになりますが、差し違えたまま深淵に呑まれ果てていきます。そのとき、一本の松に髪が掛かり、残りました。二人を追って来た宗利は、自らの振る舞いを悔い、自害します。
その時、深淵に果てた明日香姫の怨霊が現れ、宗利を伴って昇天し、他界へと導いて行きます。長親とその妻・美夜姫はそれぞれの御魂を滝の明神として合祀するという悲恋の物語です。」
石見都賀駅を出ると徐々に高度が上がっていきます。
 宇都井 08:17着 08:17発
宇都井 08:17着 08:17発

山間を縫って走る線路上、この地区では地上に線路を敷くことができず、高架部分に作った駅です。
ホームと待合室は地上約30mのところにあり、日本一の高さであることから「天空の駅」と呼ばれています。
地上からホームまでは、エレベーターは無く、116段の階段で昇り降りするそうです。
過去には、ごく短い時間この駅で長い時間停車した列車もあったそうですが、今は全て短時間の停車です。

JR西日本の若手社員が作った「山陰の旅 車窓MAP」には、残念ながら三江線の車窓は採用されていませんでした。
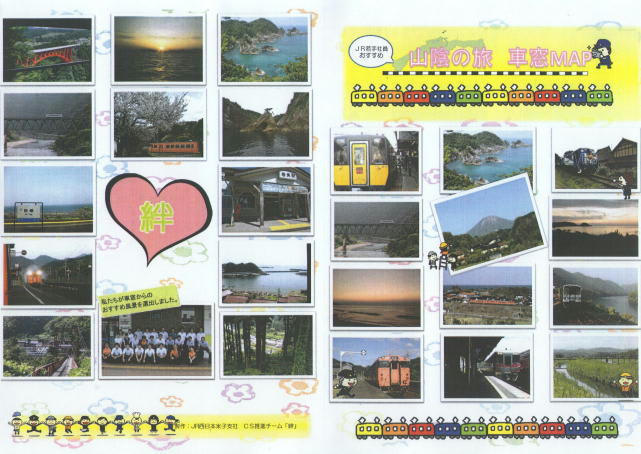

宇津井駅は「塵倫」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「「塵倫」という翼がある鬼が、異国から攻めてきて、空を飛び廻って人々を襲うので、第14代の帝・仲哀天皇が家臣・高麻呂とともに弓矢で射止めます。
仲哀天皇は神話の英雄・日本武尊の第二子です。
この神楽は鬼舞の代表的な人気演目ですが、地域によって解釈は様々。三江線沿線の神楽ルートでも、様々な姿の塵倫を見ることが出来ます。
 伊賀和志 08:22着 08:22発
伊賀和志 08:22着 08:22発
この辺りは県境付近を線路が通っているため、伊賀和志駅は広島県にありますが両隣の駅は島根県となります。
地名で「伊賀」といえば思い浮かぶのは三重県ですが、ここは「いかわし」。「いかわし」とは、江の川の蛇行地形「いかわち」からという説と、江の川がこのあたりでよく洪水が起こる「イカラセ(怒瀬)」からという説があるようですが、いずれにしてもこの辺りの地形に由来する地名のようです。

ここは、環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧種に指定されている「ブッポウソウ」
を見ることができる駅でもあるようです。

伊賀和志駅は「鈴合せ」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「この舞は、鎌倉時代、静御前が鶴ヶ岡八幡宮で演じた舞を取り入れ構成したと伝えられています。
八種類の舞で構成され、一の舞二の舞を「四花の舞」、三の舞を「静の長唄」、四の舞を「めごし」、五の舞を「かけりしず」、六の舞を「四季の舞」、七の舞を「くみづえの舞」、八の舞を「八花の舞」と称し、これらを集めて一つの舞としていることから、「八寄」、さらに転じて別名「やよし」と言われています。」
岩見都賀駅から口羽駅までは、一駅毎に江の川を渡ってきました。
 口羽 08:25着 08:25発
口羽 08:25着 08:25発
蛇行する江の川に対して、直進する三江線。江の川からはやや離れたところに口羽駅があります。

口羽駅は「神降し」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「神楽奉納の始めに舞われる儀式舞です。「深山の真榊」「百浦の潮」という清浄な物で、神楽殿の四方と中央を清め、神々をお招きするという神聖な演目であり、厳かに大切に舞い継がれています。」
再び江の川に沿って進みます。
 江平 08:32着 08:33発
江平 08:32着 08:33発

江平駅は「五龍王」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「青赤白黒の4人兄弟の龍王達は東西南北と四季を司っていました。しかし末子の黄龍王には何も領分がなく、その「使い」が「領分を分けてほしい」と尋ねてきますが、追い返します。いよいよ黄龍王が荒々しく登場し、領地を分けるよう迫りますが、四節などの哲理を論じて退けられ、ついに怒った黄龍王は兵を挙げます。兄達もそれぞれ数十万の軍勢を集め、天地を揺るがす大戦乱となります。
しかし、最後は天界から降り来た文選博士が、土用と中央を新たに分配し、五等分に収めるという壮大な物語です。口上は膨大で、四季や農事に因んだ哲学が組み込まれている重要な演目です。」
宇津井駅を過ぎた辺りから、江の川が島根県と広島県の県境になっていて、それが作木駅を過ぎるところまで続いています。
対岸は、広島県です。
 作木口 08:36着 08:37発
作木口 08:36着 08:37発

作木口駅は「胴の口」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。 「囃子方だけで演じられる神楽で、最初は厳かに、中頃は優雅に、後段は華やかに演奏され、全ての神楽囃子が組み込まれています。
かつては奉納神楽において始めに奏された演目です。」
一時弱まった雨も、再び強くなってきました。
 香淀 08:45着 08:46発
香淀 08:45着 08:46発

ログハウス調の駅舎です。

香淀駅は「羅生門」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「「戻り橋」において左の腕を切り取られた茨木童子の為、鬼の大将・酒呑童子は腕を切った張本人である渡辺綱の乳母に化け、まんまと綱の館に忍び込み、腕を取り返して茨木童子にもみ付けます。
事態に気づいた綱は戦いを挑みますが、鬼の妖術に苦戦。主君の源頼光も駆けつけますが、鬼達は虚空飛天の術で住処の大江山に逃げていきます。」
江の川も中流域でしょうか、だいぶ様子が変わってきました。
 式敷 08:50着 08:51発
式敷 08:50着 08:51発
式敷駅は「滝夜叉姫」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「天慶の乱で討たれた平将門の娘・五月姫は父の無念を晴らすため、京都貴船明神に願掛けし、妖術を授かります。その後「滝夜叉姫」と名を変え、夜叉丸・蜘蛛丸と共に「相馬城」を根城に謀反を企てます。しかし、陰陽師大宅中将光圀によって妖術は破られ、鬼女となって立ち向かいますが、あえなく討ち取られてしまいます。
美しい姫から一瞬にして鬼に変化する技が冴える人気演目です。」
沿線でよく見るのが、石洲瓦の屋根にある鯱。海に住む由来から防火のしるし、そして家の守り神としてのせているようです。
 信木 08:54着 08:54発
信木 08:54着 08:54発

信木駅は「子持山姥」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「東国を平定に向かう源頼光と渡辺綱。信州(長野県)明野山で宿を求めた場所は、山姥の屋敷でした。山姥は息子・怪童丸とともに人をだましては財宝を奪う山賊であり、夜更け、頼光らに襲い掛かります。
激しい戦いの末、とうとう頼光達の武勇に屈した二人。山姥は、昔、都の武士の妻であり、夫亡き後都を追われた悲しい身の上である事を語り、「我が子だけは」と怪童丸の助命を必死に乞います。親子の情にうたれた頼光は怪童丸の腕を見込み、家来にしま
す。そして山姥は奥山に姿を消すのでした。
怪童丸はのちに「坂田金時」となり四天王として大活躍します。子を思う母の姿に思わずホロリとしてしまう演目です。」
所木 08:57着 08:58発

所木駅は「玉藻の前」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「平安時代、天竺(インド)や唐(中国)で国家を揺るがした金毛九尾狐が日本に渡来し、坂部庄司蔵人の娘に乗り移って「玉藻の前」を名乗ります。成長するにつれその美貌は増し、ついに鳥羽上皇の寵愛を一身に受けるようになります。しかし上皇は次第に身心が衰弱したため、陰陽師・安倍清明泰親は玉藻の前に詰め寄りますが、言葉巧みにかわされます。そこで賀茂明神の加護を得て、ついにその正体を見破りますが、九尾狐は那須野ヶ原(栃木県)に飛び去ります。
泰親と玉藻の前の火花を散らす問答の場面は見逃せません。」
 船佐 09:01着 09:01発
船佐 09:01着 09:01発
船佐駅は「悪狐伝」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「都を追われ、那須野ヶ原に逃げ込んだ金毛九尾狐は、十念寺の和尚をだまして取り食らうなど悪事を重ねますが、帝の命令を受けた弓の名人、三浦介・上総介によって討ち取られます。
珍斎和尚はアドリブ全開の道化役。九尾の狐も客席になだれ込んで大暴れ。笑いあり怪しさありの、楽しい演目です。」
屋根には鯱だけでなく、空に向かって足高く揚げた唐獅子も見ます。獅子は、風水であらゆる邪気の侵入を防ぐ「吉祥瑞獣」と言われているそうです。


 長谷 09:06着 09:06発
長谷 09:06着 09:06発

長谷駅は「鍾馗」。
「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のようにのっています。

「素盞鳴尊が唐の国(中国)に渡ったとき「鍾馗」と名乗って病魔を退治しますが、その一族・春夏秋冬の病原体である「大疫神」が日本に渡って暴れるので、厄払いの茅の輪と宝剣で再び退治するという筋立てです。
無病息災を願うこの演目は、地味な二人舞ながら、重厚かつ勇壮な舞であり、とても大事にされています。」
 粟屋 09:11着 09:12発
粟屋 09:11着 09:12発

粟屋駅は「曽我兄弟」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「だまし討ちにあった父・河津三郎祐泰の遺恨を晴らすため、曽我十郎祐成・五郎時致兄弟は涙ながらに引き留める母を説得し、宿敵・工藤佐衛門尉祐経に立ち向かいます。鬼王丸の助太刀を得て、兄弟は見事に父の仇を討ち、本懐を遂げるのでした。
日本人の人情に訴える悲しくもたくましい物語です。」
江の川を渡る最後です。遠くに三次市街が見えます。
 尾関山 09:17着 09:18発
尾関山 09:17着 09:18発

尾関山駅は「紅葉狩」。

「ぶらり三江線WEB」の「神楽愛称駅名演目解説」には、次のように書かれています。
「平維茂は信州(長野県)戸隠山で鹿狩りをしていましたが、道に迷ってしまいます。
その様子をうかがう戸隠山の鬼女・白蜘蛛・赤蜘蛛は、早速「良き獲物」の到来を鬼女大王に知らせます。
鬼女達は紅葉狩に興じる美女に化け、維茂を酒宴に誘い込みます。色香に惑わされてしまった維茂は、どっぷりと酔い眠ってしまいますが、夢に八幡大菩薩が現れて美女の正体が鬼女であることを告げ、神剣を授けます。
目を覚ました維茂は、すぐさま鬼女たちに立ち向かい、見事に退治するのでした。
3人の妖艶な姫の登場には思わず息を呑みます。」
尾関山駅を出て、江の川支流の馬洗川を渡ると左にカーブします。

右手から芸備線が合流すると、間もなく終点三次駅に到着します。
 三次 09:21着
三次 09:21着

つづく