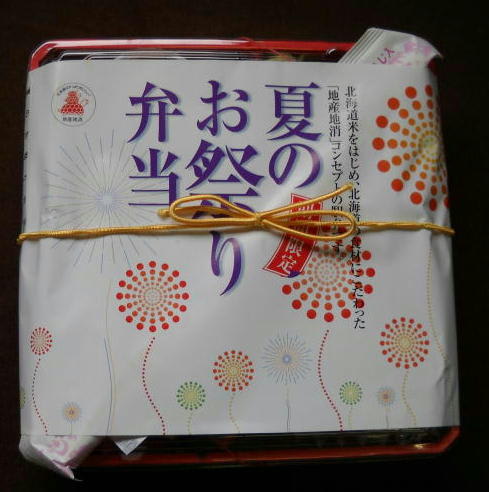今度の列車は、宗谷本線名寄行き普通列車
○旭川 14:18発
・旭川四条 14:22着 14:22発
・新旭川 14:25 14:26
・永山 14:32 14:33
・北永山 14:36 14:37
・南比布 14:41 14:42
・比布 14:46 14:47
・北比布 14:51 14:51
・蘭留 14:55 14:56
・塩狩 15:05 15:05
・和寒 15:13 15:16
・東六線 15:21 15:21
・剣淵 15:26 15:26
・北剣淵 15:31 15:32
・士別 15:36 15:37
・下士別 15:42 15:42
・多寄 15:47 15:47
・瑞穂 15:51 15:51
・風連 15:55 15:57
・東風連 16:02 16:02
○名寄 16:07着
先行する稚内行き特急サロベツが遅れたため、定刻から10分遅れて、14時28分に名寄行が出発しました。


新駅舎・高架化工事中の旭川を出て高架橋との接続地点を過ぎると、高架線上にある旭
川四条。

旭川四条を過ぎ、牛朱別川を渡って高架を下りると新旭川。左手に、日本製紙旭川工場の煙突が見えます。

新旭川で、網走方面の石北本線と分かれて宗谷本線は北上します。

永山は、ここに入植した屯田兵の指揮官の姓を取ったとか。
北永山を過ぎ、石狩川を渡るころ、左手に男山を見ることが出来ます。南比布、比布、北比布と直進します。


比布は、ピップエレキバンのCMで有名になった駅で,CMが放映されていた当時は観光客で賑わったそうですが、今は訪れる人も少なくなったようです。駅舎は比布名産のイチゴをイメージたピンク色に塗られていました。

左手に、道央自動車道比布ジャンクションが見えてくると、まもなく蘭留。

蘭留の地名は、アイヌ語のラン・ル(下る道)に由来するそうで、塩狩峠から下ったところにあります。
列車はこれから、塩狩峠越えに入ります。
線路は高いところを走り、両側を針葉樹の防雪林に囲まれ、右へ左へとカーブを切り登っていきます。特に眺めは良くありませんが、線路脇の木は切り払われて開放感があります。

こうして峠を登りきったところに塩狩駅があります。

塩狩峠は、明治42年2月、峠を走行する列車の連結器が外れ、レール上に身を投じて殉職した若き国鉄職員の悲話を基にした、三浦綾子の小説『塩狩峠』で有名になったところです。駅周辺には、遺徳顕彰碑や三浦綾子の旧宅を復元した塩狩峠記念館があります。

塩狩を出ると、峠の坂道を転げ落ちるように走り、やがて視界が開けて市街が見えてくると、和寒到着。
和寒の地名は、アイヌ語のワット(楡の木)サム(傍)が由来とのこと。
特急が停車する駅で、ホームが舗装されていました。

和寒を出ると、平行する国道40号線の向こうに和寒小学校の尖塔が見えました。北海道の学校や公共施設では、このような尖塔のある建物をよく見ます。

和寒の次は、東六線。いかにも北海道らしい駅名です。
道東や道北では、西○条とか東○線という番地がよくあります。これは未開の地を開拓するときに、まず碁盤の目のように道路を造って区画し、その区画線に番号を順に振っていったことから、このような番地になったそうです。
ただし、東六線駅の住所は「北海道上川郡剣淵町第10区」だそうです。
次の剣淵から北剣淵を通って士別まではほぼ一直線に走りますが、両側に防雪林などがあって、景色を楽しむことはできません。そのうちに、雨も落ちてきました。
剣淵川を渡るとまもなく士別です。

「羊のまち SUFFOLK LAND 士別へ ようこそ」の看板。

サフォークとは羊の種類で、士別市では観光やまちおこしの為に、サフォーク種めん羊が飼われていて、観光牧場のほかに、羊毛を利用した手作り製品を作ったり、手作り体験ができるほかに、羊肉を使った士別オリジナルの料理が楽しめるそうです。
サフォークは、野辺地町にある柴崎観光牧場で飼われていたことがあったようですが、今は定かではありません。
士別を出ると天塩川を渡り下士別を通り多寄まで、線路は正確に真北を向いて一直線に走り道路も正確に東西南北を向いた碁盤の目で、ほぼ同じ間隔で直線の道路が線路を横切ります。


瑞穂は、田園の中にぽつんと木造の短いホームや待合室がある駅で大変のどかな雰囲気です。

風連の駅は比較的新しく、窓ガラスが多く、その窓越しに一直線に伸びる駅前の通りが見えました。

東風連駅の待合室はプレハブですが、ホームは舗装されていました。

東風連を過ぎ、徐々に家の密度が高くなってくるとまもまく名寄に着きます。名寄には4人を乗せて定刻16時7分に到着しました。

次の列車までは37分の待ち合わせ。
名寄の地名は、アイヌ語のナイ・オロ・プト(渓流に注ぐ川)で、名寄川が天塩川に合流するところからついたと言われています。
駅前の表示では気温は22.7度。時折雨が降るあいにくの天気です。

つづく
○旭川 14:18発
・旭川四条 14:22着 14:22発
・新旭川 14:25 14:26
・永山 14:32 14:33
・北永山 14:36 14:37
・南比布 14:41 14:42
・比布 14:46 14:47
・北比布 14:51 14:51
・蘭留 14:55 14:56
・塩狩 15:05 15:05
・和寒 15:13 15:16
・東六線 15:21 15:21
・剣淵 15:26 15:26
・北剣淵 15:31 15:32
・士別 15:36 15:37
・下士別 15:42 15:42
・多寄 15:47 15:47
・瑞穂 15:51 15:51
・風連 15:55 15:57
・東風連 16:02 16:02
○名寄 16:07着
先行する稚内行き特急サロベツが遅れたため、定刻から10分遅れて、14時28分に名寄行が出発しました。


新駅舎・高架化工事中の旭川を出て高架橋との接続地点を過ぎると、高架線上にある旭
川四条。

旭川四条を過ぎ、牛朱別川を渡って高架を下りると新旭川。左手に、日本製紙旭川工場の煙突が見えます。

新旭川で、網走方面の石北本線と分かれて宗谷本線は北上します。

永山は、ここに入植した屯田兵の指揮官の姓を取ったとか。
北永山を過ぎ、石狩川を渡るころ、左手に男山を見ることが出来ます。南比布、比布、北比布と直進します。


比布は、ピップエレキバンのCMで有名になった駅で,CMが放映されていた当時は観光客で賑わったそうですが、今は訪れる人も少なくなったようです。駅舎は比布名産のイチゴをイメージたピンク色に塗られていました。

左手に、道央自動車道比布ジャンクションが見えてくると、まもなく蘭留。

蘭留の地名は、アイヌ語のラン・ル(下る道)に由来するそうで、塩狩峠から下ったところにあります。
列車はこれから、塩狩峠越えに入ります。
線路は高いところを走り、両側を針葉樹の防雪林に囲まれ、右へ左へとカーブを切り登っていきます。特に眺めは良くありませんが、線路脇の木は切り払われて開放感があります。

こうして峠を登りきったところに塩狩駅があります。

塩狩峠は、明治42年2月、峠を走行する列車の連結器が外れ、レール上に身を投じて殉職した若き国鉄職員の悲話を基にした、三浦綾子の小説『塩狩峠』で有名になったところです。駅周辺には、遺徳顕彰碑や三浦綾子の旧宅を復元した塩狩峠記念館があります。

塩狩を出ると、峠の坂道を転げ落ちるように走り、やがて視界が開けて市街が見えてくると、和寒到着。
和寒の地名は、アイヌ語のワット(楡の木)サム(傍)が由来とのこと。
特急が停車する駅で、ホームが舗装されていました。

和寒を出ると、平行する国道40号線の向こうに和寒小学校の尖塔が見えました。北海道の学校や公共施設では、このような尖塔のある建物をよく見ます。

和寒の次は、東六線。いかにも北海道らしい駅名です。
道東や道北では、西○条とか東○線という番地がよくあります。これは未開の地を開拓するときに、まず碁盤の目のように道路を造って区画し、その区画線に番号を順に振っていったことから、このような番地になったそうです。
ただし、東六線駅の住所は「北海道上川郡剣淵町第10区」だそうです。
次の剣淵から北剣淵を通って士別まではほぼ一直線に走りますが、両側に防雪林などがあって、景色を楽しむことはできません。そのうちに、雨も落ちてきました。
剣淵川を渡るとまもなく士別です。

「羊のまち SUFFOLK LAND 士別へ ようこそ」の看板。

サフォークとは羊の種類で、士別市では観光やまちおこしの為に、サフォーク種めん羊が飼われていて、観光牧場のほかに、羊毛を利用した手作り製品を作ったり、手作り体験ができるほかに、羊肉を使った士別オリジナルの料理が楽しめるそうです。
サフォークは、野辺地町にある柴崎観光牧場で飼われていたことがあったようですが、今は定かではありません。
士別を出ると天塩川を渡り下士別を通り多寄まで、線路は正確に真北を向いて一直線に走り道路も正確に東西南北を向いた碁盤の目で、ほぼ同じ間隔で直線の道路が線路を横切ります。


瑞穂は、田園の中にぽつんと木造の短いホームや待合室がある駅で大変のどかな雰囲気です。

風連の駅は比較的新しく、窓ガラスが多く、その窓越しに一直線に伸びる駅前の通りが見えました。

東風連駅の待合室はプレハブですが、ホームは舗装されていました。

東風連を過ぎ、徐々に家の密度が高くなってくるとまもまく名寄に着きます。名寄には4人を乗せて定刻16時7分に到着しました。

次の列車までは37分の待ち合わせ。
名寄の地名は、アイヌ語のナイ・オロ・プト(渓流に注ぐ川)で、名寄川が天塩川に合流するところからついたと言われています。
駅前の表示では気温は22.7度。時折雨が降るあいにくの天気です。

つづく