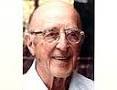バリデーションはアメリカのソーシャルワーカー、ナオミ・フェイルさんが開発したもので、重度の認知症患者が劇的に回復した等の実績が報告されて、注目を集めているコミュニケーション法です。
バリデーションは元々「確認する、強くする、認める」の意味に用いられますが、フェイルさんによると、認知症の人の「経験や感情を認め、共感し、力づける」意味でこの言葉を
用いているそうです。
バリデーションのテクニックの一部を書き出してみますと
1.アイコンタクト
アイコンタクトを取ることで、安心感を持ってもらうことができます。
2.言うことをそのまま繰り返す
つじつまの合わない言葉であっても否定せず、そのまま疑問形にして繰り返します。すると「自分の言うことを聞いてくれた」と感じてもらうことができます。
3.思い出話をする
認知症になっても、昔の記憶は残りやすい傾向があります。昔の思い出を話すことで、感情的に落ち着くことが期待出来ます。
4.やさしく触れる
完全に会話ができなくなった人でも、やさしく手を握ったりして「ここに家族がいる」と知らせると安心できます。
*上記のテクニックは、あくまで相手の気持ちに寄り添うことが目的です。介護する側が疲れていたりするときには、無理に行う必要はないとのことです。 出所:日本バリデーション協会資料
1と2はロジャーズの来談者中心療法と通じるところがあり、興味をひかれました。優れた理論は時代と状況を超越して生き続けるものだと痛感します。
人の話を聴いて自分の意見を述べるときは 「いいえ、そうではなくて・・・・」でも 「はい、でも・・・・」でもなくて 「はいそうですね、そして・・・・」とまず相手の話を肯定して それに自分の主張を加えて返すことが円滑な話法である ということは私自身が研修の講師として話してきたことなのですが・・・・やってしまいました!
まずはA信用金庫での経営相談会 支店長立会のもと 新規顧客見込みB社の 2代目若社長から話を聞くや従来のマーケティング戦略を全否定し 滔々と自説を陳述してしまいました。完全に相手のプライドを傷つけてしまい顧問契約は白紙。
私の経験が最大限に活かせる最高の案件であり クライエントにも多大な利益が見込めるものであっただけに残念です。
もう1件は 現在顧問を務めるC社 これもY社長の定着対策をヒヤリングするや真向から批判し 顔色が変わるのが解りました。 次回面談でフォローしないと 今年末で切れる契約の延長は無くなります。
どうも私は話が 自分の得意(と思われる)分野に入ると 謙虚さを失い暴走してしまうようです。
古希(70歳)を6年過ぎても ちっとも枯れて(円熟して)いない自分に愕然とします。
これを自戒し手帳の1ページ目に 表題の言葉を記した次第です。
キャリアコンサルティング協議会技能検定部長 庄子芳宏先生の
セミナーから引用しました。
表題はロジャーズが 晩年に語ったという言葉です。カウンセラーにとって最も大切なことを1つだけあげるならばそれは「presence(目の前にいる)」であるということです。「全ての理論や、技巧を超越して クライエントという一人の人間の前に ひたすらその話を聴くだけのために一人の人間として存在すること」
シンプルではありますが 実に味わい深い言葉です。
その他興味く感じた先生のコメントは
・講演の名手はスピーカーとして磨かれるため、カウンセラーとしては技量が落ちる
・本当の共感は難しい(実現はほとんど不可能であり努力目標)、むしろ違和感(共感できない部分)を大切にした方が良い
違和感を伝えることは時に、本当に傾聴して理解したという伝え返しとして相手に受け取られ、真の自己一致につながる
・ピアカウンセリング(仲間内で行うトレーニング)はライブ(架空のモデルではなく実際の悩み)で行った方が勉強になる
・シンクロ(呼吸や姿勢、話す速度等を相手に合わせる、真似すること)はクライエントとの距離を縮める
等です。
 これは解決志向ブリーフセラピー(Solution Focused Brief Therapy →SFBT)の
これは解決志向ブリーフセラピー(Solution Focused Brief Therapy →SFBT)の
「4つの発想の前提」のひとつです。(画像は創始者ミルトン・エリクソン)
SFBTに関する お勧め一押しの 参考文献は「<森・黒沢のワークショップで
学ぶ>解決志向ブリーフセラピー 2002ほんの森出版」です。これ1冊で
十分と言えるほどエッセンスが簡潔にまとめられており、しかもエピソードも
満載で、面白く読みやすい、まさに名著だと思います。
この本から要点だけ書き出しますと
1.問題には極力焦点を当てず、即 解決に焦点をあてて「より良き未来の状態を
手にいれること」に全力を傾注し 従来の療法と比較すると衝撃的とも言える
くらいブリーフ(短期)に解決に導くセラピーである
2.中心哲学(3つのルール)
①もしうまくいっているのなら、変えようとするな
②もし一度やって、うまくいったのなら、またそれをせよ
③もしうまくいっていないのであれば、(なんでもいいから)違うことをせよ
3.四つの発想の前提
①変化は絶えず起こっており、そして必然である
②小さな変化は、大きな変化を生み出す
③「解決」について知る方が「問題や」「原因」を把握することよりも有用である。
④全てのクライエントは、解決のためのリソース(資源、資質)を持っており、
解決のエキスパートである
4.面接マニュアル(5つのステップ)
①クライエントとセラピスト(カウンセラー)関係の査定(アセスメント)
②ゴールについての話し合い
③解決に向けての有効な質問(ソリューショントーク)
④介入
⑤ゴール・メンテナンス
産業カウンセラー協会講師渋谷武子先生のセミナー「ロジャーズの課程尺度を学ぶ」を
受講しました。
ロジャーズは、カウンセリングを受け続けている人々の初期の自己像と終結時の
自己像とを比べたとき、ある一つの傾向があることに気づきました。それは性にも
学歴にも社会的地位にもそのほかのあらゆる条件にも関係なく、全ての人間に同じに
認められるものでした。彼はこの傾向を数字で置き換えました。そのための物差しが
「課程尺度」と言われています。(岸田博:写真 来談者中心カウンセリング私論)
岸田先生の著作からの抜粋をテキストにして演習を行いました。ロジャーズが
ストランドと呼んだ、7つの要素・要因をそれぞれ7つの課程段階で評価し、
計49のどの段階にあるか判定するものです。
ちなみに7つのストランドとは
1.感情の個人的意味
2.体験課程の様式
3.不一致の度合
4.自己の伝達
5.自己構成概念
6.問題の関係
7.対人関係 で
7つの課程段階とは
不適応から適応、固定から流動への課程段階です。
この課程尺度を利用することにより
CLがどの段階にいるか知ることが出来、適切なスキルの選択等が可能になります。
私の友人で認知行動療法が効果を発揮できなかった事例が2件続きましたが
この知見を得ることで 永年の疑問が氷解しました。
すなわちCLが認知行動療法を行う課程に至っていなかったということです。
法政大学教授 末武康弘先生のセミナー「来談者中心療法」を受講しました。
末武先生はカール・ロジャーズ(写真)の弟子であり「フォーカシング」
の創案者であるジェンドリンとは米国の自宅にも招かれ、帰国後も文通を
重ねるような交友関係がありました。表題は先生がジェンドリンから直接
聞いた言葉とのことです。
少し補足しますと「カウンセリングを通してクライエントは日々進化する。
たとえ僅かずつであっても個体がより良く変化をすればそれは周辺にさらなる
変化の連鎖を生み それが長い期間蓄積されればダーウィンが唱えた人間の
種としての進化を促す」というものです。カウンセリングに携わる人々の
背中を押す スケール感のある言葉だと思います。
今回の講義で特徴的であったのは 末武先生が ロジャーズの理論(思想)と
ジェンドリンのそれとを一体として捉えているということです。これは先生の
習学歴からくるのでしょうが ロジャリアンの末席を自任するわたくしにとって
フォーカシングをもう少し勉強してみようとの刺激剤となりました。
復習を兼ねてロジャーズによる「人格変化の生起のための必要にして十分な条件」
をあげておきます
1.クライエント(CL)とカウンセラー(CO)との間に心理的接触がある
2.CLは不一致の状態にあり、傷つきやすく、不安の状態にある
3.COはその関係のなかで一致しており、統合していること
4.COはCLに対して無条件の受容(肯定的配慮・関心)を経験していること
5.COはCLの内的照合枠を共感的に理解しており、この経験をCLに伝えようと
努めていること
6.COの4と5の状態が最低限CLに伝わっていること
ジェンドリンは「カウンセリングで、第一に重要なのはCLとCO関係性であり、
第二が傾聴で、ようやく三番目にくるのがフォーカシング等の技法である」としています。
目白大学黒沢幸子教授の「解決志向ブリーフセラピー」セミナーから引用しました。
ワークと事例紹介がメインのためここに多くをご紹介出来ないのが残念ですが、
差しさわりのない部分から、いくつか書き出します。
*今も大切にしている恩師霜山先生の淘訓: 臨床のスタンス
・〇〇ist、△△ianになるな
・Specialistになるな、Generalistたれ
生活者としてのセンス、声なき市井の声
・Professionalであるために
医学と古今東西の人間の営み(芸術・文芸・神話等)から学べ
・一度は何かの療法にコミットせよ、その後、自分の臨床をつくれ
*臨床に役立つ発想の芽
・相手のリソースを活かす
・自分のニーズが先にありきになっていないか?(専門家中心主義の戒め)
・相手の生活環境を理解する
生態学的社会文脈の中での理解、コミュニティ感覚
・その人らしく生きる、輝く・・・何でもありだな
表題は 1級キャリア・コンサルティング技能士でアサーション認定トレーナー
文川実先生のセミナーにおけるお言葉です。
アサーションとは、「自分も相手も大切にしながら、素直に、正直に、その場に
ふさわしい方法で、自分の気持ちや考え、意見などをつたえようとすること」を
意味します。このことは、誰にとっても欠かすことのできない大切な考え方や
スキルです。
著作権の関係であまり書けませんのでカリキュラムを書き出しておきます
・アサーションとは
・アサーション権
・認知とアサーション
・日常会話のアサーション
・課題解決のアサーション
・非言語上のアサーション
・感情とアサーション
日本産業カウンセラー協会講師 中台英子先生の「職場のメンタルヘルス事例検討」セミナーを受講しました。
表題はインテーク(初回)面接でリファー(この場合精神科医への治療依頼)が必要と見立てたクライエントで 精神科受診に抵抗を示す方への対処法を述べた珠玉の名言です。
具体的な事例検討のため その内容を発表できないのは非常に残念ですが温かい人間愛、そして数十年にわたる実践と成果に裏付けられた テクニックのコラボレーションには眼から鱗が落ちまくりの6時間でした。
文教大学人間科学部臨床心理学科 布柴靖枝教授の「家族療法の理論と実際」のセミナーを
受講しました。
家族療法で特徴的なことは
*家族を「クライエント」とみなす
*家族の中で問題を抱えている人のことを「IP(アイピー)」と呼ぶ
identified patient
*IPの心の問題は、家族システムが機能不全を起こしている信号と捉える
*犯人捜しをしない
・家族を責めない姿勢
・家族と協働して問題解決を図ろうとする姿勢
*家族を見立てること
・何が問題、症状を維持させているか?
・問題解決のためにできる小さな変化をおこすためには何が出来るか?
よく使われる技法としては
①ジェノグラム(多世代学派): 3世代以上の家系図を作成し当該家族の
家族神話(意識的、無意識的に世代伝達され、個人の価値観、感情を
規制し、独自の世界観を形成している家族の物語)を探る
②リフレーミング(ミニューチン): 言い換えにより現象に対する見方を変化させる技法
例 頑固→信念がある
その他
③スケーリングクエスチョン(SFA)
④コーピンングクエスチョン(SFA)
⑤例外探しと Do differennt (SFA)
⑥問題の外在化、物語の書き換え(ナラティブ)
等の技法が多用されています
家族療法は以上のように多くの心理療法を活用した統合的もしくは折衷的療法
であるといえましょう