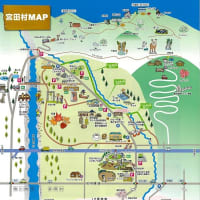久しぶりの“『伊那路』を読み返して”である。
『伊那路』昭和40年5月号に堀口貞幸氏が「枝義理」について報告している。枝義理については本日記でも何度となく触れてきたもので、わたしとしても興味深く調べてはいるものの、道半ばとなっている課題の一つである。その枝義理を扱ったものが『伊那路』に掲載されていたことを全く知らなかった。堀口氏は『伊那路』の過去記事を引用しており、それは『伊那路』昭和38年3月号に掲載された「鳥山家の不幸見舞受納帳」である。それにはいわゆる香典帳がもれなく掲載されており、言ってみれば個人情報であって、今ではとても掲載できない内容であるが、堀口氏も言うようにとても興味深い内容である。とりわけこれを報告した小池修兵氏も書いているように「葬儀の際のこの地方の風習などもわかる良い資料」である。単純に香典帳を写し取ったものであるが、中に「○○方江」と記されたものがいくつも登場する。ようは「○○へ」渡してほしい香典、いわゆる「枝義理」というわけである。これをまとめられたのが堀口氏で、表にして一覧化している。それによると枝義理の相手は下記のようになる。
分家 8
故人のおい 24
故人の妹 3
故人の妻 4
故人の息女 1
故人の妻の兄弟 13(5名)
これは現在の箕輪町三日町の鳥山家において明治7年8月に行われた葬儀のものである。故人の妻の関係者に出された枝義理が目立つほか、故人のおいという方へのものが多い。いずれにせよ、箕輪町の事例であり、現在も色濃く枝義理が残っている上伊那南部ばかりでなく、上伊那で特徴的に行われていた義理ということがわかる。堀口氏は鳥山家の受納帳とは別に、江戸時代の文政11年(1828)から文久2年(1862)までの箕輪町木下での音信見舞帳に記載されていた枝義理をまとめている。それによると施主へのもののほか施主と枝義理はもちろん、枝義理のみを持参した人もかなりの数記載されているようだ。文政時のものより文久時の参列者は次第に増加しており、枝義理の増加傾向は参列者の増加率以上に高い。たかだか30年余の間に急増している様子がうかがえ、江戸末期に枝義理の風習がピークを迎えたともいえる。枝義理が近代のものではなく、近世から継続していることもわかる資料である。