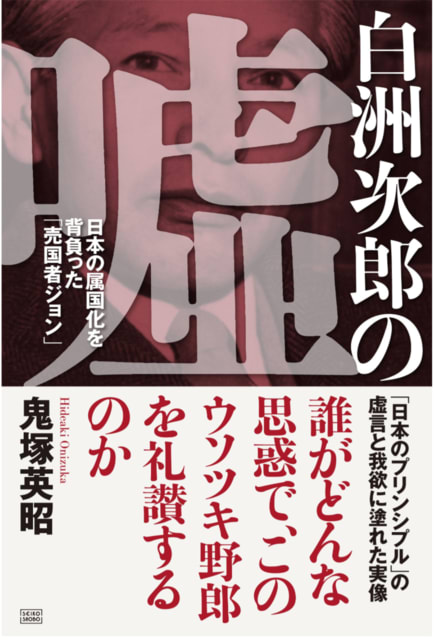72年5月の沖縄返還に際して、日本は3億2000万ドルをアメリカに差し出した。このほか密約で、さらに取られた。
核抜き本土並みの正体を日本国民は今も知らない。新聞テレビが真実を伝えないからだ。事実は沖縄にあった、もはや使いものにならない固定した大陸間弾道弾の撤去費用などにも、血税を使った。固定した核の基地は、時代遅れとなっていたのだ。移動式の多弾頭の核兵器の時代に移っていた。
米国は、撤去を口実に日本から大金をせしめたのだ。しかも、非常事態には核を持ち込む、通過させるとの密約も認めさせた。売国奴外交も極まっていた。笑いの止まらないワシントンが、沖縄返還の真相である。
今も変わらない。普天間移転にからめて米海兵隊をグァムに移転するという米産軍体制の計画を、日本の金でやる、というのだ。
沖縄に海兵隊を駐留させる理由などない。万が一のことが起きれば、一瞬にして死滅する部隊であることがわかっている。グァム移転を普天間問題にからめて、日本の金で、がワシントンの狙いなのだ*。
「アメリカというずる賢い泥棒に身ぐるみはがされる日本かな」という戦後の日本外交なのだ。
余談だが、沖縄返還時にナベツネはワシントン特派員をしていた。当時、衆院予算委員長の中野四郎がワシントンを訪問すると、待ち構えていたナベツネと日経の神末佳明特派員が、当時の日本では禁じられていた「エロ映画館」に案内している。
欧米勤務の外交官の主たる任務は、東京からのバッジ組を売春宿に連れてゆくものだった、と何度も聞いたことがある。日本の外交官・政治屋・特派員もこのレベルだった。「ワシントン帰りが、政府・議会・言論界の中枢を占める日本かな」である。
2013年9月20日8時30分記
(本澤二郎)
http://blog.livedoor.jp/jlj001/archives/52047529.html
* グアム移転に必要な経費は92億ドルで「その3分の2(約6,000億円)を日本側が負担します」と2006年当時の自民党政権が約束している。米議会が関連予算を認めないため、移転事業は進んでいないが、日本政府はすでに500億円以上を米国政府に送金している。(http://www.asahi.com/special/wikileaks/TKY201105030472.html)。