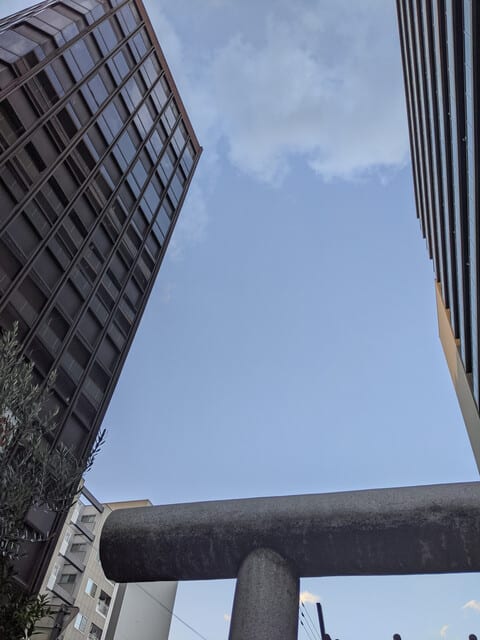横の石碑には、「このお地蔵さまは享保十二(西暦一七二七年)湛明元江和尚と宝暦六(西暦一七五七年)博道覚性沙弥二人のため、また野田池の安全と多くの人々の冥福を祈って建立されたものと思われる」とあった。一人目は福岡の戒壇院の第四代住職みたいだが……。
野田池からの眺めは、年々変化している。このブログのバナーの部分がその風景なんだが、四国山地よりもマンションがにょきにょき生えてきている。
我々は風景の中から人間を見出すみたいな顛倒から文学を作ってきた歴史のなかに生きているのだが――、これは案外柄谷行人が言うような意味でのパースペクティブの成立以上の意味がある。
桜をみていると、感覚がぼけてくる感じがして好きじゃないが、これがなんとなく鬱っぽくなることと関係があるのではないかと勝手に考えている。桜なんかより人間のほうがうつくしいに決まっている。しかし、我々は桜なんかを見てしまう、――というより、常に人間と桜の混合した状態を眺めているといってよい。古い和歌たちは無論そうである。わたしは山の中で育ったので、桜は山が白粉をしているようでなんとなくこちらも恥ずかしい感じがするが、平地の桜は、なんですかこれから小麦粉で料理はじめんですかみたいなかんじがする。――こんな認識だって、混合状態を示している。
「クラシック名曲「酷評」事典 下」には、ショスタコービチの「マクベス夫人」の米ソそれぞれの酷評が載ってておもしろかった。アメリカのニューヨーク・サンの批評は、これは「閨房オペラ」でそのセックス描写は「便所の落書き」だと言う、プラウダはよく知られているように、それをはじめ「自然主義」だと言っていたが、「形式主義」と言い出す。ここにも、人間の肉体と閨房や便所、「形式」といった二対の混合である。批評者たちは、音楽を用いて、人間のいる物質的な風景を見ているのであった。
Carl Rugglesに、「Sun-treader」 (1931) という曲があるが、これに対してドイツの「音楽報知新聞」の批評家は、「太陽を踏む者」ではなく「便所に踏み入る者」であると酷評した。しかし、なんとなく酷評の気分は分かる気もする。この無調音楽は人間のそれの感じがしなかったのだ。評者は、人間への懐かしさのあまり「便所」と言ってしまったのである。無調の陶酔で「胃が収縮」しそうだと告白しながら、無調を肉体の問題として解することまでやっている。そういえば、以前、某便所の落書き掲示板で、ショスタコービチのバイオリン協奏曲に対して、「ガクガクブルブルオシッコシャーシャーみたいな曲」と言われていたが、結構イメージとしては当たっていると思う。ショスタコービチは、無調や新古典主義や機械主義に対して、いかに性欲や肉体の勝手な動き(げっぷやおなら)をねじ込むかを若いときから考えていた。
その意味で、石の像というのは風景でもあり人間でもある、うまい解決の仕方である。
もっとも、オスカーワイルドなんかは、そんな庶民の気持ちは分からない。石になってゆく王子様に向かって燕として愛を捧げるのである。