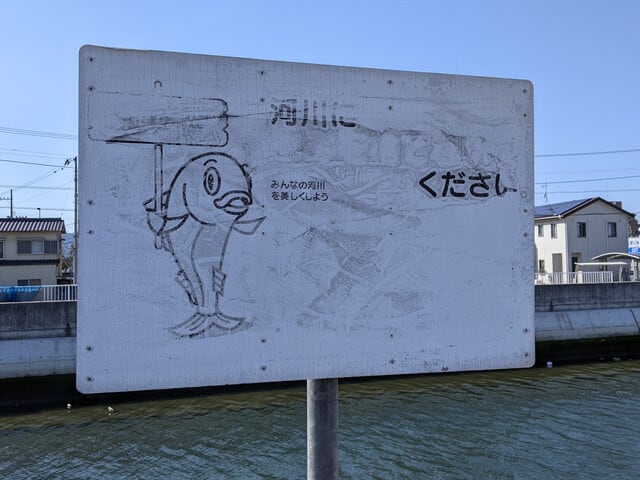石清尾八幡の市立祭である。

わたしは木曽の水無神社に頼みごとに行ったりして育ったけど、あの神社は神木のような巨大樹の中に埋没している神社なので、それが防風林になり案外風の音が聞こえない。ここの石清尾八幡は山体に沿って剥き出しになっている。だから、神事をしているときに、風が巻いたり立ったりするかんじがあり、雅楽や祝詞が風に舞っている感じがする。昔は非常にある種人口的な妙な雰囲気を醸していたに違いない。昔は海岸ももっと近かっただろうから潮の匂いもしたかもしれない。
室町時代、管領の細川頼之が戦勝奉賽祭にともなって社殿を建てたので、それを契機に4月3日にお祭りをおこなうことにし、そこで農道具や植木の市が立ったそうなのである。だから「市立祭」と言うらしい。
いまでは、非常に長い参道(八幡通)が歩行者天国となり、いろんな催しがおこなわれている。今日は、綱引き大会とか、国分寺太鼓演奏とか、今年は吉田亜希氏などのパフォーマンスもおこなわれていた。最近は水無神社の祭もそうだけど、外国人も混じった雑多な空間ができあがっている。
ところで、今日の神事をみてておもったが、地元の有力な人たち?から捧げられていたおいしそうな食べ物、もし、木曽の水無神社であったら、周囲の山猿集団の襲撃をうけてしまう気がした。高松の山にも猿はいるんだろうけど、まだ神社に集う人間の数が多いので大丈夫かもしれない。思うに、昔のお祭りはまわりの動物に対する威嚇みたいな意味もあった気がするんだな。。火を炊いて大騒ぎしてね。。