三日間かけて落語「芝浜」の勉強をした。
まず、講談社の「落語全集」(昭和4年発行)で「芝浜」(本文では旧字「芝濱」)の速記を読む。演者は柳亭左楽(五代目)である。左楽は1872年生まれ。明治末から大正・昭和20年代にかけて活躍した落語界の大物で、八代目桂文楽の師匠にあたる人だった。1911年に五代目を襲名し、1953年に没している。
さて、左楽の「芝浜」、話の内容は現代の「芝浜」とほとんど変らないが、構成がシンプルですっきりしている。主人公の魚屋の名前は熊さん、つまり熊五郎である。(志ん生も熊さんでやっている。桂三木助が勝五郎に変えたと言われる。ほかに金さんもある。)
酒は百薬の長というが、ほどほどが大切といった簡単なマクラがあって、
朝女房が熊さんを起すところから始まる。出て行くのを見送って、ほどなく熊が慌てて戻って来る。(このあたり、三木助の「芝浜」だと、浜へ行ってからの情景描写が長々とあり、革財布を拾う場面がある)
熊が女房に、後から追い駆けてくる者がいないか、戸締りをしろよとか言ってから、
おまえが時を間違えたので、ひどい目にあった。仕方なく河岸で暇をつぶしていると、なんと革財布を見つけた、と語り出す。
熊がふところから濡れた革財布を出して、中の金を数えるまで、約5分で演じるのではなかろうか。超スピードである。芝浜の描写もなければ、増上寺の鐘も鳴らない。
財布の中身は、二分金で五十両。(三木助は小粒で八十二両あるいは四十八両)
女房が熊にこの金、どうするつもりなのかと訊くと、おまえにいい着物でも買って、おれもいい半纏着て、友達呼んで前祝いしようと言う。
そこで女房が、この金わたしが預かっておくから一眠りしなさいと言い、熊を無理やり寝かしつける。その後、女房がまた熊を起す。
左楽の「芝浜」では、ここでやっと明六つ(冬だがら朝の6時半ごろか)になるわけで、最初に起したのが4時ごろだとして、今までの話はずっと暗いうちの出来事だったことになる。財布を見つけたのも暗いうちで、足に紐が引っかかって手繰り寄せたことになっている。
三木助の「芝浜」では、明六つまでの二時間を芝浜で過ごし、朝日が昇って、お天道様を拝んでから、財布を見つけたことにしている。なぜそうしたのかと言えば、芝浜の情景を描きたかったため、朝早く買出しに行く魚屋という商売の辛さと気持ち良さの両方を表現したかったためである。つまり、落語をもっとリアリスティックにして、生活感や現実感を出したかったのだろう。描写が非常に細やかになって、ある意味、文学的になったとも言えるが、その分、インテリ臭さが漂って、面白さがなくなったとも言えなくもない。落語は、会話の面白さや話のテンポも大切で、そのためには省略やいい加減さがあっても許されると思うのだが、どうだろう。志ん生の「芝浜」は、三木助の改作版とは違って、昔の「芝浜」に戻している。志ん生が演じた「芝浜」の録音は、三木助が死んでからのもので、マクラで志ん生は、三木助さんが遠くへ行ってしまい「芝浜」をやる人がいなくなったのでわたしがやってみようと断っている。
戻って、左楽の「芝浜」。起きると熊はすぐに湯に行って、帰りに友達を呼んで、酒肴を出して、どんちゃん騒ぎをして、寝てしまう。夕方過ぎて熊が目を覚ますと、女房は革財布なんか知らないと言う。結局、革財布を拾ったことは夢だったと熊に信じ込ませてしまう。それで熊は酒を断ち、改心して商売に精を出すことになる。ここまでが前半。(つづく)
まず、講談社の「落語全集」(昭和4年発行)で「芝浜」(本文では旧字「芝濱」)の速記を読む。演者は柳亭左楽(五代目)である。左楽は1872年生まれ。明治末から大正・昭和20年代にかけて活躍した落語界の大物で、八代目桂文楽の師匠にあたる人だった。1911年に五代目を襲名し、1953年に没している。
さて、左楽の「芝浜」、話の内容は現代の「芝浜」とほとんど変らないが、構成がシンプルですっきりしている。主人公の魚屋の名前は熊さん、つまり熊五郎である。(志ん生も熊さんでやっている。桂三木助が勝五郎に変えたと言われる。ほかに金さんもある。)
酒は百薬の長というが、ほどほどが大切といった簡単なマクラがあって、
朝女房が熊さんを起すところから始まる。出て行くのを見送って、ほどなく熊が慌てて戻って来る。(このあたり、三木助の「芝浜」だと、浜へ行ってからの情景描写が長々とあり、革財布を拾う場面がある)
熊が女房に、後から追い駆けてくる者がいないか、戸締りをしろよとか言ってから、
おまえが時を間違えたので、ひどい目にあった。仕方なく河岸で暇をつぶしていると、なんと革財布を見つけた、と語り出す。
熊がふところから濡れた革財布を出して、中の金を数えるまで、約5分で演じるのではなかろうか。超スピードである。芝浜の描写もなければ、増上寺の鐘も鳴らない。
財布の中身は、二分金で五十両。(三木助は小粒で八十二両あるいは四十八両)
女房が熊にこの金、どうするつもりなのかと訊くと、おまえにいい着物でも買って、おれもいい半纏着て、友達呼んで前祝いしようと言う。
そこで女房が、この金わたしが預かっておくから一眠りしなさいと言い、熊を無理やり寝かしつける。その後、女房がまた熊を起す。
左楽の「芝浜」では、ここでやっと明六つ(冬だがら朝の6時半ごろか)になるわけで、最初に起したのが4時ごろだとして、今までの話はずっと暗いうちの出来事だったことになる。財布を見つけたのも暗いうちで、足に紐が引っかかって手繰り寄せたことになっている。
三木助の「芝浜」では、明六つまでの二時間を芝浜で過ごし、朝日が昇って、お天道様を拝んでから、財布を見つけたことにしている。なぜそうしたのかと言えば、芝浜の情景を描きたかったため、朝早く買出しに行く魚屋という商売の辛さと気持ち良さの両方を表現したかったためである。つまり、落語をもっとリアリスティックにして、生活感や現実感を出したかったのだろう。描写が非常に細やかになって、ある意味、文学的になったとも言えるが、その分、インテリ臭さが漂って、面白さがなくなったとも言えなくもない。落語は、会話の面白さや話のテンポも大切で、そのためには省略やいい加減さがあっても許されると思うのだが、どうだろう。志ん生の「芝浜」は、三木助の改作版とは違って、昔の「芝浜」に戻している。志ん生が演じた「芝浜」の録音は、三木助が死んでからのもので、マクラで志ん生は、三木助さんが遠くへ行ってしまい「芝浜」をやる人がいなくなったのでわたしがやってみようと断っている。
戻って、左楽の「芝浜」。起きると熊はすぐに湯に行って、帰りに友達を呼んで、酒肴を出して、どんちゃん騒ぎをして、寝てしまう。夕方過ぎて熊が目を覚ますと、女房は革財布なんか知らないと言う。結局、革財布を拾ったことは夢だったと熊に信じ込ませてしまう。それで熊は酒を断ち、改心して商売に精を出すことになる。ここまでが前半。(つづく)











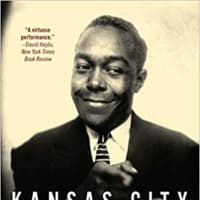

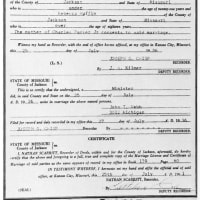







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます