現存する「浮世絵類考」の写本、異本は国内外に120種以上あるとのことですが、そのうち原初段階の写本(「南畝原撰本」に最も近いもの)でよく知られているものが4種類あります。それを以下に挙げておきます。
一、「神宮文庫本」
伊勢神宮所蔵。高松藩家老 で文人の木村黙老(1774~1856)の自筆本「聞ままの記」(全83巻の49巻に所収)。「浮世絵考証」と題する。黙老が筆写した原本は、享和2年(1802)、蝦夷地探検家で有名な近藤重蔵(1771~1829)が山東京伝所蔵の「浮世絵類考」写本から転写したものだとされている。
二、「岩波文庫底本のT氏所蔵本」
岩波文庫「浮世絵類考」(昭和16年9月発行)の序文で編者の仲田勝之助が不明瞭にしか書いていないが、T氏(誰だか不明)が持っていた写本で、享和3年(1803)ごろに作成されたとのこと。佳本だと言っているが、このT氏本も現物は編者が目にしただけで、確かめようがない。仲田勝之助は、著名な美術評論家で写楽研究者でもあったが、学問的厳密さという点ではルーズで、T氏なる謎の人物の所蔵本を底本にし、その他、翻刻本の検証もせずに、岩波文庫で売り出したので、その功も罪も共に大きいと思う。
「浮世絵類考」の研究者で、<写楽=能役者斎藤十郎兵衛>説を真っ向から否定した哲学者・由良哲次(1897~1979)は、岩波文庫版「浮世絵類考」を、「支離滅裂の感があるほどの雑収録である」と批判している。
また、岩波文庫では、T氏所蔵本の記述にならい、見出しを「写楽」ではなく「写楽斎」にしているのも特異である。
三、「六樹園本」(白揚文庫本)
文化5年(1808)8月、石川雅望(宿屋飯盛・六樹園)がおそらく南畝の原撰本から写して書き込みを入れた稿本を、文政9年に狂歌師の野四楼が転写したもの。「浮世絵師之考」という題名になっている。(北小路健氏が雑誌『萌春』に連載した「浮世絵類考 論究・10」に全文がある。加藤好夫氏「浮世絵文献資料館」に転載されている)
四、「曳尾庵本」
文化12年(1815年)、加藤曳尾庵が、南畝から直接原本を借りたか、あるいは山東京伝か南畝と親しい他の友人からその写本を借りて書写し、補記を加えた写本。曳尾庵本も、前述の写本2種同様、山東京伝の「追考」のない(三馬の補記もない)写本で、南畝原撰本に準拠している。しかし、曳尾庵の自筆本は未発見。その自筆本の写本の一つを古書収集家の林若樹(1875~1938)が所蔵していたが、その写本は現在行方不明。「曳尾庵本」として現在閲覧できるものは、昭和7年発行の「孚水ぶんこ臨時号」島田筑波校訂の翻刻本だけ。これは、昭和2年に三田村鳶魚が林若樹の蔵本を借り、一夜で書写したもので、誤記もあるとのこと。林若樹所蔵の写本自体も曳尾庵の自筆本ではないようなので、この翻刻本は、全幅の信頼は置けないといわれていると言われている。
曳尾庵本では絵師の数は37人。写楽について「筆力雅趣ありて賞すべし」とコメントを加えたのは曳尾庵だとされている。
曳尾庵による跋文を以下に引用しておきます。
*大曲駒村編「浮世絵類考」(昭和16年発行)のまえがき「翻刻に当りて」(昭和13年10月 校訂者の大曲駒村・記)からの引用。句読点は校訂者によるもの。
この書は蜀山人の編にして、寛政の初の比集められし物ならんか。予古老の談話につきて、猶其居所、事実を潤し侍る。今文化十余りの比までに至り、役者絵、錦絵むかしに倍して晴朗妖艶、奇品麗秀、今に過ぎたるものは後世にも有るべからずと思はる
文化十二亥のとし 曳尾庵 戯誌
ここで加藤曳尾庵は、「蜀山人の編纂で、寛政の初めのころ集められたものだろう」と書いています。「予古老の談話につきて、猶其居所、事実を潤し侍る」という文は、「私はお年寄りの談話にもとづいて、さらにその住所や事実を書き入れた」ということ。また、当時(文化十二年=1815年)における画風さまざまな浮世絵の流行を、「今に過ぎたるものは後世にも有るべからず」と述べています。
加藤曳尾庵(1763~1829?)という人は江戸中期の医師、文人、俳諧師で、大田蜀山人ほど有名ではありませんが、経歴が変わって、調べてみると大変興味をそそられる人物です。
宝暦13年、水戸の生まれで、幼名は平吉、水戸藩士沼田氏の三男。父と江戸に出て、水戸藩邸に勤めていたのですが、20代半ばで浪人になり、8年ほど諸国を遍歴し、寛政8年(1796)、34歳の時に江戸に定住。
その後、幕府の奥医師から医術を学び、文化2年(1805)、下谷の医師加藤玄悦の看板「亀の甲医師」を継いで、神田須田町に町医を開業し、加藤玄亀(彦亀)と名乗ります。亀の甲医師というのは明和期から流行した歯科・咽喉科の医者で、入れ歯の材料に亀の甲を使ったのでその名の由来があるように思われますが、定かではありません。
この頃から、曳尾庵は狂歌、俳諧、浄瑠璃、茶道をたしなみ、好古癖が昂じたようです。号は、曳尾庵のほかに長息、南水、召竹など。また、ライフワークとも言うべき、随想「我衣」の執筆を始めます。諸侯や文化人との付き合いも広がって、14歳年長の大田南畝をはじめ、同年代の山東京伝、山東京山(京伝の弟)、曲亭馬琴、谷文晁たちとも交流があったようです。
文化9年、妻子を置いて旅へ出て、また江戸に戻ってからは一人身となって、住所を転々と変えます。文化11年2月、ようやく猿楽町の裏手に二間の小さな家を借り、妻子を呼んで落ち着きます。文化13年7月、知人の推挙を得て、麹町三宅侯(田原藩)のお抱え医師に登用され、同屋敷内に転居。文政2年3月まで勤めます。その間、同藩士・渡辺崋山と親交を結んでいます。以後は、板橋に寓居し、医業、手習いの師匠をして余生を送り、文政12年ごろ亡くなったと推定されます。(参考文献:幸田成友「『我衣』とその著者」明治43年)
主著「我衣」(わがころも)(19巻21冊)は曳尾庵が20年かけて記した厖大な随想集で、寛永より宝暦までの世態風俗および化政期の同種の風聞などを年代順に配列したもので、江戸風俗を知るうえで重要な史料となっています。文化12年2月8日に松平鳩翁屋敷にて、大黒屋光太夫(江戸に向かう途中漂流し、ロシアに9年半滞在して、帰国した伊勢出身の船頭)に面会し、ロシアの話をいろいろ聞いたことも書かれているそうです。
加藤曳尾庵が「浮世絵類考」を書写して、書き込みを入れたのは、文化12年ですから、ちょうど大黒屋光太夫に会った後で、猿楽町に小さな家を借りて住んでいたころです。曳尾庵は、南畝の稿本を借りたか、山東京伝が手書きした写本を借りたのか、ともかく「浮世絵類考」を写して、いろいろ書き入れたようです。
一、「神宮文庫本」
伊勢神宮所蔵。高松藩家老 で文人の木村黙老(1774~1856)の自筆本「聞ままの記」(全83巻の49巻に所収)。「浮世絵考証」と題する。黙老が筆写した原本は、享和2年(1802)、蝦夷地探検家で有名な近藤重蔵(1771~1829)が山東京伝所蔵の「浮世絵類考」写本から転写したものだとされている。
二、「岩波文庫底本のT氏所蔵本」
岩波文庫「浮世絵類考」(昭和16年9月発行)の序文で編者の仲田勝之助が不明瞭にしか書いていないが、T氏(誰だか不明)が持っていた写本で、享和3年(1803)ごろに作成されたとのこと。佳本だと言っているが、このT氏本も現物は編者が目にしただけで、確かめようがない。仲田勝之助は、著名な美術評論家で写楽研究者でもあったが、学問的厳密さという点ではルーズで、T氏なる謎の人物の所蔵本を底本にし、その他、翻刻本の検証もせずに、岩波文庫で売り出したので、その功も罪も共に大きいと思う。
「浮世絵類考」の研究者で、<写楽=能役者斎藤十郎兵衛>説を真っ向から否定した哲学者・由良哲次(1897~1979)は、岩波文庫版「浮世絵類考」を、「支離滅裂の感があるほどの雑収録である」と批判している。
また、岩波文庫では、T氏所蔵本の記述にならい、見出しを「写楽」ではなく「写楽斎」にしているのも特異である。
三、「六樹園本」(白揚文庫本)
文化5年(1808)8月、石川雅望(宿屋飯盛・六樹園)がおそらく南畝の原撰本から写して書き込みを入れた稿本を、文政9年に狂歌師の野四楼が転写したもの。「浮世絵師之考」という題名になっている。(北小路健氏が雑誌『萌春』に連載した「浮世絵類考 論究・10」に全文がある。加藤好夫氏「浮世絵文献資料館」に転載されている)
四、「曳尾庵本」
文化12年(1815年)、加藤曳尾庵が、南畝から直接原本を借りたか、あるいは山東京伝か南畝と親しい他の友人からその写本を借りて書写し、補記を加えた写本。曳尾庵本も、前述の写本2種同様、山東京伝の「追考」のない(三馬の補記もない)写本で、南畝原撰本に準拠している。しかし、曳尾庵の自筆本は未発見。その自筆本の写本の一つを古書収集家の林若樹(1875~1938)が所蔵していたが、その写本は現在行方不明。「曳尾庵本」として現在閲覧できるものは、昭和7年発行の「孚水ぶんこ臨時号」島田筑波校訂の翻刻本だけ。これは、昭和2年に三田村鳶魚が林若樹の蔵本を借り、一夜で書写したもので、誤記もあるとのこと。林若樹所蔵の写本自体も曳尾庵の自筆本ではないようなので、この翻刻本は、全幅の信頼は置けないといわれていると言われている。
曳尾庵本では絵師の数は37人。写楽について「筆力雅趣ありて賞すべし」とコメントを加えたのは曳尾庵だとされている。
曳尾庵による跋文を以下に引用しておきます。
*大曲駒村編「浮世絵類考」(昭和16年発行)のまえがき「翻刻に当りて」(昭和13年10月 校訂者の大曲駒村・記)からの引用。句読点は校訂者によるもの。
この書は蜀山人の編にして、寛政の初の比集められし物ならんか。予古老の談話につきて、猶其居所、事実を潤し侍る。今文化十余りの比までに至り、役者絵、錦絵むかしに倍して晴朗妖艶、奇品麗秀、今に過ぎたるものは後世にも有るべからずと思はる
文化十二亥のとし 曳尾庵 戯誌
ここで加藤曳尾庵は、「蜀山人の編纂で、寛政の初めのころ集められたものだろう」と書いています。「予古老の談話につきて、猶其居所、事実を潤し侍る」という文は、「私はお年寄りの談話にもとづいて、さらにその住所や事実を書き入れた」ということ。また、当時(文化十二年=1815年)における画風さまざまな浮世絵の流行を、「今に過ぎたるものは後世にも有るべからず」と述べています。
加藤曳尾庵(1763~1829?)という人は江戸中期の医師、文人、俳諧師で、大田蜀山人ほど有名ではありませんが、経歴が変わって、調べてみると大変興味をそそられる人物です。
宝暦13年、水戸の生まれで、幼名は平吉、水戸藩士沼田氏の三男。父と江戸に出て、水戸藩邸に勤めていたのですが、20代半ばで浪人になり、8年ほど諸国を遍歴し、寛政8年(1796)、34歳の時に江戸に定住。
その後、幕府の奥医師から医術を学び、文化2年(1805)、下谷の医師加藤玄悦の看板「亀の甲医師」を継いで、神田須田町に町医を開業し、加藤玄亀(彦亀)と名乗ります。亀の甲医師というのは明和期から流行した歯科・咽喉科の医者で、入れ歯の材料に亀の甲を使ったのでその名の由来があるように思われますが、定かではありません。
この頃から、曳尾庵は狂歌、俳諧、浄瑠璃、茶道をたしなみ、好古癖が昂じたようです。号は、曳尾庵のほかに長息、南水、召竹など。また、ライフワークとも言うべき、随想「我衣」の執筆を始めます。諸侯や文化人との付き合いも広がって、14歳年長の大田南畝をはじめ、同年代の山東京伝、山東京山(京伝の弟)、曲亭馬琴、谷文晁たちとも交流があったようです。
文化9年、妻子を置いて旅へ出て、また江戸に戻ってからは一人身となって、住所を転々と変えます。文化11年2月、ようやく猿楽町の裏手に二間の小さな家を借り、妻子を呼んで落ち着きます。文化13年7月、知人の推挙を得て、麹町三宅侯(田原藩)のお抱え医師に登用され、同屋敷内に転居。文政2年3月まで勤めます。その間、同藩士・渡辺崋山と親交を結んでいます。以後は、板橋に寓居し、医業、手習いの師匠をして余生を送り、文政12年ごろ亡くなったと推定されます。(参考文献:幸田成友「『我衣』とその著者」明治43年)
主著「我衣」(わがころも)(19巻21冊)は曳尾庵が20年かけて記した厖大な随想集で、寛永より宝暦までの世態風俗および化政期の同種の風聞などを年代順に配列したもので、江戸風俗を知るうえで重要な史料となっています。文化12年2月8日に松平鳩翁屋敷にて、大黒屋光太夫(江戸に向かう途中漂流し、ロシアに9年半滞在して、帰国した伊勢出身の船頭)に面会し、ロシアの話をいろいろ聞いたことも書かれているそうです。
加藤曳尾庵が「浮世絵類考」を書写して、書き込みを入れたのは、文化12年ですから、ちょうど大黒屋光太夫に会った後で、猿楽町に小さな家を借りて住んでいたころです。曳尾庵は、南畝の稿本を借りたか、山東京伝が手書きした写本を借りたのか、ともかく「浮世絵類考」を写して、いろいろ書き入れたようです。















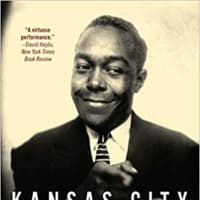

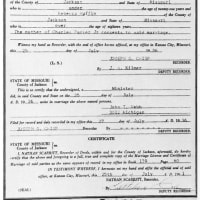


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます