「浮世絵類考」の話に戻ります。
この本は、浮世絵師に関して、江戸時代に作られた唯一の事典で、どの浮世絵師を研究するにもこの本に書かれている記述がその出発点になるほどの重要な史料です。
まず最初に江戸時代の浮世絵師について何かを書き残こしておこうと思い立ったのは、大田南畝(蜀山人 1749~1823)でした。それは寛永期の初め(1790年ごろ)だったと推定されています。(いわゆる「曳尾庵(えいびあん)本」の跋文にそのことが書かれていますが、それについては改めて述べます)
大田南畝は、大田蜀山人といった方が通りが良いのですが、彼が蜀山人の号を使い始めたのは50歳を過ぎてからのことです。そこで、彼の20代から40代初めにかけての主要な文学的業績を考える時には、大田南畝と呼ぶのが通例になっています。
さて、南畝は、江戸時代の初期から目ぼしい浮世絵師を選んで、知っていることをメモのように書き始めたようです。博覧強記の南畝にも分からないことは、知人に聞いたりして、少しずつ書き足していったのだと思います。南畝が大変な蔵書家だったことはよく知られていますが、古い浮世絵もかなり多く持っていたにちがいありません。本の挿絵や手元のあった浮世絵を参考にしながら、絵師を選び、コメントを書いていったのでしょう。
当時、浮世絵師は、狩野派、土佐派、琳派といった本画専門の絵師、いうなればアカデミックな絵師に比べ、町絵師と呼ばれ、身分も社会的評価も数段低かったのですが、逆に大衆的な知名度は高く、現役で有名な浮世絵師でもざっと挙げただけで20人以上はいたことでしょう。江戸時代中期に活躍し、すでに亡くなった浮世絵師で伝説的となった絵師も何人かいたでしょう。
南畝が浮世絵師覚書のような本を作ろうと企図したことは、今にして思えば、大変意義深いことだったわけで、南畝が後世に残した功績は非常に大きかったと言えます。浮世絵研究者はみな、南畝が端緒を開いた浮世絵師事典の恩恵をこうむっているからです。
南畝は、この覚書(「浮世絵考証」と呼ばれる)を、寛政5年終わりまでには清書して、ほぼ完成させていたと思われます。岩佐又兵衛に始まり、喜多川歌麿まで、見出しに上げた絵師の数約25名だったようです。
喜多川歌麿 神田弁慶橋久右衛門町
俗名勇助 名人
はじめは鳥山石燕門人にて狩野家の絵を学ぶ、後男女の風俗を画て絵草紙屋蔦屋重三郎方に寓居す、錦絵多し。今弁慶橋に住す。千代男女風俗絵種々工夫して当時双ぶ方なし、名人。
(仲田勝之助編、岩波文庫「浮世絵類考」が底本にしたT氏所蔵本にある記述)
この時点では、写楽も豊国も見出しになく、コメントも書いていなかったと思います。多分、南畝は2年ほど「浮世絵考証」は書斎のどこかにしまっておいて、手をつけずにいたのではないでしょうか。
なぜかと言うと、南畝は寛政6年の春に幕府の人材登用試験(「学問吟味」といい、朱子学者を公募した)を受験し、これに合格、早速出仕して以後、山積した古文書の整理に日々追われるからです。
寛政8年以降に、南畝は、「浮世絵考証」をまた引っ張り出して、何人か書き足したようです。歌麿の後に、栄之、国政、写楽、窪俊満、二代目宗理、豊国、春朗、歌舞伎堂、春潮、豊広が並んでいますが、どうも私はこのうちの何人かは南畝自身が書いたのではないような気もします。岩波文庫の底本のT氏本を信用すれば、国政、春朗、歌舞伎堂は、南畝の原撰本には書かれていなかったことになっています。岩波文庫ではこの三人は加藤曳尾庵が書き加えたようになっています。国政以降の絵師たちの配列がアットランダムで、師弟、作画期の古い順に並んでない、二代目宗理と春朗は同一人物(北斎のこと)であるののも不思議です。
国政は、この9人の中では最も後輩なのに、栄之に続いて二番目に置かれています。国政が注目されるのは寛政7年の役者絵からです。
歌舞伎堂は寛政7年の数ヶ月間だけが作画期ですし、役者絵を販売したかどうかも分からない絵師なのに、見出しに挙げたのはどうしてか分かりません。
豊広は、豊国と歌川豊春の同門で作画開始がほぼ同時期なのに、豊国の後に三人挟んで、置かれています。そして、国政は、豊国の弟子なのに、豊国の4人前に置かれているのも奇妙です。
また、本来なら、春朗も春潮も勝川春章の弟子なので、師匠の後に置くべきところです(春好と春英は、春章の見出しの横に弟子と書いて終わりです。春好は、春章のコメント中にも触れてあるので良いとしても、春英は名前だけです)。
豊国と豊広も歌川豊春の弟子なのでその後に並べて置いた方がベターですし、歌麿のすぐ前が豊春なので、最後のページだけ書き直せば、二人を入れられたのに、そうしていません。
この頃、南畝はよほど多忙だったようです。歌麿の本文途中まではすでに清書してあったので、書き直す手間を惜しんで、こういう形になったのかもしれません。
この本は、浮世絵師に関して、江戸時代に作られた唯一の事典で、どの浮世絵師を研究するにもこの本に書かれている記述がその出発点になるほどの重要な史料です。
まず最初に江戸時代の浮世絵師について何かを書き残こしておこうと思い立ったのは、大田南畝(蜀山人 1749~1823)でした。それは寛永期の初め(1790年ごろ)だったと推定されています。(いわゆる「曳尾庵(えいびあん)本」の跋文にそのことが書かれていますが、それについては改めて述べます)
大田南畝は、大田蜀山人といった方が通りが良いのですが、彼が蜀山人の号を使い始めたのは50歳を過ぎてからのことです。そこで、彼の20代から40代初めにかけての主要な文学的業績を考える時には、大田南畝と呼ぶのが通例になっています。
さて、南畝は、江戸時代の初期から目ぼしい浮世絵師を選んで、知っていることをメモのように書き始めたようです。博覧強記の南畝にも分からないことは、知人に聞いたりして、少しずつ書き足していったのだと思います。南畝が大変な蔵書家だったことはよく知られていますが、古い浮世絵もかなり多く持っていたにちがいありません。本の挿絵や手元のあった浮世絵を参考にしながら、絵師を選び、コメントを書いていったのでしょう。
当時、浮世絵師は、狩野派、土佐派、琳派といった本画専門の絵師、いうなればアカデミックな絵師に比べ、町絵師と呼ばれ、身分も社会的評価も数段低かったのですが、逆に大衆的な知名度は高く、現役で有名な浮世絵師でもざっと挙げただけで20人以上はいたことでしょう。江戸時代中期に活躍し、すでに亡くなった浮世絵師で伝説的となった絵師も何人かいたでしょう。
南畝が浮世絵師覚書のような本を作ろうと企図したことは、今にして思えば、大変意義深いことだったわけで、南畝が後世に残した功績は非常に大きかったと言えます。浮世絵研究者はみな、南畝が端緒を開いた浮世絵師事典の恩恵をこうむっているからです。
南畝は、この覚書(「浮世絵考証」と呼ばれる)を、寛政5年終わりまでには清書して、ほぼ完成させていたと思われます。岩佐又兵衛に始まり、喜多川歌麿まで、見出しに上げた絵師の数約25名だったようです。
喜多川歌麿 神田弁慶橋久右衛門町
俗名勇助 名人
はじめは鳥山石燕門人にて狩野家の絵を学ぶ、後男女の風俗を画て絵草紙屋蔦屋重三郎方に寓居す、錦絵多し。今弁慶橋に住す。千代男女風俗絵種々工夫して当時双ぶ方なし、名人。
(仲田勝之助編、岩波文庫「浮世絵類考」が底本にしたT氏所蔵本にある記述)
この時点では、写楽も豊国も見出しになく、コメントも書いていなかったと思います。多分、南畝は2年ほど「浮世絵考証」は書斎のどこかにしまっておいて、手をつけずにいたのではないでしょうか。
なぜかと言うと、南畝は寛政6年の春に幕府の人材登用試験(「学問吟味」といい、朱子学者を公募した)を受験し、これに合格、早速出仕して以後、山積した古文書の整理に日々追われるからです。
寛政8年以降に、南畝は、「浮世絵考証」をまた引っ張り出して、何人か書き足したようです。歌麿の後に、栄之、国政、写楽、窪俊満、二代目宗理、豊国、春朗、歌舞伎堂、春潮、豊広が並んでいますが、どうも私はこのうちの何人かは南畝自身が書いたのではないような気もします。岩波文庫の底本のT氏本を信用すれば、国政、春朗、歌舞伎堂は、南畝の原撰本には書かれていなかったことになっています。岩波文庫ではこの三人は加藤曳尾庵が書き加えたようになっています。国政以降の絵師たちの配列がアットランダムで、師弟、作画期の古い順に並んでない、二代目宗理と春朗は同一人物(北斎のこと)であるののも不思議です。
国政は、この9人の中では最も後輩なのに、栄之に続いて二番目に置かれています。国政が注目されるのは寛政7年の役者絵からです。
歌舞伎堂は寛政7年の数ヶ月間だけが作画期ですし、役者絵を販売したかどうかも分からない絵師なのに、見出しに挙げたのはどうしてか分かりません。
豊広は、豊国と歌川豊春の同門で作画開始がほぼ同時期なのに、豊国の後に三人挟んで、置かれています。そして、国政は、豊国の弟子なのに、豊国の4人前に置かれているのも奇妙です。
また、本来なら、春朗も春潮も勝川春章の弟子なので、師匠の後に置くべきところです(春好と春英は、春章の見出しの横に弟子と書いて終わりです。春好は、春章のコメント中にも触れてあるので良いとしても、春英は名前だけです)。
豊国と豊広も歌川豊春の弟子なのでその後に並べて置いた方がベターですし、歌麿のすぐ前が豊春なので、最後のページだけ書き直せば、二人を入れられたのに、そうしていません。
この頃、南畝はよほど多忙だったようです。歌麿の本文途中まではすでに清書してあったので、書き直す手間を惜しんで、こういう形になったのかもしれません。











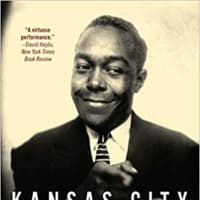

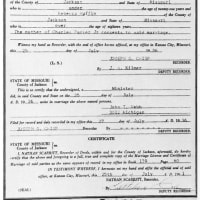







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます