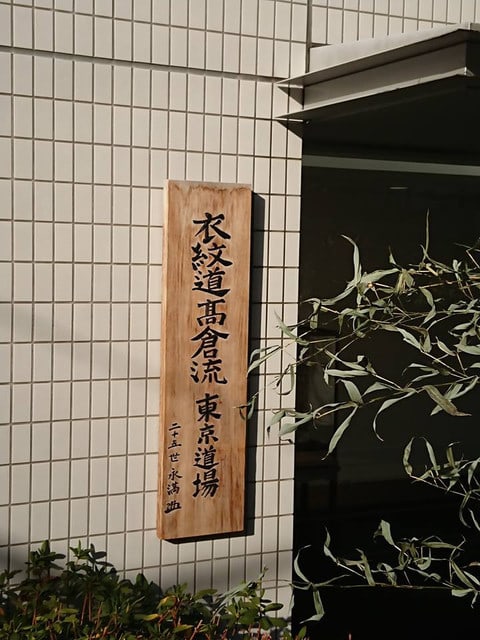「松屋銀座」で行われていた「祈りをむすぶ 正月の飾りと五節供の結び」展より、日蔭の蔓です。
http://www.matsuya.com/m_ginza/exhib_gal/details/index.html#gallery01
今更ですが、何がすごいと言って、『平安王朝絵巻ぬりえbook』のポテンシャルには驚くばかりです。千葉大学のお装束の授業に使っているわけですが、細長、汗衫なんて滅多に見るものではないのに、探すときっと必ずある。考えてみれば、この本の表紙を見せて、「これは何という装束ですか?」と聞いたなら、国民の九割九分は莞爾として「十二単ですよ」とお答えになると思いますが、これぞ「小袿細長」、裳も唐衣もつけない本当のお姫様の姿であります。もう表紙からブッ飛んでおります。来年春の早稲田の授業では、このぬりえbookを最大限活用したいと思って現在作戦計画中です。
千葉大学「中世文化論a」女性装束篇、お待ちかね、十二単です。装束班はエース投入、もう一組は、学生さんにお着付けをやっていただきました。一枚ずつじっくりフルで、というのは久しぶりで、手技の確認などもできました。

来週は、小袿・細長・汗衫篇です。

千葉大学、千葉県文化振興財団等の取り組みによる「見る、知る、伝える千葉~創作狂言~」プロジェクトの成果発表「創作狂言 里見八犬伝其ノ壱(エピソード・ワン)」拝見、和泉流小笠原匡師の指導演出、間狂言の語りよろしく、複雑きわまる八犬士登場の筋立てを語りつつ、犬塚信乃、犬川荘介、犬山道節の登場、そしてクライマックスは芳流閣の戦いで信乃と犬飼現八がまっさかさまに転落するところまで、千葉大学の学生さんたちが大車輪の奮闘でした。狂言の披露と称して劇中劇もあり、「新・八犬伝」ファンには懐かしい「網干左母二郎」も出てきますよ。
イタリアのコンメディア・デッラルテで使われる半仮面をモチーフにした小笠原師自作の狂言面も面白く、意外な効果を上げていると思いました。関連の展示もあり、勉強になりました。