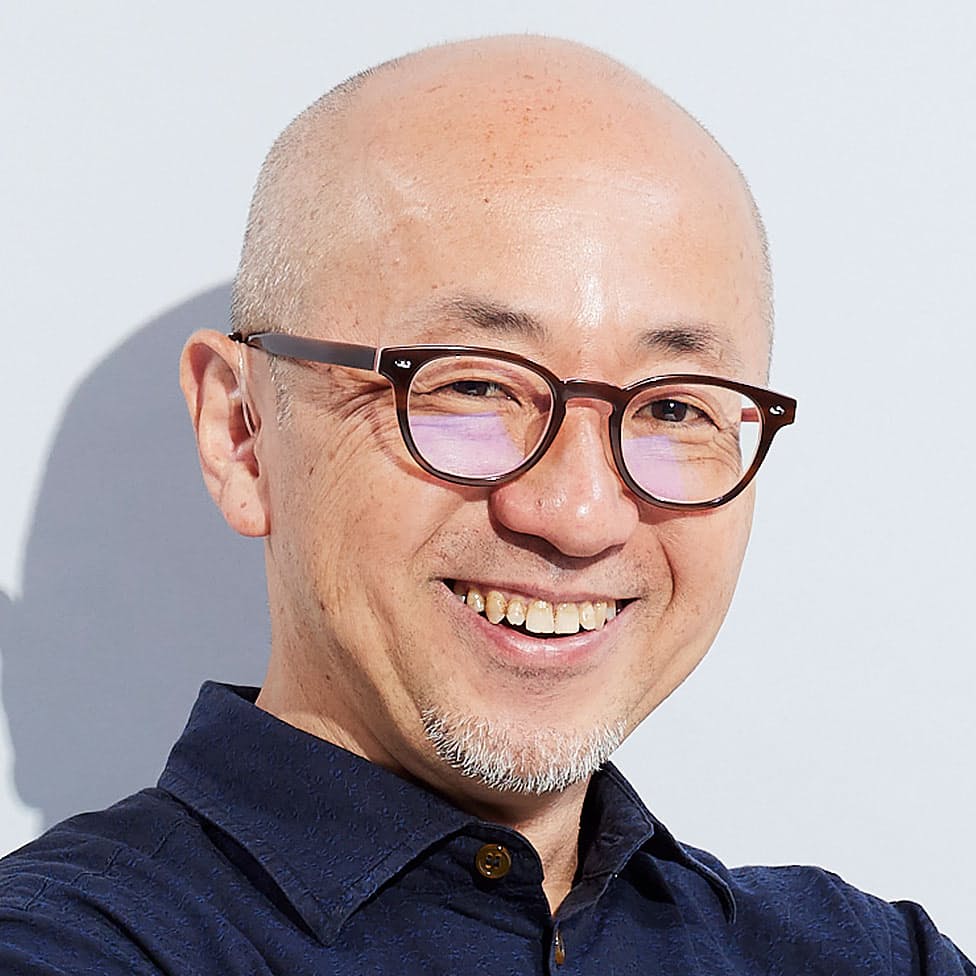金融市場で長年にわたって共有されてきた投資の格言。山あり谷ありの修羅場でもまれており、人生の大きな決断に生かせるものも少なくない。専門家が役立ちそうな格言を選んだ。
今週の専門家
▽石黒英之(野村アセットマネジメントチーフ・ストラテジスト)▽市川雅浩(三井住友DSアセットマネジメントチーフマーケットストラテジスト)
▽井出真吾(ニッセイ基礎研究所チーフ株式ストラテジスト)
▽エミン・ユルマズ(レディバードキャピタル代表)
▽岡田克彦(関西学院大学大学院経営戦略研究科教授)
▽香川睦(楽天証券経済研究所チーフグローバルストラテジスト)
▽塩田淳(大和アセットマネジメント調査部長)
▽清水毅(アセットマネジメントOne運用本部チーフマーケットアナリスト)
▽中野晴啓(なかのアセットマネジメント社長)
▽藤野英人(レオス・キャピタルワークス社長兼最高投資責任者)=敬称略、五十音順
1位 人の行く 裏に道あり 花の山

多くの人が行き交う大通りではなく、人があまり行かない道にこそ目的の「花」が咲いているという格言。
エミン・ユルマズさんは「大衆と違うことをやらないと大きなもうけを得られないことは何度も体験した」と振り返る。
「大きな利益は誰も話題にしていないような取引のときにもたらされた」(岡田克彦さん)という投資家は多いようだ。
ただ、ほかの人と違う行動をするということは「相場が上昇しても上がらない銘柄を保有している可能性も高く、忍耐力も必要」(香川睦さん)だ。
清水毅さんによると「この格言には『いずれを行くも散らぬ間に行け』という下の句がある。直ちに行動しないとチャンスそのものがなくなるという意味」とのこと。
「マーケットだけでなく、人生すべてに通じる金言」(塩田淳さん)と言えそうだ。
2位 強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、幸福の中で消えていく
相場の上昇は投資家が弱気なときに始まり、投資家が先行きに懐疑心を持つなかで進む。そして、投資家の多くが強気になると終わるといわれる。
「2000年のITバブルでファンドマネージャーだった頃がまさにこれだった」(清水さん)。伊井哲朗さんは「常に一歩引いて、今の相場のステージを確認するときにこの格言を意識する」。
足元では人工知能(AI)関連銘柄に資金が集まる相場が続く。
香川さんは「AI相場はまだ1年半しか経過しておらず楽観や幸福には至ってないとみたい」という。中野晴啓さんは「経営者としての座右の銘のひとつでもある」と打ち明ける。
3位 頭と尻尾はくれてやれ

相場の最も安い水準や高い水準を確認してから、その水準から少し高くなったり安くなったところで売り買いするという格言。
相場のピークやボトムを予想して売買に成功し続けるのは不可能に近いといわれている。
藤野英人さんは「強欲になり、底値で買って天井で売ろうとしがちだが、かえって損をするときがある」と話す。ほどほどで満足するという考え方は、人生にも通じる。
清水さんは「個人投資家からは売ったあとに株価が上昇したり、買ったあとに株価が下落することに対する愚痴を聞く。
サンクコスト(埋没費用)に捉われるとその後の投資判断が鈍る。最初からそういう前提で投資判断をすることが肝心」と指摘する。
4位 卵はひとつのかごに盛るな

投資資金を1つの対象に投じるのではなく、複数の対象に分散する重要性を説く。
資産を株式だけに集中させると相場が急落したときに損失が大きくなるが、債券や金などにも投資すればリスクを分散できる。
「資産形成は相場変動のリスクを分散できる投資先を組み合わせ、じっくりと年数をかけることが望ましい」(市川雅浩さん)
株式投資でも特定の企業のみに投資するのはリスクがある。
石黒英之さんは「特定銘柄に集中投資していたことで含み損が拡大したことがあった」と振り返る。
清水さんは「価格の動き方が異なる銘柄に分散投資すれば、リターンを下げずにリスクを下げられる」という。
実生活でも資金や時間を特定のものに集中させるほどリスクは高まる。分散投資の考えはあらゆる場面で必要となりそうだ。
5位 「もう」はまだなり、「まだ」はもうなり
上昇相場で「まだ上がる」と思っていても「もう売り時」かもしれず、下落相場で「もう底値だ」と思っても「まだ下がる」かもしれない。
「2008年の米国銀行株の値動きはまさに『まだはもうなり』で、日々ハラハラしていた」(塩田さん)
清水さんは「本来傾向がないところにあたかも傾向があるように判断しがちな人を戒める格言だ」と説明する。
「安易に『もう』『まだ』という心理を投資判断に入れるべきではない」とのことだ。
米国の著名投資家ウォーレン・バフェット氏の名言にも「他者が貪欲な時に恐怖心を抱き、他者が恐怖心を抱いている時に貪欲であれ」と似たものがある。
ほかの人の動きに流されず、自らの指針に従う行動が必要だと説く格言は人生の岐路の判断にも役立つ。
6位 相場は相場に聞け

相場の行方は分かりにくいので、自分の考えや予想を押し通すと失敗することがある。
伊井さんは「今、市場は何を語ろうとしているのかを常に考えている」という。
現在の生成AI相場についても「単に買われ過ぎとみるだけでなく、その後のイノベーションを示唆している部分を丁寧にみる」と説明する。
相場はあらゆる材料を織り込んで動く。
「市場がみているテーマやリスク材料を相場から、聞こえてくる声から判断することがとても重要」(石黒さん)。井出真吾さんは「株価は自分ではなくみんなが決めるもの」と強調。
格言は相場の話だとしながら「世の中も似たところがある」と付け加える。
7位 相場は明日もある
相場は今日で終わりではなく明日もある。焦って売買せずに冷静になろう。
塩田さんは「楽観的にならないとマーケットの波を乗り越えられない」と指摘する。
保有する銘柄が今日は上昇しなくても、次の日以降の需給や物色の変化で上昇することがある。
「一定の投資判断で買ったのであれば、大きく下落したりシナリオが変わったりしない限り相応の中長期目線で臨みたい」(香川さん)
清水さんは「取り返せない損失に捉われると、判断を誤ることが多いのは人生も一緒だ」と説明する。
井出さんも「失敗したとき『人生にはまだ先がある』と自分に言い聞かせている」という。
8位 買いは技術 売りは芸術
株を買うタイミングの見極めは学習すれば身につくが、株を売るタイミングを見極めるにはセンスや才能が必要とされる。
投資を考えるとき、企業の業績見通しや財務情報、株価水準などを調べれば買いの判断がしやすい。
一方、売りのタイミングは合理的に判断しにくい。
ユルマズさんは「株は売るのは買うことより100倍難しい。買う理由はいくらでもみつかるが、売る理由やポイントをみつけるのはハード。
スキル、知識、経験と直感が必要とされる行為なので芸術に近い部分がある」と強調する。
伊井さんも「ラストワンマイルは、アートの世界。特に売りは、違和感を感じれるかどうかが重要だ」と指摘する。
8位 利食い急ぐな損急げ

相場が上昇するなかで早めに利益を確定すると利幅が少なくなるため、急ぐ必要はない。
一方で、下落相場では損失を早めに確定しないと損失が拡大する恐れがある。
ところが「投資において損失を避けるために早く利食いしてしまうし、逆に損失を確定させたくないために損切りが遅れてしまう」(清水さん)。
人間の性(さが)だが「相場名人には損切りが上手な投資家が多い」(香川さん)。
投資の目的は利益を最大化し、損失を最小化することだ。
石黒さんによると「投資では、日常の合理的な行動を心がけることが肝要」とのこと。普段の生活でも合理的な行動をしたい。
10位 二度に買うべし 二度に売るべし

投資を始めるとき、いきなり大きな金額を投じて売り買いするのではなく、まずは様子見で少しだけ売ったり買ったりする慎重さが重要だ。
多くの人が参加する相場の世界で、ピンポイントで高値や安値、売買のタイミングを当てるのは難しい。
石黒さんは「投資はリスクコントロールが大事。
一括投資で大きなリスクを背負いすぎると、精神的にも追い込まれる」と戒める。
石黒さんは2020年の新型コロナウイルス禍でも数十回に分けて買いを入れたという。
一度で大きなリスクを取るのではなく少しずつ挑戦することの必要性は、人生でも同様だ。
まだある 判断の助けになる格言
よく知らない分野や理解できない商品には投資しないほうがいい。
歴史の重み伝える言葉
機械による高速売買が増えても、その裏にいるのは生身の人間だ。
投資格言には幾多の人々が成功や失敗から学んだ知恵が詰まっている。
格言は過去の経験を映すものであり、予測には役立たないとみられがちだ。
しかし金融市場がバブルとその崩壊を繰り返してきたように、格言の元となった相場の動きには再現性のあるものも少なくない。
長期投資の王道をいくなら、相場のリスク要因はいつも意識しておくべきだ。
時代をくぐり抜けてきた格言には投資だけでなく、人生に生かせるものも多い。
運用成績が一時的に向上したことで気が大きくなり、よりリスクの高い商品に投資したり、余計な支出を増やしたりすることを意味する「心緩めば財布も緩む」など、「市場だけでなく人生すべてに通じる金言」(塩田さん)と受け止められるものもある。
実際、今回の評価に加わった専門家の中には、事業を進めるうえで投資格言を参考にしている人もいた。
ランキングに入った格言も、変動の激しい相場のリスクを低減させる分散投資や時間を味方につける長期投資の心得に関わるものが多い。
ランキングの見方
数字は専門家の評価を点数化。イラストは松原三佐子。
調査の方法
(岩本貴子)
[NIKKEIプラス1 2024年6月1日付]