ご訪問ありがとうございます→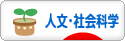 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
「そうだったのか編」(と勝手に名づけている)も3回目ですが、今回は、今まで疑問にさえ思っていなかったけれども、考えてみれば、「なぜ」という思いが湧いて当然の出来事です。
3人の偉業については、改めて述べるまでもありませんが、念のため、一通りお浚いしておきましょう。
*コロンブス:イタリア人
ポルトガルに援助を申し入れるが断られ、スペインの援助を得て、インド航路を発見すべく出発。1492年にアメリカ大陸を発見。
*バスコ・ダ・ガマ:ポルトガル人
ポルトガル王の命令により、1498年、アフリカ喜望峰回りのインド航路を発見。
*マゼラン:ポルトガル人
スペインの援助により、西回りインド航路を発見すべく、南アメリカを回って太平洋へ出て、世界一周を達成する。
コロンブスが「アメリカ大陸」を「発見」したのではないことと、マゼランが世界一周を達成した「のではない」ことは世界史の常識ですが、今回の話とは関係ないので、駄文では、文部科学省検定教科書に最大級の敬意を表して、両者の業績とします。
<念のため補足を・・・>
コロンブスは自分の発見した土地が新大陸だとは夢にも思わず、インドだと信じて疑いませんでした。そこで、原住民を「インド人」の意味で「インディアン」と呼んだのです。さらに、そもそも原住民がいる以上、「発見」という概念は成立しません。
マゼランについては、世界一周の途上、1521年にフィリピンで死亡しており、翌1522年に世界一周を果たして帰国したのは部下のエルカーノ他でしたから、本来、この名誉は彼らに与えられるべきです。・・・1521年に死亡したマゼランが、1522年に世界一周を達成したと教えている世界史の授業は・・・バカバカしいにも程があると思うのですが・・・
ただし、マゼランが若い頃インドまで来ていた事実を挙げ、「史上初めて地球上のすべての経線を横切った人物」としてマゼランを弁護する論もありますが、それは後世判明したことで、当時のマゼラン自身にその認識はありませんでしたし、仮にそれを肯定するとすれば、世界一周の開始と終わりの年号は、マゼラン生誕と死亡の年号を採用しなければなりません。
ま、どっちでもいいですが・・・
まずは3人の国籍と、援助をした国に注目してください。
*コロンブス・・・国籍イタリア、援助国スペイン(当初、ポルトガルに断られる)
*バスコ・ダ・ガマ・・・国籍ポルトガル、援助国ポルトガル
*マゼラン・・・国籍ポルトガル、援助国スペイン
ごく単純には、自国の王に援助を申し入れるのが当然でしょうが、冒険家たちにとっては、援助さえしてくれるのならどこでもよかったことが、これらから伺えます。バスコ・ダ・ガマは自国の命令を受けていますが、これも、たまたま自分の国籍と援助をした国が一致したと見るべきで、他国がいち早く彼に有利な条件を示していたら、そちらへなびいたかもしれないことは、容易に想像がつきます。
また各国についても、自国の利益に与する者なら国籍など問わなかった、特にスペインは、敵国であるはずのポルトガル人マゼランを採用していますから、節操も何もあったものではない、という観さえあります。
まとめると、世界を小さくした3つの偉業には、次のような図式ができあがります。
「ポルトガルは、コロンブスの申し出を断ったばかりに彼を手放してしまい、スペインに先を越された。焦ったポルトガルはバスコ・ダ・ガマを使ってスペインに追いついた。追いつかれたスペインは、なりふり構わず敵国ポルトガル人であるマゼランを登用し、覇権を回復した」
ということで、ポルトガルでもスペインでもどっちでもいいのですが、とにかく、これによりインドへの航路が開かれ、新大陸発見というオマケまでついて、ヨーロッパ各国は、海路での、アジア進出を果たし、日本史への関わり合いとしては、1543年種子島への鉄砲伝来、1549年キリスト教伝来へとつながります。
・・・と、教科書ならここで終わり、学生はこの事実を暗記して、受験に臨むでしょう。
しかし、それでは面白くないので、大航海時代の幕を開いた科学の発達を紹介します。
*13世紀前半頃のヨーロッパで、羅針盤が揺れる船上でも使えるよう改良され、遠洋航海が容易になった。
*1474年、天文学者トスカネッリが、地球球体説を唱えた。・・・ただし、地球球体説そのものは紀元前からあったものの、科学的証拠に乏しかった。
ローマ帝国を代表とするように、それまで航海といえば地中海が主で、大西洋は、陸地を視認できる沿岸部はともかく、大海原へ向かって船を漕ぎ出そうものなら、無事帰還する保障はありませんでしたが、羅針盤の改良と天文学の発達(天体観測)とが相俟って、目印ひとつない広い海へ進出しても、正確に元の港へ帰ってくることができるようになりました。
これにより、未知の海域へ船を進める下地はできあがります。
また古来より、地面は平らではなく球ではないか、ということは何となく言われてきました。もちろん、その「何となく」の理由は、今から考えれば全く正しかったのですが、トスカネッリはそれを詳細に研究し、西回りで地球一周する計画まで立て、この地図を携えたコロンブスは、ご存知のとおりの業績を上げたわけです。
ただし、トスカネッリは地球の直径を実際より小さく計算していたため、コロンブスは死ぬまで自分の勘違いに気づかないままでした。
こうしてヨーロッパ各国が、大西洋、結果的に太平洋まで進出するお膳立ては整いました。
では、ここからが本題です。
私も、漫然と事実だけを記憶して受験に臨んだ口なので、気づきもしなかったのですが、もう少し歴史の勉強に余裕があり、各々独立した事実を有機的に繋ぎ合わせることができたなら、次の疑問を持ってもよかったはずです。
そもそもヨーロッパ各国は、なぜ、それまで使っていた陸路のシルクロードに見切りをつけ、新たに「海路」を求めたのか?
単なる冒険ではあり得ません。冒険には人的損失とともに莫大な費用がかかり、「投資」に見合う「利益」が見込めなければ、各国とも金をドブに捨てるような真似はしません。実際、ポルトガルは、コロンブスの申し出を一旦は断っています。
だから、大航海時代のお膳立てが整ったとしても、腹が減っていなければ、膳に食らいつく必要はありません。逆に、「節操なし」のような真似をしてまで食らいつくには、シルクロードでは腹が満たされない、十分な理由があるはずです。
その理由には、次の事実が関係してきます。
*1299年、オスマン帝国(私と同年代の方は、オスマン=トルコ帝国と覚えておいででしょう)が勢力を広げ、現在のトルコあたりを支配し、シルクロードによる東西貿易の中継地として栄えた。
私も試験のため、ふんふんとこの事実を覚えていただけで、あまり深く考えなかったのですが、「東西貿易の中継地」というのが鍵でした。
オスマン帝国の隆盛は、インド・中国と貿易をするヨーロッパ各国にとって、重大な問題となります。すなわち、オスマン帝国はシルクロードのど真ん中に位置しています。
そしてオスマン帝国は、領土内を通過する者に高額の税金をかけたのです。
そうかといって、オスマン帝国を迂回するには、黒海やカスピ海をも迂回しなければならず、ロシア領土へ入り込むとともに、回り道と、冬は極寒のため損失は多くなり、下手をすれば商隊は全滅してしまいます。
ですから、オスマン帝国の税金はもちろん、商隊の損失を防ぐためにも、海路が求められたのです。さらには、陸路でラクダに荷を運ばせるより、船を使ったほうが、はるかに多くの荷が運べ、当然、利益も比例して大きくなります。
実際、ポルトガル(バスコ・ダ・ガマ)は莫大な利益を上げ、当時のヨーロッパ随一の強大国となりました。
歴史に残る大発見の動機が「税金逃れ」だったとは、想像もしていませんでした。
でも、人間臭くていいですね。
それにしても、それぞれ独立した事件だと思っていたコロンブス、バスコ・ダ・ガマ、マゼラン、オスマン帝国が、こんなふうにつながり、さらに、社会科の歴史ではなく理科の歴史である羅針盤やトスカネッリさえも、ここにつながってくるとは、なるほど、歴史は総合科学であることを、改めて認識しました。
こんな事実を学生の頃に教わっていたら、私の社会科の成績も、もう少しよかったかもしれませんが、歴史に「if」は許されませんからね。残念ながら。
「そうだったのか編」(と勝手に名づけている)も3回目ですが、今回は、今まで疑問にさえ思っていなかったけれども、考えてみれば、「なぜ」という思いが湧いて当然の出来事です。
3人の偉業については、改めて述べるまでもありませんが、念のため、一通りお浚いしておきましょう。
*コロンブス:イタリア人
ポルトガルに援助を申し入れるが断られ、スペインの援助を得て、インド航路を発見すべく出発。1492年にアメリカ大陸を発見。
*バスコ・ダ・ガマ:ポルトガル人
ポルトガル王の命令により、1498年、アフリカ喜望峰回りのインド航路を発見。
*マゼラン:ポルトガル人
スペインの援助により、西回りインド航路を発見すべく、南アメリカを回って太平洋へ出て、世界一周を達成する。
コロンブスが「アメリカ大陸」を「発見」したのではないことと、マゼランが世界一周を達成した「のではない」ことは世界史の常識ですが、今回の話とは関係ないので、駄文では、文部科学省検定教科書に最大級の敬意を表して、両者の業績とします。
<念のため補足を・・・>
コロンブスは自分の発見した土地が新大陸だとは夢にも思わず、インドだと信じて疑いませんでした。そこで、原住民を「インド人」の意味で「インディアン」と呼んだのです。さらに、そもそも原住民がいる以上、「発見」という概念は成立しません。
マゼランについては、世界一周の途上、1521年にフィリピンで死亡しており、翌1522年に世界一周を果たして帰国したのは部下のエルカーノ他でしたから、本来、この名誉は彼らに与えられるべきです。・・・1521年に死亡したマゼランが、1522年に世界一周を達成したと教えている世界史の授業は・・・バカバカしいにも程があると思うのですが・・・
ただし、マゼランが若い頃インドまで来ていた事実を挙げ、「史上初めて地球上のすべての経線を横切った人物」としてマゼランを弁護する論もありますが、それは後世判明したことで、当時のマゼラン自身にその認識はありませんでしたし、仮にそれを肯定するとすれば、世界一周の開始と終わりの年号は、マゼラン生誕と死亡の年号を採用しなければなりません。
ま、どっちでもいいですが・・・
まずは3人の国籍と、援助をした国に注目してください。
*コロンブス・・・国籍イタリア、援助国スペイン(当初、ポルトガルに断られる)
*バスコ・ダ・ガマ・・・国籍ポルトガル、援助国ポルトガル
*マゼラン・・・国籍ポルトガル、援助国スペイン
ごく単純には、自国の王に援助を申し入れるのが当然でしょうが、冒険家たちにとっては、援助さえしてくれるのならどこでもよかったことが、これらから伺えます。バスコ・ダ・ガマは自国の命令を受けていますが、これも、たまたま自分の国籍と援助をした国が一致したと見るべきで、他国がいち早く彼に有利な条件を示していたら、そちらへなびいたかもしれないことは、容易に想像がつきます。
また各国についても、自国の利益に与する者なら国籍など問わなかった、特にスペインは、敵国であるはずのポルトガル人マゼランを採用していますから、節操も何もあったものではない、という観さえあります。
まとめると、世界を小さくした3つの偉業には、次のような図式ができあがります。
「ポルトガルは、コロンブスの申し出を断ったばかりに彼を手放してしまい、スペインに先を越された。焦ったポルトガルはバスコ・ダ・ガマを使ってスペインに追いついた。追いつかれたスペインは、なりふり構わず敵国ポルトガル人であるマゼランを登用し、覇権を回復した」
ということで、ポルトガルでもスペインでもどっちでもいいのですが、とにかく、これによりインドへの航路が開かれ、新大陸発見というオマケまでついて、ヨーロッパ各国は、海路での、アジア進出を果たし、日本史への関わり合いとしては、1543年種子島への鉄砲伝来、1549年キリスト教伝来へとつながります。
・・・と、教科書ならここで終わり、学生はこの事実を暗記して、受験に臨むでしょう。
しかし、それでは面白くないので、大航海時代の幕を開いた科学の発達を紹介します。
*13世紀前半頃のヨーロッパで、羅針盤が揺れる船上でも使えるよう改良され、遠洋航海が容易になった。
*1474年、天文学者トスカネッリが、地球球体説を唱えた。・・・ただし、地球球体説そのものは紀元前からあったものの、科学的証拠に乏しかった。
ローマ帝国を代表とするように、それまで航海といえば地中海が主で、大西洋は、陸地を視認できる沿岸部はともかく、大海原へ向かって船を漕ぎ出そうものなら、無事帰還する保障はありませんでしたが、羅針盤の改良と天文学の発達(天体観測)とが相俟って、目印ひとつない広い海へ進出しても、正確に元の港へ帰ってくることができるようになりました。
これにより、未知の海域へ船を進める下地はできあがります。
また古来より、地面は平らではなく球ではないか、ということは何となく言われてきました。もちろん、その「何となく」の理由は、今から考えれば全く正しかったのですが、トスカネッリはそれを詳細に研究し、西回りで地球一周する計画まで立て、この地図を携えたコロンブスは、ご存知のとおりの業績を上げたわけです。
ただし、トスカネッリは地球の直径を実際より小さく計算していたため、コロンブスは死ぬまで自分の勘違いに気づかないままでした。
こうしてヨーロッパ各国が、大西洋、結果的に太平洋まで進出するお膳立ては整いました。
では、ここからが本題です。
私も、漫然と事実だけを記憶して受験に臨んだ口なので、気づきもしなかったのですが、もう少し歴史の勉強に余裕があり、各々独立した事実を有機的に繋ぎ合わせることができたなら、次の疑問を持ってもよかったはずです。
そもそもヨーロッパ各国は、なぜ、それまで使っていた陸路のシルクロードに見切りをつけ、新たに「海路」を求めたのか?
単なる冒険ではあり得ません。冒険には人的損失とともに莫大な費用がかかり、「投資」に見合う「利益」が見込めなければ、各国とも金をドブに捨てるような真似はしません。実際、ポルトガルは、コロンブスの申し出を一旦は断っています。
だから、大航海時代のお膳立てが整ったとしても、腹が減っていなければ、膳に食らいつく必要はありません。逆に、「節操なし」のような真似をしてまで食らいつくには、シルクロードでは腹が満たされない、十分な理由があるはずです。
その理由には、次の事実が関係してきます。
*1299年、オスマン帝国(私と同年代の方は、オスマン=トルコ帝国と覚えておいででしょう)が勢力を広げ、現在のトルコあたりを支配し、シルクロードによる東西貿易の中継地として栄えた。
私も試験のため、ふんふんとこの事実を覚えていただけで、あまり深く考えなかったのですが、「東西貿易の中継地」というのが鍵でした。
オスマン帝国の隆盛は、インド・中国と貿易をするヨーロッパ各国にとって、重大な問題となります。すなわち、オスマン帝国はシルクロードのど真ん中に位置しています。
そしてオスマン帝国は、領土内を通過する者に高額の税金をかけたのです。
そうかといって、オスマン帝国を迂回するには、黒海やカスピ海をも迂回しなければならず、ロシア領土へ入り込むとともに、回り道と、冬は極寒のため損失は多くなり、下手をすれば商隊は全滅してしまいます。
ですから、オスマン帝国の税金はもちろん、商隊の損失を防ぐためにも、海路が求められたのです。さらには、陸路でラクダに荷を運ばせるより、船を使ったほうが、はるかに多くの荷が運べ、当然、利益も比例して大きくなります。
実際、ポルトガル(バスコ・ダ・ガマ)は莫大な利益を上げ、当時のヨーロッパ随一の強大国となりました。
歴史に残る大発見の動機が「税金逃れ」だったとは、想像もしていませんでした。
でも、人間臭くていいですね。
それにしても、それぞれ独立した事件だと思っていたコロンブス、バスコ・ダ・ガマ、マゼラン、オスマン帝国が、こんなふうにつながり、さらに、社会科の歴史ではなく理科の歴史である羅針盤やトスカネッリさえも、ここにつながってくるとは、なるほど、歴史は総合科学であることを、改めて認識しました。
こんな事実を学生の頃に教わっていたら、私の社会科の成績も、もう少しよかったかもしれませんが、歴史に「if」は許されませんからね。残念ながら。










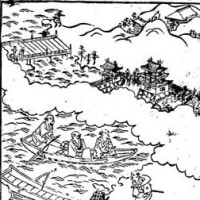
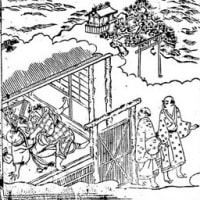
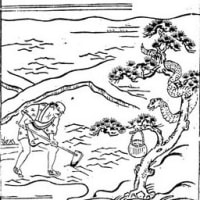

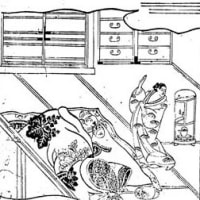


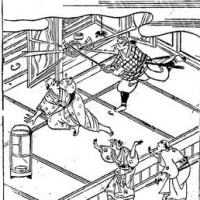
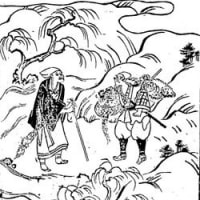
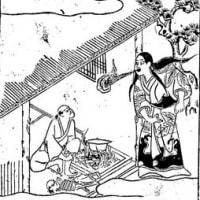
今日読んだ日経新聞にコロンブスとマゼランの記事があり検索しました。
他の講義もこれから勉強させていただきます。
最近ちょっと忙しくて、自分のブログも見れず、返事が遅くなり、失礼いたしました。
さて、過分なお褒めの言葉を、ありがとうございました。
学生時代を遥か昔に過ごした私は、ようやく今になって、理科や社会、国語や数学といった学科の垣根を越えて、一見無関係に思える事実を、有機的につなげることができるようになり、私なりの「大発見」に酔っています。・・・もっともそんなこと、専門家にとっては常識なのでしょうが。
拙い文章で恐縮ですが、オジサンの独り言、お読みいただければ幸いです。
ではまた、よかったらお立ち寄りください。
社会科が大の苦手の中学生の娘に大航海時代の解説をするのに、こちらに漂着した者です。
社会科は暗記科目ではないというのが大変良く分かりました。
ただ単にコロンブス・マゼランなどと名前を覚えるのではなく、当時の経済的な覇権争い、政治家と冒険家、全体として見ると何と面白いんだろう!と夢中になって拝読しました。
ユーラシア大陸を中心とした世界地図を書いてみるとより良く分かりますね。
娘と一緒に勉強頑張ります。
どうも有難う御座いました!
楽しんで頂けたようで、大変うれしく思います。
社会科は、歴史も地理も政治経済も、実は密接につながっていて、相互に理解出来たなら、こんなに面白いものはありませんね。
でも、残念ながら受験のためにはそんなことに構っていられず、とにかく覚えるだけ、というのでは、私のように社会科嫌いをつくるだけでしょう。
木を見て森を見ず、では、美しい景色に気づきもしない、といったところでしょうか。
娘さんの勉強に、少しでもお役に立てたのなら、こんな嬉しいことはありません。よかったら、またお立ち寄りください。
社会科の教師を長年務めているものより
本職の先生からお褒めの言葉を頂き、緊張してしまいます。単なる歴史好きの素人としては、お恥ずかしい限りです。
私は歴史好きですが、学生の頃、「歴史の授業」は嫌いでした。
翻って、カミさんも歴史好きですが、学生の頃、「歴史の授業」が面白くて堪らなかったそうです。
どこが違うのかよく話し合ってみたところ、私が教わった先生は、教科書を読み上げて事実のみを教えていたのに対し、カミさんが教わった先生は、話が脱線ばかりして、しかもその脱線話が面白くて、知らず知らずのうちに歴史が頭に入って来る、そうした授業だったそうです。
悔しいから、学生の頃、「不完全燃焼」だった歴史の勉強に、今になって夢中になり、自分で脱線話をこしらえて、ひとり悦に入っているのが駄文です。
単なる独り言に過ぎないブログですが、良かったらまた、お立ち寄りください。
Wikipediaではどうしても史実の羅列だけで、どうしても退屈になりがちなのですが、エヌ様のブログでは興味深く最後まで読んでしまいました。
また勉強させてください、有り難うございました。
ポルトガル旅行ですか。それは羨ましい。
私は、日本史の舞台(ただし古代史)なら出かけて行ったりもしましたが、世界史の舞台ヘはなかなか行けず、仕方なく「机上の空論」遊びで自己満足をしております。
それでも、Wikiにない何かを、ポルトさんへ差し上げられたのなら、駄文を綴った甲斐があります。
日本史の駄文も、良かったらご覧ください。お待ちしております。