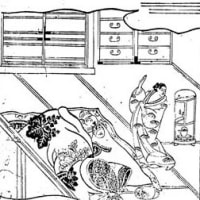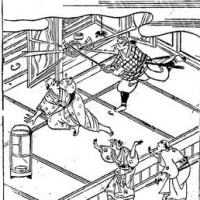ご訪問ありがとうございます→ ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
京都六条の寺内に、木綿綛(=もめんかせ:糸を巻き取る道具)を商う市左衛門という者は、息子が一人がいて、市之介といった。
親の市左衛門は、浄土宗の熱心な信心者で、毎年のお山詣りを欠かさなかったことを見込まれ、寺の大切な役目なども引き受けて本山の先立となったり、水無月の大役を勤めて、富士山詣りも二三度に及んでいた。その他、諸事の名誉ある会長なども引き受け、報謝をなし、寄進を心にかけ、人にも勧め自分も善を尽くしていた。
また、市左衛門は、一人息子の市之介にも、十三の歳より勤めをさせ、商いの合間には、共に仏事を手伝わせていた。
ところが元禄十四年の卯月始め頃から、市之介は病気になって、しかも思いのほか重く、十死一生(ほとんど助かる見込みがない)となってしまった。一人っ子でもあり、父母の悲しみは尋常でなく、何ともしてこの病気を本復させたい、自分たちの命に替えても息子の命を取り留めたいと、ありとあらゆる療治や様々の祈祷を尽し、昼夜、枕元も離れず看病を続けた。
その頃、市左衛門の隣に住む者は、日蓮宗の信者で、何事も法華経でなくては功能がないと深く思い込んでいて、市之介の病気を見舞いに来て、日蓮宗に入るよう熱心に勧め、
「日蓮宗に入って法華経を信じれば、一切の悪病に悩まされることはありません。市之介さんを日蓮宗に入れさせれば、早速、病気も平癒なさるでしょう」
と掻き口説いた。
親の身の悲しさ、子を思う闇に迷う心から市左衛門夫婦は、
「では、入信させてください」
と、曼荼羅を吊るし、題目を唱え、一生懸命に祈った。
しかし業は定まっていたものか、市之介は十八歳で、眠るが如くに、化野(あだしの)の煙となって立上っていった。
両親の嘆きは計り知れず、明け暮れ恋い焦がれ泣き悲しみ、袂の乾く間もない程であったが、いくら嘆いても甲斐のないことであれば、仏前に花を手向け、心から祈って、二週間ばかりが過ぎた。

そこへ、富士山詣りに同行したこともある、市左衛門の友人が訪ねてきた。
友人が語るには、長い間望んでいた白山や立山の山詣りを志して、弥生の末より思い立って、加州の白山から立山へ詣で、具合が良ければ富士山にも行こうかと考えながら、立山に登ったところ、山上の思いがけない所で市之介に逢ったと言う。市之介の様子は、さほど拵えた旅姿でもなく普段着のままで、この市左衛門の友人を見つけ、懐かしげに近寄って
「私は、富士山上に登り、これより立山を拝見しようとの思い付きに任せて、ここまで参りました。また、白山や湯殿山などにも上ってみたいと思い、ついでに参詣しようと思っていたのですが、貴方が、これからお帰りになるのでしたら、故郷に伝えていただきたい物がありますので、預かっていただけませんか」
と言って、小さな紙包みを一つと、袷の袖を少し切り取って、その友人に渡した。そして、
「出発してから、だいぶ日数が過ぎてしまいましたので、先を急ぎたいと思います。どうぞ、その包みをお願いいたします」
と言って、二人は別れたと言う。
それから、この友人は帰ってきて、何よりもまず市左衛門方へ立ち寄り、
「さても市之介殿は、若い人には奇特に信心を起こして、しかも一人旅と見えました。ご両親も、よく市之介殿の志を助けて、秘蔵子とも言わず、旅に出させられましたな」
などと誉め上げて、件の紙包みを渡した。
それを受け取って両親は、人目も恥じずに声をあげて泣き叫びつつ、
「羨ましいことです。貴方は、市之介に逢われたのですね。私達は別れてからというもの、夢にも見ることがなく、恋し恋しと思う余りに、命を捨ててでも来世に逢いたいと願っているほどです。でも、そんな私達に市之介はつれなくて、貴方には便りを託されたのですね」
と泣き悲しんだ。
友人は、さては市之介は死んでしまって、亡魂が現れて自分に話しかけてきたのか、と思ったが、
「何はともあれ、まずは、その紙包みを開いてごらんなさい」
と勧めた。
両親が泣く泣く包みを開けてみれば、市之介の末期に両親が唱えていた題目の曼荼羅であった。また、市之介が死んだ後、着ていた袷の袖のが切れていたのを不思議に思っていたが、立山で切り取ったという袷の切れ端を合わせてみると、紛れもなく死ぬまで着せていた袷の袖であり、これも亡者の態かと知った。
両親は、心にもあらぬ事で、むやみに宗旨を替えてはいけないと悟り、その後は偏に浄土宗門の弔いを続けた。
京都六条の寺内に、木綿綛(=もめんかせ:糸を巻き取る道具)を商う市左衛門という者は、息子が一人がいて、市之介といった。
親の市左衛門は、浄土宗の熱心な信心者で、毎年のお山詣りを欠かさなかったことを見込まれ、寺の大切な役目なども引き受けて本山の先立となったり、水無月の大役を勤めて、富士山詣りも二三度に及んでいた。その他、諸事の名誉ある会長なども引き受け、報謝をなし、寄進を心にかけ、人にも勧め自分も善を尽くしていた。
また、市左衛門は、一人息子の市之介にも、十三の歳より勤めをさせ、商いの合間には、共に仏事を手伝わせていた。
ところが元禄十四年の卯月始め頃から、市之介は病気になって、しかも思いのほか重く、十死一生(ほとんど助かる見込みがない)となってしまった。一人っ子でもあり、父母の悲しみは尋常でなく、何ともしてこの病気を本復させたい、自分たちの命に替えても息子の命を取り留めたいと、ありとあらゆる療治や様々の祈祷を尽し、昼夜、枕元も離れず看病を続けた。
その頃、市左衛門の隣に住む者は、日蓮宗の信者で、何事も法華経でなくては功能がないと深く思い込んでいて、市之介の病気を見舞いに来て、日蓮宗に入るよう熱心に勧め、
「日蓮宗に入って法華経を信じれば、一切の悪病に悩まされることはありません。市之介さんを日蓮宗に入れさせれば、早速、病気も平癒なさるでしょう」
と掻き口説いた。
親の身の悲しさ、子を思う闇に迷う心から市左衛門夫婦は、
「では、入信させてください」
と、曼荼羅を吊るし、題目を唱え、一生懸命に祈った。
しかし業は定まっていたものか、市之介は十八歳で、眠るが如くに、化野(あだしの)の煙となって立上っていった。
両親の嘆きは計り知れず、明け暮れ恋い焦がれ泣き悲しみ、袂の乾く間もない程であったが、いくら嘆いても甲斐のないことであれば、仏前に花を手向け、心から祈って、二週間ばかりが過ぎた。

そこへ、富士山詣りに同行したこともある、市左衛門の友人が訪ねてきた。
友人が語るには、長い間望んでいた白山や立山の山詣りを志して、弥生の末より思い立って、加州の白山から立山へ詣で、具合が良ければ富士山にも行こうかと考えながら、立山に登ったところ、山上の思いがけない所で市之介に逢ったと言う。市之介の様子は、さほど拵えた旅姿でもなく普段着のままで、この市左衛門の友人を見つけ、懐かしげに近寄って
「私は、富士山上に登り、これより立山を拝見しようとの思い付きに任せて、ここまで参りました。また、白山や湯殿山などにも上ってみたいと思い、ついでに参詣しようと思っていたのですが、貴方が、これからお帰りになるのでしたら、故郷に伝えていただきたい物がありますので、預かっていただけませんか」
と言って、小さな紙包みを一つと、袷の袖を少し切り取って、その友人に渡した。そして、
「出発してから、だいぶ日数が過ぎてしまいましたので、先を急ぎたいと思います。どうぞ、その包みをお願いいたします」
と言って、二人は別れたと言う。
それから、この友人は帰ってきて、何よりもまず市左衛門方へ立ち寄り、
「さても市之介殿は、若い人には奇特に信心を起こして、しかも一人旅と見えました。ご両親も、よく市之介殿の志を助けて、秘蔵子とも言わず、旅に出させられましたな」
などと誉め上げて、件の紙包みを渡した。
それを受け取って両親は、人目も恥じずに声をあげて泣き叫びつつ、
「羨ましいことです。貴方は、市之介に逢われたのですね。私達は別れてからというもの、夢にも見ることがなく、恋し恋しと思う余りに、命を捨ててでも来世に逢いたいと願っているほどです。でも、そんな私達に市之介はつれなくて、貴方には便りを託されたのですね」
と泣き悲しんだ。
友人は、さては市之介は死んでしまって、亡魂が現れて自分に話しかけてきたのか、と思ったが、
「何はともあれ、まずは、その紙包みを開いてごらんなさい」
と勧めた。
両親が泣く泣く包みを開けてみれば、市之介の末期に両親が唱えていた題目の曼荼羅であった。また、市之介が死んだ後、着ていた袷の袖のが切れていたのを不思議に思っていたが、立山で切り取ったという袷の切れ端を合わせてみると、紛れもなく死ぬまで着せていた袷の袖であり、これも亡者の態かと知った。
両親は、心にもあらぬ事で、むやみに宗旨を替えてはいけないと悟り、その後は偏に浄土宗門の弔いを続けた。