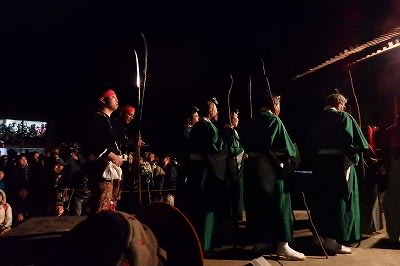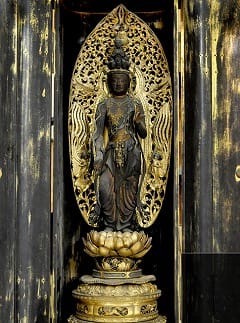仕事の帰り道にある、このお堂、以前にも書いたが
中々中を見ることができなかった、今日帰り道、お堂の
扉が開いていた。

村はずれの地蔵堂
近くのお婆さんやお母さんが8人、掃除をしてお参りして
おしゃべりに花が咲いていた。
きっとここに集まるのは、このおしゃべりがすきなんだなぁと
思った。家のこと、亭主のこと、子供、孫のことと話しの
輪が広がっていく。
そんな他愛ない話を少し聞いていた、他愛ないんだが、なぜか
ほっとする時間でもある。きっと昔はこうして隣近所との関係を
作ってきたのであろう。そして助け合う精神、譲り合う精神が育まれて
きたのであろうか。
このお堂には地蔵菩薩が祀ってあった。
ずっとここに居て村人を守ってきたのであろう、

きっと楽しいおしゃべりタイムであろう
先日のお彼岸の
中日での説教では繋がり、家族の繋がり、地域社会との繋がりが
大事で「おかげさん」の気持ちが重要だと寺の住職は言われていた。
そうなんですね。基本は家族、それが崩壊しないようにしておかないと
とても社会、地域、しいては国家、世界まで広がらない。
~搾取の世紀から譲り合いの世紀へ~
と金田一秀穂さんの言葉