伊東潤『夜叉の都』(文藝春秋)を読む。
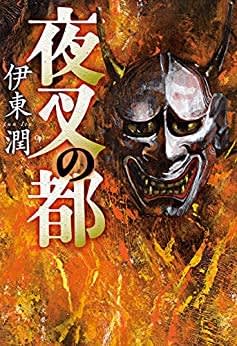
二代将軍頼家のもとで「十三人の合議制」が発足したところから、
ストーリーが始まります。
時系列では『修羅の都』の続きになりますが、細かい設定が異なるので、
続編ではなく独立した物語として読むべきです。
「十三人の合議制」自体がテーマではありませんが、
メモ的に十三人の宿老がどうなったのかを見ておきます。
十三人のうち、頼家の乳父だった梶原景時が失脚。梶原一族は滅亡します。
梶原と同じく頼家の乳父だった比企能員は暗殺され、比企一族も滅亡。
将軍職を降ろされ、修善寺に幽閉されていた頼家も暗殺されます。
三代将軍実朝に代えて、源氏の門葉で御家人筆頭の平賀朝雅を
将軍に擁立しようとした北条時政(平賀朝雅は時政の娘婿)が失脚。
「十三人の合議制」発足当時は「江間義時」として宿老に列した義時が、
「北条義時」として政所別当の座に就きます。
この時点で、十三人のうち三浦義澄、二階堂行政、安達盛長はすでに病死。
八田知家は頼朝の弟で政子の妹婿の阿野全成を誅殺。権力中枢から外されます。
足立遠元と中原親能は高齢で隠居状態。貴族出身の大江広元と三善康信は健在。
有力御家人で侍所別当の和田義盛も健在です。
のちに北条義時の謀略で挙兵に追い込まれた和田義盛と和田一族は滅亡。
承久の乱まで生き残ったのは北条義時、大江広元、三善康信の3人でした。
あたかも「マザー・グース」の『Ten Little Indians』のように、
十三人の宿老は次々と消え去りますが、そこはストーリーの主軸ではありません。
Ten Little Indians | Nursery Rhymes And Kids Songs by KidsCamp
尼御台政子の次女三幡の死で物語が始まり、
長男頼家、次男実朝、孫の一幡、公曉、禅曉と、
頼朝と政子の血を受け継ぐ者が政争の渦中で次々と死んでいきます。
たとえ頼朝と政子の血脈は絶えようとも、「武士の府」である鎌倉府は残す。
タイトル通り、政子は徹頭徹尾「夜叉」として行動します。
この作品の主役は、あくまでも尼御台政子です。
大河ドラマ『草燃える』では岩下志麻が政子を演じていましたが、
そのイメージが重なります。
この物語の影の主役とも言うべき存在が後鳥羽上皇。
後鳥羽院は文武両道に秀でた英邁な君主で、三代将軍実朝と協調し、
院の下に公家・武家・寺社の三者を置く「権門体制」を政権構想としています。
(と、いうことは中世は権門体制ではなかった、ということになりますが…)
鎌倉府の実権を握る北条義時の排除を掲げて後鳥羽院が挙兵したのが承久の乱。
尼御台政子は鎌倉府を守るため、御家人たちに出陣を促し、京都方に勝利しました。
そして、鎌倉府を守るために政子が下した決断とは…
頼朝の血縁者に限らず、源氏の門葉を将軍に担ぎ上げて実権を握る、
という権力奪取のパターンが常態化すると、抗争が終わることはありません。
源氏の門葉よりも高い身分である親王を将軍にすることで、
源氏の門葉を擁する権力闘争を無効化させる実朝の構想は、
鎌倉府の安定のための妙手でした。
それが頼朝の血族を殺す連鎖を止めることでもあったのですが、
甥(頼家の長男)の公暁にその思いは通じなかったようです。
実朝の死で親王将軍構想は頓挫し、
頼朝の妹の曾孫、三寅(藤原頼経)を将軍に迎えますが、
源氏の門葉より高い家格の摂家(藤原摂関家)なので、
この人事もなかなかの妙手です。
「摂家将軍を擁して関東武士団を糾合する」というアイデアは、
戦国時代に近衛前嗣を鎌倉殿(鎌倉公方)とする構想につながるのか…と、
想像が膨らみます。
政子の死の半年後に三寅が将軍宣下を受け、
征夷大将軍藤原頼経、執権北条泰時の体制で鎌倉府は安定します。
『太平記』が将軍足利義満、管領細川頼之の就任で終わるように、
『夜叉の都』も将軍藤原頼経、執権北条泰時の就任で筆を置きます。
もしかしたら『太平記』を意識した結びだったのでしょうか?
考えてみると、源氏の門葉で有力御家人でもある足利高氏の挙兵で北条一族が滅亡。
これを「鎌倉幕府の滅亡」と呼びますが、宮将軍と北条一族に代わり、
将軍職と守護を含む幕府の要職を足利一門で占めたのが室町幕府ですから、
現代の自民党にたとえれば「北条派一強支配から足利派新体制への交代」であって、
当時の武士たちにとって「幕府の滅亡」という感覚はなかったはずです。
もし後醍醐院が北条一族滅亡直後に、足利高氏を将軍に任命していたら、
南北朝の動乱もなく安定した時代になった…かもしれません。
なるほど、歴史を考える上で、たくさんのヒントを得られる作品でした。
| Trackback ( 0 )
|
|