シドニー五輪柔道男子81キロ級金メダルの滝本誠が総合格闘技を引退することが16日、発表された。プロ戦績は11戦6勝5敗で、今後は柔道で後進の指導に当たる。04年大みそかに総合格闘技デビューした滝本はPRIDEと戦極で活躍。判定勝ちした昨年9月の戦極第十陣後、モチベーションが上がらなくなったという。同じ吉田道場所属のバルセロナ五輪柔道男子78キロ級覇者の吉田秀彦は「柔道界に復帰して頑張ってもらいたい」と新たな門出を祝福した。
〔2010年3月17日のサンケースポーツの記事より〕
* * * * *
PRIDEや戦極で活躍したプロ格闘家の瀧本誠は、本来なら4月25日に引退試合を行う吉田秀彦の興行に出場する予定でしたが、「気力の限界」を理由に引退を発表しました。昨年の大みそかに予定されていたSRCの有明大会でダン・ホーンバックルとのウェルター級王座決定戦に臨む予定でしたが、「Dynamite!!」との対抗戦となり同タイトル戦が消滅。試合が流れてモチベーションが低下したことが大きかったみたいです。ただ、個人的には、瀧本は総合格闘家よりも、今から10年前の2000年シドニー五輪で金メダルを獲得したイメージがどうしても強いですね。
シドニー五輪では日本は5つの金メダルを獲得しました。内訳は、女子マラソンの高橋尚子、柔道女子48kg級の田村亮子(現姓・谷)、柔道男子60kg級の野村忠宏、100kg級の井上康生。そして、81㎏級の瀧本です。高橋、田村、野村、井上は実力者なので、金メダルを獲るべくして獲ったイメージがあります。しかし、瀧本に関してはこの4人とは全く逆で、予想外の金メダル獲得でした。むしろ、日本柔道界としては、瀧本よりも1999年の世界選手権で2階級制覇を果たした篠原信一の方を遥かに期待していたはずです。瀧本の金メダルまでの道程を調べれば、いかにメディアや世間一般から全く期待されてなかったのかが自ずと分かります。
1999年10月に英国のバーミンガムで開催された世界選手権。この世界選手権は翌年のシドニー五輪の予選を兼ねており、男女それぞれ8位以内に入った選手の国に五輪出場権を与えられました。なお、世界選手権で出場権を逃した国は、翌年の大陸選手権に回る事を余儀なくされました。日本は、男女それぞれ4階級を制して合計8個の金メダルを獲得するなど大活躍。一方、日本は男女各8階級のうち、男子が3(66㎏級、73kg級、81kg級)、女子が1(57kg級)の合計4階級の五輪出場権をこの世界選手権で獲得できませんでした。その為、翌2000年4月の全日本体重別選手権を制したこの4階級の選手が、5月に大阪で開催されたアジア選手権に回りました。
最終的に、男子66㎏級がアトランタ銀メダリストの中村行成、73kg級がアトランタ五輪優勝の中村兼三、81kg級が瀧本、女子57kg級が日下部基栄の4人が全日本体重別選手権を制します。4人の五輪代表“候補”選手は、余計な2文字を取り外す為に、決戦の地である大阪に乗り込みました。男子が5枠、女子が3枠がアジアに与えられた五輪出場枠でした。決して容易ではありませんが、柔道の母国としては全階級出場は絶対のノルマでした。大会は中村兄弟と日下部が見事に優勝を果たして、シドニーの切符を無事に獲得。しかし、1人だけ大苦戦を強いられた選手がおりました。それが瀧本です。
瀧本は初戦の2回戦は一本勝ちで楽勝します。ところが、次の3回戦で落とし穴に嵌ります。瀧本の3回戦の相手はイランのカゼム・サリハニ。このサリハ二がとんでもない曲者でした。試合はまず、サリハニが河津掛けで有効を奪います。その後サリハニは、極端な左半身から左手で奥襟を掴むと、左足を小内刈りを牽制するように瀧本の両膝の間に執拗に差し込みます。しかし、サリハニは右手の引き手を取ろうとはしません。次の瞬間、サリハニは瀧本の左膝裏を跳ね上げ、同時に自分の股の間から右手で瀧本の右大腿部を強引に掬い上げます。そして、自らも後方に体を捨てます。滝本が頭から仰向けに宙を舞った瞬間、会場が唖然となりました。
☆それがこの技です(2000年5月27日 @大阪市中央体育館)
公式の結果は小外刈りでしたが、この蟹挟を変化させた変則技は「ギャバーレ」という名前の技で、今でも柔道ファンの間で語り継がれてます。当時の全日本監督だった山下泰裕はこの技に関して、「変則技の多い欧州でも初めてみる技だ」と驚きを隠せずに語ってます。ちなみに、元レスリング選手であるサリハニのコーチは「レスリングの伝統技として2000年の歴史を持っている」とコメント。ちなみに「ギャバーレ」とはハンモックという意味だそうです。この技を掛けられると相手は逃げられず、ハンモックに揺られるようにゴロンと後ろに倒されます。さらに、この大会を優勝したサリハニは「この技は何故か日本人と韓国人にはよく掛かり易いね」と得意満面に語ってました。それもそのはずで、瀧本はサリハニには前年のアジア選手権でも同じ技でやられてました。
この痛恨の敗戦で瀧本は敗者復活戦に回ります。その後、瀧本は敗者復活戦の3試合を全て一本勝ちで勝ち上がって3位に入り、青色吐息で五輪出場権獲得となりました。ちなみに、柔道で五輪出場資格に制限を加えられたのは1996年のアトランタ五輪からです。おそらく、これまでの過去4大会を見渡しても、日本が五輪出場権獲得失敗に最も近づいたのは、おそらくシドニー五輪の瀧本だったと思われます。
ちなみに、瀧本は国内1次選考会では、講道学舎と世田谷学園の先輩の古賀稔彦に敗退してました。しかし、他の選手が負傷した為、幸運にも次の選考会に進むことが出来た経緯があります。1997年の世界選手権も瀧本は3回戦で敗退。国際大会でこれといった実績も無し。相手を見過ぎたり、消極的な戦いで反則を繰り返す悪癖もありました。このシドニー五輪の男子代表7人のうち、瀧本以外の6人が過去に五輪と世界選手権で優勝経験がありました。なので、世間やメディアは瀧本を「7番目の男」と評して全くノーマークでした。ただ、瀧本はセンスが抜群で意外性のある選手でした。「勝つも負けるも一本」と明らかな一発狙いのタイプの選手でもありました。
瀧本のその意外性が発揮されるのが本番のシドニー五輪です。柔道競技の4日目となった2000年9月19日。大会初日の日本勢は田村と野村がアベック金メダルを獲得しますが、その後2日間は金メダルがゼロに終わります。男子に至っては中村兄弟が敗れた為、この2日間はメダルすら皆無。だが、この4日目に金メダルを期待されたのは瀧本ではなく、女子の前年の63kg級の世界王者だった前田桂子でした。しかし、期待された前田が2回戦でまさかの初戦敗退。誰もが「今日も柔道は金メダルがゼロ」だと諦めの気持ちを抱きました。
ところが、全く期待されてなかった瀧本が世間の低評価を見返すかのように、“一発屋”の本領を存分に発揮します。常に先手を取った思い切りの良い試合で瀧本は勝ち上がります。初戦となった2回戦と3回戦を連続一本勝ち。準々決勝も優勢勝ちでまさかの準決勝に進出。なお、天敵だったアジア王者のサリハニとは反対側のブロックだったことも幸運に働きました(なお、サリハニはシドニー五輪では5位に終わります)。
準決勝の相手は、前回アトランタ五輪の78kg級金メダリストのジャメル・ブーラ(フランス)。ブーラは前回の決勝戦で古賀を旗判定で降した相手でした。瀧本は試合の途中でブーラの左肘が目に直撃するアクシデントがありました。その直後にブーラが瀧本に飛び掛ってきましたが、瀧本は上体を交わして体落しで技ありを奪います。このポイントがものを言って瀧本が優勢勝ちで決勝進出。先輩の敵を獲りました。
決勝戦の相手は、前回アトランタ五輪78kg級銅メダリストで1997年の世界王者の趙麒徹(韓国)。実績から言っても趙の方が間違いなく格上でした。瀧本は前日に敗退した中村兼三の帯を借りて決勝に臨みます。試合は積極的に攻める瀧本のペース。趙が前に出る瞬間に、瀧本は袖釣り込み腰で有効を奪います。その後、焦る趙に対して燕返しで切り返す妙技まで見せるなど、積極果敢に攻めた瀧本は完全に勢いに乗りました。そして、試合終了のブザーが鳴って滝本が優勢勝ち。全く期待してなかった無印選手が、日本に3つ目の金メダルをもたらしました。
☆シドニー五輪決勝で韓国の趙麒徹に優勢勝ちで金メダル獲得
(2000年9月19日 @シドニー・コンベンション・アンド・エキシビジョンセンター)
なお、瀧本は今回の総合格闘技を引退後は、柔道の指導者になる事を希望してます。実は、全日本柔道連盟(全柔連)のこれまでの規定では、「他の格闘技でプロ活動した者に対し、プロ活動を終えてから3年間を経過しなければ再登録を拒否できる」との条項がありました。要するに、柔道界は伝統的にプロ格闘技への拒否反応が強く、プロ転向者への制裁的な意味合いで復帰に対して高いハードルを設けてました。しかし、さすがにこのような制約は時代錯誤なので、3月18日に全柔連は「指導者など競技者以外で復帰する場合に限り1年間に短縮」と緩和しました(なお、選手として復帰する場合は現行通り3年間を要します)。
瀧本は昨年9月から試合をしてないので、早ければ今年の秋に指導者として柔道界に復帰できます。吉田も来春には復帰できます。プロ格闘家としての経験は柔道にも役に立つ面があると思いますので、2人には指導者としても柔道界の発展の為にも頑張ってほしいと思います。
※瀧本誠オフィシャルブログ
〔2010年3月17日のサンケースポーツの記事より〕
* * * * *
PRIDEや戦極で活躍したプロ格闘家の瀧本誠は、本来なら4月25日に引退試合を行う吉田秀彦の興行に出場する予定でしたが、「気力の限界」を理由に引退を発表しました。昨年の大みそかに予定されていたSRCの有明大会でダン・ホーンバックルとのウェルター級王座決定戦に臨む予定でしたが、「Dynamite!!」との対抗戦となり同タイトル戦が消滅。試合が流れてモチベーションが低下したことが大きかったみたいです。ただ、個人的には、瀧本は総合格闘家よりも、今から10年前の2000年シドニー五輪で金メダルを獲得したイメージがどうしても強いですね。
シドニー五輪では日本は5つの金メダルを獲得しました。内訳は、女子マラソンの高橋尚子、柔道女子48kg級の田村亮子(現姓・谷)、柔道男子60kg級の野村忠宏、100kg級の井上康生。そして、81㎏級の瀧本です。高橋、田村、野村、井上は実力者なので、金メダルを獲るべくして獲ったイメージがあります。しかし、瀧本に関してはこの4人とは全く逆で、予想外の金メダル獲得でした。むしろ、日本柔道界としては、瀧本よりも1999年の世界選手権で2階級制覇を果たした篠原信一の方を遥かに期待していたはずです。瀧本の金メダルまでの道程を調べれば、いかにメディアや世間一般から全く期待されてなかったのかが自ずと分かります。
1999年10月に英国のバーミンガムで開催された世界選手権。この世界選手権は翌年のシドニー五輪の予選を兼ねており、男女それぞれ8位以内に入った選手の国に五輪出場権を与えられました。なお、世界選手権で出場権を逃した国は、翌年の大陸選手権に回る事を余儀なくされました。日本は、男女それぞれ4階級を制して合計8個の金メダルを獲得するなど大活躍。一方、日本は男女各8階級のうち、男子が3(66㎏級、73kg級、81kg級)、女子が1(57kg級)の合計4階級の五輪出場権をこの世界選手権で獲得できませんでした。その為、翌2000年4月の全日本体重別選手権を制したこの4階級の選手が、5月に大阪で開催されたアジア選手権に回りました。
最終的に、男子66㎏級がアトランタ銀メダリストの中村行成、73kg級がアトランタ五輪優勝の中村兼三、81kg級が瀧本、女子57kg級が日下部基栄の4人が全日本体重別選手権を制します。4人の五輪代表“候補”選手は、余計な2文字を取り外す為に、決戦の地である大阪に乗り込みました。男子が5枠、女子が3枠がアジアに与えられた五輪出場枠でした。決して容易ではありませんが、柔道の母国としては全階級出場は絶対のノルマでした。大会は中村兄弟と日下部が見事に優勝を果たして、シドニーの切符を無事に獲得。しかし、1人だけ大苦戦を強いられた選手がおりました。それが瀧本です。
瀧本は初戦の2回戦は一本勝ちで楽勝します。ところが、次の3回戦で落とし穴に嵌ります。瀧本の3回戦の相手はイランのカゼム・サリハニ。このサリハ二がとんでもない曲者でした。試合はまず、サリハニが河津掛けで有効を奪います。その後サリハニは、極端な左半身から左手で奥襟を掴むと、左足を小内刈りを牽制するように瀧本の両膝の間に執拗に差し込みます。しかし、サリハニは右手の引き手を取ろうとはしません。次の瞬間、サリハニは瀧本の左膝裏を跳ね上げ、同時に自分の股の間から右手で瀧本の右大腿部を強引に掬い上げます。そして、自らも後方に体を捨てます。滝本が頭から仰向けに宙を舞った瞬間、会場が唖然となりました。
☆それがこの技です(2000年5月27日 @大阪市中央体育館)
公式の結果は小外刈りでしたが、この蟹挟を変化させた変則技は「ギャバーレ」という名前の技で、今でも柔道ファンの間で語り継がれてます。当時の全日本監督だった山下泰裕はこの技に関して、「変則技の多い欧州でも初めてみる技だ」と驚きを隠せずに語ってます。ちなみに、元レスリング選手であるサリハニのコーチは「レスリングの伝統技として2000年の歴史を持っている」とコメント。ちなみに「ギャバーレ」とはハンモックという意味だそうです。この技を掛けられると相手は逃げられず、ハンモックに揺られるようにゴロンと後ろに倒されます。さらに、この大会を優勝したサリハニは「この技は何故か日本人と韓国人にはよく掛かり易いね」と得意満面に語ってました。それもそのはずで、瀧本はサリハニには前年のアジア選手権でも同じ技でやられてました。
この痛恨の敗戦で瀧本は敗者復活戦に回ります。その後、瀧本は敗者復活戦の3試合を全て一本勝ちで勝ち上がって3位に入り、青色吐息で五輪出場権獲得となりました。ちなみに、柔道で五輪出場資格に制限を加えられたのは1996年のアトランタ五輪からです。おそらく、これまでの過去4大会を見渡しても、日本が五輪出場権獲得失敗に最も近づいたのは、おそらくシドニー五輪の瀧本だったと思われます。
ちなみに、瀧本は国内1次選考会では、講道学舎と世田谷学園の先輩の古賀稔彦に敗退してました。しかし、他の選手が負傷した為、幸運にも次の選考会に進むことが出来た経緯があります。1997年の世界選手権も瀧本は3回戦で敗退。国際大会でこれといった実績も無し。相手を見過ぎたり、消極的な戦いで反則を繰り返す悪癖もありました。このシドニー五輪の男子代表7人のうち、瀧本以外の6人が過去に五輪と世界選手権で優勝経験がありました。なので、世間やメディアは瀧本を「7番目の男」と評して全くノーマークでした。ただ、瀧本はセンスが抜群で意外性のある選手でした。「勝つも負けるも一本」と明らかな一発狙いのタイプの選手でもありました。
瀧本のその意外性が発揮されるのが本番のシドニー五輪です。柔道競技の4日目となった2000年9月19日。大会初日の日本勢は田村と野村がアベック金メダルを獲得しますが、その後2日間は金メダルがゼロに終わります。男子に至っては中村兄弟が敗れた為、この2日間はメダルすら皆無。だが、この4日目に金メダルを期待されたのは瀧本ではなく、女子の前年の63kg級の世界王者だった前田桂子でした。しかし、期待された前田が2回戦でまさかの初戦敗退。誰もが「今日も柔道は金メダルがゼロ」だと諦めの気持ちを抱きました。
ところが、全く期待されてなかった瀧本が世間の低評価を見返すかのように、“一発屋”の本領を存分に発揮します。常に先手を取った思い切りの良い試合で瀧本は勝ち上がります。初戦となった2回戦と3回戦を連続一本勝ち。準々決勝も優勢勝ちでまさかの準決勝に進出。なお、天敵だったアジア王者のサリハニとは反対側のブロックだったことも幸運に働きました(なお、サリハニはシドニー五輪では5位に終わります)。
準決勝の相手は、前回アトランタ五輪の78kg級金メダリストのジャメル・ブーラ(フランス)。ブーラは前回の決勝戦で古賀を旗判定で降した相手でした。瀧本は試合の途中でブーラの左肘が目に直撃するアクシデントがありました。その直後にブーラが瀧本に飛び掛ってきましたが、瀧本は上体を交わして体落しで技ありを奪います。このポイントがものを言って瀧本が優勢勝ちで決勝進出。先輩の敵を獲りました。
決勝戦の相手は、前回アトランタ五輪78kg級銅メダリストで1997年の世界王者の趙麒徹(韓国)。実績から言っても趙の方が間違いなく格上でした。瀧本は前日に敗退した中村兼三の帯を借りて決勝に臨みます。試合は積極的に攻める瀧本のペース。趙が前に出る瞬間に、瀧本は袖釣り込み腰で有効を奪います。その後、焦る趙に対して燕返しで切り返す妙技まで見せるなど、積極果敢に攻めた瀧本は完全に勢いに乗りました。そして、試合終了のブザーが鳴って滝本が優勢勝ち。全く期待してなかった無印選手が、日本に3つ目の金メダルをもたらしました。
☆シドニー五輪決勝で韓国の趙麒徹に優勢勝ちで金メダル獲得
(2000年9月19日 @シドニー・コンベンション・アンド・エキシビジョンセンター)
なお、瀧本は今回の総合格闘技を引退後は、柔道の指導者になる事を希望してます。実は、全日本柔道連盟(全柔連)のこれまでの規定では、「他の格闘技でプロ活動した者に対し、プロ活動を終えてから3年間を経過しなければ再登録を拒否できる」との条項がありました。要するに、柔道界は伝統的にプロ格闘技への拒否反応が強く、プロ転向者への制裁的な意味合いで復帰に対して高いハードルを設けてました。しかし、さすがにこのような制約は時代錯誤なので、3月18日に全柔連は「指導者など競技者以外で復帰する場合に限り1年間に短縮」と緩和しました(なお、選手として復帰する場合は現行通り3年間を要します)。
瀧本は昨年9月から試合をしてないので、早ければ今年の秋に指導者として柔道界に復帰できます。吉田も来春には復帰できます。プロ格闘家としての経験は柔道にも役に立つ面があると思いますので、2人には指導者としても柔道界の発展の為にも頑張ってほしいと思います。
※瀧本誠オフィシャルブログ
















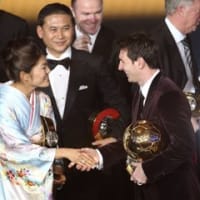


そういえば、そういう方がいたような、気がする・・・、といったところでしょうか。
その他の、お名前を見て、すぐに顔や競技中の場面が思い浮かぶのとは大違い!
でも、この記事を読んで、瀧本選手の事を良く知れたように思います。
柔道というのも、国際競技としてどんどん変化していきますが、猫なべさんの柔道記事を読んでいると、その流れが良く理解できます。
たしかに、シドニーの5人の金メダリストの中では、瀧本は過去の実績と期待度が皆無だったので、印象が薄いのは無理も無いでしょうね。
私はこのアジア選手権をテレビで見てましたけど、解説を務めていた上村春樹が瀧本を「金メダルを獲る力は十分に持ってます」と評してましたけど、「上げ底にも程があるよ!」と、この時点では思ってました。
とはいえ、瀧本は金メダリストになる“何か”を持っていたと思いますね。逆に“何か”を持ってなかったのが、誤審に泣かされた篠原(現・男子代表監督)でした。
日本は前年の世界選手権で7人の世界王者を生み出して、全員がシドニー五輪に出場しました。だが、そのうち金メダルを獲ったのは田村と井上だけでした。五輪は過去の実績も大切ですが、所詮名刺代わりに過ぎず、運や勢いも重要だと思い知りました。
ちなみに、現在の国際柔道界は日本人が思っている以上に変化してます。畳の上では原点回帰が進んでますが、運営面ではプロ化を目指した“JUDO”に確実に変容しつつあります。日本も手を拱いていると、しっぺ返しを喰らう可能性も無きに非ずです。
まさに、猫なべさまの姿勢を表しているなぁ、
と思いました。
私個人の印象ですが、
男性というのは、結果を出すまでの経過には偉く熱心で、異常なほどの関心を持っている方が多いような気がします。
しかし、結果が出さえすれば、
勝ちであっても負けであっても、
後に引きずらないというか、
あっさりしているというか・・・。
だから、男性向けの記事は、御伽噺のめでたし、めでたし風に纏め上げられて(例え負けても)終わってしまうことが多い。
その前後も、選手の人生は続いているし、
私は、どちらかというと、結果は人生においての経過の一つと思っているので、スポーツやスポーツマンに関心を持っても、その関心が長く続かないことが多かったです。
それもきっと、その前後のつながりを知る機会が少なかったからだと思う。
でも、猫なべさまの記事を読んでいると、
こうやって、ちゃんと見るべき人が時系列に添って見ているのだなぁ、ということがわかるし、
更に、私のような一般人でも、ついていけるような画像の貼り付けなどもあり、選手が“生きている”感覚を取り戻すことができます。
これからも、ぜひがんばって、いい記事をアップしてくださいね。
お褒めのお言葉を頂戴しまして、
照れる次第でございます。
とても励みになります。
私は記事を書くにあたって、自分なりになるべく
背景を調べることを心掛けるように努めてます。
そうすれば、深みが増してより一層楽しめると思いますので。
たしかに、試合の結果が人生の全てでは無いと思います。だけど、背負っているものが大きい責任のある立場ですと、一つ一つの勝敗に重みが増し、その後の人生を分けることが多々あります。
「たかがスポーツ」なのかもしれませんが、
「されどスポーツ」でもありますね。
あと、自分のブログは、過去の栄光の話だけでなく、苦い記憶の話を取り上げる事も多いと思います。それは、同じ過ちを繰り返してほしくないからです。
野球のノムさんの言葉を借りれば、負ける時は何らかの理由が必ずあります。
それに負ける時は、大抵同じパターンですから。過去の苦い経験を教訓にすれば、同じような場面が今後遭遇した時に未然に防止できます。
なので、記憶を風化させない為にも、自分が知っている範囲内で多くの人に伝えられたらと思い、記事にしてます。(読者は少ないですが(苦笑))
これからも、ご訪問並びにコメントをお待ちしております。