【修復腎移植ものがたり:(15)虚報】
今はカルテの電子化で様変わりしたが、当時の臨床医は月初めに「レセプト請求」という事務作業に追われた。社会保険支払い基金に提出する診療報酬請求書を「レセプト」という。元は英語のレシート(Receipt)だが、医者はドイツ語読みをする。締切りが毎月10日で、請求書の審査が行われ内容がチェックされる。妥当と査定された額の医療費が、2ヶ月後に病院や医院に支払われる。
レセプトの審査は事務方と県医師会委員と医師の学識経験者とが行う。光畑の病腎移植は全国紙に報道されたので、移植に問題があればそこでひっかかるはずだが、基金は何も問題にしなかった。それどころか、後に広島県医師会は「病腎移植支持」を理事会決定した日本最初の医師会となった。
「臓器移植法」に違反しているわけでないので、呉共済病院の隣にある呉警察署も広島県警も問題にしなかった。また当時、日本移植学会の幹部は誰一人としてオブジェクションを唱えなかった。
海軍造船所の職工病院を前身とする呉共済病院は独立採算制だが、組織上は「国家公務員共済組合連合会」に属している。従って職員は「みなし公務員」であり、移植医療のような高額医療に関しては、東京・竹橋の毎日新聞本社の隣にある「竹橋会館(現KKRホテル竹橋)」に入っている、連合会本部で審査がおこなわれることになっている。連合会の理事長ポストは、かつては大蔵事務次官を経験した高級官僚の天下り先だった。「虎の門病院」は連合会の直営病院である。その連合会の本部審査でも、病腎移植は何も問題にならなかった。
その後「捨てる腎臓で助かる命がある」というのが瀬戸内グループの医師たちの合い言葉になった。実際には、摘出された腎臓は病理検査により一部が標本にされ、病理診断された後も最低5年間は保存され、その後に火葬場に送られて焼却処分されるので、最初から「捨てる」のではない。だが当時90年代には病理診断の重要性がまだ社会的に認知されておらず、保険点数も低かったので、病理単体での採算を考えると、院内で病理検査をしない病院もあった。
広島県医師会が長年にわたって行っている「腫瘍組織登録制度」のデータから推計すると、日本全国では年間に腎がんが約6,500件、尿管がんは約2,000件発生していると推定される。多い方の腎がんではなく、少ない方の尿管がんが連続して3件も移植に用いられたのは偶然ではなく、スコラ医師と同様に、単純に「下部尿管がんの腎臓なら移植に使えるはず」と男が考えたからであろう。
がんの頻度としては、尿管がんより腎がんの方が3倍も高い。全国で全摘される小径腎がんは年間2,664件、尿管がんのため腎臓が摘出されるケースは年間1,220件と推計されている。尿管がんのうち下部に限局していて移植に使える症例は、そのうち10%程度であろう。人口比を無視しても、そのような症例は愛媛県全体で年間4例が最大であろう。実際に、この最初の3例の尿管がんの患者はすべて愛媛県在住だった。同じ癌でも、なぜ腎がんでなく、尿管がんから始めたのか? もし腎がんから始めていたら、2例目以下も腎がんが続くはずだが、初めて小径腎がんの腎臓が移植に用いられたのは、98年11月以後の4例である。
スコラ医師が1951年に考えたように、40年後に男も腎臓から離れた尿管のがんなら腎移植に使えるだろうと考えたのだ。そこで男の修復腎移植は、まず下部尿管がんの症例から始まった。
尿管をふくめ尿路と膀胱それに尿道の表面を被う上皮を「尿上皮(ウロテル)」という。ウロは尿(Urine)をテル(-thel)は上皮(エピテル: epithel)の略である。尿上皮は「移行上皮」という、皮膚や口腔粘膜、食道粘膜に似ているが、少し異なる粘膜からできている。皮膚、口腔、食道の上皮は「重層扁平上皮」といい、平坦なゴムタイルを積み重ねたような構造をしている。このうち皮膚では細胞の新生が下から起こり、既存の細胞は次第に上に押し上げられ、その途中で角化が生じる。角化した細胞(ケラチンを産生した細胞)は表面から剝げ落ちる。これが垢である。
口腔や食道の重層扁平上皮は、正常では角化を起こさないので浸透性に富み、たやすく水分を分泌したり、逆に吸収したりすることができる。皮膚の最上層をなす表皮は、角化性の扁平上皮から成り立っているので、水分の吸収も分泌もむつかしい。風呂に長く浸かっていると手の皮がふやけることがあるが、あれは角化層が水分を吸収したためである。
もともと皮膚の表皮や口腔と食道の粘膜は「外界に対するバリアー」としてあるのだから、そういう性質を本来的に要請されている。ところが胃や腸の粘膜上皮は、円柱状の細胞が横にびっしり並んだ構造をしており、細胞内や細胞の間を通って水が移動しやすくなっている。
動物の胃や膀胱は、生理的に容易に膨脹するところから、かつて皮袋として利用された。『新訳聖書』に「新しい酒は新しい皮袋にいれよ」という言葉が出てくる。「マタイ伝 9-17」にある文言で、実際には酒はワインのことで、皮袋は膀胱から作られたものだ。胃を用いた皮袋は水漏れしやすく、長持ちしないのである。
ではなぜ膀胱性の皮袋は水漏れが起こらないのか。その秘密は移行上皮の構造にある。膀胱や尿管の内面を被うこの上皮は、2種類の細胞から成り立っている。表面にある細胞は平たくて、いくらでも拡張できる。その下にある細胞は膀胱が収縮した時には、核が多層性に並んでいるように見えるが、膨脹するときにはアコーデオンのように広がり、細胞同士の結合が切れることがない。
こういう2種類の細胞により水漏れを防げるから、膀胱をなめしたものは皮袋として勝れているのである。単層の円柱細胞で被われている胃袋にはこういう性質がない。
移行上皮から発生するがんが「移行上皮がん」で、前に述べたように主に腎盂、尿管、膀胱にできる。その悪性度と進展度合いは、幾つかの指標で決まる。これはWHOの「国際疾病分類・腫瘍学(ICD-O)」で定められている。疾病それぞれの診断基準と腫瘍の場合は悪性の度合いも同じでないと、国別や治療法別の国際比較ができないからこういう規約がある。
第1例目の尿管がんの病理診断は「乳頭状移行上皮がん、グレード1」という悪性度が低いもので、「尿管断端に浸潤なし」とあった。
第2例目の尿管がんでは右尿管下部にがんがあった。病理診断は「乳頭状移行上皮がん、グレード2」だった。1例目との違いは「グレード」が1と2である点だ。
「グレード分類」というのはがんを顕微鏡的に調べて、がん細胞の分化度と細胞分裂の頻度を数値化したものだ。がんは正常組織と細胞形態からの乖離が増すほど、悪性度が高くなる。この乖離度を「異型性(アティピア)」といい1〜4まで4段階ある。異型性が細胞レベルでも組織構築レベルでももっとも軽く、正常組織に近いものがグレード1である。「高分化型」あるいは「分化型」と呼ばれ、グレード3は「低分化型」と呼ばれ、グレード4は「未分化型」といい最も悪性度が高い。「グレード分類」は1980年代になって日本の病理学教科書に導入されたので、男は大学で習っていない。それでなくても、病理学をあまり勉強せずビーコンを食らっていた。
第3例目の右尿管がん患者の腎尿管全摘を行い、下部尿管の腫瘍を切除した後に、45歳のユキオに移植した。最終診断は「非乳頭状移行上皮がん、グレード3>グレード2、一部SCCあり」であった。
がん細胞の悪性度が低く、下方への浸潤が起こらない場合は、がん細胞シートの面積が広がり上方へ指状に盛り上がる。このため断面を顕微鏡で見ると「乳頭状」になっている。肉眼でも表面が粒々が認められる。これが乳頭状移行上皮がんで悪性度は低いが、多発する傾向がある。
これに対して「非乳頭状」を呈するのは下方への増殖が起こっているためで、乳頭状のものより悪性度が高いのが普通である。すべての尿路がんが、移行上皮の形をとどめているわけではなく、ごく少数だが食道がんのような「扁平上皮がん」に変化することがあるし、初めから扁平上皮がんとして発生することもある。これは悪性度がより高い。SCCというのは「扁平上皮がん(Squamous Cell Cancer)」の略号である。
このようにがんの場合、悪性度が高いとしばしば元の組織の構造から逸脱して、別の組織に似た構造に変わることがあり、これを「退形成(アナプラシア)」という。がん幹細胞がいったん多能性幹細胞に戻り、そこから別系統の組織に分化するために起こると考えられている。膵臓がんの一部に見られる「巨細胞がん」、悪性リンパ腫の一部に認められる「退形成性巨細胞リンパ腫」が有名である。前者は上皮細胞由来なのに骨肉腫に似た組織像を呈し、後者はリンパ球由来なのに、上皮由来のがんに似た組織像を示す。
「グレード3>2」という記号は、腫瘍組織では低分化で、より悪性度が高いものが多くを占めていることを、「一部SCCあり」とは、退形成的に扁平上皮への化生が生じていることを、それぞれ示している。扁平上皮がんが乳頭状に増殖することはきわめてまれである。従ってこの第3例目は「非乳頭状移行上皮がん」と最終診断されたのである。
男は尿管がんの悪性度の順番を知っていて患者を選んだわけではなく、次第に悪性度が高くなる尿管がんのドナー腎臓を、たまたま、順番に移植に用いていたのだ。
1994年10月に行われた第3例目の尿管がん腎移植術も成功した。だが第3例目のユキオの場合は問題が起こった。術後の経過は良く、拒絶反応も起こらなかったが、月に1回の定期検査が14回目に達したとき、移植した腎臓の腎盂に腫瘍の再発が認められたのだ。「腎盂」とは腎臓の門部にある尿管の起始部である。尿の細胞診では、はっきりとした移行上皮がんの細胞は見つからなかったが、万一のことを考え、男は移植した腎臓ごと摘出することをつよく勧めた。
「先生、悪いところだけ取って下さい。もともと尿管の悪いところを取って移植した腎臓じゃから、今度もそうできるでしょうが。わしゃあ、死んでも透析に戻るのはいやじゃ」
ユキオは頑として腎尿管全摘に同意しなかった。男は仕方なく、腎門部を切開して、腎盂の腫瘍を部分切除する手術をおこなった。病理検査の結果は、「乳頭状移行上皮がん」で再発ではなく、新たに発生した腫瘍だった。もともと尿管と膀胱には多発性にがんが発生しやすいのである。
2007年1月23日、「朝日」は全国版社会面で「病気腎使用、移植後がんで死亡。潜伏細胞持ち込む?」という見出しの5段記事で、「病気腎移植を受けた患者にがんが再発し、肺に転移して死亡した」と報じた。1月29日の「読売」も似たような報道をしている。
ユキオが99年1月、つまり病腎移植から4年3ヶ月後に「転移性肝がん」で死亡したのは事実である。では真相はどうか。ユキオは96年1月、咳が出るようになり、痰の細胞診で「扁平上皮がん」と診断された。宇和島市立病院内科の診断では転移性の肺がんではなく、「原発性の肺がん」であった。
肺は肝臓、脳と並んで転移が起こりやすい臓器で、原発性と転移性の鑑別は臨床的には必ずしも容易くない。
が、この場合、細胞診で喀痰中から扁平上皮がんの細胞が見つかっている。これは原発性である可能性が高いことを意味する。病変が気管支内に露出していなければ、痰にがん細胞が出ることはまずありえない。腎盂のがんが転移したとすれば、肺野末梢の毛細血管が支配する領域に転移巣が発生し、レントゲン写真上「硬貨様病変(Coin lesion)」と呼ばれる特徴的な病変を形成するのが普通だ。
その後の調査により、マスオが3年後の99年1月に死亡したことが判明した。宇和島市立病院のカルテは破棄されていたが、妻のもとに残されていた死亡診断書も発見された。それによると病理解剖はなされず、死因は「原発性肺がんの肝転移による肝不全」であった。
当時、厚労省「病気腎移植調査班」の班長を務めていたのは、慶応大医学部昭和52年卒の東邦医大泌尿器科教授相川厚だった。相川は2005年に教授になったばかりで、名前の売り出しをねらっていた。大島伸一移植学会副理事長が協力を要請した、慶応大医学部卒の厚労省の局長が後輩の彼を班長に依嘱したのだ。
当時(あるいは今も)、厚労省・学会と親密だった「朝日」は病腎移植を否定するために、この記事を書いた。だがこれは完全な誤報だった。マスオの死因は病腎移植とは関係がなく、「原発性肺がんの肝転移」によるものだった。「朝日」は今年の8月に「吉田清治報道」の誤報を認め撤回したが、この記事は未撤回のままだ。(続)
今はカルテの電子化で様変わりしたが、当時の臨床医は月初めに「レセプト請求」という事務作業に追われた。社会保険支払い基金に提出する診療報酬請求書を「レセプト」という。元は英語のレシート(Receipt)だが、医者はドイツ語読みをする。締切りが毎月10日で、請求書の審査が行われ内容がチェックされる。妥当と査定された額の医療費が、2ヶ月後に病院や医院に支払われる。
レセプトの審査は事務方と県医師会委員と医師の学識経験者とが行う。光畑の病腎移植は全国紙に報道されたので、移植に問題があればそこでひっかかるはずだが、基金は何も問題にしなかった。それどころか、後に広島県医師会は「病腎移植支持」を理事会決定した日本最初の医師会となった。
「臓器移植法」に違反しているわけでないので、呉共済病院の隣にある呉警察署も広島県警も問題にしなかった。また当時、日本移植学会の幹部は誰一人としてオブジェクションを唱えなかった。
海軍造船所の職工病院を前身とする呉共済病院は独立採算制だが、組織上は「国家公務員共済組合連合会」に属している。従って職員は「みなし公務員」であり、移植医療のような高額医療に関しては、東京・竹橋の毎日新聞本社の隣にある「竹橋会館(現KKRホテル竹橋)」に入っている、連合会本部で審査がおこなわれることになっている。連合会の理事長ポストは、かつては大蔵事務次官を経験した高級官僚の天下り先だった。「虎の門病院」は連合会の直営病院である。その連合会の本部審査でも、病腎移植は何も問題にならなかった。
その後「捨てる腎臓で助かる命がある」というのが瀬戸内グループの医師たちの合い言葉になった。実際には、摘出された腎臓は病理検査により一部が標本にされ、病理診断された後も最低5年間は保存され、その後に火葬場に送られて焼却処分されるので、最初から「捨てる」のではない。だが当時90年代には病理診断の重要性がまだ社会的に認知されておらず、保険点数も低かったので、病理単体での採算を考えると、院内で病理検査をしない病院もあった。
広島県医師会が長年にわたって行っている「腫瘍組織登録制度」のデータから推計すると、日本全国では年間に腎がんが約6,500件、尿管がんは約2,000件発生していると推定される。多い方の腎がんではなく、少ない方の尿管がんが連続して3件も移植に用いられたのは偶然ではなく、スコラ医師と同様に、単純に「下部尿管がんの腎臓なら移植に使えるはず」と男が考えたからであろう。
がんの頻度としては、尿管がんより腎がんの方が3倍も高い。全国で全摘される小径腎がんは年間2,664件、尿管がんのため腎臓が摘出されるケースは年間1,220件と推計されている。尿管がんのうち下部に限局していて移植に使える症例は、そのうち10%程度であろう。人口比を無視しても、そのような症例は愛媛県全体で年間4例が最大であろう。実際に、この最初の3例の尿管がんの患者はすべて愛媛県在住だった。同じ癌でも、なぜ腎がんでなく、尿管がんから始めたのか? もし腎がんから始めていたら、2例目以下も腎がんが続くはずだが、初めて小径腎がんの腎臓が移植に用いられたのは、98年11月以後の4例である。
スコラ医師が1951年に考えたように、40年後に男も腎臓から離れた尿管のがんなら腎移植に使えるだろうと考えたのだ。そこで男の修復腎移植は、まず下部尿管がんの症例から始まった。
尿管をふくめ尿路と膀胱それに尿道の表面を被う上皮を「尿上皮(ウロテル)」という。ウロは尿(Urine)をテル(-thel)は上皮(エピテル: epithel)の略である。尿上皮は「移行上皮」という、皮膚や口腔粘膜、食道粘膜に似ているが、少し異なる粘膜からできている。皮膚、口腔、食道の上皮は「重層扁平上皮」といい、平坦なゴムタイルを積み重ねたような構造をしている。このうち皮膚では細胞の新生が下から起こり、既存の細胞は次第に上に押し上げられ、その途中で角化が生じる。角化した細胞(ケラチンを産生した細胞)は表面から剝げ落ちる。これが垢である。
口腔や食道の重層扁平上皮は、正常では角化を起こさないので浸透性に富み、たやすく水分を分泌したり、逆に吸収したりすることができる。皮膚の最上層をなす表皮は、角化性の扁平上皮から成り立っているので、水分の吸収も分泌もむつかしい。風呂に長く浸かっていると手の皮がふやけることがあるが、あれは角化層が水分を吸収したためである。
もともと皮膚の表皮や口腔と食道の粘膜は「外界に対するバリアー」としてあるのだから、そういう性質を本来的に要請されている。ところが胃や腸の粘膜上皮は、円柱状の細胞が横にびっしり並んだ構造をしており、細胞内や細胞の間を通って水が移動しやすくなっている。
動物の胃や膀胱は、生理的に容易に膨脹するところから、かつて皮袋として利用された。『新訳聖書』に「新しい酒は新しい皮袋にいれよ」という言葉が出てくる。「マタイ伝 9-17」にある文言で、実際には酒はワインのことで、皮袋は膀胱から作られたものだ。胃を用いた皮袋は水漏れしやすく、長持ちしないのである。
ではなぜ膀胱性の皮袋は水漏れが起こらないのか。その秘密は移行上皮の構造にある。膀胱や尿管の内面を被うこの上皮は、2種類の細胞から成り立っている。表面にある細胞は平たくて、いくらでも拡張できる。その下にある細胞は膀胱が収縮した時には、核が多層性に並んでいるように見えるが、膨脹するときにはアコーデオンのように広がり、細胞同士の結合が切れることがない。
こういう2種類の細胞により水漏れを防げるから、膀胱をなめしたものは皮袋として勝れているのである。単層の円柱細胞で被われている胃袋にはこういう性質がない。
移行上皮から発生するがんが「移行上皮がん」で、前に述べたように主に腎盂、尿管、膀胱にできる。その悪性度と進展度合いは、幾つかの指標で決まる。これはWHOの「国際疾病分類・腫瘍学(ICD-O)」で定められている。疾病それぞれの診断基準と腫瘍の場合は悪性の度合いも同じでないと、国別や治療法別の国際比較ができないからこういう規約がある。
第1例目の尿管がんの病理診断は「乳頭状移行上皮がん、グレード1」という悪性度が低いもので、「尿管断端に浸潤なし」とあった。
第2例目の尿管がんでは右尿管下部にがんがあった。病理診断は「乳頭状移行上皮がん、グレード2」だった。1例目との違いは「グレード」が1と2である点だ。
「グレード分類」というのはがんを顕微鏡的に調べて、がん細胞の分化度と細胞分裂の頻度を数値化したものだ。がんは正常組織と細胞形態からの乖離が増すほど、悪性度が高くなる。この乖離度を「異型性(アティピア)」といい1〜4まで4段階ある。異型性が細胞レベルでも組織構築レベルでももっとも軽く、正常組織に近いものがグレード1である。「高分化型」あるいは「分化型」と呼ばれ、グレード3は「低分化型」と呼ばれ、グレード4は「未分化型」といい最も悪性度が高い。「グレード分類」は1980年代になって日本の病理学教科書に導入されたので、男は大学で習っていない。それでなくても、病理学をあまり勉強せずビーコンを食らっていた。
第3例目の右尿管がん患者の腎尿管全摘を行い、下部尿管の腫瘍を切除した後に、45歳のユキオに移植した。最終診断は「非乳頭状移行上皮がん、グレード3>グレード2、一部SCCあり」であった。
がん細胞の悪性度が低く、下方への浸潤が起こらない場合は、がん細胞シートの面積が広がり上方へ指状に盛り上がる。このため断面を顕微鏡で見ると「乳頭状」になっている。肉眼でも表面が粒々が認められる。これが乳頭状移行上皮がんで悪性度は低いが、多発する傾向がある。
これに対して「非乳頭状」を呈するのは下方への増殖が起こっているためで、乳頭状のものより悪性度が高いのが普通である。すべての尿路がんが、移行上皮の形をとどめているわけではなく、ごく少数だが食道がんのような「扁平上皮がん」に変化することがあるし、初めから扁平上皮がんとして発生することもある。これは悪性度がより高い。SCCというのは「扁平上皮がん(Squamous Cell Cancer)」の略号である。
このようにがんの場合、悪性度が高いとしばしば元の組織の構造から逸脱して、別の組織に似た構造に変わることがあり、これを「退形成(アナプラシア)」という。がん幹細胞がいったん多能性幹細胞に戻り、そこから別系統の組織に分化するために起こると考えられている。膵臓がんの一部に見られる「巨細胞がん」、悪性リンパ腫の一部に認められる「退形成性巨細胞リンパ腫」が有名である。前者は上皮細胞由来なのに骨肉腫に似た組織像を呈し、後者はリンパ球由来なのに、上皮由来のがんに似た組織像を示す。
「グレード3>2」という記号は、腫瘍組織では低分化で、より悪性度が高いものが多くを占めていることを、「一部SCCあり」とは、退形成的に扁平上皮への化生が生じていることを、それぞれ示している。扁平上皮がんが乳頭状に増殖することはきわめてまれである。従ってこの第3例目は「非乳頭状移行上皮がん」と最終診断されたのである。
男は尿管がんの悪性度の順番を知っていて患者を選んだわけではなく、次第に悪性度が高くなる尿管がんのドナー腎臓を、たまたま、順番に移植に用いていたのだ。
1994年10月に行われた第3例目の尿管がん腎移植術も成功した。だが第3例目のユキオの場合は問題が起こった。術後の経過は良く、拒絶反応も起こらなかったが、月に1回の定期検査が14回目に達したとき、移植した腎臓の腎盂に腫瘍の再発が認められたのだ。「腎盂」とは腎臓の門部にある尿管の起始部である。尿の細胞診では、はっきりとした移行上皮がんの細胞は見つからなかったが、万一のことを考え、男は移植した腎臓ごと摘出することをつよく勧めた。
「先生、悪いところだけ取って下さい。もともと尿管の悪いところを取って移植した腎臓じゃから、今度もそうできるでしょうが。わしゃあ、死んでも透析に戻るのはいやじゃ」
ユキオは頑として腎尿管全摘に同意しなかった。男は仕方なく、腎門部を切開して、腎盂の腫瘍を部分切除する手術をおこなった。病理検査の結果は、「乳頭状移行上皮がん」で再発ではなく、新たに発生した腫瘍だった。もともと尿管と膀胱には多発性にがんが発生しやすいのである。
2007年1月23日、「朝日」は全国版社会面で「病気腎使用、移植後がんで死亡。潜伏細胞持ち込む?」という見出しの5段記事で、「病気腎移植を受けた患者にがんが再発し、肺に転移して死亡した」と報じた。1月29日の「読売」も似たような報道をしている。
ユキオが99年1月、つまり病腎移植から4年3ヶ月後に「転移性肝がん」で死亡したのは事実である。では真相はどうか。ユキオは96年1月、咳が出るようになり、痰の細胞診で「扁平上皮がん」と診断された。宇和島市立病院内科の診断では転移性の肺がんではなく、「原発性の肺がん」であった。
肺は肝臓、脳と並んで転移が起こりやすい臓器で、原発性と転移性の鑑別は臨床的には必ずしも容易くない。
が、この場合、細胞診で喀痰中から扁平上皮がんの細胞が見つかっている。これは原発性である可能性が高いことを意味する。病変が気管支内に露出していなければ、痰にがん細胞が出ることはまずありえない。腎盂のがんが転移したとすれば、肺野末梢の毛細血管が支配する領域に転移巣が発生し、レントゲン写真上「硬貨様病変(Coin lesion)」と呼ばれる特徴的な病変を形成するのが普通だ。
その後の調査により、マスオが3年後の99年1月に死亡したことが判明した。宇和島市立病院のカルテは破棄されていたが、妻のもとに残されていた死亡診断書も発見された。それによると病理解剖はなされず、死因は「原発性肺がんの肝転移による肝不全」であった。
当時、厚労省「病気腎移植調査班」の班長を務めていたのは、慶応大医学部昭和52年卒の東邦医大泌尿器科教授相川厚だった。相川は2005年に教授になったばかりで、名前の売り出しをねらっていた。大島伸一移植学会副理事長が協力を要請した、慶応大医学部卒の厚労省の局長が後輩の彼を班長に依嘱したのだ。
当時(あるいは今も)、厚労省・学会と親密だった「朝日」は病腎移植を否定するために、この記事を書いた。だがこれは完全な誤報だった。マスオの死因は病腎移植とは関係がなく、「原発性肺がんの肝転移」によるものだった。「朝日」は今年の8月に「吉田清治報道」の誤報を認め撤回したが、この記事は未撤回のままだ。(続)












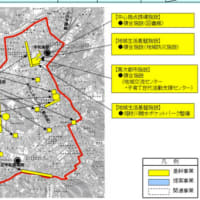
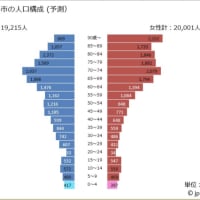



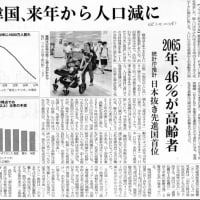












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます