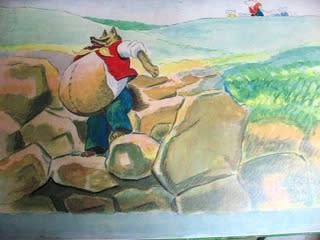5日(土)キトラ古墳壁画「四神」の特別公開を見に
飛鳥資料館へ出掛けました。
長女夫婦の車に同乗、らくらくドライブです。

奈良といえば「彩華ラーメン」というわけで、ここで昼食をとります。
白菜など炒め野菜が載った「彩華ラーメン」が売りのお店ですが
私はあっさり「醤油ラーメン」にしました。
これもとっても美味しかったです!

飛鳥資料館に着いたのはPM2時過ぎ。
報道では30分~1時間待ち等と聞いていましたが
なんと「待ち時間 0分!」ゆっくり見学できラッキーでした。
(帰る頃また混んできました)

「四神」の他、天井には「天文図」が描かれている
古墳は盗掘されながらも、壁画が無事に残ったのはまさに奇跡!
でも、埋葬当時はどれほど華麗だったろう!?と思うと、やはり盗掘は恨めしい。

パンフレットより 「朱雀」
「四神」は予想外に小さなもので、装飾目的ではないと感じます。
展示室を巡る内 「四神」が描かれた各壁面の下部に
十二支が3体ずつ描かれていた事を知り、大きさの謎も解けました。
遺体を四方から守るために描かれ
お札のような役割を果たす物だったのですね。
7世紀末に描かれた繊細な筆跡を目にすることができるとは。。。
感無量でした!
飛鳥資料館へ出掛けました。
長女夫婦の車に同乗、らくらくドライブです。

奈良といえば「彩華ラーメン」というわけで、ここで昼食をとります。
白菜など炒め野菜が載った「彩華ラーメン」が売りのお店ですが
私はあっさり「醤油ラーメン」にしました。
これもとっても美味しかったです!

飛鳥資料館に着いたのはPM2時過ぎ。
報道では30分~1時間待ち等と聞いていましたが
なんと「待ち時間 0分!」ゆっくり見学できラッキーでした。
(帰る頃また混んできました)

「四神」の他、天井には「天文図」が描かれている
古墳は盗掘されながらも、壁画が無事に残ったのはまさに奇跡!
でも、埋葬当時はどれほど華麗だったろう!?と思うと、やはり盗掘は恨めしい。

パンフレットより 「朱雀」
「四神」は予想外に小さなもので、装飾目的ではないと感じます。
展示室を巡る内 「四神」が描かれた各壁面の下部に
十二支が3体ずつ描かれていた事を知り、大きさの謎も解けました。
遺体を四方から守るために描かれ
お札のような役割を果たす物だったのですね。
7世紀末に描かれた繊細な筆跡を目にすることができるとは。。。
感無量でした!