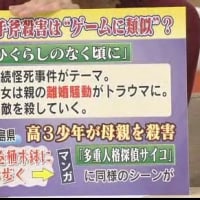卒業証書を高校が回収、授業料滞納の生徒から別室で…山梨(読売新聞) - goo ニュース
山梨県立増穂商業高校(増穂町最勝寺)で、授業料を滞納していた昨年の卒業生と今春卒業の計2人に対し、いったん渡した卒業証書を預かる措置を取っていたことが分かった。
同校によると、1日の卒業式当日、出席した生徒には卒業証書を一度手渡し、その後、別室で預かった。事前に保護者を交えて措置の趣旨を説明、本人や保護者の了承を得たという。卒業そのものには影響がない。昨年の卒業生については、同様に学校側が卒業証書を預かり、昨年5月に完納した後に戻した。今年の卒業生にも完納後に手渡すとしている。
取材に対し、同校の久津川孝校長は「好ましいことではないが、授業料を払う義務を果たしてほしいという思いで行った」と話した。県教委は「学校からは合意の上で行ったと報告を受けている」とし、対応は学校側に任せているとする。
県立高校の年間授業料は1、2年生は11万8800円、3年生は11万5200円。授業料の滞納額は増加傾向にあり、県教委は今年度から対策要綱を運用し、解消に取り組んでいる。要綱には、滞納している家庭に対し「電話督促」「納入計画書の提出」などを段階的に行うことや、最終的には法的措置を取ることが盛り込まれている。
この類のニュースは他に確か島根県の高校でもあったように思うが、これを格差社会や貧困といった流れで理解するのは誤りであると思う。確かに、高校の授業料を支払えない家庭のなかには、貧困に苦しんでいる家庭もあるだろう。しかし、年間授業料が12万円弱ということは、1ヶ月換算するならば、月々の負担は1万円にもならない。よほどの理由のない限り、決して支払えない金額ではないだろう。少なくとも、子供に携帯を持たす余裕があるならば、確実に支払える額である。
この山梨県のケースでは、2人は卒業要件を満たしていたため、高卒の認定はされており、進路に関しての支障はないため、高校側の取った行動は校長の言うように「授業料を払う義務を果たしてほしいという思いで行った」というのが本当のところであり、教育の一環としての行動と理解するのが適切である。私は高校側の対応に異論はないという立場だ。
卒業証書の授与に関しては、学校教育法施行規則104条により、小学校の卒業証書授与に関する規定である58条(校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。) が高等学校にも準用されることになっていることから、学校側は卒業の要件を生徒が満たしている場合、卒業証書を授与しなければならない。学校側がこのことを知らないわけがないから、やはり今回の措置は教育上の指導である。
やや杓子定規な議論になってしまうが、高校は義務教育ではないのだから、正当な理由もなく授業料の支払いを拒む家庭に対しては、積極的に法的措置に出ていいと思う。実際、島根県の場合には、授業料の支払い能力があるにもかかわらず、支払いを拒んでいた(滞納していた)保護者が65人もいたという。先ほども述べたが、高校は義務教育ではないのだから、子供を通わせる以上、保護者には対価(授業料)を支払う義務がある。
授業料という対価を支払わず、高卒の資格だけ得ようというのは、食い逃げと同じ発想である。食い逃げならは立派な窃盗罪(刑法235条)である。つまり、犯罪である。授業料を支払う資力があるにもかかわらずこれを支払いというのは犯罪行為を行っていることと同じであるということを、保護者は自覚しなければならない。
今回の学校側の対応をめぐって一部からは学校側を批判する向きがあるが、これには賛同できない。まず、そもそもの原因を作ったのは学校側ではなく生徒(保護者)の側である。公立学校ということを逆手にとって、授業料を支払いもせず、学校に何食わぬ顔で行かせ続けてる保護者のほうがまず責められるべきであって、学校側を一方的に批判するのはおかしい。
山梨県教育委員会も、「卒業証書の取り扱いは校長の権限で判断は任せている」としているし、生徒には卒業式後に戻った教室で他の生徒と同様に卒業証書を渡し、ホームルームを解散した後に返却を求めたという(朝日新聞)ことから、不適切な対応だったとしても、卒業証書の取り扱いも比較的穏便になされたと言える。
しかも校長の話によれば、この保護者は生徒が1年生の時から度々滞納をしており、学校側は電話や家庭訪問などで支払いを求めていたという(朝日新聞)。学校側は、保護者がきちんと授業料の支払いさえしていれば、こうした措置に出なかったことは明らかである。学校側を批判するということは、食い逃げに飲食料を支払わせるなと言っていることと同じだ。盗人に追い銭である。
山梨日日新聞によれば、卒業生の保護者らが、「子供は悪くないのに、卒業証書を人質に取るようなやり方だ」と学校側を批判しているようであるが、こうした批判が的外れであるのは既に述べたとおりだ。ましてや「人質」などではない。人質とは「要求実現や自身の安全のために、脅迫手段として拘束しておく人。」(大辞林)であって、今回のような場合に使う言葉ではない。
学校側の対応に問題がなかったわけではないが、学校側の対応以上に問題であったのはこの保護者サイドである。高校に子供を通わせるということは、学校と保護者の間には一種の双務・有償の契約関係が発生しており、学校側の授業をフリーライド(ただ乗り)できるわけではないことぐらい分からないものだろうか。
山梨県立増穂商業高校(増穂町最勝寺)で、授業料を滞納していた昨年の卒業生と今春卒業の計2人に対し、いったん渡した卒業証書を預かる措置を取っていたことが分かった。
同校によると、1日の卒業式当日、出席した生徒には卒業証書を一度手渡し、その後、別室で預かった。事前に保護者を交えて措置の趣旨を説明、本人や保護者の了承を得たという。卒業そのものには影響がない。昨年の卒業生については、同様に学校側が卒業証書を預かり、昨年5月に完納した後に戻した。今年の卒業生にも完納後に手渡すとしている。
取材に対し、同校の久津川孝校長は「好ましいことではないが、授業料を払う義務を果たしてほしいという思いで行った」と話した。県教委は「学校からは合意の上で行ったと報告を受けている」とし、対応は学校側に任せているとする。
県立高校の年間授業料は1、2年生は11万8800円、3年生は11万5200円。授業料の滞納額は増加傾向にあり、県教委は今年度から対策要綱を運用し、解消に取り組んでいる。要綱には、滞納している家庭に対し「電話督促」「納入計画書の提出」などを段階的に行うことや、最終的には法的措置を取ることが盛り込まれている。
この類のニュースは他に確か島根県の高校でもあったように思うが、これを格差社会や貧困といった流れで理解するのは誤りであると思う。確かに、高校の授業料を支払えない家庭のなかには、貧困に苦しんでいる家庭もあるだろう。しかし、年間授業料が12万円弱ということは、1ヶ月換算するならば、月々の負担は1万円にもならない。よほどの理由のない限り、決して支払えない金額ではないだろう。少なくとも、子供に携帯を持たす余裕があるならば、確実に支払える額である。
この山梨県のケースでは、2人は卒業要件を満たしていたため、高卒の認定はされており、進路に関しての支障はないため、高校側の取った行動は校長の言うように「授業料を払う義務を果たしてほしいという思いで行った」というのが本当のところであり、教育の一環としての行動と理解するのが適切である。私は高校側の対応に異論はないという立場だ。
卒業証書の授与に関しては、学校教育法施行規則104条により、小学校の卒業証書授与に関する規定である58条(校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。) が高等学校にも準用されることになっていることから、学校側は卒業の要件を生徒が満たしている場合、卒業証書を授与しなければならない。学校側がこのことを知らないわけがないから、やはり今回の措置は教育上の指導である。
やや杓子定規な議論になってしまうが、高校は義務教育ではないのだから、正当な理由もなく授業料の支払いを拒む家庭に対しては、積極的に法的措置に出ていいと思う。実際、島根県の場合には、授業料の支払い能力があるにもかかわらず、支払いを拒んでいた(滞納していた)保護者が65人もいたという。先ほども述べたが、高校は義務教育ではないのだから、子供を通わせる以上、保護者には対価(授業料)を支払う義務がある。
授業料という対価を支払わず、高卒の資格だけ得ようというのは、食い逃げと同じ発想である。食い逃げならは立派な窃盗罪(刑法235条)である。つまり、犯罪である。授業料を支払う資力があるにもかかわらずこれを支払いというのは犯罪行為を行っていることと同じであるということを、保護者は自覚しなければならない。
今回の学校側の対応をめぐって一部からは学校側を批判する向きがあるが、これには賛同できない。まず、そもそもの原因を作ったのは学校側ではなく生徒(保護者)の側である。公立学校ということを逆手にとって、授業料を支払いもせず、学校に何食わぬ顔で行かせ続けてる保護者のほうがまず責められるべきであって、学校側を一方的に批判するのはおかしい。
山梨県教育委員会も、「卒業証書の取り扱いは校長の権限で判断は任せている」としているし、生徒には卒業式後に戻った教室で他の生徒と同様に卒業証書を渡し、ホームルームを解散した後に返却を求めたという(朝日新聞)ことから、不適切な対応だったとしても、卒業証書の取り扱いも比較的穏便になされたと言える。
しかも校長の話によれば、この保護者は生徒が1年生の時から度々滞納をしており、学校側は電話や家庭訪問などで支払いを求めていたという(朝日新聞)。学校側は、保護者がきちんと授業料の支払いさえしていれば、こうした措置に出なかったことは明らかである。学校側を批判するということは、食い逃げに飲食料を支払わせるなと言っていることと同じだ。盗人に追い銭である。
山梨日日新聞によれば、卒業生の保護者らが、「子供は悪くないのに、卒業証書を人質に取るようなやり方だ」と学校側を批判しているようであるが、こうした批判が的外れであるのは既に述べたとおりだ。ましてや「人質」などではない。人質とは「要求実現や自身の安全のために、脅迫手段として拘束しておく人。」(大辞林)であって、今回のような場合に使う言葉ではない。
学校側の対応に問題がなかったわけではないが、学校側の対応以上に問題であったのはこの保護者サイドである。高校に子供を通わせるということは、学校と保護者の間には一種の双務・有償の契約関係が発生しており、学校側の授業をフリーライド(ただ乗り)できるわけではないことぐらい分からないものだろうか。