女子生徒の入学認める=中学入学訴訟問題で-奈良(時事通信)
身体に障害があることを理由に奈良県下市町立下市中学への入学を拒否された谷口明花さん(12)に対し、同町教育委員会は21日、同中学への就学を認める通知書を渡した。これに伴い明花さんらは、同教委を相手に入学を認めるよう求めていた訴訟を同日付で取り下げた。
明花さんは記者会見で「本当の下市中の生徒になることができて、本当にうれしく思います。たくさん友だちをつくりたい」と話した。母親の美保さん(45)は、教育長らが16日に自宅を訪れ「長い間待たせてしまい、申し訳ありませんでした」と謝罪したことを明らかにした。
私は、今回のこの子の入学には反対だ。しかし、障害者への差別的意識ゆえのものではないことは断っておく。理由は簡単である。この子が不幸な道を歩むのではないかと危惧するからだ。
障害があるということは、健常者と一緒の生活ができないということを意味する。だからこそ「障害」者なのだ。
彼女は中学生という。中学時代といえば、遊びたい盛りの時代である。部活に励んだり、友達と一緒に遊んだり・・・。もちろん、彼女にもできる。しかし、それには「限界」がある。障害のためだ。
彼女が中学校に入学して友達ができたとする。その友達は彼女が障害をもっているためにできないことを彼女の前でするだろう。いや、友達以外の、彼女の周囲の人間は、みなそうだ。それがこの中学校に入ることによって突きつけられる現実だ。
自分も一緒に遊んだり運動したい。こう彼女は思うだろう。もちろん、それはこれまでも同じであったろうが、多感な時期である思春期を過ごす中学時代に味わうそれは、彼女の心にどう刻まれるのだろうか。
更にこの学校には、障害者でも生活できるバリアフリーを備えていないという。ならば、なおさら彼女にとって不幸ではないか。
しかも、だ。非常に残酷な話だが、毎日車いすで障害を抱えて登校してくる彼女に、親身になって面倒を見てくれる人はどれだけいようか。障害がある人に接するとき、健常者は「差別にならないか」と、腫れ物に触るような接し方をする。そして集団の中に障害者がいると、差別だと騒がれたくないために、その人に合わせようとする。
しかし、これらは相当なストレスである。そうすると、健常者は彼女と接することを「面倒くさい」と思うようになり、彼女から離れていくことになる。そうなると、彼女はせっかく裁判まで起こして地元の中学校に入学できたのに、孤立して寂しい生活を強いられることになる。これは彼女にとって不幸の何ものでもないだろう。
不適切な喩えかも知れないが、差別と区別とは以下のようなことである。
「差別」とは、私がチョコレートケーキで、あなたがショートケーキをもらえるというときに、私がショートケーキに乗っている苺の大きさを見て、「私がチョコレートケーキなのはおかしい」というときであって、対して「区別」とは、私がチョコレートケーキをもらい、あたたがショートケーキをもらうときである。
つまり、差別とは、主観による価値判断、すなわち個人のモノサシによる見方によって成立したりしなくなったりする概念であるのに対して、区別とは、あくまでも客観的な違いによって分かれている(分けている)だけの場合である。男・女と性別が分かれていることが「差別」と言えないように。
差別というのは、差別されていると思う人間の内心において他者との優劣関係が想起されるが、区別とは、どちらが優れていてどちらが劣っているかという判断ができることではない。
今回の彼女と彼女の家族の取った行動は、どちらも差などないショートケーキとチョコレートケーキの違いを「差別」と感じたようなものではないだろうか。障害を持っている人が通うような学校がなく、健常者しか学校に通えないのであれば、彼女が裁判を起こして地元の中学校に通おうとすることは意味もあり理解できるが、障害者にも同じように通う学校が用意されているのだから、これは差別ではなく区別の問題である。
またしても喩えで恐縮だが、たとえば、足が速い人と遅い人がいたとする。この場合、足の速い遅いはあくまでも「個人差」であるため、足の速い人と遅い人とは同じ集団内で生活ができる。
しかし、足がないもしくは足があってもまともに立つことができない人は、上記の人たちと同じスタートラインに立てない。こういう人たちには別のスタートラインを用意することが、実は本当の意味での「平等」ではないかと思う。
平等とは、何でもかんでも健常者と同じ環境に障害者を置くことではないだろう。そういう措置を取ると、障害者が生活から取り残されてしまい、逆に健常者と障害者とが、お互いにとって不幸な差別という結果を招いてしまうのではないか。
私は障害を持っているからといって「劣っている」とは思っていないし、健常者が障害者に対して「優れている」とも思っていない(肉体的、精神的な観点から見ての客観的な違いあるだろうが、それによってどちらが優れている劣っているという結果を論理必然的に招くことはできない)。障害者であっても素晴らしい活躍をしている人をたくさん知っている。ただ、逆差別みたいなことが起こらないようにするためにも、ある程度の「棲み分け」は避けられないことだろうと思う。
繰り返すが、障害者と健常者がまるっきり同じ環境で暮らすことが平等に繋がるとは、必ずしも言えないのではないか。行き過ぎた平等思想は双方を不幸にするだけで何も生み出さない。
身体に障害があることを理由に奈良県下市町立下市中学への入学を拒否された谷口明花さん(12)に対し、同町教育委員会は21日、同中学への就学を認める通知書を渡した。これに伴い明花さんらは、同教委を相手に入学を認めるよう求めていた訴訟を同日付で取り下げた。
明花さんは記者会見で「本当の下市中の生徒になることができて、本当にうれしく思います。たくさん友だちをつくりたい」と話した。母親の美保さん(45)は、教育長らが16日に自宅を訪れ「長い間待たせてしまい、申し訳ありませんでした」と謝罪したことを明らかにした。
私は、今回のこの子の入学には反対だ。しかし、障害者への差別的意識ゆえのものではないことは断っておく。理由は簡単である。この子が不幸な道を歩むのではないかと危惧するからだ。
障害があるということは、健常者と一緒の生活ができないということを意味する。だからこそ「障害」者なのだ。
彼女は中学生という。中学時代といえば、遊びたい盛りの時代である。部活に励んだり、友達と一緒に遊んだり・・・。もちろん、彼女にもできる。しかし、それには「限界」がある。障害のためだ。
彼女が中学校に入学して友達ができたとする。その友達は彼女が障害をもっているためにできないことを彼女の前でするだろう。いや、友達以外の、彼女の周囲の人間は、みなそうだ。それがこの中学校に入ることによって突きつけられる現実だ。
自分も一緒に遊んだり運動したい。こう彼女は思うだろう。もちろん、それはこれまでも同じであったろうが、多感な時期である思春期を過ごす中学時代に味わうそれは、彼女の心にどう刻まれるのだろうか。
更にこの学校には、障害者でも生活できるバリアフリーを備えていないという。ならば、なおさら彼女にとって不幸ではないか。
しかも、だ。非常に残酷な話だが、毎日車いすで障害を抱えて登校してくる彼女に、親身になって面倒を見てくれる人はどれだけいようか。障害がある人に接するとき、健常者は「差別にならないか」と、腫れ物に触るような接し方をする。そして集団の中に障害者がいると、差別だと騒がれたくないために、その人に合わせようとする。
しかし、これらは相当なストレスである。そうすると、健常者は彼女と接することを「面倒くさい」と思うようになり、彼女から離れていくことになる。そうなると、彼女はせっかく裁判まで起こして地元の中学校に入学できたのに、孤立して寂しい生活を強いられることになる。これは彼女にとって不幸の何ものでもないだろう。
不適切な喩えかも知れないが、差別と区別とは以下のようなことである。
「差別」とは、私がチョコレートケーキで、あなたがショートケーキをもらえるというときに、私がショートケーキに乗っている苺の大きさを見て、「私がチョコレートケーキなのはおかしい」というときであって、対して「区別」とは、私がチョコレートケーキをもらい、あたたがショートケーキをもらうときである。
つまり、差別とは、主観による価値判断、すなわち個人のモノサシによる見方によって成立したりしなくなったりする概念であるのに対して、区別とは、あくまでも客観的な違いによって分かれている(分けている)だけの場合である。男・女と性別が分かれていることが「差別」と言えないように。
差別というのは、差別されていると思う人間の内心において他者との優劣関係が想起されるが、区別とは、どちらが優れていてどちらが劣っているかという判断ができることではない。
今回の彼女と彼女の家族の取った行動は、どちらも差などないショートケーキとチョコレートケーキの違いを「差別」と感じたようなものではないだろうか。障害を持っている人が通うような学校がなく、健常者しか学校に通えないのであれば、彼女が裁判を起こして地元の中学校に通おうとすることは意味もあり理解できるが、障害者にも同じように通う学校が用意されているのだから、これは差別ではなく区別の問題である。
またしても喩えで恐縮だが、たとえば、足が速い人と遅い人がいたとする。この場合、足の速い遅いはあくまでも「個人差」であるため、足の速い人と遅い人とは同じ集団内で生活ができる。
しかし、足がないもしくは足があってもまともに立つことができない人は、上記の人たちと同じスタートラインに立てない。こういう人たちには別のスタートラインを用意することが、実は本当の意味での「平等」ではないかと思う。
平等とは、何でもかんでも健常者と同じ環境に障害者を置くことではないだろう。そういう措置を取ると、障害者が生活から取り残されてしまい、逆に健常者と障害者とが、お互いにとって不幸な差別という結果を招いてしまうのではないか。
私は障害を持っているからといって「劣っている」とは思っていないし、健常者が障害者に対して「優れている」とも思っていない(肉体的、精神的な観点から見ての客観的な違いあるだろうが、それによってどちらが優れている劣っているという結果を論理必然的に招くことはできない)。障害者であっても素晴らしい活躍をしている人をたくさん知っている。ただ、逆差別みたいなことが起こらないようにするためにも、ある程度の「棲み分け」は避けられないことだろうと思う。
繰り返すが、障害者と健常者がまるっきり同じ環境で暮らすことが平等に繋がるとは、必ずしも言えないのではないか。行き過ぎた平等思想は双方を不幸にするだけで何も生み出さない。











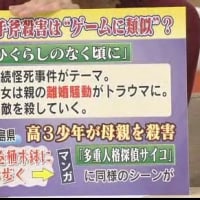
最初はなんとか歩いていましたがそのうち車椅子になりそのうち車輪も回せなくなりました。
3年になり同じクラスになって,自分ともう1人が主に彼の車椅子を押したり,数人で段差や階段を持ち上げたり,近くの生徒たちがみな自然に手伝いました。
山への遠足は先生が彼を背負って登りました。海への遠足にも一緒に行きました。
何の苦もありません。
どこからが障害と言い,どこからがそうでないのか。コトの多寡はあれ,誰にでもできないことはあり,それは差異であり個性として認めて,必要なら誰かが手を貸す。自然のことだと僕らは思っていました。
社会に出ればもっと様々なひとがいます。海外に行ってそこの言葉が話せなければこんどは自分が不自由な立場です。なにかしらのアレルギーをもっているひとも珍しくないし,向き不向き。若さ未熟さ。老い。分けてしまえば知ることさえできない。そっちの方が怖いです。
もちろん分けて欲しいと思うひとはそっとしておいてあげればいい。ただなぜそう思ってしまうのかを考えると原因は他の人たちが分けてしまうからだと思います。
考えすぎですか・・・。そうならばいいですけどね。
私は心配です。
もちろんmunetcさんの仰ることは分かります。その方は恵まれた環境にいれて良かったと思います。
学校のバリアフリー化が推進されればいいですが、やはり障害の差はありますが、彼女の場合は障害者のための設備が充実している学校に行くことが、自立への近道じゃないかなって思います。