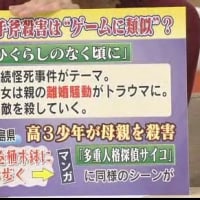【金曜討論】夫婦別姓 八木秀次氏、青野慶久氏(産経新聞)
夫婦は同姓か、別姓も認めるのか。民主党は「選択的夫婦別姓の早期実現」を政策集で掲げており、議論が再燃しそうだ。夫婦別姓には「民法改正は家族制度の根幹にかかわる」との慎重論が根強い一方、職場での旧姓使用は広がっている。「家族のつながりを希薄化させる入り口」と民法改正に反対してきた高崎経済大学教授の八木秀次氏と、自ら旧姓を使用し「制度は変わる」と確信するサイボウズ社長の青野慶久氏に聞いた。
今回は、民主党政権になったということもあり、家族制度の根本的問題である夫婦別姓制度の導入について検討したい。そこで検討にあたり、上記記事で夫婦別姓を賛成している青野慶久氏の主張を取り上げる。以下、青野氏の主張。
①青野氏:仕事で旧姓の青野を使えば、損失を最小限に抑えられると結婚当時は思っていたが、実際には大変なことが多い。印鑑を作り直し、銀行口座やクレジットカードなど本名登録の必要なものはすべて登録し直した。女性は、これほどのコストを負担しているのだと思った。
②青野氏:同姓にすることで離婚に歯止めをかけられるなら、これほど離婚が増えないはずだ。家族形態は変化しており、止めることはできない。かつて祖母がアルツハイマーを発症し、母がひとりで介護した。しかし、今は老人ホームや介護サービスといった選択肢がある。家族が強固でなければ生活が厳しい時代があったが、今は家族という枠組みにこだわらなくてもいい時代になっている
③青野氏:(民法を改正しなくても、パスポートに旧姓を併記するなど各分野の運用面で対応できるのでは、との質問に対して)かえって手間がかかる。今名乗っている名前を使い続けられる制度にすべきであり、この制度は変わると確信している。夫婦別姓に限らず、社会のルールは選択肢が多い方が人は幸せになる。今では職業や住む所が選べるように、名前も選べていい
以上、青野氏の夫婦別姓推進の主張を紹介したが、彼の主張を一言でまとめるなら、「夫婦同姓だと手続上色々と面倒である」、ということになろう。なるほど、この主張は確かに説得力を持っているように思える。結婚を経験した女性に対してはなおのことだと思う。
しかし、彼のこれら主張が民法を改正して夫婦別姓を創設すべしという結論に結び付くものとは思えない。だいたい、手続上の問題を指摘するならば、その煩雑な手続を変えればいいだけで、必ずしも民法を改正する必要性はないはずだ。
むしろ私としては、夫婦別姓を「選択的」にするほうが、かえって手続が煩雑になるように思える。
その理由として、まず、子供が産まれたときの対応がある。
平成8年に法制審議会が提示した民法改正要綱では、子の氏は統一することにしたが、別姓を選択した夫婦は婚姻時に子がどちらの氏を名乗るか決めるものとした。
もちろん、現在の制度ならば夫婦は同姓でなければならないので、わざわざ子の氏をどちらにするか決めるまでもなく、子は自動的に夫婦と同じ氏になる。手続の煩雑さを言うのなら、こちらのほうがかえって「面倒」ではないだろうか。
それから、子の氏をどちらにするか決まらない場合、そのリスクはどうやって処理するのか。こうした点から、社会の家族観を上手に反映して一つの制度を作り上げることは容易ではない。子の氏は、安定した家庭を子供に提供するという観点からの議論がなければならない。青野氏のように、目先の手続の煩雑さに囚われて夫婦別姓を主張することは、非常に危険なことである。
次に、手続の煩雑さという理由を、行政や公共サービスを提供する側などの立場になって考えてみると、実は夫婦別姓は公務員の仕事を増やし、行政のスリム化という喫緊の課題と相反することになるのではないか。
単純に考えて、これまで一つに統一されていたものを二つに分割すれば、その分仕事が増えるということは誰でも理解できる。夫婦別姓を選択的に導入することによって、公務員の窓口業務の仕事量が増加したりはしないか。
そして、現在では国家公務員であっても、2001年10月より旧姓の使用ができるようになっている。ということは、現行のままで夫婦別姓を選択的の導入するということは、仕事でもプライベートでも結婚後の氏を使う夫婦、プライベートでは結婚後の氏だが仕事では婚姻前の氏を使う夫婦、そして、夫婦の氏が別々の夫婦、という3つのパターンの夫婦が出てくるとも言え、このことは後述するように徒に社会の混乱を招きはしないか。
したがって、厄介なのはこの夫婦別姓が、夫婦同姓を廃止して夫婦別姓を導入するというのではなくて、夫婦別姓か夫婦同姓かを各個人が自由に選択できるという「選択的夫婦別姓」にある点だ。確かに青野氏の言うように、選択肢は多様であるほうが人は幸せである。しかし、ことは家族という社会の基盤となる制度に関するものである。よって青野氏の主張は些か短絡的ではないか。
「選択的」ということは、これまでと違い、夫婦のあり方が二種類になるということだ。二種類になることによって選択の幅は広がるが、それによる社会の混乱は制度導入のメリットを上回るものだと思う。
そもそも、氏を決めるというのは、単なる個人の自由でどうにかしていい問題ではなく、社会全般にかかわる公的制度の問題である。私は平等と自由ならば迷うことなく自由を選ぶが、社会制度の根幹である家族の統一を図るのに必須の氏についてまで、それを各人の自由な処分に委ねるという主張には、全く賛同できない。
ところで、上記産経新聞のアンケートによれば、選択的夫婦別姓を導入しても、それを活用するかという問いには56%が「ノー」と答えている。夫婦別姓導入の理由に国民からのニーズがあるとすれば、その当の国民がノーと答えているのに、導入する理由は一体何なのかということになる。
最後に、夫婦別姓を導入する者はしばしば、憲法上の男女平等を持ち出す。しかし、そこで、これについて批判をしておく。
まず、男女平等の思想から夫婦別姓は帰結しない。夫婦は同じ氏を名乗るか別の氏を名乗るかを、婚姻の際に確立5割のくじによって決める制度も男女平等の思想には反しない(内田貴『民法Ⅳ』)。
次に、これについては既に岐阜家庭裁判所が、「親族共同生活の中心となる夫婦が、同じ氏を称することは、主観的には夫婦の一体感を高めるのに役立ち、客観的には利害関係を有する第三者に対し夫婦であることを示すのを容易にするものといえる。したがって、国民感情または国民感情及び社会的慣習を根拠として制定されたといわれる民法750条は、現在においてもなお合理性を有するものであって、何ら憲法13条、24条1項に反するものではない。」と判示している(岐阜家審平1・6・23)。私はこちらの主張のほうが説得的だと思う。
なお、しばしば夫婦別姓の国として韓国が出てくるが、その理由は、氏は父系血統を表示するものとして不変のものとされ、夫の血統の家庭には入れないという思想ゆえであり、夫婦別姓を主張するフェミニストのような理由によって夫婦別姓が敷かれているわけではなく、むしろこの思想はフェミニズムと正面から対立するものであることを付言しておく。
夫婦は同姓か、別姓も認めるのか。民主党は「選択的夫婦別姓の早期実現」を政策集で掲げており、議論が再燃しそうだ。夫婦別姓には「民法改正は家族制度の根幹にかかわる」との慎重論が根強い一方、職場での旧姓使用は広がっている。「家族のつながりを希薄化させる入り口」と民法改正に反対してきた高崎経済大学教授の八木秀次氏と、自ら旧姓を使用し「制度は変わる」と確信するサイボウズ社長の青野慶久氏に聞いた。
今回は、民主党政権になったということもあり、家族制度の根本的問題である夫婦別姓制度の導入について検討したい。そこで検討にあたり、上記記事で夫婦別姓を賛成している青野慶久氏の主張を取り上げる。以下、青野氏の主張。
①青野氏:仕事で旧姓の青野を使えば、損失を最小限に抑えられると結婚当時は思っていたが、実際には大変なことが多い。印鑑を作り直し、銀行口座やクレジットカードなど本名登録の必要なものはすべて登録し直した。女性は、これほどのコストを負担しているのだと思った。
②青野氏:同姓にすることで離婚に歯止めをかけられるなら、これほど離婚が増えないはずだ。家族形態は変化しており、止めることはできない。かつて祖母がアルツハイマーを発症し、母がひとりで介護した。しかし、今は老人ホームや介護サービスといった選択肢がある。家族が強固でなければ生活が厳しい時代があったが、今は家族という枠組みにこだわらなくてもいい時代になっている
③青野氏:(民法を改正しなくても、パスポートに旧姓を併記するなど各分野の運用面で対応できるのでは、との質問に対して)かえって手間がかかる。今名乗っている名前を使い続けられる制度にすべきであり、この制度は変わると確信している。夫婦別姓に限らず、社会のルールは選択肢が多い方が人は幸せになる。今では職業や住む所が選べるように、名前も選べていい
以上、青野氏の夫婦別姓推進の主張を紹介したが、彼の主張を一言でまとめるなら、「夫婦同姓だと手続上色々と面倒である」、ということになろう。なるほど、この主張は確かに説得力を持っているように思える。結婚を経験した女性に対してはなおのことだと思う。
しかし、彼のこれら主張が民法を改正して夫婦別姓を創設すべしという結論に結び付くものとは思えない。だいたい、手続上の問題を指摘するならば、その煩雑な手続を変えればいいだけで、必ずしも民法を改正する必要性はないはずだ。
むしろ私としては、夫婦別姓を「選択的」にするほうが、かえって手続が煩雑になるように思える。
その理由として、まず、子供が産まれたときの対応がある。
平成8年に法制審議会が提示した民法改正要綱では、子の氏は統一することにしたが、別姓を選択した夫婦は婚姻時に子がどちらの氏を名乗るか決めるものとした。
もちろん、現在の制度ならば夫婦は同姓でなければならないので、わざわざ子の氏をどちらにするか決めるまでもなく、子は自動的に夫婦と同じ氏になる。手続の煩雑さを言うのなら、こちらのほうがかえって「面倒」ではないだろうか。
それから、子の氏をどちらにするか決まらない場合、そのリスクはどうやって処理するのか。こうした点から、社会の家族観を上手に反映して一つの制度を作り上げることは容易ではない。子の氏は、安定した家庭を子供に提供するという観点からの議論がなければならない。青野氏のように、目先の手続の煩雑さに囚われて夫婦別姓を主張することは、非常に危険なことである。
次に、手続の煩雑さという理由を、行政や公共サービスを提供する側などの立場になって考えてみると、実は夫婦別姓は公務員の仕事を増やし、行政のスリム化という喫緊の課題と相反することになるのではないか。
単純に考えて、これまで一つに統一されていたものを二つに分割すれば、その分仕事が増えるということは誰でも理解できる。夫婦別姓を選択的に導入することによって、公務員の窓口業務の仕事量が増加したりはしないか。
そして、現在では国家公務員であっても、2001年10月より旧姓の使用ができるようになっている。ということは、現行のままで夫婦別姓を選択的の導入するということは、仕事でもプライベートでも結婚後の氏を使う夫婦、プライベートでは結婚後の氏だが仕事では婚姻前の氏を使う夫婦、そして、夫婦の氏が別々の夫婦、という3つのパターンの夫婦が出てくるとも言え、このことは後述するように徒に社会の混乱を招きはしないか。
したがって、厄介なのはこの夫婦別姓が、夫婦同姓を廃止して夫婦別姓を導入するというのではなくて、夫婦別姓か夫婦同姓かを各個人が自由に選択できるという「選択的夫婦別姓」にある点だ。確かに青野氏の言うように、選択肢は多様であるほうが人は幸せである。しかし、ことは家族という社会の基盤となる制度に関するものである。よって青野氏の主張は些か短絡的ではないか。
「選択的」ということは、これまでと違い、夫婦のあり方が二種類になるということだ。二種類になることによって選択の幅は広がるが、それによる社会の混乱は制度導入のメリットを上回るものだと思う。
そもそも、氏を決めるというのは、単なる個人の自由でどうにかしていい問題ではなく、社会全般にかかわる公的制度の問題である。私は平等と自由ならば迷うことなく自由を選ぶが、社会制度の根幹である家族の統一を図るのに必須の氏についてまで、それを各人の自由な処分に委ねるという主張には、全く賛同できない。
ところで、上記産経新聞のアンケートによれば、選択的夫婦別姓を導入しても、それを活用するかという問いには56%が「ノー」と答えている。夫婦別姓導入の理由に国民からのニーズがあるとすれば、その当の国民がノーと答えているのに、導入する理由は一体何なのかということになる。
最後に、夫婦別姓を導入する者はしばしば、憲法上の男女平等を持ち出す。しかし、そこで、これについて批判をしておく。
まず、男女平等の思想から夫婦別姓は帰結しない。夫婦は同じ氏を名乗るか別の氏を名乗るかを、婚姻の際に確立5割のくじによって決める制度も男女平等の思想には反しない(内田貴『民法Ⅳ』)。
次に、これについては既に岐阜家庭裁判所が、「親族共同生活の中心となる夫婦が、同じ氏を称することは、主観的には夫婦の一体感を高めるのに役立ち、客観的には利害関係を有する第三者に対し夫婦であることを示すのを容易にするものといえる。したがって、国民感情または国民感情及び社会的慣習を根拠として制定されたといわれる民法750条は、現在においてもなお合理性を有するものであって、何ら憲法13条、24条1項に反するものではない。」と判示している(岐阜家審平1・6・23)。私はこちらの主張のほうが説得的だと思う。
なお、しばしば夫婦別姓の国として韓国が出てくるが、その理由は、氏は父系血統を表示するものとして不変のものとされ、夫の血統の家庭には入れないという思想ゆえであり、夫婦別姓を主張するフェミニストのような理由によって夫婦別姓が敷かれているわけではなく、むしろこの思想はフェミニズムと正面から対立するものであることを付言しておく。