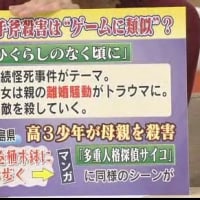2007年3月23日、7歳男児が学童保育でおやつとして支給されたこんにゃくゼリーを食べたところ、喉に詰まらせ亡くなったという事件と、4月29日、同じく7歳男児が祖父母宅でこんにゃくゼリーを食べたところ、喉に詰まらせ、数日後に亡くなったという事件が、今月23日になって相次いで明るみになりました。これを受けて、いわゆる「こんにゃくゼリー」の安全性の問題が再浮上してきました。
以前にも、こんにゃくゼリーは、原料に他のゼリーと異なり蒟蒻を使用しているため、口の中で溶けづらく、お年寄りや小さな子供が死亡したりするケースが報告されてきました。そのため、業者側も販売当初の頃よりも、ゼリーをかみ砕きやすいソフトタイプにするなど改良を重ね、そういったリスクを軽減させるため対策を講じてきました。
そういった流れの中で事故が起こりましたから、業者側には、こんにゃくゼリーを口で吸って食べるタイプだと、喉に詰まらせる可能性は否定できないので、この点は改善すべき責任があると思います。
しかし、です。食品・非食品問わず、どの製品にも何らかの「リスク」はつきものです(こんにゃくゼリーに似たものなら、たとえば飴玉や餅などが考えられるでしょう)。そしてそのリスクを完全に除去することは不可能です(リスクを除去すべき努力義務は、当然に事業者側にはあります)。
今回の事件を受けて一部マスコミや消費者問題の運動家の間では、こんにゃくゼリーの販売を規制もしくは禁止しろと言わんばかりの主張がなされましたが、商品のリスク削減のための対策までは否定しませんが、これには断固反対です。
確かに、EUでは2003年5月に、ゼリー菓子への蒟蒻の使用許可を撤回する決定を行い、以降、ゼリー菓子へのこんにゃくを使用を禁止しました。FDA(アメリカ食品・医薬品局)でも、こんにゃくゼリー等によって窒息の被害が起きる可能性があることを指摘し、消費者に蒟蒻入りのゼリー等を見かけたら連絡するように呼びかけています。
EUやアメリカというと(特に近時はEUというと)、あらゆる問題対策の最先端のような認識がなされ(そういった面があるのも否定はしませんが)、「EUがやってるなら日本もそれに倣うべきだ」みたいな、「EU信仰」的な風潮があります。しかし、上記のEUやアメリカの講じた対策は「行き過ぎ」ではないでしょうか。
過剰な消費者保護政策は、消費者に「自らの頭で考えて行動する」ことをやめさせ、消費者を「おんぶに抱っこ」の状態に堕落させることにはならないのでしょうか。そして更に、事業者側の自由な経済活動を阻害することにも繋がらならないでしょうか。
今回のこんにゃくゼリーの場合、生後間もない乳幼児に与えて窒息死させたケースや(中には2歳児に凍った状態でこんにゃくゼリーを与え、窒息死に至ったケースもあります)、高齢者の方が喉に詰まらせて窒息死したケースもありますが、元も子もない言い方ですが、これは自己責任だと思います。このようなケースにまで、事業者が消費者の尻拭いをしてやる必要はあるのでしょうか(配慮する必要は皆無とまでは言っていません)。
今回のケースはいずれも上記の場合には当てはまらないですが、こんにゃくゼリーによる事故の多くは、高齢者と小さな子供に集中しており、今回のような7歳~10歳ぐらいの子供の場合なら、親が子供に注意を促したり、親の目の届くところで食べさせるよう心がけたり、高齢者の場合なら、要介護の老人には与えない、もしくは自身で予め砕いてから食べるようにするなど、事業者側の非をあげつらう前に、取るべき行動はたくさんあるように思えます。
先ほども申したとおり、あらゆる製品には何らかの危険性があるのであって、最終的には、自分でその製品を購入することを決定した消費者が責任を負い、リスクも甘受すべきです。エキセントリックに、規制すればいい、禁止すればいい、では、かえって更に消費者の被害を生むことにもなりかねないとすら言えるのではないでしょうか。
以前にも、こんにゃくゼリーは、原料に他のゼリーと異なり蒟蒻を使用しているため、口の中で溶けづらく、お年寄りや小さな子供が死亡したりするケースが報告されてきました。そのため、業者側も販売当初の頃よりも、ゼリーをかみ砕きやすいソフトタイプにするなど改良を重ね、そういったリスクを軽減させるため対策を講じてきました。
そういった流れの中で事故が起こりましたから、業者側には、こんにゃくゼリーを口で吸って食べるタイプだと、喉に詰まらせる可能性は否定できないので、この点は改善すべき責任があると思います。
しかし、です。食品・非食品問わず、どの製品にも何らかの「リスク」はつきものです(こんにゃくゼリーに似たものなら、たとえば飴玉や餅などが考えられるでしょう)。そしてそのリスクを完全に除去することは不可能です(リスクを除去すべき努力義務は、当然に事業者側にはあります)。
今回の事件を受けて一部マスコミや消費者問題の運動家の間では、こんにゃくゼリーの販売を規制もしくは禁止しろと言わんばかりの主張がなされましたが、商品のリスク削減のための対策までは否定しませんが、これには断固反対です。
確かに、EUでは2003年5月に、ゼリー菓子への蒟蒻の使用許可を撤回する決定を行い、以降、ゼリー菓子へのこんにゃくを使用を禁止しました。FDA(アメリカ食品・医薬品局)でも、こんにゃくゼリー等によって窒息の被害が起きる可能性があることを指摘し、消費者に蒟蒻入りのゼリー等を見かけたら連絡するように呼びかけています。
EUやアメリカというと(特に近時はEUというと)、あらゆる問題対策の最先端のような認識がなされ(そういった面があるのも否定はしませんが)、「EUがやってるなら日本もそれに倣うべきだ」みたいな、「EU信仰」的な風潮があります。しかし、上記のEUやアメリカの講じた対策は「行き過ぎ」ではないでしょうか。
過剰な消費者保護政策は、消費者に「自らの頭で考えて行動する」ことをやめさせ、消費者を「おんぶに抱っこ」の状態に堕落させることにはならないのでしょうか。そして更に、事業者側の自由な経済活動を阻害することにも繋がらならないでしょうか。
今回のこんにゃくゼリーの場合、生後間もない乳幼児に与えて窒息死させたケースや(中には2歳児に凍った状態でこんにゃくゼリーを与え、窒息死に至ったケースもあります)、高齢者の方が喉に詰まらせて窒息死したケースもありますが、元も子もない言い方ですが、これは自己責任だと思います。このようなケースにまで、事業者が消費者の尻拭いをしてやる必要はあるのでしょうか(配慮する必要は皆無とまでは言っていません)。
今回のケースはいずれも上記の場合には当てはまらないですが、こんにゃくゼリーによる事故の多くは、高齢者と小さな子供に集中しており、今回のような7歳~10歳ぐらいの子供の場合なら、親が子供に注意を促したり、親の目の届くところで食べさせるよう心がけたり、高齢者の場合なら、要介護の老人には与えない、もしくは自身で予め砕いてから食べるようにするなど、事業者側の非をあげつらう前に、取るべき行動はたくさんあるように思えます。
先ほども申したとおり、あらゆる製品には何らかの危険性があるのであって、最終的には、自分でその製品を購入することを決定した消費者が責任を負い、リスクも甘受すべきです。エキセントリックに、規制すればいい、禁止すればいい、では、かえって更に消費者の被害を生むことにもなりかねないとすら言えるのではないでしょうか。