
 堺正章氏を中心にキュートでポップな小林麻耶アナウンサーとユニークなゲストが毎回、美味なるお料理作りに挑戦する「チューボーですよ!」という番組があります。随分、前のことで申し訳ないのですが、8月5日(土)のゲストは格闘家の須藤元気さんでした。その日の献立は石鍋キムチチャーハンでした。
堺正章氏を中心にキュートでポップな小林麻耶アナウンサーとユニークなゲストが毎回、美味なるお料理作りに挑戦する「チューボーですよ!」という番組があります。随分、前のことで申し訳ないのですが、8月5日(土)のゲストは格闘家の須藤元気さんでした。その日の献立は石鍋キムチチャーハンでした。 3人の軽妙な会話のやり取りもとても楽しかったのですが、須藤元気率いる、堺正章&小林麻耶アナウンサーによる3人の(格闘技の前に行われる)入場ダンスのパフォーマンスは最高の出来映えでした。
3人の軽妙な会話のやり取りもとても楽しかったのですが、須藤元気率いる、堺正章&小林麻耶アナウンサーによる3人の(格闘技の前に行われる)入場ダンスのパフォーマンスは最高の出来映えでした。 須藤元気さんのことは、彼が、以前に「オーラの泉」や「はなまるマーケット」にゲスト出演されていた折に、たまたまテレビを観ていて、その存在を知るようになった経緯があります。元気さんのスピリチャルな独特の精神世界に触れてからは、機会があれば、出演される番組は気がつけば、必ずチェックするようにしています。面白い人だなぁ~という印象を抱くようになっていたからです。格闘家なのに、ムキムキの筋肉マンタイプではない上に、四国巡礼などをしている人だということにも関心を持ちました。番組の中で、須藤さんの新刊書についてのインフォメーションがありました。
須藤元気さんのことは、彼が、以前に「オーラの泉」や「はなまるマーケット」にゲスト出演されていた折に、たまたまテレビを観ていて、その存在を知るようになった経緯があります。元気さんのスピリチャルな独特の精神世界に触れてからは、機会があれば、出演される番組は気がつけば、必ずチェックするようにしています。面白い人だなぁ~という印象を抱くようになっていたからです。格闘家なのに、ムキムキの筋肉マンタイプではない上に、四国巡礼などをしている人だということにも関心を持ちました。番組の中で、須藤さんの新刊書についてのインフォメーションがありました。 須藤さんが本を書いていることは知りませんでした。新刊書の題名は「風の谷のあの人と結婚する方法」というものです。「風の谷」ってどこにあるの?「あの人」って誰のこと?…題名一つからも、そんなふうに次から次へと興味や関心が湧いてきます。早速、ネットで、内容を調べてみました。すると、次のような説明がありました。『処女作「幸福論」がベストセラーとなった格闘家・須藤元気の待望の新刊書籍!リングを離れて人間“スドウゲンキ”として、「学びについて」、「人間関係について」、「心のコントロールについて」、「時間について」、「成功について」、「身体作りについて」、「リラックスについて」を、ライター・森沢明夫氏とのメールのやりとりでまとめた、人生を楽しく生きるための哲学を語った一冊となっています。書籍内に写真は一切使用せずに、あえて活字だけで構成し、格闘技・試合についての論述もほとんどありません。すべて須藤さんご自身のこだわりです。』
須藤さんが本を書いていることは知りませんでした。新刊書の題名は「風の谷のあの人と結婚する方法」というものです。「風の谷」ってどこにあるの?「あの人」って誰のこと?…題名一つからも、そんなふうに次から次へと興味や関心が湧いてきます。早速、ネットで、内容を調べてみました。すると、次のような説明がありました。『処女作「幸福論」がベストセラーとなった格闘家・須藤元気の待望の新刊書籍!リングを離れて人間“スドウゲンキ”として、「学びについて」、「人間関係について」、「心のコントロールについて」、「時間について」、「成功について」、「身体作りについて」、「リラックスについて」を、ライター・森沢明夫氏とのメールのやりとりでまとめた、人生を楽しく生きるための哲学を語った一冊となっています。書籍内に写真は一切使用せずに、あえて活字だけで構成し、格闘技・試合についての論述もほとんどありません。すべて須藤さんご自身のこだわりです。』 本屋さんで探してみましたが見つけられなかったので、いつものように、御用達の図書館にリクエストを出すことにしました。
本屋さんで探してみましたが見つけられなかったので、いつものように、御用達の図書館にリクエストを出すことにしました。 村上春樹さんの「そうだ。村上さんに聞いてみよう。」も読者とのメールのやり取りを一冊の本にまとめたものですが、とても読みやすく、しかもメールを書いている人やメールに答えている村上さんの人となりが誠実に伝わってくる優れた一冊でしたので、須藤さんの新刊もメールのやり取りをまとめたものと知って、その内容をとても楽しみにしています。この本を読まれた方の感想も是非、知りたいものです。
村上春樹さんの「そうだ。村上さんに聞いてみよう。」も読者とのメールのやり取りを一冊の本にまとめたものですが、とても読みやすく、しかもメールを書いている人やメールに答えている村上さんの人となりが誠実に伝わってくる優れた一冊でしたので、須藤さんの新刊もメールのやり取りをまとめたものと知って、その内容をとても楽しみにしています。この本を読まれた方の感想も是非、知りたいものです。★「風の谷のあの人と結婚する方法」










 不思議な本です。何十年も前に書かれて一度は絶版になり、著者についても名前は分かっていても、どういう人なのかについての詳しい情報は皆無といういわくつきの本です。平明な言葉で極めて簡潔に単純に、当たり前に見えることが書かれてあるだけなので、この本の智恵をすべての人が享受できるとは限らないとも思われます。読み流してしまうだけで終わる人がほとんどではないでしょうか?こうした本に書かれてあることの内容は表現は違っていても中身は極めて似通ったものであることが多いので、馴染みの知識を確認し直すという傾向に流されがちになりますが、今回は、「本当の意味で努力を持続できる人はほとんどいません。目覚しい成功がほんの少ししかないのはそのせいなのです。」という言葉にはっとさせられるものを感じていました。。今の私の気持ちが若干ダレ気味になり始めていたからなのだと思います。どんな状況にも果敢に取り組み、環境に順応していこうとする力というものは、いかにも頼もしく勇ましいことのようにも思えますが、非日常をほどなく日常に変えてしまうほどの強力な性質というものは、一歩間違えれば、いい意味での緊張感をも容易に失わさせ、自己への挑戦や現在のありようを更新していく前向きの姿勢にも水をかけて、怠惰で安逸をむさぼろうとする「もう一人の自分」を蘇らさせる魔物としての側面をも備えているからです。退路を断とうとする自分と、「まあそんなに力まなくてもいいじゃないか!」とか「今のままでいいじゃないか!」と誘惑的に囁く自分との耐えざるせめぎあいが、私の人生の実相でもあります。
不思議な本です。何十年も前に書かれて一度は絶版になり、著者についても名前は分かっていても、どういう人なのかについての詳しい情報は皆無といういわくつきの本です。平明な言葉で極めて簡潔に単純に、当たり前に見えることが書かれてあるだけなので、この本の智恵をすべての人が享受できるとは限らないとも思われます。読み流してしまうだけで終わる人がほとんどではないでしょうか?こうした本に書かれてあることの内容は表現は違っていても中身は極めて似通ったものであることが多いので、馴染みの知識を確認し直すという傾向に流されがちになりますが、今回は、「本当の意味で努力を持続できる人はほとんどいません。目覚しい成功がほんの少ししかないのはそのせいなのです。」という言葉にはっとさせられるものを感じていました。。今の私の気持ちが若干ダレ気味になり始めていたからなのだと思います。どんな状況にも果敢に取り組み、環境に順応していこうとする力というものは、いかにも頼もしく勇ましいことのようにも思えますが、非日常をほどなく日常に変えてしまうほどの強力な性質というものは、一歩間違えれば、いい意味での緊張感をも容易に失わさせ、自己への挑戦や現在のありようを更新していく前向きの姿勢にも水をかけて、怠惰で安逸をむさぼろうとする「もう一人の自分」を蘇らさせる魔物としての側面をも備えているからです。退路を断とうとする自分と、「まあそんなに力まなくてもいいじゃないか!」とか「今のままでいいじゃないか!」と誘惑的に囁く自分との耐えざるせめぎあいが、私の人生の実相でもあります。 この本を感心しながら読んだのは、もう随分、以前のことになるのですが、この本の内容が、あまりにも優れたものだったので、今でも、時々、しかも定期的に思い出しては、ところどころを拾い読みしながら、感心している私がいます。何度、読み直しても、村上氏の、ものの考え方の素晴らしさには色褪せない普遍性が含まれているので、その度に、新たな感銘を受けてしまうのです。読者からのメールによる人生相談の一つ一つに村上氏が丁寧に答えたものを1冊の本にまとめたものに「そうだ、村上さんに聞いてみよう」というタイトルが付けられているのですが、このタイトルがまた、とても気が利いているので、その点も気に入っています。村上氏の著作は熱烈なファン層によって根強く支えられていますが、私にとっては、必ずしも読みやすいものではないので、失礼ながら、2~3冊くらいしか読んだことがありません。ところが、「そうだ、村上さんに聞いていよう」はまったく違っていました。村上氏の、実に端的で硬質で誠実で的確でブレのない人柄に、私はかなりの衝撃を受けたのです。今時、これほどの人間がまだいたんだ!という事実に、真の感動を覚えたのです。超一流の人格の持ち主だと思いました。それ以来、私は村上春樹氏を心から尊敬するようになりました。その気持ちは、かつても、今も、そしてこれからも、きっと永遠に変わらないことでしょう。
この本を感心しながら読んだのは、もう随分、以前のことになるのですが、この本の内容が、あまりにも優れたものだったので、今でも、時々、しかも定期的に思い出しては、ところどころを拾い読みしながら、感心している私がいます。何度、読み直しても、村上氏の、ものの考え方の素晴らしさには色褪せない普遍性が含まれているので、その度に、新たな感銘を受けてしまうのです。読者からのメールによる人生相談の一つ一つに村上氏が丁寧に答えたものを1冊の本にまとめたものに「そうだ、村上さんに聞いてみよう」というタイトルが付けられているのですが、このタイトルがまた、とても気が利いているので、その点も気に入っています。村上氏の著作は熱烈なファン層によって根強く支えられていますが、私にとっては、必ずしも読みやすいものではないので、失礼ながら、2~3冊くらいしか読んだことがありません。ところが、「そうだ、村上さんに聞いていよう」はまったく違っていました。村上氏の、実に端的で硬質で誠実で的確でブレのない人柄に、私はかなりの衝撃を受けたのです。今時、これほどの人間がまだいたんだ!という事実に、真の感動を覚えたのです。超一流の人格の持ち主だと思いました。それ以来、私は村上春樹氏を心から尊敬するようになりました。その気持ちは、かつても、今も、そしてこれからも、きっと永遠に変わらないことでしょう。
 神田橋條治先生の『古稀記念―「現場からの治療論」という物語』という新刊書は難しい言葉は使われていないため、一見、読みやすい内容なのかと勘違いしてしまうかもしれませんが、大変に難解で、私には歯が立ちませんでした。頭では、ほとんど理解できないのです。感覚的にしか、しかも自分なりにしか、この‘童話’を読み解くことはできませんでした。ただ、ここに出てくる‘ファントム’という単語が、現代の人間のあり様や実態をとても分かりやすく表現してくれていると感じられて、目からウロコの思いに捉われました。恐らく、ヒトを、このように捉えて、今の現実社会で散見されている種々の現象を説明してくれている書籍は現在のところは他にはないと思われます。その意味では、まったく新しい概念に出会ったという驚きと新鮮さを覚えました。
神田橋條治先生の『古稀記念―「現場からの治療論」という物語』という新刊書は難しい言葉は使われていないため、一見、読みやすい内容なのかと勘違いしてしまうかもしれませんが、大変に難解で、私には歯が立ちませんでした。頭では、ほとんど理解できないのです。感覚的にしか、しかも自分なりにしか、この‘童話’を読み解くことはできませんでした。ただ、ここに出てくる‘ファントム’という単語が、現代の人間のあり様や実態をとても分かりやすく表現してくれていると感じられて、目からウロコの思いに捉われました。恐らく、ヒトを、このように捉えて、今の現実社会で散見されている種々の現象を説明してくれている書籍は現在のところは他にはないと思われます。その意味では、まったく新しい概念に出会ったという驚きと新鮮さを覚えました。
 『7つの習慣』という名著のことをご存知ですか?ここには、人が人として成長していくとはどういうことなのかが分かりやすく書かれてあります。成長のプロセスを理解するために、依存・自立・相互依存のそれぞれの成長レベルにいる人の持つパラダイム(思考の枠組み)の違いを説明してくれていますので、触れてみたいと思います。
『7つの習慣』という名著のことをご存知ですか?ここには、人が人として成長していくとはどういうことなのかが分かりやすく書かれてあります。成長のプロセスを理解するために、依存・自立・相互依存のそれぞれの成長レベルにいる人の持つパラダイム(思考の枠組み)の違いを説明してくれていますので、触れてみたいと思います。 私は、今話題になっている小説とかエッセイとか自己啓発の類の本以外はほとんど読んだことがありません。が、最近、日系四世のロバートキヨサキ氏と公認会計士のシャロン・レクターという人の共著の「金持ち父さん貧乏父さん」という本を読んでみました。タイトルとは裏腹に(そんなにお気楽な本ではなく…)お金や経営に関するなかなか難しい内容が詳細に詰まっている本でした。私は株や不動産を初めとする資産運用のことにはまったく無知ですので、書かれてあることの字面を追うだけで、本の知識を生かして、自分も資産を増やしてみよう…というようなわけには行きませんが、幾つかの項目は、経営者になろうとする人でなくても、人生訓として面白く読めるものです。特に、セールスとマーケッティングすなわち、売る(モノだけではなく、自分の才覚や機転や信用などを含む)能力のことについて説明している件の部分は大変勉強になりました。売る能力の基本にあるものは『相手が顧客であれ従業員であれ、上司、配偶者、または子どもであれ、他人と意思を疎通させる能力だ。人生で成功するのに不可欠なのは、書く、話す、交渉するといったコミュニケーション能力だと言ってもいい。~中略~私はセールスとマーケッティングの能力ほど重要な技術はないと思う。大抵の人はセールスとマーケッティングの能力を習得するのは難しいと思っている。その大きな理由は、拒否されることに対する恐怖だ。コミュニケーションや交渉の仕方がうまくなり、拒否されることに対する恐怖心をコントロールすることが出来るようになれば、それだけ人生が楽になる。』私はセールスマンではありませんので、何とかして、商品を売るための努力や工夫に頭をひねらなければならないということが一切ありません。このことはとても有難いことでもあるのですが、人生や人間関係における重大な危機意識を見落としてきた要因でもあったのではないだろうかと、今頃になって自問自答しています。生きるためには、嫌でも人との関わりのことを考えなければならない…という局面に立つ必要が通常はあるものなのに、私にはそれが希薄だったような気がしています。嫌ならやめればいい。もうその人とは会わなければいい。極端に言えばそれでも済んできたわけです。商品についても然りです。どうしても、その商品を気に入ってもらうためには、商品に関する知識や、その商品の唯一無二の価値と素晴らしさを人に理解してもらわなければなりません。これまでは、私は、人に‘お願い’をしてまで何かを訴えることなど一度もしないで済んできたのです。(もちろん、プライベートは別です。)であればこそ、人に頭を下げる必要がないから、人とは対等な関係や立場で仕事をすることが可能であったわけですが、それはそれで、私にはとても良かったことなのですが、だからなのでしょうか?仕事をしていく上で、どうしても人を大切にしなければならない…とまでは考えてこなかったような気もするのです。相手の欲しいものが何なのか。どういうことを相手にしてあげればいいのか。そういう観点から人を眺めたことがあったでしょうか?コミュニケーション能力はそれほど洗練されていなくても、「私は人付き合いが下手だから…」で済ませてきてしまいました。以前に、精神分析の先生が、「分析の過程は交渉能力の過程でもある。」といわれた時、私はその言葉の新鮮さにひどく感動したものでした。書くという行為の不思議さはブログの世界で日々味わっています。話すという部分は、Blissさんとの時々の対話で行きつ戻りつ学ばせてもらっています。交渉能力というと仕事における取引上の言葉のような印象を受けてしまいますが、そういうドライなニュアンスとは別に、優れて人間的なコミュニケーションの手続きの用語でもあると、私は思っています。拒否されることに対する恐怖…これは本当に深刻です。拒否されたって平気だなんて決して思えません。だからこそ、この部分をどのように扱うかに‘鍵’があるのでしょうね!
私は、今話題になっている小説とかエッセイとか自己啓発の類の本以外はほとんど読んだことがありません。が、最近、日系四世のロバートキヨサキ氏と公認会計士のシャロン・レクターという人の共著の「金持ち父さん貧乏父さん」という本を読んでみました。タイトルとは裏腹に(そんなにお気楽な本ではなく…)お金や経営に関するなかなか難しい内容が詳細に詰まっている本でした。私は株や不動産を初めとする資産運用のことにはまったく無知ですので、書かれてあることの字面を追うだけで、本の知識を生かして、自分も資産を増やしてみよう…というようなわけには行きませんが、幾つかの項目は、経営者になろうとする人でなくても、人生訓として面白く読めるものです。特に、セールスとマーケッティングすなわち、売る(モノだけではなく、自分の才覚や機転や信用などを含む)能力のことについて説明している件の部分は大変勉強になりました。売る能力の基本にあるものは『相手が顧客であれ従業員であれ、上司、配偶者、または子どもであれ、他人と意思を疎通させる能力だ。人生で成功するのに不可欠なのは、書く、話す、交渉するといったコミュニケーション能力だと言ってもいい。~中略~私はセールスとマーケッティングの能力ほど重要な技術はないと思う。大抵の人はセールスとマーケッティングの能力を習得するのは難しいと思っている。その大きな理由は、拒否されることに対する恐怖だ。コミュニケーションや交渉の仕方がうまくなり、拒否されることに対する恐怖心をコントロールすることが出来るようになれば、それだけ人生が楽になる。』私はセールスマンではありませんので、何とかして、商品を売るための努力や工夫に頭をひねらなければならないということが一切ありません。このことはとても有難いことでもあるのですが、人生や人間関係における重大な危機意識を見落としてきた要因でもあったのではないだろうかと、今頃になって自問自答しています。生きるためには、嫌でも人との関わりのことを考えなければならない…という局面に立つ必要が通常はあるものなのに、私にはそれが希薄だったような気がしています。嫌ならやめればいい。もうその人とは会わなければいい。極端に言えばそれでも済んできたわけです。商品についても然りです。どうしても、その商品を気に入ってもらうためには、商品に関する知識や、その商品の唯一無二の価値と素晴らしさを人に理解してもらわなければなりません。これまでは、私は、人に‘お願い’をしてまで何かを訴えることなど一度もしないで済んできたのです。(もちろん、プライベートは別です。)であればこそ、人に頭を下げる必要がないから、人とは対等な関係や立場で仕事をすることが可能であったわけですが、それはそれで、私にはとても良かったことなのですが、だからなのでしょうか?仕事をしていく上で、どうしても人を大切にしなければならない…とまでは考えてこなかったような気もするのです。相手の欲しいものが何なのか。どういうことを相手にしてあげればいいのか。そういう観点から人を眺めたことがあったでしょうか?コミュニケーション能力はそれほど洗練されていなくても、「私は人付き合いが下手だから…」で済ませてきてしまいました。以前に、精神分析の先生が、「分析の過程は交渉能力の過程でもある。」といわれた時、私はその言葉の新鮮さにひどく感動したものでした。書くという行為の不思議さはブログの世界で日々味わっています。話すという部分は、Blissさんとの時々の対話で行きつ戻りつ学ばせてもらっています。交渉能力というと仕事における取引上の言葉のような印象を受けてしまいますが、そういうドライなニュアンスとは別に、優れて人間的なコミュニケーションの手続きの用語でもあると、私は思っています。拒否されることに対する恐怖…これは本当に深刻です。拒否されたって平気だなんて決して思えません。だからこそ、この部分をどのように扱うかに‘鍵’があるのでしょうね! 日本を代表する精神科医である中井久夫先生の『関与と観察』という著作を読んでいます。その中の【現代社会に生きること】という論文は、あまりにも近代社会の本質がつまびらかにあぶりだされているので、身につまされる部分が多すぎて、胸苦しさが迫ってくるのです。改めて「そうかぁ~。私たちはこんなに厳しい時代を生きているんだ!」と再認識し、どうしたら、このテンションから抜け出すことが出来るのかと頭を抱え込んでしまっています。このままでは命を永らえることさえ難しくなるだろうなと感じたほどです。昔は良かった…という話ではないのですが、『たとえば、かつて荷車を弾く人の精神状態如何はさして問題ではなかった。たとえ、少し偏っていてもさほど重大な結果は引き起こさなかっただろうけれど、今日繰り返し取り上げられているように、高速で疾走する電車、自動車、飛行機の運転者の精神異常が引き起こすだろう結果の大きさは格段のものだろう。そうした任にある人に要求される注意力の、ほとんど人間の限界とさえ思えるような厳しさ、過酷さは想像の外である。~中略~高度に組織された社会の、「組織の中の人間」には、そのような、機械的といわずとも、機能的な正確さ、正常さの要求は、今後もますます高まるであろう。~中略~ゆとりなしの労働が当然のこととして要求される社会。現代では、勤勉自体よりも、能率や効果が優先される。そうして要求されるものは、何よりもまず、機能・性能の正常さであるが、~中略~現代の要求する「正常さ」には、ある非情な、さらには異常なものがないであろうか。~中略~「正常」であれという非情な要求、そうして、現代の人間として落伍しないために「自分は正常であろうか」とつぶやき続ける人間-なぜなら高度に組織された社会からの落伍はそうでない社会からよりも、はるかに徹底的で救いのないものであろうから-「自分は正常であろうか」というつぶやきは、落伍-失業の不安を背にし非情な要求を前にし、そうして仕事から究極には阻害されているといわれる現代の人間の悲惨な自己点検ではなかろうか。そうして、先に述べた「性能崇拝」もそのような人間の悲しい夢想ではないだろうか。』と続きます。私はパソコンのキー一つがシステム全体に影響を及ぼすような仕事をしているわけでもないですし、多くの人命をあずかるような重大な職務についているわけでもありません。それでも、仕事面においても、人事面においても、高度に組織化された箱の中で、いつでも交換可能な歯車の一つとして、取り敢えずは動いている…という現実を日々ひしひしと感じるようになっています。そして、心は、目には見えないほど少しずつ磨耗していっています。こうした社会システムの中で、非情かつ強靭に生き残っていくことに、私自身は特段の意義をも、もはや感じることは出来なくなっています。
日本を代表する精神科医である中井久夫先生の『関与と観察』という著作を読んでいます。その中の【現代社会に生きること】という論文は、あまりにも近代社会の本質がつまびらかにあぶりだされているので、身につまされる部分が多すぎて、胸苦しさが迫ってくるのです。改めて「そうかぁ~。私たちはこんなに厳しい時代を生きているんだ!」と再認識し、どうしたら、このテンションから抜け出すことが出来るのかと頭を抱え込んでしまっています。このままでは命を永らえることさえ難しくなるだろうなと感じたほどです。昔は良かった…という話ではないのですが、『たとえば、かつて荷車を弾く人の精神状態如何はさして問題ではなかった。たとえ、少し偏っていてもさほど重大な結果は引き起こさなかっただろうけれど、今日繰り返し取り上げられているように、高速で疾走する電車、自動車、飛行機の運転者の精神異常が引き起こすだろう結果の大きさは格段のものだろう。そうした任にある人に要求される注意力の、ほとんど人間の限界とさえ思えるような厳しさ、過酷さは想像の外である。~中略~高度に組織された社会の、「組織の中の人間」には、そのような、機械的といわずとも、機能的な正確さ、正常さの要求は、今後もますます高まるであろう。~中略~ゆとりなしの労働が当然のこととして要求される社会。現代では、勤勉自体よりも、能率や効果が優先される。そうして要求されるものは、何よりもまず、機能・性能の正常さであるが、~中略~現代の要求する「正常さ」には、ある非情な、さらには異常なものがないであろうか。~中略~「正常」であれという非情な要求、そうして、現代の人間として落伍しないために「自分は正常であろうか」とつぶやき続ける人間-なぜなら高度に組織された社会からの落伍はそうでない社会からよりも、はるかに徹底的で救いのないものであろうから-「自分は正常であろうか」というつぶやきは、落伍-失業の不安を背にし非情な要求を前にし、そうして仕事から究極には阻害されているといわれる現代の人間の悲惨な自己点検ではなかろうか。そうして、先に述べた「性能崇拝」もそのような人間の悲しい夢想ではないだろうか。』と続きます。私はパソコンのキー一つがシステム全体に影響を及ぼすような仕事をしているわけでもないですし、多くの人命をあずかるような重大な職務についているわけでもありません。それでも、仕事面においても、人事面においても、高度に組織化された箱の中で、いつでも交換可能な歯車の一つとして、取り敢えずは動いている…という現実を日々ひしひしと感じるようになっています。そして、心は、目には見えないほど少しずつ磨耗していっています。こうした社会システムの中で、非情かつ強靭に生き残っていくことに、私自身は特段の意義をも、もはや感じることは出来なくなっています。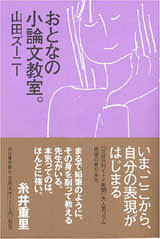 山田ズーニーという人をご存知ですか?糸井重里さんのWeb上の『ほぼ日刊イトイ新聞』の中の【おとなの小論文教室 感じる・考える・伝わる!】を運営・指導している女性です。難しい語彙も使わず、非常に平明な優しい言葉で話しかけるように文章を綴ってくれています。しかも、その文章も書かれてある内容も無味乾燥な冷たいものではなく非常に【熱い】想いで貫かれていて首尾一貫性のあるものなので、眉間に皺を寄せて取り組む必要もない大変有難い論文教室です。文章を書くという作業は、いざとなるとなかなか手ごわいものです。自分の書きたいことだけを書いている分には問題ありませんが、仕事で【お題】を与えられて、興味のない内容について書かなければならないとかなると、文章を書くという行為がたちまち苦行に姿を変え、途端に筆が進まなくなります。論旨の一貫性が前提ですし知識や資料の斬新性と先端性も問われてきます。独りよがりの内容では、興味を持ってはもらえませんし、読んでくれる人に、伝えたいことが伝わるような書き方がとても大事になります。【おとなの小論文教室 感じる・考える・伝わる!】の中のある記事(就職の採用試験後に複数の内定を貰えるようになった方が何故、そのようになったかの経緯についてズーニーさんのインタビューに答えていて、その理由をズーニーさんが考察するくだりのペーパー)が非常に興味深かったです。自分の【好き】を極めるために、【直感】を頼りに【思考の粘り】を重ねていったら現実の壁を突破することが出来た…という貴重な体験が経過を追って説明されています。ズーニーさんの勢いある筆力のおかげで、一気に楽しく読めてしまいます。(ページの最下段にある目次から【Lesson250 伝わると伝わらないの境界】と【Lesson261 好きを掘りさげる力(4)伝わると伝わらないの境界】を選んで読んでみてください。)すべての論文がとにかく素晴らしい!のです。花も実もある論文とは、こういう論文をいうのでしょう。上っ面の文章ではなく、書く人の【人間性に裏付けられた人生観】がきちんと表現されているのです。
山田ズーニーという人をご存知ですか?糸井重里さんのWeb上の『ほぼ日刊イトイ新聞』の中の【おとなの小論文教室 感じる・考える・伝わる!】を運営・指導している女性です。難しい語彙も使わず、非常に平明な優しい言葉で話しかけるように文章を綴ってくれています。しかも、その文章も書かれてある内容も無味乾燥な冷たいものではなく非常に【熱い】想いで貫かれていて首尾一貫性のあるものなので、眉間に皺を寄せて取り組む必要もない大変有難い論文教室です。文章を書くという作業は、いざとなるとなかなか手ごわいものです。自分の書きたいことだけを書いている分には問題ありませんが、仕事で【お題】を与えられて、興味のない内容について書かなければならないとかなると、文章を書くという行為がたちまち苦行に姿を変え、途端に筆が進まなくなります。論旨の一貫性が前提ですし知識や資料の斬新性と先端性も問われてきます。独りよがりの内容では、興味を持ってはもらえませんし、読んでくれる人に、伝えたいことが伝わるような書き方がとても大事になります。【おとなの小論文教室 感じる・考える・伝わる!】の中のある記事(就職の採用試験後に複数の内定を貰えるようになった方が何故、そのようになったかの経緯についてズーニーさんのインタビューに答えていて、その理由をズーニーさんが考察するくだりのペーパー)が非常に興味深かったです。自分の【好き】を極めるために、【直感】を頼りに【思考の粘り】を重ねていったら現実の壁を突破することが出来た…という貴重な体験が経過を追って説明されています。ズーニーさんの勢いある筆力のおかげで、一気に楽しく読めてしまいます。(ページの最下段にある目次から【Lesson250 伝わると伝わらないの境界】と【Lesson261 好きを掘りさげる力(4)伝わると伝わらないの境界】を選んで読んでみてください。)すべての論文がとにかく素晴らしい!のです。花も実もある論文とは、こういう論文をいうのでしょう。上っ面の文章ではなく、書く人の【人間性に裏付けられた人生観】がきちんと表現されているのです。 村上春樹氏の『東京奇譚集』という短編集の中の一編の不思議なお話しのタイトルです。淳平とキリエという二人の男女の、短い期間の交流を、都会的な乾いたそれでいて非常に豊かな潤いのあるタッチで描いた作品です。小品ながら佳作でもあります。淳平は、「愛情を適時に適切に具象化するという重要な意味を持つ能力」に自信を持てなくなって、「心は光明と温かみを欠いた場所に沈みこんでいった。」時を過ごしています。そんな時に、ひょんなきっかけでキリエという女性と出会い、ライトな感覚で、どちらからともなく近づき、恋のような雰囲気に浸りながら濃密な時間を共に過ごすことになります。二人には、「ここに来るまでは決して簡単な道のりではなかったけれど、小さい頃からやりたいと思っていたことを職業にしている」という共通点があります。淳平は、「職業というのは本来は愛の行為であるべきなんだ。便宜的な結婚みたいなものじゃなくて」と言います。キリエは言います。「誰かと日常的に深い関係を結ぶということが、私にはできないの。あなたとだけじゃなく、誰とも」「もし誰かと日常生活を共にしたり、その相手に感情的に深くのめり込んだりしたら、今自分がやっていることに完全に集中できなくなってしまうから、今みたいなままがいい」と。心が乱されるとバランスが失われて、自分のキャリアに重大な支障が生じるかもしれないということを心配しています。淳平は小説家なので、キリエという存在に触発されて、人の目が届かない時に限って場所を移動する腎臓のかたちをした石を題材にした小説を書きます。二人の関係が突然終わるなどと想像も出来なかったのに、淳平が小説を書き上げた途端にキリエとは連絡がつかなくなります。その後、ラジオから聞こえてくるある番組を通して、思いがけずも淳平はキリエの素性と正体を知ることになります。失って初めて、淳平はキリエのことを「他の女性には一度も感じたことのない、特別な感情を抱くようになっている」ことに気づきます。それは「明瞭な輪郭を持ち、手応えをそなえた、奥行きの深い感情」でした。その感情にどのような名前をつければいいのか、淳平には分かりません。「しかし少なくとも、他の何かと取り替えることの出来ない思いだ。」ということに気づきます。「もう二度とキリエに会えないとしても、この思いはいつまでも彼の心にあるいは骨の髄のような場所に残ることだろう。彼は身体のどこかでキリエの欠落を感じ続けることだろう。」ことをひしひしと感じます。これを機に、それまでの臆病だった淳平の気持ちにある変化が訪れます。キリエは彼にとって、「本当に意味を持つ」女性の一人だったということを思い知ります。彼の中にはもう以前のような恐怖はありません。大事なのは付き合った女性の数ではなく、‘いつまでに誰かと何かの関係に落ち着く’というようなカウントダウンにも何の意味もないことを悟ります。大事なのは誰か一人をそっくり受容しようという気持ちなのだということを理解するようになるのです。腎臓のかたちをした黒い石は小説の中の一つのアイテムなのですが、彼の心を操る重要なツールとして不可思議な動きでうごめき続けます。が、彼の心が定まった時、その黒い石は姿を消し、もう二度とは戻ってこないものとなるのです。石が夜毎、勝手に歩き回るわけはありません。でも、そんなことが本当に起こりうるような心持ちになるのですから、小説家の想像力というものはものすごい威力を持つものなのだと感心します。黒い石は何を象徴しているのでしょうか?私には分かりません。ただ、とても言葉では言い表すことなど出来ない宇宙の拡がりを感じるばかりでした。
村上春樹氏の『東京奇譚集』という短編集の中の一編の不思議なお話しのタイトルです。淳平とキリエという二人の男女の、短い期間の交流を、都会的な乾いたそれでいて非常に豊かな潤いのあるタッチで描いた作品です。小品ながら佳作でもあります。淳平は、「愛情を適時に適切に具象化するという重要な意味を持つ能力」に自信を持てなくなって、「心は光明と温かみを欠いた場所に沈みこんでいった。」時を過ごしています。そんな時に、ひょんなきっかけでキリエという女性と出会い、ライトな感覚で、どちらからともなく近づき、恋のような雰囲気に浸りながら濃密な時間を共に過ごすことになります。二人には、「ここに来るまでは決して簡単な道のりではなかったけれど、小さい頃からやりたいと思っていたことを職業にしている」という共通点があります。淳平は、「職業というのは本来は愛の行為であるべきなんだ。便宜的な結婚みたいなものじゃなくて」と言います。キリエは言います。「誰かと日常的に深い関係を結ぶということが、私にはできないの。あなたとだけじゃなく、誰とも」「もし誰かと日常生活を共にしたり、その相手に感情的に深くのめり込んだりしたら、今自分がやっていることに完全に集中できなくなってしまうから、今みたいなままがいい」と。心が乱されるとバランスが失われて、自分のキャリアに重大な支障が生じるかもしれないということを心配しています。淳平は小説家なので、キリエという存在に触発されて、人の目が届かない時に限って場所を移動する腎臓のかたちをした石を題材にした小説を書きます。二人の関係が突然終わるなどと想像も出来なかったのに、淳平が小説を書き上げた途端にキリエとは連絡がつかなくなります。その後、ラジオから聞こえてくるある番組を通して、思いがけずも淳平はキリエの素性と正体を知ることになります。失って初めて、淳平はキリエのことを「他の女性には一度も感じたことのない、特別な感情を抱くようになっている」ことに気づきます。それは「明瞭な輪郭を持ち、手応えをそなえた、奥行きの深い感情」でした。その感情にどのような名前をつければいいのか、淳平には分かりません。「しかし少なくとも、他の何かと取り替えることの出来ない思いだ。」ということに気づきます。「もう二度とキリエに会えないとしても、この思いはいつまでも彼の心にあるいは骨の髄のような場所に残ることだろう。彼は身体のどこかでキリエの欠落を感じ続けることだろう。」ことをひしひしと感じます。これを機に、それまでの臆病だった淳平の気持ちにある変化が訪れます。キリエは彼にとって、「本当に意味を持つ」女性の一人だったということを思い知ります。彼の中にはもう以前のような恐怖はありません。大事なのは付き合った女性の数ではなく、‘いつまでに誰かと何かの関係に落ち着く’というようなカウントダウンにも何の意味もないことを悟ります。大事なのは誰か一人をそっくり受容しようという気持ちなのだということを理解するようになるのです。腎臓のかたちをした黒い石は小説の中の一つのアイテムなのですが、彼の心を操る重要なツールとして不可思議な動きでうごめき続けます。が、彼の心が定まった時、その黒い石は姿を消し、もう二度とは戻ってこないものとなるのです。石が夜毎、勝手に歩き回るわけはありません。でも、そんなことが本当に起こりうるような心持ちになるのですから、小説家の想像力というものはものすごい威力を持つものなのだと感心します。黒い石は何を象徴しているのでしょうか?私には分かりません。ただ、とても言葉では言い表すことなど出来ない宇宙の拡がりを感じるばかりでした。
 アーユルヴェーダ関連の書籍を読んでいると、しばしば‘純粋意識’という言葉が出てきます。この言葉の意味は自明の理として使われていることが多いので、何となく、自分なりの理解で読み飛ばしていましたが、この言葉の意味を詳細に説明してくれている本に出会いました。「私」という意識というものは、「私」という自分を‘見る’意識と、「私」という自分を‘見られる’意識とに分かれているそうです。それから、実は、もう一つ、見る意識が見られる意識を見ている状態という意識もあるそうです。アーユルヴェーダでは、見る意識のことを「認識者(リシ)」・見ている状態の意識のことを「過程(デーヴァタ)」・見られる意識のことを「対象(チャンダス)」と呼んでいます。このように、意識は一つでありながら、同時に三つに分かれているということの解説で、意識という捉えどころのない実態をより重層的に理解できるような気がしました。意識は常に一つに統一された状態にありながら、三つに分かれることによって自分を認識しているのです。マハシリ・ヴェーダ医療(形骸化していたヴェーダ医学をマハシリという人が生き返らせたところから、この名称を使っているようです。)この統一された意識のことを「純粋意識」と呼ぶのだということを今頃になってやっと知ることとなりました。三つに分かれた意識は、そのままには留まらず、認識している認識者を認識する、というような行程を繰り返し、分かれ続けているということです。(極めて哲学的ですネ!)私たちが日常生活で経験していることは、すべて意識の認識によって成り立っています。たとえば、お腹が痛い人がいるとして、このことは、その人が腹部の痛みを認識しているということであり、痛みを認識する意識が、痛みを認識する過程によって、痛みという対象の意識を認識しているということにもなります。純粋意識は普遍的な存在であり、永遠にその統一の状態を保ちつつ、同時に、それ自身の揺らぎによって認識者ともなります。そして認識者は自分自身を見ることによって過程を生じさせます。そこでさらに、意識は自分が見られる対象へと変化していくのです。過程とは、意識が自分自身を主観的に認識している状態であると表現できるそうです。私たちが、一般に「心」と呼んでいるものは、実はこの“過程”に相当するのだそうです。悲しいとか辛いとかの感情的体験を伴う「心」というものが、あくまでも個人の主観的な体験であることは誰もが知っています。心が常に動きを持っているのは(心コロコロという表現があるように…)その本質が活動だからだそうです。そして、過程は対象へと変化を遂げます。つまり、意識は自分を主観的に体験している状態から、客観的なものへと切り離し、対象となるのです。意識には‘あたかも自分を自分ではないものへと’変換するような力が備わっているということです。体や物質は意識から見た時、それは対象という状態にあるものなのです。……というようなことがヴァータとかラジャスとかタマスとかの専門用語を駆使しながら説明されますが、難しい用語はすべて省きましたし、途中の解説も、私が分からない部分は表現を変えたり、はしょったりしました。意識という小宇宙はこのように智恵深いもののようです。三つの機能を巧みに使い分けて、常に事象を観察し続けている賢い哲学者はいつも、どの人の心身の中にも常駐していると思うと、何だか一気に賢くなれるような気がしてくるから、不思議です。
アーユルヴェーダ関連の書籍を読んでいると、しばしば‘純粋意識’という言葉が出てきます。この言葉の意味は自明の理として使われていることが多いので、何となく、自分なりの理解で読み飛ばしていましたが、この言葉の意味を詳細に説明してくれている本に出会いました。「私」という意識というものは、「私」という自分を‘見る’意識と、「私」という自分を‘見られる’意識とに分かれているそうです。それから、実は、もう一つ、見る意識が見られる意識を見ている状態という意識もあるそうです。アーユルヴェーダでは、見る意識のことを「認識者(リシ)」・見ている状態の意識のことを「過程(デーヴァタ)」・見られる意識のことを「対象(チャンダス)」と呼んでいます。このように、意識は一つでありながら、同時に三つに分かれているということの解説で、意識という捉えどころのない実態をより重層的に理解できるような気がしました。意識は常に一つに統一された状態にありながら、三つに分かれることによって自分を認識しているのです。マハシリ・ヴェーダ医療(形骸化していたヴェーダ医学をマハシリという人が生き返らせたところから、この名称を使っているようです。)この統一された意識のことを「純粋意識」と呼ぶのだということを今頃になってやっと知ることとなりました。三つに分かれた意識は、そのままには留まらず、認識している認識者を認識する、というような行程を繰り返し、分かれ続けているということです。(極めて哲学的ですネ!)私たちが日常生活で経験していることは、すべて意識の認識によって成り立っています。たとえば、お腹が痛い人がいるとして、このことは、その人が腹部の痛みを認識しているということであり、痛みを認識する意識が、痛みを認識する過程によって、痛みという対象の意識を認識しているということにもなります。純粋意識は普遍的な存在であり、永遠にその統一の状態を保ちつつ、同時に、それ自身の揺らぎによって認識者ともなります。そして認識者は自分自身を見ることによって過程を生じさせます。そこでさらに、意識は自分が見られる対象へと変化していくのです。過程とは、意識が自分自身を主観的に認識している状態であると表現できるそうです。私たちが、一般に「心」と呼んでいるものは、実はこの“過程”に相当するのだそうです。悲しいとか辛いとかの感情的体験を伴う「心」というものが、あくまでも個人の主観的な体験であることは誰もが知っています。心が常に動きを持っているのは(心コロコロという表現があるように…)その本質が活動だからだそうです。そして、過程は対象へと変化を遂げます。つまり、意識は自分を主観的に体験している状態から、客観的なものへと切り離し、対象となるのです。意識には‘あたかも自分を自分ではないものへと’変換するような力が備わっているということです。体や物質は意識から見た時、それは対象という状態にあるものなのです。……というようなことがヴァータとかラジャスとかタマスとかの専門用語を駆使しながら説明されますが、難しい用語はすべて省きましたし、途中の解説も、私が分からない部分は表現を変えたり、はしょったりしました。意識という小宇宙はこのように智恵深いもののようです。三つの機能を巧みに使い分けて、常に事象を観察し続けている賢い哲学者はいつも、どの人の心身の中にも常駐していると思うと、何だか一気に賢くなれるような気がしてくるから、不思議です。