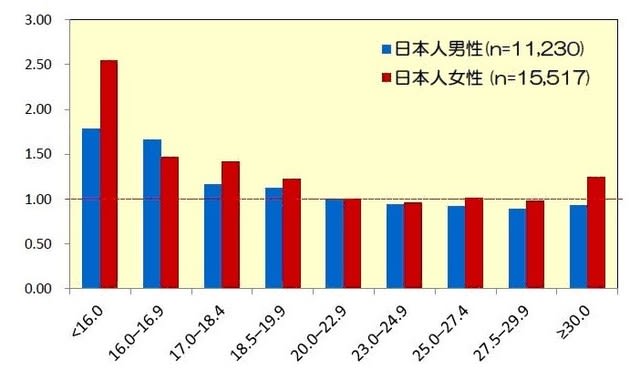今回は、あまりにも身近すぎて普段は特別に意識しない“呼吸”について考えてみましょう。 起床時に、朝日を浴びながら胸一杯に空気を吸い込んで一日の始まりをすがすがしく迎える方もおられることと思います。
ただ、ここで問題があります。私たちは、深呼吸は体にいいと思い込んでいないでしょうか。確かに、ストレッチ効果もあり数回深呼吸することは何ら問題ありません。しかし呼吸は、し過ぎると体にとって良くないのです。
まず呼吸のメカニズムをご説明します。鼻から吸い込まれた空気は、鼻腔、気管を通り、肺(肺胞)に到達します。空気中からガス拡散で血液中に取り込まれた酸素は、ヘモグロビンというたんぱく質に結合して血液中を体の隅々まで運ばれます。ヘモグロビンは、細胞に酸素を渡し、細胞で産生された二酸化炭素を受け取り肺に戻ります。言い換えると、酸素を体に取り込み、二酸化炭素を排出するのが呼吸の役割となります。
ここで重要なのは、ヘモグロビンが細胞にどれだけたくさん酸素を渡すことができるかです。この割合を決めているのは、実は酸素濃度ではなく、二酸化炭素の濃度なのです。具体的には、二酸化炭素濃度が高いほど効率よく酸素を細胞に届けることができ、逆に低ければ、酸素がヘモグロビンから細胞に渡されにくくなります(ボーア効果)。
体の動脈血酸素濃度は、通常の呼吸ですでに95~99%あり、いくら呼吸量を増やしてもこれ以上増やすことはできません。一方、二酸化炭素は、呼吸量の増加に伴い体の外への排出量が増え、体の中の濃度は下がってきます。したがって、呼吸量が増えすぎると二酸化炭素濃度が下がり、効率よく酸素を細胞に届けることができなくなってしまいます。逆に呼吸量を減らすと二酸化炭素の濃度が上がり細胞への効率的な酸素分配ができます。
大昔の人類では、交感神経緊張させ、呼吸を意識的に増大させ、生命の危機を乗り切る必要な場面もありました。一方現代人は、ストレス社会により慢性的に交感神経緊張状態となり、知らず知らずのうちに呼吸過多の状態になっています。また食生活においても、野菜、果物、水(アルカリ形成食品)から、肉、加工食品、砂糖、コーヒーなど(酸形成食品)中心の生活になり、体の中が酸性に傾きやすくなっています。体は弱アルカリ性(PH=7.4)であるため、二酸化炭素の量を減らして代償する必要があり、呼吸過多になりがちです(無論、体のPHを維持するのは、呼吸だけでなく腎臓の役割も大きいです)。これらにより、現代社会では、二酸化炭素濃度が下がり、酸素を効率よく細胞に届けることができず、労作時の息切れや全身倦怠感を自覚する人が多いのです。
さてここで、呼吸法についても考えてみましょう。
皆さんは、イライラや興奮した時あるいは運動時(すなわち呼吸過多になりやすい場面)に鼻呼吸ではなく、口呼吸になっていないでしょうか?また睡眠中に口を開けていませんか?あるいは普段から口呼吸になっている人はいませんか?
口呼吸になると、胸郭を拡げ浅く速い呼吸(胸式呼吸)になってしまいます。一方、鼻呼吸では、自然に横隔膜を使ってお腹を膨らませるゆったりした呼吸(腹式呼吸)ができます。
この一見当たり前のようで意外にできていない“鼻呼吸”こそが、最高の呼吸法と言われる方法なのです。
鼻呼吸のメリットは、鼻腔を通ることと腹式呼吸となることにより得られます。適温に温められ、適度な湿気を帯び、ゴミや細菌が除去されたきれいな空気が肺に届きます。また鼻腔内にある高濃度の一酸化窒素(NO)を一緒に吸入することができます。このNOは、血管や気管を拡張させ、免疫や神経伝達を高め、生命の恒常性を維持し健康にしてくれる気体です。 またお腹が膨らんだりへこんだりすることでリンパ循環がよくなり老廃物除去が促進されます。さらに、口呼吸に比し、呼吸抵抗が50%大きくなるため呼吸量が減り、体内に取り込める酸素の量が20%増えます。
一方、口呼吸では、猫背気味になり脱水になります。口腔内の病気が増え、口臭、いびきや睡眠障害の原因になります。さらに鼻の血管の炎症を起こし鼻づまりがひどくなり、ますます口呼吸が習慣化してしまいます。NOの恩恵にあずかれず脳の血流量が減って集中力が低下します。
そして、この鼻呼吸をゆっくりなるべく呼吸量を減らすようにおこなうことにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症に対応する能力が向上し、結果として健康維持や運動能力アップが可能となります。 これは、ヨガ習得者や一流のアスリートが身に着けている呼吸法なのです。高地トレーニングと同様な効果が、平地でも鼻呼吸で呼吸量を減らし(時に息止めをする)運動することにより期待できます。
さあ今日から、ゆっくり鼻呼吸を意識して生活し、もし口を開けて寝ているのであれば口にテープを張って寝てみましょう。とても簡単で費用のかからない素晴らしい健康法です。
参考文献:パトリック・マキューン 『人生が変わる最高の呼吸法』
ただ、ここで問題があります。私たちは、深呼吸は体にいいと思い込んでいないでしょうか。確かに、ストレッチ効果もあり数回深呼吸することは何ら問題ありません。しかし呼吸は、し過ぎると体にとって良くないのです。
まず呼吸のメカニズムをご説明します。鼻から吸い込まれた空気は、鼻腔、気管を通り、肺(肺胞)に到達します。空気中からガス拡散で血液中に取り込まれた酸素は、ヘモグロビンというたんぱく質に結合して血液中を体の隅々まで運ばれます。ヘモグロビンは、細胞に酸素を渡し、細胞で産生された二酸化炭素を受け取り肺に戻ります。言い換えると、酸素を体に取り込み、二酸化炭素を排出するのが呼吸の役割となります。
ここで重要なのは、ヘモグロビンが細胞にどれだけたくさん酸素を渡すことができるかです。この割合を決めているのは、実は酸素濃度ではなく、二酸化炭素の濃度なのです。具体的には、二酸化炭素濃度が高いほど効率よく酸素を細胞に届けることができ、逆に低ければ、酸素がヘモグロビンから細胞に渡されにくくなります(ボーア効果)。
体の動脈血酸素濃度は、通常の呼吸ですでに95~99%あり、いくら呼吸量を増やしてもこれ以上増やすことはできません。一方、二酸化炭素は、呼吸量の増加に伴い体の外への排出量が増え、体の中の濃度は下がってきます。したがって、呼吸量が増えすぎると二酸化炭素濃度が下がり、効率よく酸素を細胞に届けることができなくなってしまいます。逆に呼吸量を減らすと二酸化炭素の濃度が上がり細胞への効率的な酸素分配ができます。
大昔の人類では、交感神経緊張させ、呼吸を意識的に増大させ、生命の危機を乗り切る必要な場面もありました。一方現代人は、ストレス社会により慢性的に交感神経緊張状態となり、知らず知らずのうちに呼吸過多の状態になっています。また食生活においても、野菜、果物、水(アルカリ形成食品)から、肉、加工食品、砂糖、コーヒーなど(酸形成食品)中心の生活になり、体の中が酸性に傾きやすくなっています。体は弱アルカリ性(PH=7.4)であるため、二酸化炭素の量を減らして代償する必要があり、呼吸過多になりがちです(無論、体のPHを維持するのは、呼吸だけでなく腎臓の役割も大きいです)。これらにより、現代社会では、二酸化炭素濃度が下がり、酸素を効率よく細胞に届けることができず、労作時の息切れや全身倦怠感を自覚する人が多いのです。
さてここで、呼吸法についても考えてみましょう。
皆さんは、イライラや興奮した時あるいは運動時(すなわち呼吸過多になりやすい場面)に鼻呼吸ではなく、口呼吸になっていないでしょうか?また睡眠中に口を開けていませんか?あるいは普段から口呼吸になっている人はいませんか?
口呼吸になると、胸郭を拡げ浅く速い呼吸(胸式呼吸)になってしまいます。一方、鼻呼吸では、自然に横隔膜を使ってお腹を膨らませるゆったりした呼吸(腹式呼吸)ができます。
この一見当たり前のようで意外にできていない“鼻呼吸”こそが、最高の呼吸法と言われる方法なのです。
鼻呼吸のメリットは、鼻腔を通ることと腹式呼吸となることにより得られます。適温に温められ、適度な湿気を帯び、ゴミや細菌が除去されたきれいな空気が肺に届きます。また鼻腔内にある高濃度の一酸化窒素(NO)を一緒に吸入することができます。このNOは、血管や気管を拡張させ、免疫や神経伝達を高め、生命の恒常性を維持し健康にしてくれる気体です。 またお腹が膨らんだりへこんだりすることでリンパ循環がよくなり老廃物除去が促進されます。さらに、口呼吸に比し、呼吸抵抗が50%大きくなるため呼吸量が減り、体内に取り込める酸素の量が20%増えます。
一方、口呼吸では、猫背気味になり脱水になります。口腔内の病気が増え、口臭、いびきや睡眠障害の原因になります。さらに鼻の血管の炎症を起こし鼻づまりがひどくなり、ますます口呼吸が習慣化してしまいます。NOの恩恵にあずかれず脳の血流量が減って集中力が低下します。
そして、この鼻呼吸をゆっくりなるべく呼吸量を減らすようにおこなうことにより、低酸素血症や高二酸化炭素血症に対応する能力が向上し、結果として健康維持や運動能力アップが可能となります。 これは、ヨガ習得者や一流のアスリートが身に着けている呼吸法なのです。高地トレーニングと同様な効果が、平地でも鼻呼吸で呼吸量を減らし(時に息止めをする)運動することにより期待できます。
さあ今日から、ゆっくり鼻呼吸を意識して生活し、もし口を開けて寝ているのであれば口にテープを張って寝てみましょう。とても簡単で費用のかからない素晴らしい健康法です。
参考文献:パトリック・マキューン 『人生が変わる最高の呼吸法』