コロイド状態とは結晶質へと変化する可能性がある物質に於ける動的な状態として定義しておこう。
つまりコロイド状態には「ENERGIA」を秘めている。新たに発見されたエネルギー状態への造語に、アリストテレスの影を認めるのは自由である。
その含意は、結晶とか非晶質とか、そのような仮の姿や宿を問題とはしていないけれども、造語に頼って語り掛けなければならない自らの立場としては、その説明責任を果たす覚悟がいる。言うなれば比喩をもってその勤めを果たさんと、つまりリベラルアーツ、知覚問題である。
グラファイトなどの実験等を通して結晶・非晶質にも通じていた彼がここでことさら峻別する事はない!方便として、クリスタロイドそしてコロイドと分離してみせたまでだ。
事実その反響はアメリカの開業医ミッチェルからの第一報にはじまり、生理学者とか医化学者などから寄せられた事は彼にとっては本望ではなかったか。
それが浸透問題へと及ぶにつれて確かな手応えを覚えていたに違いない。それがリービッヒやホフマンなどからの厳しくも優しい励ましは歴史的にも有難かったはず。とは言えその道筋が気体にも似たランダム・ウオークながらも、先人たちの叡智に頼りつつ時分を歩んできた。
小史
1859年 ベンジャミン・コリンズ・ブロディの論文「グラファイトの原子量について」
査読者はトーマス・グレーアム
1860年 第一回世界化学者会議 ブロディ参加。
カニッツァーロの小冊子 アボガドロの仮説とデュロン-プティの仮説を首尾一貫して用いて,物理学的データに矛盾しない原子量体系をつくりあげた.
1861年 “Liquid diffusion applied to analysis” コロイド概念を得る。
1863年 ”On the molecular mobility of gases” 満を持しての原子論を示唆。
不可知論者ブロデイと共にあったグレーアム、あの論文はこの事実を下敷きとして読み解かれなくてはならない。実験哲学の書だけではすまない!物理・化学その境界を切り拓いたミクロコスモス。造語であるコロイド問題。つまり「COSMOSのai!」それが素朴な秩序を意味して要るわけではない。
 そこからの彼は造幣局長官の重責を果たす中で、そこでの問題を終結させてゆく日々でもあったと、我々は知る。残された5年足らずにも論文を仕上げきった。振り返ればたった一本の「膠道」である。
そこからの彼は造幣局長官の重責を果たす中で、そこでの問題を終結させてゆく日々でもあったと、我々は知る。残された5年足らずにも論文を仕上げきった。振り返ればたった一本の「膠道」である。
共にあったアンガー・スミスは、伝記作家としての役目も果たしてくれた。ギリシャ由来とかインドからの思想とかに言及しながら、それが五輪塔のような、五大の認識だと読み解ける。
つまりニュートニアンが受け継ぎ守ってきたその結果としてのパラダイム転換であった。万有引力ではない万有重力と言うべきか、
①疑問1;物体は距離をおいて光に作用し、その作用によって光の射線を曲げるのではないか。
②疑問5;物質と光は互いに作用し合うのではないか。
③疑問8;全ての不揮発性物質は、加熱させると光を放出して輝くのではないか。
⓸疑問30;粗大な物質と光は互いに転換できるのではないか
⑤Query 31 Queryのうちで最も長く最後にあるのが31である。ニュートニアンと言われる多くの人がこの問題を重要視した。その背景には『プリンキピア』の末尾での結語として書かれていたとされている。
Dobbsにょれぽ,「ニュートンが錬金術から得ようと望んだのは,小宇宙において,物質を構成している活力のない諸粒子を組織付け活気づけるような,神の手による作用を,正確に知ることであった」のである。
つまり拡散・浸透等で語られるそれである。正に膠観である。
温故知新は対応原理である。
父 ヴォルフガング・ヨーゼフ・パウリ(Wolfgang Josef Pauli、1869年=1955)オーストリアの医師、生化学者(コロイド化学、タンパク質化学)。彼はコロイド化学の基礎的な研究を行い、コロイドの理論を開発しました。
タンパク質の表面電荷がpH値に依存するという観察により、彼は電気泳動の基礎を提供し、カール ランドシュタイナー(ABO式血液型を発見)と一緒に電気泳動装置(タンパク質精製用の移送装置)の先駆けを開発しました。彼は、水和、膨潤、旋光性に対するタンパク質の電荷の影響を研究し、タンパク質に対する保護コロイドの効果と電離放射線の影響を研究しました。
その子、パウリと言えば排他律!? 誰もが知るその息子であり、誰もが知らない父である。
しかし親子して同じ道を棲み分けていた。古典的なコロイド化学であり、量子論的なコロイド化学の世界である。
二元論的止揚からの「膠観」つまり相補償的なコロイド世界が彼を虜にしていた。
その息子の研究の足跡を参考に供する。1920-1938
① コロイドの純度問題
② 電気傾瀉法によって、実質的には電解質を含まないコロイドを得た。
③ コロイド状イオウの化学的製法 非常に周到な研究により、イオウ粒子はチオ硫酸で安定化されていることを明らかにした。
⓸ 増感および安定化の現象 水酸化クロムの非常に純粋なゾルは振盪により容易に凝結する。
その彼は曰く「ハイゼンベルグは哲学的考察に欠けています!」と、ボーアに書き送る。その1年後「残念ながら私自身の哲学的立場は、全くもってはっきりしません。」とパウリへ書く。
その彼は多くの哲学的な書を残してくれた事には注意する必要があろう。彼ら二人して「膠場」を建設したとさえ言いうる。量子化学の建設者である。
アインシュタインの一般相対性理論が1916年に発表され、人々が競ってその解説を求めたとき、パウリは『数理科学百科事典』の一項目でそれに応えた時、21歳であった。
①「結局、君は正しかった!この野郎!!」1932年1月22日 アインシュタイン⇒パウリ
② 他 あの1905年、ブラウンもグレーアムも知らなかった、知らぬが仏!
参考文献など
①「コロイド化学」B.ヤーケンソンス M.E.ストラマニス 玉虫文一監訳
② パウリは、原子核が出す放射線(ベータ線)のエネルギー分布を研究しているとき、エネルギーがどこかへ消えてしまうことをどう説明すべきか悩みました。そしてつじつまを合わせるために立てた仮説が、「電気を帯びていなくて、知らないうちにどこかへ飛び出してしまう、幽霊のような粒子がある」というもの。フェルミは、パウリの考えた粒子について研究し、ベータ崩壊の理論を構築していました。1932年に現在のニュートロン(中性子)が発見されていたので、幽霊粒子のほうを「ニュートリノ」と名づけ直しました。
丁度、その頃のマヨラナは「物理学と社会科学における統計的法則の価値」等を書き上げていたらしい。けれども出版する事を躊躇していた。そこにもパラダイム転換があったものと理解される!
つまりコロイド状態には「ENERGIA」を秘めている。新たに発見されたエネルギー状態への造語に、アリストテレスの影を認めるのは自由である。
その含意は、結晶とか非晶質とか、そのような仮の姿や宿を問題とはしていないけれども、造語に頼って語り掛けなければならない自らの立場としては、その説明責任を果たす覚悟がいる。言うなれば比喩をもってその勤めを果たさんと、つまりリベラルアーツ、知覚問題である。
グラファイトなどの実験等を通して結晶・非晶質にも通じていた彼がここでことさら峻別する事はない!方便として、クリスタロイドそしてコロイドと分離してみせたまでだ。
事実その反響はアメリカの開業医ミッチェルからの第一報にはじまり、生理学者とか医化学者などから寄せられた事は彼にとっては本望ではなかったか。
それが浸透問題へと及ぶにつれて確かな手応えを覚えていたに違いない。それがリービッヒやホフマンなどからの厳しくも優しい励ましは歴史的にも有難かったはず。とは言えその道筋が気体にも似たランダム・ウオークながらも、先人たちの叡智に頼りつつ時分を歩んできた。
小史
1859年 ベンジャミン・コリンズ・ブロディの論文「グラファイトの原子量について」
査読者はトーマス・グレーアム
1860年 第一回世界化学者会議 ブロディ参加。
カニッツァーロの小冊子 アボガドロの仮説とデュロン-プティの仮説を首尾一貫して用いて,物理学的データに矛盾しない原子量体系をつくりあげた.
1861年 “Liquid diffusion applied to analysis” コロイド概念を得る。
1863年 ”On the molecular mobility of gases” 満を持しての原子論を示唆。
不可知論者ブロデイと共にあったグレーアム、あの論文はこの事実を下敷きとして読み解かれなくてはならない。実験哲学の書だけではすまない!物理・化学その境界を切り拓いたミクロコスモス。造語であるコロイド問題。つまり「COSMOSのai!」それが素朴な秩序を意味して要るわけではない。
 そこからの彼は造幣局長官の重責を果たす中で、そこでの問題を終結させてゆく日々でもあったと、我々は知る。残された5年足らずにも論文を仕上げきった。振り返ればたった一本の「膠道」である。
そこからの彼は造幣局長官の重責を果たす中で、そこでの問題を終結させてゆく日々でもあったと、我々は知る。残された5年足らずにも論文を仕上げきった。振り返ればたった一本の「膠道」である。共にあったアンガー・スミスは、伝記作家としての役目も果たしてくれた。ギリシャ由来とかインドからの思想とかに言及しながら、それが五輪塔のような、五大の認識だと読み解ける。
つまりニュートニアンが受け継ぎ守ってきたその結果としてのパラダイム転換であった。万有引力ではない万有重力と言うべきか、
①疑問1;物体は距離をおいて光に作用し、その作用によって光の射線を曲げるのではないか。
②疑問5;物質と光は互いに作用し合うのではないか。
③疑問8;全ての不揮発性物質は、加熱させると光を放出して輝くのではないか。
⓸疑問30;粗大な物質と光は互いに転換できるのではないか
⑤Query 31 Queryのうちで最も長く最後にあるのが31である。ニュートニアンと言われる多くの人がこの問題を重要視した。その背景には『プリンキピア』の末尾での結語として書かれていたとされている。
Dobbsにょれぽ,「ニュートンが錬金術から得ようと望んだのは,小宇宙において,物質を構成している活力のない諸粒子を組織付け活気づけるような,神の手による作用を,正確に知ることであった」のである。
つまり拡散・浸透等で語られるそれである。正に膠観である。
温故知新は対応原理である。
父 ヴォルフガング・ヨーゼフ・パウリ(Wolfgang Josef Pauli、1869年=1955)オーストリアの医師、生化学者(コロイド化学、タンパク質化学)。彼はコロイド化学の基礎的な研究を行い、コロイドの理論を開発しました。
タンパク質の表面電荷がpH値に依存するという観察により、彼は電気泳動の基礎を提供し、カール ランドシュタイナー(ABO式血液型を発見)と一緒に電気泳動装置(タンパク質精製用の移送装置)の先駆けを開発しました。彼は、水和、膨潤、旋光性に対するタンパク質の電荷の影響を研究し、タンパク質に対する保護コロイドの効果と電離放射線の影響を研究しました。
その子、パウリと言えば排他律!? 誰もが知るその息子であり、誰もが知らない父である。
しかし親子して同じ道を棲み分けていた。古典的なコロイド化学であり、量子論的なコロイド化学の世界である。
二元論的止揚からの「膠観」つまり相補償的なコロイド世界が彼を虜にしていた。
その息子の研究の足跡を参考に供する。1920-1938
① コロイドの純度問題
② 電気傾瀉法によって、実質的には電解質を含まないコロイドを得た。
③ コロイド状イオウの化学的製法 非常に周到な研究により、イオウ粒子はチオ硫酸で安定化されていることを明らかにした。
⓸ 増感および安定化の現象 水酸化クロムの非常に純粋なゾルは振盪により容易に凝結する。
その彼は曰く「ハイゼンベルグは哲学的考察に欠けています!」と、ボーアに書き送る。その1年後「残念ながら私自身の哲学的立場は、全くもってはっきりしません。」とパウリへ書く。
その彼は多くの哲学的な書を残してくれた事には注意する必要があろう。彼ら二人して「膠場」を建設したとさえ言いうる。量子化学の建設者である。
アインシュタインの一般相対性理論が1916年に発表され、人々が競ってその解説を求めたとき、パウリは『数理科学百科事典』の一項目でそれに応えた時、21歳であった。
①「結局、君は正しかった!この野郎!!」1932年1月22日 アインシュタイン⇒パウリ
② 他 あの1905年、ブラウンもグレーアムも知らなかった、知らぬが仏!
参考文献など
①「コロイド化学」B.ヤーケンソンス M.E.ストラマニス 玉虫文一監訳
② パウリは、原子核が出す放射線(ベータ線)のエネルギー分布を研究しているとき、エネルギーがどこかへ消えてしまうことをどう説明すべきか悩みました。そしてつじつまを合わせるために立てた仮説が、「電気を帯びていなくて、知らないうちにどこかへ飛び出してしまう、幽霊のような粒子がある」というもの。フェルミは、パウリの考えた粒子について研究し、ベータ崩壊の理論を構築していました。1932年に現在のニュートロン(中性子)が発見されていたので、幽霊粒子のほうを「ニュートリノ」と名づけ直しました。
丁度、その頃のマヨラナは「物理学と社会科学における統計的法則の価値」等を書き上げていたらしい。けれども出版する事を躊躇していた。そこにもパラダイム転換があったものと理解される!











 道後「飛鳥乃湯」、その形見。
道後「飛鳥乃湯」、その形見。 大循環 「膠界の虚私」
大循環 「膠界の虚私」


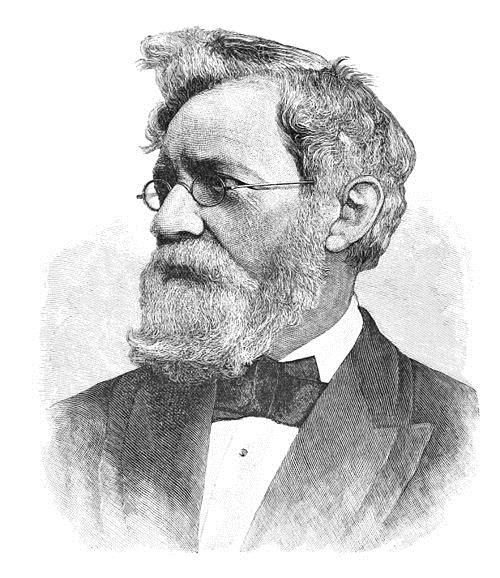 然しながら、ドイツから来たホフマンは全く違っていた。
然しながら、ドイツから来たホフマンは全く違っていた。
 青地林宗の墓
青地林宗の墓




