読了してから3週間くらい経つのですが、この傑作の感想を。
貫井徳郎は好きな作家の一人で、このブログでも『愚行録』などを取り上げてきましたが、本作も上下巻で計1150頁、著者渾身の2100枚と読み応えのある小説です。
本作は14歳の中学生3人が主人公です。彼らは全く別々の事情で重大犯罪(殺人)を犯し、中等少年院で出会うことになります。「少年」ですから1年足らずで出所しますが、3人の人生は好むと好まざると再び一つに交錯し、銀行強盗という犯罪に向かいます。そしてその先にあるものは・・・というのがあらすじです。

上巻では、各少年の凶行に至るまでの経緯が丹念に描かれ、世間的には「心の闇」などという言葉で片づけられてしまうものの正体に迫ろうとしています。そして、彼らが遭遇する少年院ライフは壮絶です。『あしたのジョー』の時代から変わっていないのかと思うような、二段ベット上からの落下リンチとか、徹底して理不尽な扱いを強いられます。少年院て更正施設ではなかったのでしょうか??
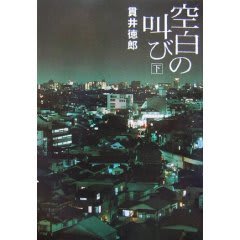
下巻では、出所した3人それぞれの「その後」と破綻が語られます。最終盤は昔の大映ドラマ(赤いシリーズとか)的な展開で少々興醒めでしたが、この小説の価値は謎解きや銀行強盗のトリックよりも、犯罪少年の精神世界を照射したことにあります。
「出所後の更正がいかに困難か」というテーマの作品には、真保裕一の『繋がれた明日』があります。少年法が罰さなくても世間が制裁するという現実ですね。犯罪被害者遺族が味わう塗炭の苦しみや狂おしいほどの慟哭は、これまで多くの小説の題材になっていますが、著者のもう一つの代表作『殺人症候群』なども傑作だと思います。また、遺族の復讐願望をクローズアップして、報復殺人の是非を問うた東野圭吾『さまよえる刃』という小説もありました。
今回この小説を取り上げたのは、少し前ですが、佐藤秀さんが時事を考えるのマルセルさんとプチ論争をしていたのを読んでいたからです。佐藤さんが取り上げておられた奥野修司著『心にナイフをしのばせて』は、1969年4月、川崎市で起きた同級生首切り殺人事件の加害者がその後、弁護士として法律事務所を経営し、ひとかどの名士になった一方で、被害者遺族は筆舌に尽くせぬほどの苦しみを長期にわたって味わっていることの対比をレポートしたルポです。少年法の立法精神(処罰ではなく教育)からすると理想的な「更生」の実例なのですが、著者はインタビューで「お金など物質的なことなのか、あるいは謝罪など精神的なものなのか、とにかく被害者がある程度納得したときに、初めて更生したといえるのではないでしょうか」と、更生はあくまで被害者との関係性の中でなされるものだと論じています。

また、著者はそもそもの取材・執筆動機を「神戸の事件が起きたとき、あの事件そのものを取材しても何も分からないだろう、それより昔似たような事件が起きていたなら、そちらを調べた方が『酒鬼薔薇』少年に迫れるのではないかと考えたのが、この本を書くきっかけでした」と語っているのですが、罪の軽重問わず、類似の事件が起こる度に過去の事件をむしかえされるのでは、過去の過ちを悔いて生きている人も、おちおち実社会で暮らしていけなくなるという現実もあります。
これは非常に難しい問題です。
もちろん被害者遺族に過酷な現行少年法にも課題はありますが、発達したマスコミとインターネットの普及(匿名掲示板だけでなく、SNSのような相互監視社会も)により、情報開示の度合いによっては、前科者が事実上抹殺される社会になる危険を孕んでいます。でも、何故そういう事件が起こったか? ということは想像したいし、考えたい。そこで私は、小説家に期待したいと考えているのです。少年犯罪の加害者を追跡して実像に迫るのは、やはりノンフィクションでは制約があるからです。
評論家の佐高信が対談で面白いことを言っていました。
「日本の企業の実態は小説の中にある」と。
日本では、本当の内部告発が出にくいのと、経済ジャーナリズムにはクライアントタブーが存在し、いわゆる「書けない」ことも多いので、城山三郎や清水一行や梶山季之などの企業モデル小説が、フィクションでありながらも(あるがゆえに)ノンフィクションよりも企業の真相や実態に迫っていたのだというのです。最近では高杉良の小説なんかも、モデルがどこだかすぐわかっちゃいますけど、「これは小説ですから」と一応いえるわけです。
企業小説の場合は、書けない新聞記者からネタをもらったり取材しているという事情がありますが、イマジネーションとリーダビリティーを持った作家には、今回の『空白の叫び』のように、一般の目から厚いベールに覆われた存在を小説という形で、白日の下に曝してほしいと思うのです。
それにしても作家の想像力は凄いものがあります。本書の主人公の一人は、放火により実母を殺しています。もう一人は医者の息子で、一緒に暮らすのは女好きの父が迎えた後妻、顔立ちも端整で学業優秀、開成中学を想起させるような私立のトップ校「開明中学」に通うという設定です。私も再三このブログで取り上げましたが、今年の6月に起きた奈良の東大寺学園生徒による放火殺人事件をまるで予見していたかのようです。この小説は、初出が小学館の『文芸ポスト』という季刊誌だったため、01年~06年と連載が長期間にわたるものですから、完全に小説先行です。
たしかに貧しい前科少年は、職を転々としたり、普通の職業に就けずにその日暮らしを余儀なくされて・・・という一般イメージから遠くない人生を送ることが多いのかも知れませんが、親に権力や圧倒的な経済力があって、子どもの犯罪によっても致命的なダメージを負うことから免れたような場合、少年法の制度メリットを最大限享受できる可能性があります。全てが覆い隠されるわけですから。
お金に不自由しなければ、すぐに働かなくてもよいので、社会とリンクすることで生じるリスクも少ない。人並みの知力があれば、Z会かなんかで独習して大学に入り、そのまま法科大学院に行ったりして、するするっと法曹界に進むなんてことも不可能ではないでしょう。実際に弁護士になった人がいるのですから。
この小説が全ての役割を果たすわけではありませんが、少なくとも、「事件」の後で語られる評論家や心理学者などの紋切り型の発言を聞くよりも、よほど有益であると思います。
貫井徳郎は好きな作家の一人で、このブログでも『愚行録』などを取り上げてきましたが、本作も上下巻で計1150頁、著者渾身の2100枚と読み応えのある小説です。
本作は14歳の中学生3人が主人公です。彼らは全く別々の事情で重大犯罪(殺人)を犯し、中等少年院で出会うことになります。「少年」ですから1年足らずで出所しますが、3人の人生は好むと好まざると再び一つに交錯し、銀行強盗という犯罪に向かいます。そしてその先にあるものは・・・というのがあらすじです。

上巻では、各少年の凶行に至るまでの経緯が丹念に描かれ、世間的には「心の闇」などという言葉で片づけられてしまうものの正体に迫ろうとしています。そして、彼らが遭遇する少年院ライフは壮絶です。『あしたのジョー』の時代から変わっていないのかと思うような、二段ベット上からの落下リンチとか、徹底して理不尽な扱いを強いられます。少年院て更正施設ではなかったのでしょうか??
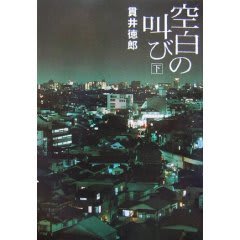
下巻では、出所した3人それぞれの「その後」と破綻が語られます。最終盤は昔の大映ドラマ(赤いシリーズとか)的な展開で少々興醒めでしたが、この小説の価値は謎解きや銀行強盗のトリックよりも、犯罪少年の精神世界を照射したことにあります。
「出所後の更正がいかに困難か」というテーマの作品には、真保裕一の『繋がれた明日』があります。少年法が罰さなくても世間が制裁するという現実ですね。犯罪被害者遺族が味わう塗炭の苦しみや狂おしいほどの慟哭は、これまで多くの小説の題材になっていますが、著者のもう一つの代表作『殺人症候群』なども傑作だと思います。また、遺族の復讐願望をクローズアップして、報復殺人の是非を問うた東野圭吾『さまよえる刃』という小説もありました。
今回この小説を取り上げたのは、少し前ですが、佐藤秀さんが時事を考えるのマルセルさんとプチ論争をしていたのを読んでいたからです。佐藤さんが取り上げておられた奥野修司著『心にナイフをしのばせて』は、1969年4月、川崎市で起きた同級生首切り殺人事件の加害者がその後、弁護士として法律事務所を経営し、ひとかどの名士になった一方で、被害者遺族は筆舌に尽くせぬほどの苦しみを長期にわたって味わっていることの対比をレポートしたルポです。少年法の立法精神(処罰ではなく教育)からすると理想的な「更生」の実例なのですが、著者はインタビューで「お金など物質的なことなのか、あるいは謝罪など精神的なものなのか、とにかく被害者がある程度納得したときに、初めて更生したといえるのではないでしょうか」と、更生はあくまで被害者との関係性の中でなされるものだと論じています。

また、著者はそもそもの取材・執筆動機を「神戸の事件が起きたとき、あの事件そのものを取材しても何も分からないだろう、それより昔似たような事件が起きていたなら、そちらを調べた方が『酒鬼薔薇』少年に迫れるのではないかと考えたのが、この本を書くきっかけでした」と語っているのですが、罪の軽重問わず、類似の事件が起こる度に過去の事件をむしかえされるのでは、過去の過ちを悔いて生きている人も、おちおち実社会で暮らしていけなくなるという現実もあります。
これは非常に難しい問題です。
もちろん被害者遺族に過酷な現行少年法にも課題はありますが、発達したマスコミとインターネットの普及(匿名掲示板だけでなく、SNSのような相互監視社会も)により、情報開示の度合いによっては、前科者が事実上抹殺される社会になる危険を孕んでいます。でも、何故そういう事件が起こったか? ということは想像したいし、考えたい。そこで私は、小説家に期待したいと考えているのです。少年犯罪の加害者を追跡して実像に迫るのは、やはりノンフィクションでは制約があるからです。
評論家の佐高信が対談で面白いことを言っていました。
「日本の企業の実態は小説の中にある」と。
日本では、本当の内部告発が出にくいのと、経済ジャーナリズムにはクライアントタブーが存在し、いわゆる「書けない」ことも多いので、城山三郎や清水一行や梶山季之などの企業モデル小説が、フィクションでありながらも(あるがゆえに)ノンフィクションよりも企業の真相や実態に迫っていたのだというのです。最近では高杉良の小説なんかも、モデルがどこだかすぐわかっちゃいますけど、「これは小説ですから」と一応いえるわけです。
企業小説の場合は、書けない新聞記者からネタをもらったり取材しているという事情がありますが、イマジネーションとリーダビリティーを持った作家には、今回の『空白の叫び』のように、一般の目から厚いベールに覆われた存在を小説という形で、白日の下に曝してほしいと思うのです。
それにしても作家の想像力は凄いものがあります。本書の主人公の一人は、放火により実母を殺しています。もう一人は医者の息子で、一緒に暮らすのは女好きの父が迎えた後妻、顔立ちも端整で学業優秀、開成中学を想起させるような私立のトップ校「開明中学」に通うという設定です。私も再三このブログで取り上げましたが、今年の6月に起きた奈良の東大寺学園生徒による放火殺人事件をまるで予見していたかのようです。この小説は、初出が小学館の『文芸ポスト』という季刊誌だったため、01年~06年と連載が長期間にわたるものですから、完全に小説先行です。
たしかに貧しい前科少年は、職を転々としたり、普通の職業に就けずにその日暮らしを余儀なくされて・・・という一般イメージから遠くない人生を送ることが多いのかも知れませんが、親に権力や圧倒的な経済力があって、子どもの犯罪によっても致命的なダメージを負うことから免れたような場合、少年法の制度メリットを最大限享受できる可能性があります。全てが覆い隠されるわけですから。
お金に不自由しなければ、すぐに働かなくてもよいので、社会とリンクすることで生じるリスクも少ない。人並みの知力があれば、Z会かなんかで独習して大学に入り、そのまま法科大学院に行ったりして、するするっと法曹界に進むなんてことも不可能ではないでしょう。実際に弁護士になった人がいるのですから。
この小説が全ての役割を果たすわけではありませんが、少なくとも、「事件」の後で語られる評論家や心理学者などの紋切り型の発言を聞くよりも、よほど有益であると思います。


























更正の道があるからその芽をつむいではならないそういう事でしょうか?私は疑問に想う昔は、叱る大人や先生がいました。今はいませんよね教育委員会に訴えると子供に脅され家では過保護これが問題ではないでしょうか
私も人の親として、自分の子が被害者になったときのことを想像すると、とても冷静ではいれなくなります。ただ、逆に加害者になってしまうことがないとも言い切れません。そうなったら死んでお詫びすれば、遺族や一般の市民感情をある程度鎮めることができるのでしょうが、
我が子がその先、ことごとく行く手を塞がれてしまうのもやりきれない思いがあります。
「更生」とは何か? というのは、とても難しい問題です。
このくら~い世界観でも大好きな貫井ワールドバシバシでした
少年犯罪を被害者側から書くか、加害者側から書くか、家族側から書くかの視点の違いで随分印象も違うかもしれませんが結局誰もがやりきれないのでしょうね お子様がいらっしゃるということなので被害者になった時の心理はもちろん、失礼ながら加害者の親という立場でも見れたりするのでしょうか
被害者の親になっても加害者の親になってもいわれのない同情と非難に同時さらされることはあるんでしょうね
どうにかして自分を納得させるためにすべての結末に何か「これだ!」と断言できる理由を探して空回りしそうです
大人の犯罪と子供の犯罪を分けてしまうのは社会的な救済と更生のシステムの違い上で必要性を認めますが、今現在大人が起こしてる犯罪も精神レベル、行動原理が子供レベルだったりするからしょうがないですよね 他人の行動を批判することにいかなる基準でも役に立たない気がします それが精神鑑定であったり、法律であったりしても
そして例えば作中にあった様に葛城がこの後弁護士などになったとしたら何かやりきれない、批判したくなるような気持ちをつい持ってしまうこと自体本当に「いわれのない」ものなのでしょうね
それにしてもいつもながら素晴らしい記事ですよね
知識の量を支える記憶力の素晴らしさと洞察の深さに拍手です
私は卒論が少年法だったせいなのか、マルセルさんのラジカルなご意見には賛同しかねますが・・・。謝罪云々は当事者同士のこととして、彼がどういう人生を送ったか、心情を含めてその軌跡は聞いてみたい気がします。貴重なケーススタディーですから。死後に仮名で出版してもらうのも難しいかな。
>ひろさん、どうもです。
たしかにこの小説の主人公たちは、「怒られる」ことがないんですね。それぞれ事情は違いますが。肝腎なのは幼少期でしょうね。
>羽月さん、ありがとうございます。
「今現在大人が起こしてる犯罪も精神レベル、行動原理が子供レベルだったりするからしょうがないですよね」→たしかにそうですね。
そういう意味では、法が無意味に思えるほどに、チャイルディッシュな大人と大人顔負けの子どもを峻別する境界線が曖昧になってきているということでしょうか。