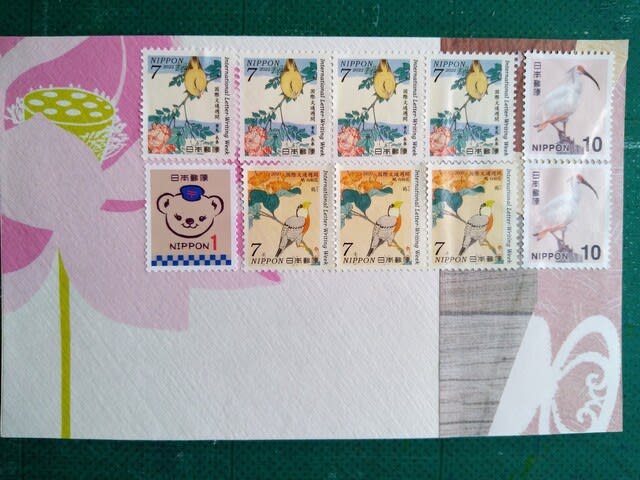今回もサブ農産物の本摘粒。
そしてこの作業のお手伝いは今回で最終です。
次回は7月の予定(仮)です。
さて前日と同じ作業なので簡単…と言いたいところですが、この日は違う品種なので少し違いました。
↓本摘粒前。

↓本摘粒後

えーと、何が違うかと言えば、今回の品種は30粒前後残すのです。
ところが前日まで25~30粒(できれば25粒に近い方がいい)だったのを、今回は30粒前後となると途端にできないンです。
これも25粒ほどにまで摘粒してしまって、ガックリです。
30粒前後の許容範囲は28~32粒という感じで、なるべく30粒にします。
兄が言うには「だいたいの目安で35粒くらいまで摘まんだら、残り5粒をバランスを見て数を揃えるといいよ」。
ウンウン、そうやってみているんだけれどさ、目安35粒のつもりが数えると、もう28粒くらいで、そこから見落としていた変形果を摘まむと25粒くらいなのよね…。
ってか、なんでこの品種は変形果が多いのよっ!
もうそれを延々とやり続けていて、やっと慣れて来た頃には作業時間終了。
来年まで二度とやらない作業なので、なにも習得できないままに終わってしまった、という焦りで精神的にジリジリと焼けただれた気持ちになりました。
今回の品種は、昭和の中頃に静岡県の個人が作出した品種です。
今は緑色の実ですが、これからグラデーションがある濃紫色に色づいていきます。
川崎市や横浜市でもほかの生産者はいらっしゃるものの、絶対数が少ないため身バレ防止のために品種名は明記しませんのであしからず。
なお有名品種なので、スーパーマーケットの広告などで一度は見聞きしたことがある品種だと思います。
私が作業を手伝っているサブ農産物の生産は、メイン農産物の作業の狭間に合致して作業ができる作物として、近隣の果樹園では「果樹栽培の両輪」と言われていた時代がありました。
それは当地では、1964年の大渇水でメイン農産物をうまく生産ができずに離農する方が増えたので、行政が2種類の果樹を組み合わせて、果樹生産の安定化を勧めたから。
私の実家の果樹園は、まだ果樹を主体とした営農ではなく、蔬菜、植木、稲作、麦作、果樹などで、直売所ではなく市場出荷主体の頃。
何度かの危機を乗り越えて現在は果樹を主体にメイン農産物(昭和30頃から)、サブ農産物1号(今回手伝っている品目、昭和45年頃から)、サブ農産物2号(平成10年頃前から)の3本柱で生産しています。
他にもサブ農産物はたくさんありますが、少量多品目にしていまして、多少天候不順であろうとも、どこかで挽回できるようにしています。
40年近く前、キウイフルーツも3年くらい生産していました。私は「こんなに美味しいキウイが毎年食べられるだなんてラッキー!」と思っていました。
ところが父は生産性、収益性、他の農作業との兼ね合いから短期間で生産を止めて、ほかの作物に切り替えてしまいました。
理由は「儲からないから」だそうで、父の言葉は「二度と作らない」と同義語ですから、当時の私はガッカリしました。
母に至っては「うちでキウイなんて作っていたことあったっけ?」とすっかり忘却の彼方です。
また実家の農園は丘陵地なので、丘の上と下の農地では、同じ品種でも育ち方が違っています。
台風、渇水、降雹などの時、丘の上と下の農地では被害もかなり違っているそうです。
先日の台風2号の大雨も丘の下の果樹園では、排水量がムチャクチャ多くて、道路の側溝に流出する雨水がなかなか減らなかったとか。
丘の下の果樹園は、丘の上から土中に染み込んだ雨水を溝切りという部分を通って道路の側溝に排出する仕組みになっています。
この溝切りをしていないと土中の水分量が多くなりすぎて、果樹が病気になりやすかったり、最悪の場合は土砂崩れの原因になります。
当地はまだ梅雨入りしていないのですが、梅雨入り前からこの調子では、排水対策にも兄や両親は頭を抱えるかもしれません。
今後の作業では、防除と袋かけ、防鳥網のセッティング、移動支柱の追加でしょうか。
そして梅雨明け前からの新梢(しんしょう)の夏期誘引。
今年の春に伸びた勢いのある枝を棚に沿って理想型に仕上げ、来春花芽をつけます。
ゆえに来年の収穫に向けた作業を前年7月(収穫の1年以上前)に行います。
このあたりは私も多少の実習しかしたことがないので、手伝いらしい手伝いができません。
ま、人手が欲しければまたお手伝いを頼まれるかもしれません。
今回も楽しくお手伝いできました。
次回はいつかわかりませんが、楽しくお手伝いしたいです。