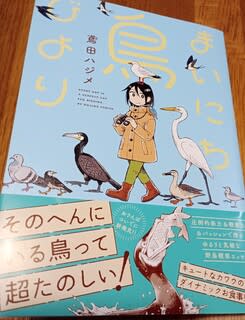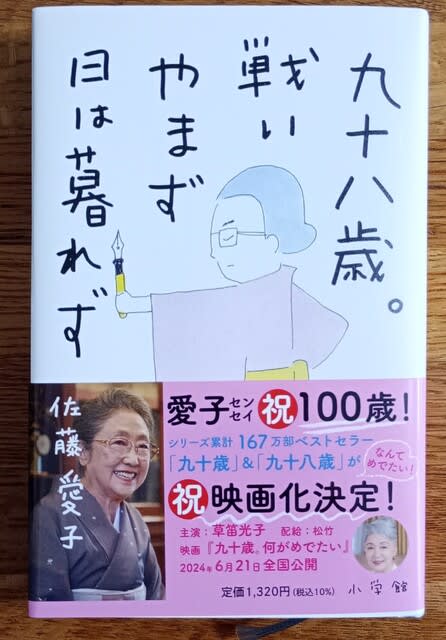本郷和人著。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を楽しむにあたって再読しました。
ざっくりといえば、大河ドラマの時代とほぼ丸かぶりなので登場人物も丸かぶりと言えます。
ただちょいと違うのは、大河ドラマでは登場人物の血縁関係がイマイチ詳細まで描かれていない部分でしょう。
例えば今のところドラマで「朝廷に仕える下級貴族で頼朝に朝廷の動きを知らせている三善康信」としか紹介されていない三善康信。
関係性は、頼朝の4人の乳母のうち長らく支えていた比企尼の妹婿であり、自身の叔母も4人の乳母の1人。
当時の乳母は、現代的に言えば後援会会長。4人の乳母がいるのでそれぞれの支部会長たちという感じです。乳母は女性なので、現代から見ても当時の女性の地位の高さが分かる訳です。
この本は本郷先生が書かれていて、五味文彦先生の考え方も示されています。
さて、五味文彦先生。
私が好きな写実絵画の画家さんと同名ですが、別人です。
私が歴史研究者の五味文彦先生のお名前を知ったのは、大学1年の時。「鎌倉幕府の成立年」についての授業の時でした。
1192(いいくに)つくろう鎌倉幕府…これを信じて受験勉強をしてきた年代の私にとって衝撃的でしたねぇ、この授業は。
結果、最も遅い説で1192年に成立したけれどどの段階で成立していたかは諸説ある、そもそも幕府という言葉は明治政府が命名したから当時は幕府とは言わない等、自分が歴史学を学ぶ学生として何の準備もできていなかった、と思い知らされた授業でした。
結局、私は卒業しても歴史ファンにしかなれなかったとつくづく手痛い一撃の授業を思い出します。
私は武士が台頭してきた時代から鎌倉幕府はあまり興味を持って来ませんでした。
一番の理由は、史料が限られていて、まず「吾妻鏡」、あとは公家や僧侶の日記、そのさらに補完で軍記物や絵詞(絵と短い文章の巻物)くらいしか調べる方法がなく、絶対的に誰かの主観が色濃い史料しか無いという印象だったからです。
先日、私が実際に見てきた小田原市の石橋山古戦場は、ここで頼朝軍300騎と大庭景親軍3000騎が衝突したとは思えないのです。
10分の1スケールの30騎対300騎だったとしても、騎馬ではなく歩兵戦中心じゃあないと、あんな急峻な斜面で戦闘できるかな?と思いました。
それに騎馬の場合、馬1頭に人間2~3人くらいは必要なので、1騎=1人にはならないのです。
その点、本郷先生も軍記物は人数を盛るのが当たり前として、いろいろな試算を載せて算出根拠も書いています。
そして本郷先生も「仁義なき戦い」と表現していますが、頼朝が理想とした武家政権は私が思っていたよりももっと武装集団の団結システムは暴力的だったのかも、と気がつきました。
現代の感覚で読み解こうとするから理解が難しいのであって、当時の風習習慣を知ることで読み解ける幅が広がる思いがしました。
組長の頼朝のが理想とした武家政権を、北条義時が若頭として組み立て、政子の姉御が引き締めて行く、と言う感じかしら?
北条氏が執権政治を行うことは、ちょいと源氏乗っ取りのようにも感じていました。
しかし武家政権という新社会システム創業者のアイデアを、優秀な番頭さんが引き継いだおかげで安定した武家政権というシステムを維持できたとも言えるのだと考えが改まりました。
もし私がこの本を中学3年か高校1年くらいで読んでいたら、歴史に惹かれたとしてももっと違う時代に興味を持ったのかな?とも思えます。
ま、そんなifを考えたら、きりがありませんが。
承久の乱は、天皇に弓を引いた武士階級が唯一勝利した戦争です。
ここから時代の風向きが変わり、明治維新までの650年の武家政権が続いたことを思うと、歴史のターニングポイントなんだと感慨深く思いました。