
月1回の講座なので続いています。来期も引き続き参加予定、
私の体力も半年先くらいまでは大丈夫のはずです。
今回のテーマは「縄文時代の知多半島」。
いままで古代にはあまり関心なく
私の好きなのは江戸時代~明治維新なのですが
知らないことを知るのはなかなか楽しいものと思いました。
知多半島↓
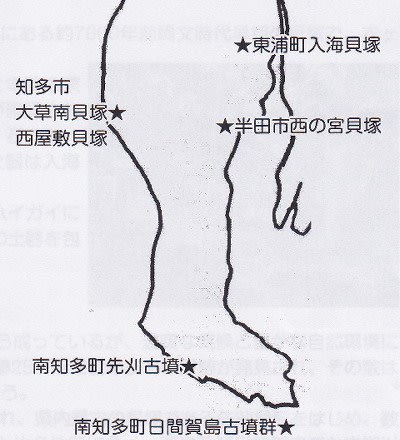
縄文時代は私には「大昔」です。
その次は弥生時代くらいの知識しかありません。
人がいきていくためには「食糧、水、塩」が必要です。
知多は半島ですからこの3つの条件は満たしているわけです。
先生のお話で驚いたことの一つに、「古代は争いがなかった」と。
古代人の暮らしもさることながら、古代に
なぜ争いがなかったかに関心を持ちました。
中世、近世、そして現代と争いなくして歴史は語れないほど
戦争連続の時代ですのに、古代には争いがなかったとは?
海から必要なだけ貝を採って食べ、川の水を汲む。
海の資源は豊かだったのでしょう。古代人は欲望がなかった?
何故争いごとがなかった?
専門的でなく易しい解説があれば、検索してみたいと思います

「明滅の海のきらめきしろき夢 知多の岬を船はめぐりて」
宮沢賢治・知多を旅して(大正5年)














