『初夜権』
「ふうむ…」
王国の領地を預かる領主の一人、その時の人ロアン=ブリティッシュは悩んでいた。
毎日、見ず知らずの女と一晩を供にしなければならない生活に、嫌気がさしていたのだ。それもただの女ではない。夜伽を強制されるのは、およそ世の穢(けが)れを知らない処女ばかりだ。
「教会の僧侶どもは、今日も知らない女を私に抱かせるのか」
静かな夜の寝室に一人、一杯の紅茶を片手に深いため息を漏らすロアン。
現代から遡る事、およそ数百年。時にして15世紀半ば、王から土地を預けられた領主には、政務以外に一つ任された、裏の仕事があった。領内の由緒正しき家柄を持つ男女が結婚する時、そこに立ち会うことである。だが、ただ結婚式に立ち会うだけではない。両人が結婚する前夜に、花嫁の処女を領主自ら奪わねばならない、という掟があったのだ。
当時の社会の風習は、科学が発達した今と比べれば、異常なほど迷信に縁深かった。
その迷信の中の一つに、『処女は結婚する男にとって、後々に災いをもたらす』と言われて忌み嫌われ、それ故に『聖職者』と呼ばれる僧侶や領主が『初夜権』と称して、その処女を奪う事を当然としていた。
もちろん、これには裏がある。
後の歴史書などでは、暗黒時代と呼ばれるほど社会風紀の乱れた中世ヨーロッパ世界において、聖職者は教会という強大な権力の加護の元に座していた。だがその実態は、聖職者とは名ばかりの色欲に堕落し、物欲に腐敗していた。しかし、『みだりに姦淫してはならぬ』という一応の戒律があるため、その公の行動は一定制限されているのが実情だった。
が、一概に欲深な聖職者というのは意地汚いものである。
自らの色欲を満足させるために、処女への姦淫を悪の象徴とし、それを聖職者が奪うことによって、娘の身を清めるという『迷信』を広めたのだ。無償で生娘たちの処女を嗜める事の出来る『初夜権』は、教会権力に守護される僧侶達にとって、非常に都合の良い理屈であった。
要するに、『初夜権』というのは、聖職者とは名ばかりの性欲旺盛な僧侶や領主達など支配者階層の『娯楽』だったのだ。
もちろん、自分の花嫁の処女を奪わせまいと迷信を嫌う者も少なからず居た。
だから、この『初夜権』を欲しいという花婿が居れば、僧侶や領主が花嫁に値をつけて、それに相当する金品を献上する事で解決するという時もあった。判りやすく言い換えれば、『初夜権』は支配階級が設けた臨時の税収。結婚税であったのだ。
だが、当時の市民は、貧困にあえぐ者も多く、裕福な市民以外は皆、花嫁の処女を泣く泣く諦めるのが実情であった。内心、誰もが迷信など信じていなかった。ただ腐敗を続ける宗教家達に、結婚という身近な物でさえ支配される。領主、僧侶達の公然の横暴は、市民の怨嗟の声の中、当然として繰り返されていたのだ。
そんな世間の風潮の中。
市民を愛し、国を愛し、領主の中でも賢明と呼ばれたロアンは、どうにか僧侶達の権力を捻じ伏せられないかと画策した。だが、当時の絶対権力であった信仰教会を傘に着る僧侶達の抵抗は凄まじく、たかだか一地方の領主が、とやかく口を出せるような事ではなかった。
「どうにかできないものか…」
熱心な愛妻家でもあったロアンは、自ら妻が居る立場でありながら、毎日教会の僧侶達に命ぜられて、代わる代わる見ず知らずの処女を抱かされる事に多大な罪悪感を覚えていた。
キィー…
そんな葛藤の日々を送っていたロアンに、軋む悪魔の音色。
開門すれば、人四人がゆうに潜り抜けられる幅広さを持つ木製の扉が、まるで老婆の招き手のようにゆっくりと開き、同時に生ぬるい風が室内を通り抜ける。
「…ほっほ、ロアン様。今夜の花嫁の準備が整いましたぞ。それでは、ご政務のほう頑張りくだされ」
苦悩する領主ロアンの部屋の戸から、老いを感じさせるしゃがれた声が聞こえる。
その声の先には、薄らと灯火の灯ったカンテラを持ちながら、風の通り抜ける扉を通り抜け、下卑た高笑いを浮かべてロアンをジッと見る、骨と皮で出来たシワシワの老僧侶。
その薄汚い聖職者の皮一枚剥げば、路頭を歩く性欲の獣と同じだ。と、ロアンは激しい苛立ちを老僧侶への視線に含ませ、キッと睨みつける。
だが、老僧侶は「ヒッヒッ」と欲望に満ちた口で笑うだけで、何も語らず、そそくさと会釈をして扉の影へと消えてゆく。敬虔(けいけん)な聖職者と呼ばれ、太陽の昇る日中は市民から高僧と慕われるこの老僧侶もまた、今は人間的な欲望に支配されていた。
きっと、今日も手頃な『生娘』を見つけたのだろう。
「ふうむ…」
王国の領地を預かる領主の一人、その時の人ロアン=ブリティッシュは悩んでいた。
毎日、見ず知らずの女と一晩を供にしなければならない生活に、嫌気がさしていたのだ。それもただの女ではない。夜伽を強制されるのは、およそ世の穢(けが)れを知らない処女ばかりだ。
「教会の僧侶どもは、今日も知らない女を私に抱かせるのか」
静かな夜の寝室に一人、一杯の紅茶を片手に深いため息を漏らすロアン。
現代から遡る事、およそ数百年。時にして15世紀半ば、王から土地を預けられた領主には、政務以外に一つ任された、裏の仕事があった。領内の由緒正しき家柄を持つ男女が結婚する時、そこに立ち会うことである。だが、ただ結婚式に立ち会うだけではない。両人が結婚する前夜に、花嫁の処女を領主自ら奪わねばならない、という掟があったのだ。
当時の社会の風習は、科学が発達した今と比べれば、異常なほど迷信に縁深かった。
その迷信の中の一つに、『処女は結婚する男にとって、後々に災いをもたらす』と言われて忌み嫌われ、それ故に『聖職者』と呼ばれる僧侶や領主が『初夜権』と称して、その処女を奪う事を当然としていた。
もちろん、これには裏がある。
後の歴史書などでは、暗黒時代と呼ばれるほど社会風紀の乱れた中世ヨーロッパ世界において、聖職者は教会という強大な権力の加護の元に座していた。だがその実態は、聖職者とは名ばかりの色欲に堕落し、物欲に腐敗していた。しかし、『みだりに姦淫してはならぬ』という一応の戒律があるため、その公の行動は一定制限されているのが実情だった。
が、一概に欲深な聖職者というのは意地汚いものである。
自らの色欲を満足させるために、処女への姦淫を悪の象徴とし、それを聖職者が奪うことによって、娘の身を清めるという『迷信』を広めたのだ。無償で生娘たちの処女を嗜める事の出来る『初夜権』は、教会権力に守護される僧侶達にとって、非常に都合の良い理屈であった。
要するに、『初夜権』というのは、聖職者とは名ばかりの性欲旺盛な僧侶や領主達など支配者階層の『娯楽』だったのだ。
もちろん、自分の花嫁の処女を奪わせまいと迷信を嫌う者も少なからず居た。
だから、この『初夜権』を欲しいという花婿が居れば、僧侶や領主が花嫁に値をつけて、それに相当する金品を献上する事で解決するという時もあった。判りやすく言い換えれば、『初夜権』は支配階級が設けた臨時の税収。結婚税であったのだ。
だが、当時の市民は、貧困にあえぐ者も多く、裕福な市民以外は皆、花嫁の処女を泣く泣く諦めるのが実情であった。内心、誰もが迷信など信じていなかった。ただ腐敗を続ける宗教家達に、結婚という身近な物でさえ支配される。領主、僧侶達の公然の横暴は、市民の怨嗟の声の中、当然として繰り返されていたのだ。
そんな世間の風潮の中。
市民を愛し、国を愛し、領主の中でも賢明と呼ばれたロアンは、どうにか僧侶達の権力を捻じ伏せられないかと画策した。だが、当時の絶対権力であった信仰教会を傘に着る僧侶達の抵抗は凄まじく、たかだか一地方の領主が、とやかく口を出せるような事ではなかった。
「どうにかできないものか…」
熱心な愛妻家でもあったロアンは、自ら妻が居る立場でありながら、毎日教会の僧侶達に命ぜられて、代わる代わる見ず知らずの処女を抱かされる事に多大な罪悪感を覚えていた。
キィー…
そんな葛藤の日々を送っていたロアンに、軋む悪魔の音色。
開門すれば、人四人がゆうに潜り抜けられる幅広さを持つ木製の扉が、まるで老婆の招き手のようにゆっくりと開き、同時に生ぬるい風が室内を通り抜ける。
「…ほっほ、ロアン様。今夜の花嫁の準備が整いましたぞ。それでは、ご政務のほう頑張りくだされ」
苦悩する領主ロアンの部屋の戸から、老いを感じさせるしゃがれた声が聞こえる。
その声の先には、薄らと灯火の灯ったカンテラを持ちながら、風の通り抜ける扉を通り抜け、下卑た高笑いを浮かべてロアンをジッと見る、骨と皮で出来たシワシワの老僧侶。
その薄汚い聖職者の皮一枚剥げば、路頭を歩く性欲の獣と同じだ。と、ロアンは激しい苛立ちを老僧侶への視線に含ませ、キッと睨みつける。
だが、老僧侶は「ヒッヒッ」と欲望に満ちた口で笑うだけで、何も語らず、そそくさと会釈をして扉の影へと消えてゆく。敬虔(けいけん)な聖職者と呼ばれ、太陽の昇る日中は市民から高僧と慕われるこの老僧侶もまた、今は人間的な欲望に支配されていた。
きっと、今日も手頃な『生娘』を見つけたのだろう。











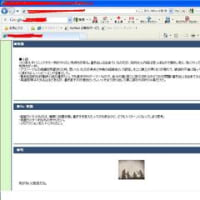







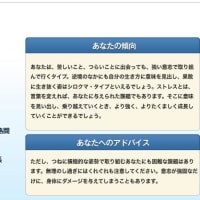

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます