


祖父と二人暮しをしているレントン。彼は、決められた将来や、何も起こる気配のない単調な毎日にうんざりしていた。
そんなある日のこと。レントンに転機が訪れる。彼の家に、幻のLFO、ニルヴァーシュが落ちてきたのだ。
コクピットから現れたのは、エウレカという美少女。メカニック業を営む彼の家に、ニルヴァーシュの整備を頼みに来たというのだ。
ところが、エウレカを追って、塔州連邦空軍のKLF部隊が現れる。
レントンはエウレカを救うため、祖父サーストンから預かったアミタドライヴを手に、外へ飛び出していく。
そこへ、レントン憧れのゲッコーステイトも現れる。【公式あらすじ】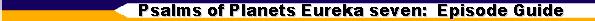
珊瑚の大地が広がるこの星は、穏やかな、浅い眠りについていた。
何百万、何千万という夥しい数の小さな生き物が表面にうごめき、この星のそこかしこで自らの権利を必死に主張していたが、星は意に介さず、ときおり寝返りを打っては、この小さな生き物たちの夢を見続けていた。
一方では常に太陽の暖かな光を浴び、もう一方では常に夜の宇宙のひんやりとした冷気を感じ、この星は依然として夢を見続けていた。
真空の海のただなかで、自分が一人ぼっちなことに気づいた珊瑚礁は、自分の背中にいる生き物たちと友達になれればいいのにと、同じ夢を何千年も、繰り返して見続けていた。
夕焼けに包まれた空。眠る星の息遣いの中に、人間が生み出した電波が紛れ、無数に飛び交っていた。
人々の欲望は、この星にとって何ら関係がなく、人々もまた、この星の気持ちなどは理解していなかった。


「・・・なあ、聞いてるか?」ストナーは、前方の操縦席に座っているマシューに向かって言った。
「何がだよ・・・」効果的なポイントを探して視線をスクリーンのあちこちに移していたマシューは、いい加減うんざりしていた。が、反射的に答えてしまったことにすぐ後悔した。
相変わらず後部座席の男は訳の分からないことを言っては、彼を煙に巻いていた。答えたことで、彼──カメラマンのストナーは、またさらに訳の分からないことを言い出すだろう。
しかし、マシューが無視したところで、ストナーは構わず訳の分からないことを延々としゃべり続けることには違いなかった。マシューは苛立ちを感じた。
操縦桿を引き、自分と相棒のストナーが搭乗する、前後式複座LFO「ターミナスtypeR606」の高度をさらに上げた。惑星の大気に含まれるトラパー粒子が606のボードに干渉・反発して、緑色に輝く光の尾が606の航跡にそってたなびいた。マシューの苛立ちを気にもせず、ストナーは話を続けた。
「──音楽とか映画とかって、『その中身が』っていうよりも、『そのときの記憶』っていうかさ、『そのときの人と人との関係』を思い出すことが多いだろう?」
「あのさ、黙っててくんね? 集中できねえから」マシューはピシャリと言い放ち、ストナーの言葉を遮った。
「何だよ、これからいいこと言おうと思ってたのに・・・」
優秀なLFOライダーにして、DJでもあるマシューにとって、音楽はそのときの身体が求めるものを表現する手段であり、材料だ。膨大な数のバイナルを取り揃え、選曲し、必要に応じてミックスやイコライジングを施し、スムーズにつなげることでテンションを維持する。重要なのはライブ感であり、カメラマンのストナーのように、強制的に固定された一瞬に対する哲学は持ち合わせていなかった。
「お前も仕事に集中しろよ」そう言い捨て、マシューはインパネのソケットに取り付けてあるコンパクドライブに目をやり、異常がないことを確かめた。高度は十分なはずだ。ストナーが効果的な「絵」を撮れるよう、太陽の位置も計算済みだ。コックピットのスクリーンから見える、眼下の景色に向かって叫んだ。「・・・なあ、リーダー! まだ上がれないのかよ?」


「うっせえなあ! もうすぐだ!」すぐさまスピーカーからリーダーの声が返ってきた。マシューに劣らず、リーダーのホランドも苛立っているらしい。「目の前に大きな『波』が来ている。エンゲージまであと25秒!」
「ほぉ・・・やってる、やってる」マシューは眼下の雲の切れ間に爆発の火球が次々と開くのを確認すると、振り返ってストナーに声をかけた。「ストナー、そろそろだぞ」
ストナーは愛用のマニュアルフォーカス一眼レフに、36枚撮りの高感度フィルムがセットされているのを確認するとケースを閉め、巻き上げレバーをリズミカルに操作しながら、先ほどの話を再開した。
「そーう・・・つまり『記憶というものは、決してそれ単体で存在せず、それを取り巻く環境に支配されている』というわけだ・・・誰の言葉か知ってるか? マシュー」シートから身を乗り出して、キャノピー越しにカメラを構えるストナー。レンズの距離リングを調整し、眼下で暴れる光の先端にフォーカスを合わせる。
「知らねえよ」マシューがうんざりして答える。
「まったく、学がねえなあ・・・」
606のカメラセンサーが捉え、解析された光景がキャノピー内側のスクリーンに投影される。それはさらに一眼レフのレンズを通し、リフレックスミラーで反射され、ファインダースクリーンに二次投影される。そしてさらにストナーの眼の水晶体を通して、最終的に彼の網膜に焼きつく一瞬の絵が、彼の哲学そのものとなるのだ。戦場カメラマンであるストナーは、その一瞬を捉えるためならば、命の危険すら顧みない。
「・・・『俺』の言葉だよ」学のないマシューに、ストナーはそう言って聞かせた。


敵小隊と交戦中のホランド機、「ターミナスtypeR909」の機体の紫色が、ファインダーの中で急激にふくらみ、あっという間にフレームの外に抜けた。マシューとストナーの606の脇を通過し、そのままさらに上空へ突き進んでいく。それを追って、青い機体の敵機が3体、間をおかずに突っ切っていった。
すれ違いざまに起こった衝撃波に、606のコックピットが激しく振動する。「んんんっ・・・来たーっ!!」
踏ん張り、マシューは909と敵小隊をスクリーン上に捉え続けるよう、機体を反転させた。
「・・・いいもん拝ませてもらうぜ!」
3機の敵機に後ろを取られている909を前に、マシューの606は加勢をしようとしない。今の彼の役目は、ホランドの909が敵機を撃墜する瞬間をストナーが撮影できるように、効果的なポジションをキープし続けることだ。マシューやストナーはホランドが撃墜されるなどとは微塵も思っていない。
606のスクリーン上に、水色で表示されている「MS-10」の識別コードが3つと、オレンジ色の「909」の表示が狂ったように踊っていた。
3機のMS-10──ホランドが交戦しているKLF、すなわち軍用大型LFO「モンスーノtype10」は、両手に抱えているレーザー銃を乱射しはじめた。
ホランドの909は巧みにターンを重ね、連続してこれらの攻撃を回避した。銃が通用しないと知ると、敵モンスーノ小隊は、909に向け一斉に誘導ミサイルを発射した。


ホランドは909をトラパーの大波に乗せて大きく弧を描いて上昇させると、大胆にも反転してミサイルの群れに向けて909を巧みに操り、ミサイルが接触する寸前に激しくボードを切り返しては誤爆させ、一発も被弾することなく、この攻撃もかわしきった。
「うへえ・・・ノリノリじゃねえの」ホランドのテクニックに、マシューが軽口をたたいた。
「浮かれすぎるとLFOの電池が切れちまうぜ、ホランド」ストナーもそれにあわせた。
「・・・あぁ? うるせぇな、お前ら!」再び909にトラパーの波を駆け上がらせて、3機のモンスーノを引き連れて上昇するホランド。後ろを振り返って、モンスーノが思惑通りに追従してきて、有利な位置を取ろうとして揃って旋回行動に入ったことを確認すると、叫んで909をいきなり宙返りさせた。「それくらい・・・分かってんだよッ!」


ただの宙返りではない。直前に小刻みにジグザグ移動をすることでトラパーの波を力場としてボードにかき集め、それをバネにして爆発したような瞬発速度と、コックピットに襲ってくるGにも構わず、ホランドがかけた鋭いターンの回転半径の小ささも相まって、後ろから追っていたモンスーノのライダーにしてみれば、目の前を逃げていた敵機が一瞬にして自分に向かって反撃してきたという、信じられない悪夢のような光景として映ったことだろう。
すれ違いざまに、ホランドは909の前腕部に仕込まれていた接近兵器であるブーメランナイフで、モンスーノの1機を胴体から切断した。
爆発するモンスーノ。両脇の2機は分かれて回避行動をとり、そのままこの戦闘空域から離脱していった。
「さすがだなぁ・・・」その様子を見つめながら感嘆するマシュー。生身でボードにのるときですら、ホランドの見せたターンは離れ業だ。彼はそれを、人型大型ロボットのLFOでそれを戦闘中にやってのけた。
「『カットバック・ドロップターン』・・・か」最高の成果を収めることができ、ストナーも満足げにつぶやいた。
戦闘が終わり、606と909は、並行飛行に入り、本来の目的地へと向かうことにした。
「こちらマシュー、606。敵機の撤退を確認!」無線に向かって報告するマシュー。
「こちら『月光号』、了解」スピーカーから、女性の声が返ってくる。


「・・・『ニルヴァーシュ』は予定通り、ポイント『イ-62』を通過。作戦続行中!」
「606、了解!」マシューが応答する。909のホランドは応答しない。
「909! ・・・ホランド! 返事は?」無線からは女性の催促する声が流れてきた。
催促とは関係なく、心底嫌そうに、ホランドがつぶやいた。「行きたくねえ」
606と909の母艦である最新鋭飛行戦艦「月光号」の操舵手、タルホ・ユーキは、呆れて物が言えなくなるというよりは、呆れて大声を張り上げる性格の持ち主だった。魅力的な美人で完璧なプロモーションを誇る彼女の、唯一と思える欠点が、その性格だった。
「はぁー!? 何いってんのよ! ・・・アンタが突然、『ベルフォレストに行く』っていうから、みんなついてきてんじゃない!」
909のコンソールディスプレイには、月光号の操舵席に座っているタルホの姿が映っていたが、ホランドは、ポケットから写真を取り出して、それに目を落としていた。老人と、少年と、女性の、3人が映っている写真。左側に立っている女性の顔だけが、マジックで黒く塗りつぶされている。
タルホの声が耐えられないレベルにまで甲高くなってきたので、ホランドは答えた。「へえへえ、行きますよ、行きますともっ! ・・・まったく・・・」
写真からコックピットの前方に広がる景色に視線を移して、ホランドはつぶやいた。
「・・・なんて月曜日だ・・・」
行く手には、沈む夕日に赤々と照らし出される、ベルフォレストの塔がそびえたっていた。


→(2)に続きます
最新の画像[もっと見る]
-
 第1話「ブルー・マンデー」Blue Monday (1)
18年前
第1話「ブルー・マンデー」Blue Monday (1)
18年前
-
 第1話「ブルー・マンデー」Blue Monday (1)
18年前
第1話「ブルー・マンデー」Blue Monday (1)
18年前
-
 第1話「ブルー・マンデー」Blue Monday (1)
18年前
第1話「ブルー・マンデー」Blue Monday (1)
18年前
-
 小説版のカテゴリを追加しました
18年前
小説版のカテゴリを追加しました
18年前
-
 小説版のカテゴリを追加しました
18年前
小説版のカテゴリを追加しました
18年前
-
 第3期OP(初期)
18年前
第3期OP(初期)
18年前
-
 第3期OP(初期)
18年前
第3期OP(初期)
18年前
-
 北米版「Eureka seveN」今夜放送!
18年前
北米版「Eureka seveN」今夜放送!
18年前
-
 第49話「シャウト・トゥ・ザ・トップ!」Shout To The Top! 後編
18年前
第49話「シャウト・トゥ・ザ・トップ!」Shout To The Top! 後編
18年前
-
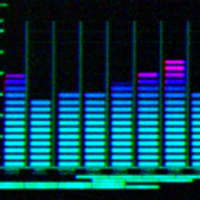 第49話「シャウト・トゥ・ザ・トップ!」Shout To The Top! 後編
18年前
第49話「シャウト・トゥ・ザ・トップ!」Shout To The Top! 後編
18年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます