事業仕分けの詳細を見ようと内閣府のHPを見ていて、偶然見つけた赤坂迎賓館参観に応募し当選したので、出かけました。
迎賓館赤坂離宮は年に一度事前に申込み、当選すると参観証が送られてきて見学する事が出来ます。構造補強等大規模修理が終わり昨年から参観が再開されたそうで、綺麗になった迎賓館を見学する事ができました。
地下鉄丸の内線四ッ谷駅で下車、
 ここは地下鉄なのに、ホームは地上です。
ここは地下鉄なのに、ホームは地上です。 徒歩5~6分で正門が見えて来ました。
徒歩5~6分で正門が見えて来ました。 


白い綺麗な門扉から奥を覗くとかなり広いです、もちろん見学者が入るのは正門ではなく脇の西門からです。
 西門の前は学習院初等科の正門でした。
西門の前は学習院初等科の正門でした。セキュリティーチェックを受けて入館


かつて紀州徳川家の江戸中屋敷があった広大な敷地の一部に1909(M42)年に東宮御所(後に赤坂離宮)として建設され、戦後外国の賓客を迎えることが多くなったので改修し1974(S49)年迎賓館として開館された、日本で唯一のネオバロック様式の洋風宮殿建築。
内部は撮影禁止なのでHPから借用して掲載します。

 羽衣の間
羽衣の間謡曲の「羽衣」の景趣を描いた300平米の曲面画法による大絵画が天井に描かれていることに由来。
3基のシャンデリアは迎賓館で最も豪華なもので、およそ7,000個もの部品で組み立てられており高さは約3メートル重さは約800キログラム、壁は楽器・楽譜等をあしらった石膏の浮彫りで飾られ、また正面の中2階はオーケストラ・ボックスとなっており、この部屋が舞踏会場として設計されたことが偲ばれます。 雨天の際に歓迎行事を行ったりレセプションや会議場等として使用されており、また晩餐会の招待客に食前酒や食後酒を供するところでもあります。

 花鳥の間
花鳥の間天井に描かれた36枚の油絵や欄間に張られた錦綴織、壁面に飾られた30枚の楕円形の七宝などに花や鳥が描かれていることに由来。
周囲の腰壁は茶褐色のシオジ材で板張りしてあり、その壁の中段を飾るのが七宝で、下絵は日本画家の渡辺省亭が描き、明治期の七宝焼の天才・涛川惣助が焼いたものです。 主に国・公賓主催の公式晩餐会が催される大食堂で、最大130名の席が設けられます。

 彩鸞(さいらん)の間
彩鸞(さいらん)の間左右の鏡の上と大理石で造られた暖炉の両脇に'鸞'(らん)と呼ばれる霊鳥をデザインした金色の浮彫りがあることに由来。
白い天井と壁は金箔が施された石膏の浮彫りで装飾され10枚の鏡が部屋を広く見せています。 晩餐会の招待客が国・公賓に謁見したり、条約・協定の調印式や国・公賓とのテレビインタビュー等に使用されています。

 2階大ホール
2階大ホール正面の左右の壁面には2枚の大油絵(小磯良平画伯作 左は'絵画'右は'音楽')が飾られています。
 中央階段
中央階段床にはイタリア産の大理石が張られた上に赤じゅうたんが敷きつめられています。階段の左右の壁にはフランス産の大理石が鏡張りされ欄干はフランス産の大理石でその上に8基の黄金色の大燭台が置かれています。

 朝日の間
朝日の間天井に描かれた「朝日を背にして女神が香車を走らせている姿」の絵に由来。
周囲の16本の円柱はノルウェー産の大理石で、壁には京都西陣の金華山織の美術織物が張られ、床は紫色を基調とした47種類の糸を使い分けて桜花を織り出した緞通が敷かれています。 国・公賓用のサロンとして使われ、ここで表敬訪問や首脳会談等の行事が行われます。
参観できるのは中央階段を入れて6箇所、ここでも室名の由来・使用目的・見所等をボランティアの説明付きです、聞きやすい説明だしよく勉強されていて感心です、ありがとうございました。
室内は宮殿風で見応えがあるけど、リニュアルで塗替えた壁が安っぽく感じたのは私だけでしょうか?
館内見学は50分程で終了、これから庭を見学します。
<続く>
3月27日(土)
都内に用事で出かけたので新宿に寄道し、今月で閉館する東京厚生年金会館(ウェルシティ東京)を覗いて来ました。
タモリの‘笑っていいとも’でお馴染 新宿アルタの脇を通って、
正面に08(H20)年末で閉館した新宿コマ劇場が見えたので寄道、前を何度か通ったけど、一度も入った事はありません。
豆知識:もともと「歌舞伎町」という名前は、歌舞伎演舞場を建設しようという計画があったが歌舞伎演舞場は結局作られず、コマ劇場が中核施設として作られ町名はその名残。
よく目や耳にする、花園神社の文字が目に入ったので、また寄道。
立派な本堂です、お参りをしてふと見上げると雷電神社・花園神社・大鳥神社と三つの額が、神社のマンション?ご利益は三倍かな?
① たまにしか行かなくても、気にいった店が閉店・移転します。
② 見学・見物に行った場所が工事中のことが良くあります。
唐十郎・朝丘雪路・大月みやこ・前田吟・阿藤快・八代亜紀・中条きよし・佐野史郎・藤村俊二・由美かおる・若林豪・コロッケ
目的の東京厚生年金会館(ウェルシティ東京)に到着。
昭和36年4月の開業でホールは客席は2062席
本館はヨドバシカメラヨドが落札博物館・ギャラリー・オフィスの予定、別館は不動産会社が落札マンション建設予定らしいです。
ホールとして一級品らしいけど残念です、約50年ご苦労様でした。因みに最終日は松山千春の公演だそうです。
新宿駅に戻る途中、伊勢丹新宿店が目に入りまたも寄道。
1933(S8)年開店(当時はアイススケート場を併設していたそうです)
2年後に隣接する百貨店ほてい屋を買収し翌年には(新宿三丁目交差点に面した部分)と建物を一体化。
古いデパートは威厳があって、見ていて楽しいです、中も見たいけど、時間が無いので、次の機会に。
今日は12,000歩歩きました。
新聞で 《横浜開港150周年記念企画》今回が初めて!三渓園の 古建築全17棟を一挙に公開 の記事を見つけたので出かけました。
普段は外周か開けられた戸や窓から覗くだけの、建物全部に入って見る事が出来るので楽しみです。

 入場すると直ぐ蓮池、花を愛でたら出発。
入場すると直ぐ蓮池、花を愛でたら出発。
 鶴翔閣《横浜市指定有形文化財》 1,909(M42)年築
鶴翔閣《横浜市指定有形文化財》 1,909(M42)年築
 御門《横浜市指定有形文化財》 1,708年頃築
御門《横浜市指定有形文化財》 1,708年頃築
 白雲邸《横浜市指定有形文化財》 1,920(T9)年築
白雲邸《横浜市指定有形文化財》 1,920(T9)年築
 臨春閣《国指定重要文化財》 1,649年築
臨春閣《国指定重要文化財》 1,649年築
 橋を渡って。
橋を渡って。
 旧天瑞寺寿塔覆堂《国指定重要文化財》 1,591年築
旧天瑞寺寿塔覆堂《国指定重要文化財》 1,591年築
 月華殿《国指定重要文化財》 1,603年築
月華殿《国指定重要文化財》 1,603年築
 金毛窟 1,918(T7)年築の茶室
金毛窟 1,918(T7)年築の茶室
 天授院《国指定重要文化財》 1,651年築
天授院《国指定重要文化財》 1,651年築
 聴秋閣《国指定重要文化財》 1,623年築
聴秋閣《国指定重要文化財》 1,623年築

 春草廬《国指定重要文化財》
春草廬《国指定重要文化財》
 蓮華院 1,917(T6)年築
蓮華院 1,917(T6)年築

 森林浴をしながら三重塔へ
森林浴をしながら三重塔へ
 旧燈明寺三重塔《国指定重要文化財》 1,457年築 関東地方最古の塔
旧燈明寺三重塔《国指定重要文化財》 1,457年築 関東地方最古の塔
 高台から見える高速道路と工場群、数十年前近くに会社の寮があり3年程住んでいました、その頃は直ぐ下が海でした。
高台から見える高速道路と工場群、数十年前近くに会社の寮があり3年程住んでいました、その頃は直ぐ下が海でした。
 林洞庵 1,970(S45)年築
林洞庵 1,970(S45)年築
 横笛庵 明治時代の草庵
横笛庵 明治時代の草庵
 旧東慶寺仏殿《国指定重要文化財》 1,634年築
旧東慶寺仏殿《国指定重要文化財》 1,634年築
 旧矢箆原家住宅《国指定重要文化財》 江戸時代 岐阜白川郷庄屋の家
旧矢箆原家住宅《国指定重要文化財》 江戸時代 岐阜白川郷庄屋の家
 旧燈明寺本堂《国指定重要文化財》 室町時代初期築
旧燈明寺本堂《国指定重要文化財》 室町時代初期築
 スタンプラリーの用紙に17棟押印してきました、中学生以下はプレゼントがもらえます、大人はダメ 残念。
スタンプラリーの用紙に17棟押印してきました、中学生以下はプレゼントがもらえます、大人はダメ 残念。
 最後は池を見ながら一休み。
最後は池を見ながら一休み。
ガイド・建物内での説明を兼て監視・合掌造の家で薪をくべる方と、ここでも多くのボランティアの方を見かけました、ご苦労様です。
今日は14.000歩でした。
6月26日(金) 
5月に森光子さんの舞台「放浪記」が2,000回を突破し話題の、作者林芙美子の住まいだった 新宿区立林芙美子記念館 が命日にちなみ、普段公開されていない建物内部を特別公開するとの事で、申込み抽選に当たったので出かけしました。
 住宅街の一画(当然です)にある記念館に到着。
住宅街の一画(当然です)にある記念館に到着。
ここでもボランテアガイドの解説があります、始まるまで時間があるので、外をウロウロ  姪の林 福江さん(82才だとか)にお会いしました、芙美子と一緒に暮し没後も芙美子のご主人が亡くなるまでここに住み、今は近くにお住まいで毎日顔を見せ来館者やスタッフの方に挨拶されているそうです。
姪の林 福江さん(82才だとか)にお会いしました、芙美子と一緒に暮し没後も芙美子のご主人が亡くなるまでここに住み、今は近くにお住まいで毎日顔を見せ来館者やスタッフの方に挨拶されているそうです。

 寝室
寝室  裏側
裏側
 茶の間
茶の間  書斎
書斎

 小間
小間 
芙美子は家づくりに際し、東西南北風の吹き抜ける家といふのが家に対する最も重要な信念で、客間には金をかけない、茶の間と風呂と厠と台所には十二分に金をかけるといふのが私の考えであると言い、大工と一緒に京都まで行って色々見て来たそうです。




茶室・京都の町屋で自分に快適と思われる部分を取り入れ、収納・台所・風呂・トイレは現代に通じ、竣工した1941(S16)年当時としては斬新的な工夫がされている、が私の感想です。


 門から玄関に至る
門から玄関に至る
あっと言う間の1時間、ボランテアガイドの平片さん小西さんありがとうございました。
1月18日(日)
三菱財閥創業者岩崎家の旧邸宅 煉瓦塀など屋敷全体が国重要文化財
入場したらボランティアガイドの説明案内が始まるとこなので参加。
 撞球(ビリヤード)場外壁は山小屋風(校倉風)造り
撞球(ビリヤード)場外壁は山小屋風(校倉風)造り
1896(明治29)年 設計:J・コンドル 近代日本住宅を代表する西洋木造建築
11月10日(月) 11月8日(土)の続き
芝東照宮から歩いて数分、高速道路の脇に建つ妙定院は改修間もないお寺です。
 熊野堂 国の登録有形文化財 1796(寛政8)年
熊野堂 国の登録有形文化財 1796(寛政8)年
外部は新築ですが、内部の石・木材等使用できる部材は其の儘使用されています
 上土蔵(浄土蔵) 国の登録有形文化財1811(文化8)年
上土蔵(浄土蔵) 国の登録有形文化財1811(文化8)年
 練塀 築地塀と思っていましたが、「練塀」と記されていたので調べたら、土塀のなかに更に瓦を横に並べて入れた土塀を「練塀」というそうです。
練塀 築地塀と思っていましたが、「練塀」と記されていたので調べたら、土塀のなかに更に瓦を横に並べて入れた土塀を「練塀」というそうです。
これから駒場の日本民藝館に回ります。
渋谷で井の頭線(京王電鉄株式会社)に乗換え、駒場東大前駅で下車、井の頭線には始めて乗りました。
 日本民藝館 国の有形文化財 1936(S11)年
日本民藝館 国の有形文化財 1936(S11)年
民芸運動を起こした思想家・美術評論家の柳宗悦らが建てた美術館で柳宗悦、自らの設計。
![]() 目的の特別展 韓国の鍵と錠
目的の特別展 韓国の鍵と錠
正面石屋根の長屋門は栃木県から移築(明治期)、奥は柳宗悦の自宅
これから、駒場公園内の旧前田公爵邸へ向かいます。
11月8日(土)
東京文化財ウィーク2008~東京を旅しよう~で文化財の特別公開があるのを新聞でみつけ、芝増上寺周辺と駒場公園に出かけました、天気予報は時々雨でしたが、ほとんど傘をささずに済んだ1日でした。
JR浜松町駅で下車、  大門をくぐり増上寺へ、
大門をくぐり増上寺へ、
右手にヴィクトリア朝風の洋館を発見、帰宅して調べてみたら、
建物は築40年程の美術商店舗兼レストランでした。
三解脱門とは三つの煩悩「(むさぼり)、(いかり)、(おろかさ)」を解脱する門のことだそうです。
 入口でアクシデント発生、目的の1つ経蔵(きょうぞう)特別公開は雨天のため中止
入口でアクシデント発生、目的の1つ経蔵(きょうぞう)特別公開は雨天のため中止
 入ったら、これからボランティアの方の境内説明案内が始まるとのことで、早速参加。
入ったら、これからボランティアの方の境内説明案内が始まるとのことで、早速参加。
鐘楼堂自体は戦後の再建、大梵鐘は1673(延宝元)年(東日本で最大級)
六人の将軍ほか歴代将軍の子女多数が埋葬されています
30分程説明を受け終了、ありがとうございました。
 旧方丈門(黒門) 17世紀後半(江戸時代初期)港区有形文化財
旧方丈門(黒門) 17世紀後半(江戸時代初期)港区有形文化財
次は近くの妙定院へ向かいます。
重要文化財 渡辺家住宅
9月29日(月)
房総の小江戸大多喜と自称するだけあって、素晴らしい町並みなので9月28日の建物見て歩きとして書きます。
城下町大多喜の歴史や文化を活かしたまちづくりを進めようと、平成12年度から景観を整備しているそうで、 改築や店頭看板の設置にも配慮してありました。
武者行列を見物した辺りは、商家が集まっていた通りの様で古い商家の建物が多くあります。
 向かいの家が同じ様な作りなので聞いたら同じ大工さんが建てたそうです。
向かいの家が同じ様な作りなので聞いたら同じ大工さんが建てたそうです。
お祭で各家の方が表に出ておられ、色んなことが聞けました。
国の重要文化財「渡辺家住宅」1849(嘉永2 ペルー来航の4年前)年築。
この町を代表する大商家の建物で、テレビ東京の人気番組『開運!なんでも鑑定団』のレギュラー鑑定士(書画古文書)を長年つとめ、1998年10月に亡くなられた渡辺包夫氏のお宅で、今でも人が住んでおられるそうです。
お城の門を解体した木材が使われているので、木材は200年程経っているとの事です。
昨日風が強くて今日に順延された、メインストリート城下町通り (延長500m)を、18:00~21:00まで暗闇の歩行者天国とし、行灯・竹細工・陶芸品などに光を入れた作品を展示し、光アート展を行なう為の行灯と竹灯篭が置いてありました。






























































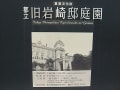







 当時のガラスも一部残っています
当時のガラスも一部残っています

















































