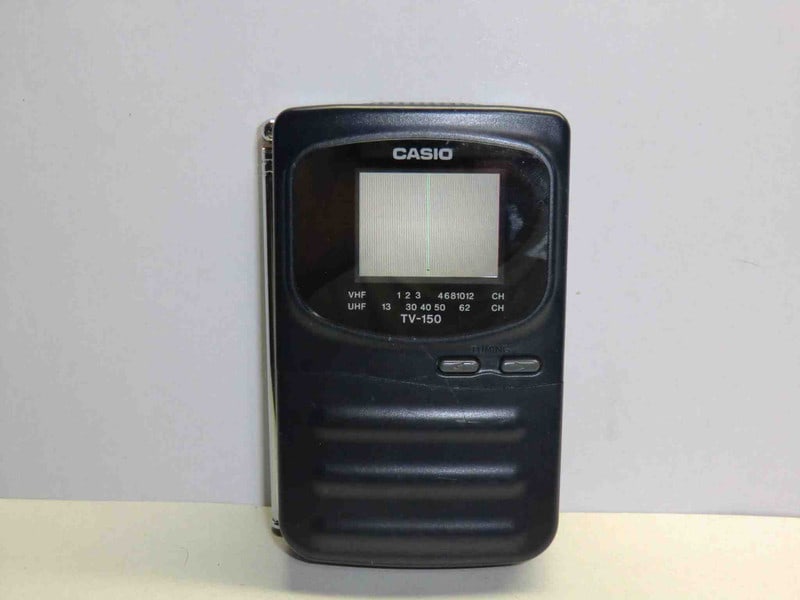かつての時代では定番だった乾電池で動作して持ち運べるポータブルラジオです。現在はラジオというサービスが開始されてある程度の層はラジオを聴いているらしいのですが昔ほどではないのは他に娯楽が増えたとか番組が面白くないなどといった要因があるのでしょう。
ソニーのポータブルラジオ…というよりソニーそのものがラジオが発展要因の1つとなった感じで最近一般的な機器では見かけませんが006P(9V)形電池もソニー(当時は東京通信工業)が胸ポケットに入るラジオの為に制作したらしい。そのソニーも国産ラジオは十和田オーディオが製造する一部高級機ばかりになってしまいました。
購入価格は普通のホームセンターにて2500円
現在だったらもっと安く購入できる場所があるかもしれません。
販促用ステッカーの通りFM/AMの2バンドで同調したらインジケーターが点灯、モノラルイヤホンが付属など安いながらも色々使えるモデルとなっています。流行りのデジタル選局ではなく昔ながらのダイヤルをごろごろするタイプ。
テレビ音声もかつては聞けたのですが現在はアナログ放送終了により聞けなくなってしまいました。
SONY
DC : 3V 単3形 R6×2
ソニー株式会社 MADE IN CHINA
随分シンプルな裏面
中国製となっていますがこんなものでしょう。一時期誤って石油ファンヒータの前に放置してしまい、かなり厚くなってしまいましたが壊れませんでした。
音質は小さいラジオにしてはそこそこ
電源は先ほどの裏面の表記の通り単3形電池を2本使用。しかしR6という記載がある通り推奨電池はマンガン(R6ということは赤マンガン?)になっているみたいです。販促ステッカーにもあったとおり電池長持ちなのでマンガン電池でも十分に動作してしかもアルカリ乾電池と比べると軽くなるので良いです。
画像のようなニッケル水素電池は一般的にラジオ用途には向かないといわれていますが使えないという訳ではないのであまりパワーが残っていない古充電池を使ったりします。
左から
HITACHI KH-1300 日立株式会社
SONY ICF-8 ソニー株式会社
TOSHIBA RP-82 東京芝浦電気株式会社
最近は東京芝浦電気のRP-82ばかり使ってます…
レトロながらもかっこいいデザインと個人的に好きな横長TOSHIBAロゴ、トランジスターラジオながらも音質の良さからお気に入りです。