近日、市のボランティア講師として、公民館で高齢者向けの寄せ植え教室をすることになりました。
予算や持ち帰り時の重さなど考えて、少しでも軽く可愛らしい寄せ植えにしたいと思い、ご近所の花の生産農家さんや、ショップを回って花材を集めました。
嬉しいことに、新種のパンジーなど生産されていて、今までとは少し違った寄せ植えになるのではないかと思っています。
クリスマスっぽく手持ちのスティックを挿してみた試作品。
奥に植えているのはプリムラですが、植えてみるとゴチャゴチャした感じになりそうなので、実際にはストックにしようと思っています。
そして当日はちょっとした魔法 をかけるつもり
をかけるつもり

お教室に来た方々が、フリフリパンジーのフリズルシズルを、気に入ってくれると良いな~

花材を同系色の色合いでそろえたので、どの花を使っても全体的に安定した色合いの寄せ植えができるよう、工夫しました。
植物に触れている時間は、やっぱり幸せ
そんな幸せを、おすそ分けできればと思います
























 と感じました。
と感じました。

 」と歓心
」と歓心









 10月20日(木)に行われた「みどりのサポーター養成講座」の6回目のご報告を。
10月20日(木)に行われた「みどりのサポーター養成講座」の6回目のご報告を。

 〇〇番と〇〇番と2種類必要かな。」
〇〇番と〇〇番と2種類必要かな。」 明日こそ、行ってきます
明日こそ、行ってきます











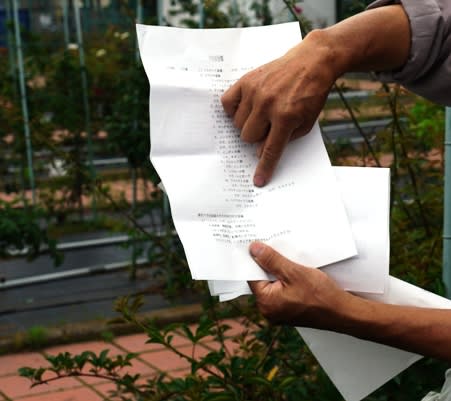











 なっておりましたが、最後の見頃のようでした。
なっておりましたが、最後の見頃のようでした。



