

丸亀城の南門が大手門であった生駒家・山崎家の時代の北門は、石垣もなく唯だ粗末な丸木柱があっただけだった。
戦国時代の余波が残っていた事もあり、北方の海上警備として東汐入川の川口に川口番所が、そしてその上手に物見番所を置いた。
渡し場附近の東汐入川は、旧土器川であり、丸亀城ができて東方に付け替えられたという。
その川跡が外堀の一部となり、また丸亀城の外堀は東西から汐入川を抜け、瀬戸内海に通じていた。
『新修丸亀市史』(昭和46年、丸亀市)参照。
京極家により大手門が南より北に移設、それはつまり大坂冬の陣も終わり、北方が警備警戒の対象から外交・商業の対象に変わった、もしくはそれを幕府にアピールすることで幕府への警戒を和らげようとしたのかも。
平成26年5月撮影。
→丸亀城~生駒氏の時代
←丸亀城搦手門より三の丸まで1
お読み下さり、ありがとうございます。ブログランキングに参加しています。
下のボタンのどれか一つ押して下さればとても嬉しいです。












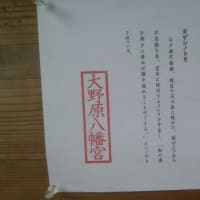


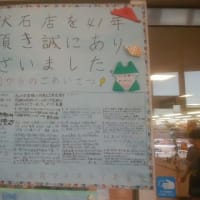




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます