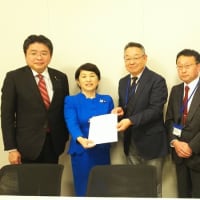【中村局長】給付の障害程度区分の判定が大事。それがどうサービスに結びつくかが大事。モデル事業を紹介したが新しく27項目。特記事項、医師の判定の3つを2次判定に加えて、考慮してニーズに変えてる状況。医師の所見はサービス利用のプロセスの中で重要だと考えているので現場の意見も聞きながら運用していきたい。
【西島】相談支援事業で一番大事なのは中立公平な担保ができること。介護保険はここのところがいろいろな問題がおきてきた。続いて相談支援事業所の権限について聞きたい。事業者に作成費が設定されるのかどうか。このケアプランだけでは成り立たないところに問題がある。介護保険の時には地域支援センターの機能がよく発揮されていなかったので縮小されてきた。介護保険の二の舞にならないように見解をききたい。
【局長】委員指摘のとおり。市町村に地域自立支援協議会で具体的に検討する中で中立公平を保って行きたい。市町村が相談支援事業者に委託するのなら委託費を出す。その他に個々にサービス利用計画を作った場合個別給付として計画書が提出されたら計画作成費を出す。報酬水準については民間の相談支援事業者が十分に活用できるよう求められるのでよく検討したい。
【西島】介護保険と同じにならないよう御願いします。次に障害程度区分判定の施行事業の実施結果速報が出たので資料提出している。一時判定では精神障害者の場合3/1が非該当、3/1が要支援、4/1が要介護1。ほとんど個人の状態が反映されなかった。障害程度区分について医師の意見書を重視して判定されている。今後市町村の審査会について意見書の通訳役としての医師の参加がのぞましいが。
【中村局長】審査会の委員構成について26.3%がメンバーの4人に1人が医師という報告がある。医師の参画は認められないという地域があるなら精査したい。モデル事業は現状の1次判定に加えて新しく2次判定79項目が追加されている。医師の意見書等についていろんな面から判定の中身を分析していく必要があると考えている。さらにつめていきたい。
【西島】今回の対象者に進行性筋萎縮症等難病がふくまれている。これらの病気は進行すると喀痰吸引の24時間体制が必要になってくる。重度者にたいするサービスの量について、利用者から不安がでて来ている。大臣の見解を。
【大臣】重い障害を持っていても地域で暮らしたいと思っている人を支援することが重要課題。重度訪問介護、重度障害者等包括支援という新しい給付類型で対応する予定。今回の調査結果をふまえて対象者の範囲、報酬基準や国庫負担基準等について見当していく。現在の利用者におおきな変化が生じないように配慮していく。
【西島】 命に関わるので是非御願いしたい。これからは精神障害者は入院支援から地域ケアが中心になる。住居のサポート体制が地域ケアで一番重要。特にアパートを借りるのが大変。まだまだ大きな偏見がある。安心してアパートを借りられるような公的な支援が必要では。
【大臣】おっしゃるとおり精神障害者の方の住居の問題は重要。グループホームの充実に加えて一般住宅の問題も重要と認識している。地域生活支援事業の中で不動産業者に対しての物件あっせん依頼、入居契約手続き支援、夜間を含めた緊急時の相談支援連絡体制についても検討している。精神障害者知的障害者の単身入居支援について国土交通省とも連携しながら検討をすすめる。
【西島(自民党)】 極めて重要な部分。ぜひよろしく。
老人性の認知疾患支援センターの件。これは、平成元年に創設された部分。これから認知症の人が急激に増えていく…ということで、これに対応する形で作られてきた。精神保健課の担当でやってきたが、これまで検証がなかった。経済的な問題があるということで、老人保険課に移った。
それ以降、精神保健福祉課がこれに関わるというのが、非常にエネルギーが薄くなってきた。これに対する認識が薄まってきた。今年、これが消えようとしていた。しかし、これが全国に160カ所あった。歴史的にあるシステム。検証もしないまま切り捨てていくというのはいかがなものか。認知症の問題は、これからも出てくる。
24時間の相談体制、入院用に空所を確保する、という厳しい状況で運営がなされている。風前の灯。十分な検証が必要。省庁内の縦割りが、こういったことを引き起こしたのではないかと思う。
【尾辻大臣】 今、精神病床棟について話があった。センターに関心を持っていただいていることに感謝。認知症を人たちへの対応はおろそかにできない。せっかく160カ所に設置しているセンターを、今後どのように活用していくのか。検討が必要。検討しながら、しっかりした答えを出さねばと思っている。
【西島(自民党)】この問題は、省庁内で考えてほしい。
【草川(公明党)】育成医療にしぼって若干の質問を。先ほど西島先生も育成医療について関心があるとか。先生は医師ですから、先生からの質問の方があうかもしれないが…。
もともと、育成医療の問題に関心を持ったのは、子どもが心臓疾患だった若いお母さんから話を聞いたところから。高額の医療負担が負担になっている。
特に、少子高齢化が今問題になっている。特に少子化対策が重要な施策。7/28の審議でも発言したが、障害児の障害の早期除去戸言うことが重要な問題だと思う。親の負担の軽減も考えるべき。そういう問題がある。今般、育成医療を自立支援医療とする。自立支援医療となっても、これまで育成医療が担ってきたことはそのままであると思う。大臣、いかがか。
【尾辻大臣】 育成医療が果たしている役割は重要。今回の改正については、育成医療の主旨は欠いていない。障害児を健全に育成するために考えている。
【草川(公明党)】負担ということを考えると、公明党の中でも議論したが、こういう問題については早期に答えを出すべきだったのではないか、という話があった。育成医療の現状は、どうなっているのか、というところを検討したい。私はたまたま心臓疾患のことを言ったが、どういういった疾患が含まれるのか。どの程度の負担を保護者が担うのか、その辺を教えていただきたい。
【中谷部長】 育成医療の医療費について。15年度の実績をベースに答えると、一番多いのは心臓病。これが全体の医療費の44.8%。その他内臓機能障害17.9%、その他、身体不自由が15.2%。現状で言うと、応能負担ということで所得にあわせた負担になっている。
【草川(公明党)】今、心臓疾患に関わる負担は約半数という答弁だった。一般的に心臓疾患の場合の入院医療はどれくらい?
【中谷部長】 都道府県からの報告から答える。レセプトによると、一ヶ月170万円。
【草川(公明党)】一ヶ月170万円。高額。素人で考えても、大切な部位の疾患であるから高額なのだと思う。例えば大きな心臓の手術をした場合、トータルで一ヶ月300万円ほどかかったとする。中間的な所得層の場合、どの程度の負担になるのか。障害者自立支援法の中ではどうなるのか。
【中谷部長】 自立支援医療費については、低所得者については月額2,500円、5,000円と上限が決まっている。問題になるのは中間所得層。市町村税が課税されているが所得税が非課税の世帯。4,500円、5800円。
障害者自立支援法案の基本的なルールを適用すると、99,890円+食費の標準負担額を負担してもらう。
激変緩和をしたら95,000円+食費の標準負担額。
【草川(公明党)】 激変緩和をしても、95,000円のホテルコストがかかる。私たちの質問の主旨に答えていない。更なる激変緩和をする必要があると思う。財政当局との調整はどうなっているのか。答えられる範囲で答えてほしい。
【尾辻大臣】前国会で、いろいろな意見指摘があった。今のことは、一番気がかりだったものの一つ。私たちはやりたいと思っていたが、財政的な裏づけが必要だった。そこで、見直すことにした。市町村民税は課税されるけれども、年間の所得税額が30万円未満である中間層の世帯に対して、課税の状況に応じて二つの区分を作り、それぞれに、新しい上限額を作るつもりだということ。
【草川(公明党)】 中間層が一番多いのだからがんばってほしい。激変緩和が適用されると、実際いくらぐらいの負担になるのか?
【尾辻大臣】 先ほど言ったように、市町村民税は課税されるが、所得税額が30万円未満のうち、二つに分ける。
所得税非課税世帯では、10,000円を定率負担の上限としたい。これに、食費と標準負担額を負担していただくということにする。すなわち、10,000円が医療費負担の上限。
課税世帯については、40,200円を上限としている。
【草川(公明党)】二つに分けて適用する、という内容。それについてはそれなりに評価する。全国の心臓病の子どもを持つ親の会からも要望が出ているのだが、負担を考えるときの「所帯」とは?「所帯」の考え方は?
同じ医療保険に加入している家族を単位とするのは、原則変わりないのか?
【尾辻大臣】世帯の単位は障害者本人と同じ医療保険に加入している人が対象。
【草川(公明党)】住民上のは別に取り扱う、ということですね。今の話を具体化し、病気の内容等いろんなケースをわかりやすく表にしてPRしてほしい。最後に大臣に聞いてほしい。経済財政「諮問会議社会保障のあり方に関する懇談会」の座長の資料が出ている。尾辻さんの医療制度改革についての見解が出されている。私としては諮問会議がものを言うことに対して疑問がある。経済の成長の枠のなかで定めるべきではなかろうか。経済産業大臣からも提案が出ている。「適度な公的負担は経済規模に見合ったものにしたほうがいい。」上記の資料に見合った新産業政策公的医療給付を低減するという文言が大切。マクロ指標の製作にさいする反論が必要なんではないでしょうか。
【尾辻大臣】今の制度が複雑なものになっている。できるだけわかりやすく説明したいのだが、なかなか大変。宮島座長が出席していた。社会保障全体の見直しに対する説明をききたいということで出席していた。私は呼ばれたら行くメンバー。国民の医療を守る立場から言い続けているがみんなで頑張る必要がある。
【西島】相談支援事業で一番大事なのは中立公平な担保ができること。介護保険はここのところがいろいろな問題がおきてきた。続いて相談支援事業所の権限について聞きたい。事業者に作成費が設定されるのかどうか。このケアプランだけでは成り立たないところに問題がある。介護保険の時には地域支援センターの機能がよく発揮されていなかったので縮小されてきた。介護保険の二の舞にならないように見解をききたい。
【局長】委員指摘のとおり。市町村に地域自立支援協議会で具体的に検討する中で中立公平を保って行きたい。市町村が相談支援事業者に委託するのなら委託費を出す。その他に個々にサービス利用計画を作った場合個別給付として計画書が提出されたら計画作成費を出す。報酬水準については民間の相談支援事業者が十分に活用できるよう求められるのでよく検討したい。
【西島】介護保険と同じにならないよう御願いします。次に障害程度区分判定の施行事業の実施結果速報が出たので資料提出している。一時判定では精神障害者の場合3/1が非該当、3/1が要支援、4/1が要介護1。ほとんど個人の状態が反映されなかった。障害程度区分について医師の意見書を重視して判定されている。今後市町村の審査会について意見書の通訳役としての医師の参加がのぞましいが。
【中村局長】審査会の委員構成について26.3%がメンバーの4人に1人が医師という報告がある。医師の参画は認められないという地域があるなら精査したい。モデル事業は現状の1次判定に加えて新しく2次判定79項目が追加されている。医師の意見書等についていろんな面から判定の中身を分析していく必要があると考えている。さらにつめていきたい。
【西島】今回の対象者に進行性筋萎縮症等難病がふくまれている。これらの病気は進行すると喀痰吸引の24時間体制が必要になってくる。重度者にたいするサービスの量について、利用者から不安がでて来ている。大臣の見解を。
【大臣】重い障害を持っていても地域で暮らしたいと思っている人を支援することが重要課題。重度訪問介護、重度障害者等包括支援という新しい給付類型で対応する予定。今回の調査結果をふまえて対象者の範囲、報酬基準や国庫負担基準等について見当していく。現在の利用者におおきな変化が生じないように配慮していく。
【西島】 命に関わるので是非御願いしたい。これからは精神障害者は入院支援から地域ケアが中心になる。住居のサポート体制が地域ケアで一番重要。特にアパートを借りるのが大変。まだまだ大きな偏見がある。安心してアパートを借りられるような公的な支援が必要では。
【大臣】おっしゃるとおり精神障害者の方の住居の問題は重要。グループホームの充実に加えて一般住宅の問題も重要と認識している。地域生活支援事業の中で不動産業者に対しての物件あっせん依頼、入居契約手続き支援、夜間を含めた緊急時の相談支援連絡体制についても検討している。精神障害者知的障害者の単身入居支援について国土交通省とも連携しながら検討をすすめる。
【西島(自民党)】 極めて重要な部分。ぜひよろしく。
老人性の認知疾患支援センターの件。これは、平成元年に創設された部分。これから認知症の人が急激に増えていく…ということで、これに対応する形で作られてきた。精神保健課の担当でやってきたが、これまで検証がなかった。経済的な問題があるということで、老人保険課に移った。
それ以降、精神保健福祉課がこれに関わるというのが、非常にエネルギーが薄くなってきた。これに対する認識が薄まってきた。今年、これが消えようとしていた。しかし、これが全国に160カ所あった。歴史的にあるシステム。検証もしないまま切り捨てていくというのはいかがなものか。認知症の問題は、これからも出てくる。
24時間の相談体制、入院用に空所を確保する、という厳しい状況で運営がなされている。風前の灯。十分な検証が必要。省庁内の縦割りが、こういったことを引き起こしたのではないかと思う。
【尾辻大臣】 今、精神病床棟について話があった。センターに関心を持っていただいていることに感謝。認知症を人たちへの対応はおろそかにできない。せっかく160カ所に設置しているセンターを、今後どのように活用していくのか。検討が必要。検討しながら、しっかりした答えを出さねばと思っている。
【西島(自民党)】この問題は、省庁内で考えてほしい。
【草川(公明党)】育成医療にしぼって若干の質問を。先ほど西島先生も育成医療について関心があるとか。先生は医師ですから、先生からの質問の方があうかもしれないが…。
もともと、育成医療の問題に関心を持ったのは、子どもが心臓疾患だった若いお母さんから話を聞いたところから。高額の医療負担が負担になっている。
特に、少子高齢化が今問題になっている。特に少子化対策が重要な施策。7/28の審議でも発言したが、障害児の障害の早期除去戸言うことが重要な問題だと思う。親の負担の軽減も考えるべき。そういう問題がある。今般、育成医療を自立支援医療とする。自立支援医療となっても、これまで育成医療が担ってきたことはそのままであると思う。大臣、いかがか。
【尾辻大臣】 育成医療が果たしている役割は重要。今回の改正については、育成医療の主旨は欠いていない。障害児を健全に育成するために考えている。
【草川(公明党)】負担ということを考えると、公明党の中でも議論したが、こういう問題については早期に答えを出すべきだったのではないか、という話があった。育成医療の現状は、どうなっているのか、というところを検討したい。私はたまたま心臓疾患のことを言ったが、どういういった疾患が含まれるのか。どの程度の負担を保護者が担うのか、その辺を教えていただきたい。
【中谷部長】 育成医療の医療費について。15年度の実績をベースに答えると、一番多いのは心臓病。これが全体の医療費の44.8%。その他内臓機能障害17.9%、その他、身体不自由が15.2%。現状で言うと、応能負担ということで所得にあわせた負担になっている。
【草川(公明党)】今、心臓疾患に関わる負担は約半数という答弁だった。一般的に心臓疾患の場合の入院医療はどれくらい?
【中谷部長】 都道府県からの報告から答える。レセプトによると、一ヶ月170万円。
【草川(公明党)】一ヶ月170万円。高額。素人で考えても、大切な部位の疾患であるから高額なのだと思う。例えば大きな心臓の手術をした場合、トータルで一ヶ月300万円ほどかかったとする。中間的な所得層の場合、どの程度の負担になるのか。障害者自立支援法の中ではどうなるのか。
【中谷部長】 自立支援医療費については、低所得者については月額2,500円、5,000円と上限が決まっている。問題になるのは中間所得層。市町村税が課税されているが所得税が非課税の世帯。4,500円、5800円。
障害者自立支援法案の基本的なルールを適用すると、99,890円+食費の標準負担額を負担してもらう。
激変緩和をしたら95,000円+食費の標準負担額。
【草川(公明党)】 激変緩和をしても、95,000円のホテルコストがかかる。私たちの質問の主旨に答えていない。更なる激変緩和をする必要があると思う。財政当局との調整はどうなっているのか。答えられる範囲で答えてほしい。
【尾辻大臣】前国会で、いろいろな意見指摘があった。今のことは、一番気がかりだったものの一つ。私たちはやりたいと思っていたが、財政的な裏づけが必要だった。そこで、見直すことにした。市町村民税は課税されるけれども、年間の所得税額が30万円未満である中間層の世帯に対して、課税の状況に応じて二つの区分を作り、それぞれに、新しい上限額を作るつもりだということ。
【草川(公明党)】 中間層が一番多いのだからがんばってほしい。激変緩和が適用されると、実際いくらぐらいの負担になるのか?
【尾辻大臣】 先ほど言ったように、市町村民税は課税されるが、所得税額が30万円未満のうち、二つに分ける。
所得税非課税世帯では、10,000円を定率負担の上限としたい。これに、食費と標準負担額を負担していただくということにする。すなわち、10,000円が医療費負担の上限。
課税世帯については、40,200円を上限としている。
【草川(公明党)】二つに分けて適用する、という内容。それについてはそれなりに評価する。全国の心臓病の子どもを持つ親の会からも要望が出ているのだが、負担を考えるときの「所帯」とは?「所帯」の考え方は?
同じ医療保険に加入している家族を単位とするのは、原則変わりないのか?
【尾辻大臣】世帯の単位は障害者本人と同じ医療保険に加入している人が対象。
【草川(公明党)】住民上のは別に取り扱う、ということですね。今の話を具体化し、病気の内容等いろんなケースをわかりやすく表にしてPRしてほしい。最後に大臣に聞いてほしい。経済財政「諮問会議社会保障のあり方に関する懇談会」の座長の資料が出ている。尾辻さんの医療制度改革についての見解が出されている。私としては諮問会議がものを言うことに対して疑問がある。経済の成長の枠のなかで定めるべきではなかろうか。経済産業大臣からも提案が出ている。「適度な公的負担は経済規模に見合ったものにしたほうがいい。」上記の資料に見合った新産業政策公的医療給付を低減するという文言が大切。マクロ指標の製作にさいする反論が必要なんではないでしょうか。
【尾辻大臣】今の制度が複雑なものになっている。できるだけわかりやすく説明したいのだが、なかなか大変。宮島座長が出席していた。社会保障全体の見直しに対する説明をききたいということで出席していた。私は呼ばれたら行くメンバー。国民の医療を守る立場から言い続けているがみんなで頑張る必要がある。