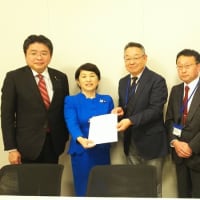(最初、委員長の指名等がありましたが音声が聞き取れませんでした)
【中野副大臣】 厚生労働副大臣になった中野です。全ての人が意欲と能力を生かして働ける環境整備が重要。現場の声に耳を傾け誠実かつ積極的にやっていきたい。大臣を補佐したい。
【西川政務官】 選挙中、国民の要望課題の多くが厚生労働行政に含まれると思った。重い課題。努力する。
【委員長】 国政調査、社会保障労働問題に関する調査について、意義ないか。異議なし。政府参考人について。障害者自立支援法案の審議のため社会援護局長他6名の参考人の出席。異議ないか。異議なし。では障害者自立支援法の主旨説明を聴取します。
【尾辻大臣】 提案理由と内容概要を説明します。障害保健施策については障害者・児の自立…を目的に、現在障害種別でサービスが異なっているので一元化。利用者のニーズに対応できるよう持続可能なものに。障害者・児が適性に応じ自立できるよう必要な…・福祉の増進を図り障害の有無に関わらず国民が人格を尊厳し…。しかし衆議院の解散で成立できなかった。今回の改正を一刻も早く実現したいので再提案した。
1.自立支援給付は当該給付を受けようとするものは市町村…
2.給付額は通常要する額の100分の90を原則に、多額となるものは給付割合の軽減を考える。
3.地域生活支援事業に関することを定める
4.市町村は国の定める基本…障害福祉計画を定める
5.費用は市町村が負担。1/4を都道府県、1/2を国が補助できる
関係諸法律について改正を。
施行は一部除き、平成18年4月1日。
【委員長】 次に委員派遣要求について。現地において意見を聴取するため大阪府に委員派遣したい。異議は? 異議なし。委員検討の決定は委員長に一任してほしい。異議は? 異議なし。次に質疑ある方は順次質疑を。
【小林(民主党)】 大臣にききたい。障害者に関わる法はいくつかある。総じてその目的理念に大臣はどういう所感をもっているのか。
【尾辻大臣】 関する法は、福祉、雇用、建築物、交通移動などがある。障害者施策に共通の考え方は障害者基本法に述べている。自立や社会参加の施策、差別の禁止、自立と社会参加のための国の責務などが基本的な考え方。
【小林(民主党)】 障害者の想いはだいたい3つに集約できるのでは。現状の福祉水準を維持向上。もっと社会参加できる環境を。所得保障なき応益負担に反対。今回の法律を考えた時にそれに集約できるのでは。まず、社会参加という切り口で質問したい。障害者でも健常者でも社会参加をすることは自立の大きな要因。移動支援サービスの見直しについて。障害者の社会参加を保障するものと理解している。市町村の地域生活支援事業には自立した日常生活…必要なとある。個別給付から地域生活支援にかわるのは、具体的にどうかわるのか事例を出して示してほしい。現在の方法とこれからの方法の利点と欠点。
【中村社会援護局長】 移動支援は社会参加の促進、地域の自立を支えるのに重要。支援費制度では個別給付だったが今回は地域生活支援。法律上市町村の義務的事業に。費用は国・都道府県が補助できる規定を。市町村がつくる障害福祉事業にもりこむことに制度的には。厚生労働省では地域生活支援事業運営にかかわるガイドラインを作成。障害者の個々のニーズに対応するサービスにしたい。どうかわるかは。個別給付にも良さがあるが事前に申請が必要なので臨機応変に対応できないとか、1人に複数の人が対応できないなど柔軟でない。こういう点は解消されるのでは。地域特性や利用者に応じた柔軟な形態で。問題恬としては、委託先が限定されて自由に選べないのではという懸念やサービス水準の確保がある。確保はそもそも財政基盤を安定することを考えて提案。障害福祉計画に盛り込むこと。市町村の必須に…そういったことで財源確保に。個別給付の利点を引き継ぎ柔軟な対応ができる地域生活支援をはかっていきたい。
【小林(民主党)】 個人に合わせてのサービス提供ができなくなる。サービス後退になるのでは? 例えばバスの配車。この日のこの時間のこの場所に集合となるのでは? 体調や個別の状況に合わせるのではなく、バスの配車されることに合わせることになる。人でなくものに合わせるサービスが大臣が言った社会福祉、みんなで支えるということに反するのでは。
【尾辻大臣】 出かける人を無理に何人かをまとめて、ということでこの仕組みを作ったつもりも言うつもりもない。体調に合わせて、そのサービスをするのは当然。そのやり方をかえるつもりない。むしろ個別給付では手続き上、臨機に対応できない。今日いきなりちょっと、というときに対応できるように考えている。
【小林(民主党)】 社会参加という意味。障害児の放課後児童クラブの入所枠の状況は。ノーマライゼーションが大切。普通のこととして受入られる世の中。私は昨年のこの委員会で児童クラブの入所枠についての質問をした。1割程度の自治体で制限を求めていることがわかった。それを受けて、厚生労働省から今年の4月に文書が出て「適切な受入を求めて放課後…」と指導した。これはよかった。1割の自治体が現在どうなっているのか把握できていれば教えてほしい。
【○○児童局長】 7月に地方自治体に通知して適切な受入を図るよう指導した。その後の対応状況は現時点では全国調査していない。しかし毎年、放課後児童クラブに対し調査しているので来年の調査に追加項目を入れる予定。自治体にも予告している。
【小林(民主党)】 放課後児童クラブの入所は社会生活の出発点と思う。更なる取り組みを。調査して結果まとめるということだが、もっとつっこんで、なぜ枠が設けられていたのか把握して。厚生労働省としてぜひ改善の強い指導をしてもらいた。きめ細かく丁寧に
【尾辻大臣】 障害児の児童クラブにおいて補助がある。今後も加算する。実施する側として、障害児の受け入れにあたっては最善の受け入れができるよう、最善の支援が基本。一律障害児枠を設定することは適当でないと考えている。今の調査とともに推進したい。
【小林(民主党)】 保育所について、障害児枠がないのはどうなのか。
【○○局長】 障害児を受け入れる施設ではない。体制が十分でないため、各自治体で個別で判断していると認識している。
【小林(民主党)】 条件整備が必要なのはわかるが、早く解決する必要。この改善を早く進めてほしい。
【尾辻大臣】 厚生労働省として障害児保育には取り組んできた。先程の答弁は国の制度を説明する側として答えたのだろう。今後、調整して進める必要。
【小林(民主党)】 障害児や家族で入所したいと思う人は多い。受け入れられる社会を早く作ってほしい。3番目、障害者の文化活動への参加支援について。展示会、発表会などみんなに見てもらうのは励みにもなるし障害者への理解が広まる。障害者基本法第3条、「社会を構成する一員として参加する…」の文言にあるとおり、障害者の自立への取り組みが必要。そこで障害者の文化活動の基本的な考えと予算の推移について伺いたい。
【中村社会援護局長】 障害者基本法に基づき、障害者の基本的な文化活動は自立、社会活動につながる。平成13年度から障害者芸術文化祭を行っている。今年は5回目、山形で開催し、4070万円を補助している。都道府県・市区町村でも、総合推進事業として48億円の中の1事業として行っている。
【小林(民主党)】 個人ボランティアで障害者に習字を教えている人から、生活圏内で無料の展示場を探すのが難しいとの意見をもらった。展示の受け入れに対する指導、役立つ情報の周知など、取り組む必要。東京、関東で、スーパー、駅などの実態を調べた。時間なく細かく報告できないが、総じて県レベルで民間の取り組みを把握していないことがわかった。全国公民館連合会、鉄道協会などにも問合せたところ「申し出がない」とか「個別の把握をしていない」など、足掛かりすらつかめていない状況。障害者を社会全体で支えるために、展示の協力や生活圏内での文化活動に関する役立つ提供できるよう、取り組んでほしい。
【尾辻大臣】 大事であるのはわかる。自治体、区市町村では芸術文化祭を行っている。自分でやっている範囲はわかるが、民間は把握していない。情報把握は必要なので、取り組みを進め、真剣に検討する。
【小林(民主党)】 ぜひよろしくお願いしたい。次に、成年後見制度につい、福祉サービスや支援費制度などで契約方式となり、自己決定できるが、一方すべて自己責任 となるため、判断力の弱い精神障害者などへの課題がある。そのような人に対しての保護のためにも成年後見制度の期待は更に高まる。制度改正後は知的障害者にも活用が望まれるが、精神障害者・知的障害者と認知症とは違うか。
【中村社会援護局長】 知的障害、精神障害ある権利を擁護するためのもの、認知症と共通課題があると認識している。
【小林(民主党)】 厚生労働省からの資料について、実施と周知方法は?
【磯部老健局】 扱いはこのようにする。介護保険法改正課長会議で周知した。
【小林(民主党)】 2親等へと改正されたのはよいので、多くの人に周知をしてほしい。制度利用の際、例えば弁護士をお願いすると、報酬が月2~3万円。障害者や家族の負担は大きい。 手続きの緩和だけでなく、報酬が高額なことにも取り組むべき。新聞記事で東京都が区市町村に推進機関を設置し費用を補助することが載っていた。今後補助枠も広げる予定とのこと。国全体でこのような取り組みが必要では。
【尾辻大臣】 成年後見制度は使ってもらえなかった。高齢者などの被害で使ってもらえるようになった。課題、費用は特に大変。どのくらいかかるか調べ、検討したい。
【中野副大臣】 厚生労働副大臣になった中野です。全ての人が意欲と能力を生かして働ける環境整備が重要。現場の声に耳を傾け誠実かつ積極的にやっていきたい。大臣を補佐したい。
【西川政務官】 選挙中、国民の要望課題の多くが厚生労働行政に含まれると思った。重い課題。努力する。
【委員長】 国政調査、社会保障労働問題に関する調査について、意義ないか。異議なし。政府参考人について。障害者自立支援法案の審議のため社会援護局長他6名の参考人の出席。異議ないか。異議なし。では障害者自立支援法の主旨説明を聴取します。
【尾辻大臣】 提案理由と内容概要を説明します。障害保健施策については障害者・児の自立…を目的に、現在障害種別でサービスが異なっているので一元化。利用者のニーズに対応できるよう持続可能なものに。障害者・児が適性に応じ自立できるよう必要な…・福祉の増進を図り障害の有無に関わらず国民が人格を尊厳し…。しかし衆議院の解散で成立できなかった。今回の改正を一刻も早く実現したいので再提案した。
1.自立支援給付は当該給付を受けようとするものは市町村…
2.給付額は通常要する額の100分の90を原則に、多額となるものは給付割合の軽減を考える。
3.地域生活支援事業に関することを定める
4.市町村は国の定める基本…障害福祉計画を定める
5.費用は市町村が負担。1/4を都道府県、1/2を国が補助できる
関係諸法律について改正を。
施行は一部除き、平成18年4月1日。
【委員長】 次に委員派遣要求について。現地において意見を聴取するため大阪府に委員派遣したい。異議は? 異議なし。委員検討の決定は委員長に一任してほしい。異議は? 異議なし。次に質疑ある方は順次質疑を。
【小林(民主党)】 大臣にききたい。障害者に関わる法はいくつかある。総じてその目的理念に大臣はどういう所感をもっているのか。
【尾辻大臣】 関する法は、福祉、雇用、建築物、交通移動などがある。障害者施策に共通の考え方は障害者基本法に述べている。自立や社会参加の施策、差別の禁止、自立と社会参加のための国の責務などが基本的な考え方。
【小林(民主党)】 障害者の想いはだいたい3つに集約できるのでは。現状の福祉水準を維持向上。もっと社会参加できる環境を。所得保障なき応益負担に反対。今回の法律を考えた時にそれに集約できるのでは。まず、社会参加という切り口で質問したい。障害者でも健常者でも社会参加をすることは自立の大きな要因。移動支援サービスの見直しについて。障害者の社会参加を保障するものと理解している。市町村の地域生活支援事業には自立した日常生活…必要なとある。個別給付から地域生活支援にかわるのは、具体的にどうかわるのか事例を出して示してほしい。現在の方法とこれからの方法の利点と欠点。
【中村社会援護局長】 移動支援は社会参加の促進、地域の自立を支えるのに重要。支援費制度では個別給付だったが今回は地域生活支援。法律上市町村の義務的事業に。費用は国・都道府県が補助できる規定を。市町村がつくる障害福祉事業にもりこむことに制度的には。厚生労働省では地域生活支援事業運営にかかわるガイドラインを作成。障害者の個々のニーズに対応するサービスにしたい。どうかわるかは。個別給付にも良さがあるが事前に申請が必要なので臨機応変に対応できないとか、1人に複数の人が対応できないなど柔軟でない。こういう点は解消されるのでは。地域特性や利用者に応じた柔軟な形態で。問題恬としては、委託先が限定されて自由に選べないのではという懸念やサービス水準の確保がある。確保はそもそも財政基盤を安定することを考えて提案。障害福祉計画に盛り込むこと。市町村の必須に…そういったことで財源確保に。個別給付の利点を引き継ぎ柔軟な対応ができる地域生活支援をはかっていきたい。
【小林(民主党)】 個人に合わせてのサービス提供ができなくなる。サービス後退になるのでは? 例えばバスの配車。この日のこの時間のこの場所に集合となるのでは? 体調や個別の状況に合わせるのではなく、バスの配車されることに合わせることになる。人でなくものに合わせるサービスが大臣が言った社会福祉、みんなで支えるということに反するのでは。
【尾辻大臣】 出かける人を無理に何人かをまとめて、ということでこの仕組みを作ったつもりも言うつもりもない。体調に合わせて、そのサービスをするのは当然。そのやり方をかえるつもりない。むしろ個別給付では手続き上、臨機に対応できない。今日いきなりちょっと、というときに対応できるように考えている。
【小林(民主党)】 社会参加という意味。障害児の放課後児童クラブの入所枠の状況は。ノーマライゼーションが大切。普通のこととして受入られる世の中。私は昨年のこの委員会で児童クラブの入所枠についての質問をした。1割程度の自治体で制限を求めていることがわかった。それを受けて、厚生労働省から今年の4月に文書が出て「適切な受入を求めて放課後…」と指導した。これはよかった。1割の自治体が現在どうなっているのか把握できていれば教えてほしい。
【○○児童局長】 7月に地方自治体に通知して適切な受入を図るよう指導した。その後の対応状況は現時点では全国調査していない。しかし毎年、放課後児童クラブに対し調査しているので来年の調査に追加項目を入れる予定。自治体にも予告している。
【小林(民主党)】 放課後児童クラブの入所は社会生活の出発点と思う。更なる取り組みを。調査して結果まとめるということだが、もっとつっこんで、なぜ枠が設けられていたのか把握して。厚生労働省としてぜひ改善の強い指導をしてもらいた。きめ細かく丁寧に
【尾辻大臣】 障害児の児童クラブにおいて補助がある。今後も加算する。実施する側として、障害児の受け入れにあたっては最善の受け入れができるよう、最善の支援が基本。一律障害児枠を設定することは適当でないと考えている。今の調査とともに推進したい。
【小林(民主党)】 保育所について、障害児枠がないのはどうなのか。
【○○局長】 障害児を受け入れる施設ではない。体制が十分でないため、各自治体で個別で判断していると認識している。
【小林(民主党)】 条件整備が必要なのはわかるが、早く解決する必要。この改善を早く進めてほしい。
【尾辻大臣】 厚生労働省として障害児保育には取り組んできた。先程の答弁は国の制度を説明する側として答えたのだろう。今後、調整して進める必要。
【小林(民主党)】 障害児や家族で入所したいと思う人は多い。受け入れられる社会を早く作ってほしい。3番目、障害者の文化活動への参加支援について。展示会、発表会などみんなに見てもらうのは励みにもなるし障害者への理解が広まる。障害者基本法第3条、「社会を構成する一員として参加する…」の文言にあるとおり、障害者の自立への取り組みが必要。そこで障害者の文化活動の基本的な考えと予算の推移について伺いたい。
【中村社会援護局長】 障害者基本法に基づき、障害者の基本的な文化活動は自立、社会活動につながる。平成13年度から障害者芸術文化祭を行っている。今年は5回目、山形で開催し、4070万円を補助している。都道府県・市区町村でも、総合推進事業として48億円の中の1事業として行っている。
【小林(民主党)】 個人ボランティアで障害者に習字を教えている人から、生活圏内で無料の展示場を探すのが難しいとの意見をもらった。展示の受け入れに対する指導、役立つ情報の周知など、取り組む必要。東京、関東で、スーパー、駅などの実態を調べた。時間なく細かく報告できないが、総じて県レベルで民間の取り組みを把握していないことがわかった。全国公民館連合会、鉄道協会などにも問合せたところ「申し出がない」とか「個別の把握をしていない」など、足掛かりすらつかめていない状況。障害者を社会全体で支えるために、展示の協力や生活圏内での文化活動に関する役立つ提供できるよう、取り組んでほしい。
【尾辻大臣】 大事であるのはわかる。自治体、区市町村では芸術文化祭を行っている。自分でやっている範囲はわかるが、民間は把握していない。情報把握は必要なので、取り組みを進め、真剣に検討する。
【小林(民主党)】 ぜひよろしくお願いしたい。次に、成年後見制度につい、福祉サービスや支援費制度などで契約方式となり、自己決定できるが、一方すべて自己責任 となるため、判断力の弱い精神障害者などへの課題がある。そのような人に対しての保護のためにも成年後見制度の期待は更に高まる。制度改正後は知的障害者にも活用が望まれるが、精神障害者・知的障害者と認知症とは違うか。
【中村社会援護局長】 知的障害、精神障害ある権利を擁護するためのもの、認知症と共通課題があると認識している。
【小林(民主党)】 厚生労働省からの資料について、実施と周知方法は?
【磯部老健局】 扱いはこのようにする。介護保険法改正課長会議で周知した。
【小林(民主党)】 2親等へと改正されたのはよいので、多くの人に周知をしてほしい。制度利用の際、例えば弁護士をお願いすると、報酬が月2~3万円。障害者や家族の負担は大きい。 手続きの緩和だけでなく、報酬が高額なことにも取り組むべき。新聞記事で東京都が区市町村に推進機関を設置し費用を補助することが載っていた。今後補助枠も広げる予定とのこと。国全体でこのような取り組みが必要では。
【尾辻大臣】 成年後見制度は使ってもらえなかった。高齢者などの被害で使ってもらえるようになった。課題、費用は特に大変。どのくらいかかるか調べ、検討したい。