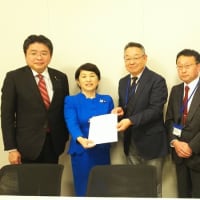【朝日(民主党)】
【尾辻大臣】 精神障害の見直しが必要と思い、法案つくったが、わが国の精神障害者対策は、精神障害者福祉は入院中心だった。医療の質の向上、社会復帰と、近年、方向転換がなされてきたが、成果は十分でないという認識のもとで、法案改正の作業始めた。
【朝日(民主党)】 精神障害者の医療保健でいわねばならないのは、現在、約35万人が入院しており、諸外国と比べて入院中心主義であること。そこで、これを、地域で生活できるよう、保健医療と福祉の領域をとっぱらうことが基本では?という認識をもって、改革にあたってほしかった。改めて、お伺いしたいが、今回の法改正で、地域生活ができるようもっていけるのか?
【尾辻大臣】 そう申し上げたつもり。不十分だった。そう申し上げたいと思ってお答えした。入院から在宅への方向転換がなされてはいるが、成果は十分でないということを申し上げたつもり。推進するため、この法をつくるということ。
【朝日(民主党)】 昨年9月にまとめた精神保健医療の改革ビジョンでは、?????、診療報酬の改定で検討もらえると思うが、少なくとも、精神障害者のことも障害者自立支援法案の中でとりまとめをしたと思ってよいか?
【尾辻大臣】そのとおりでございます。
【朝日(民主党)】 大臣の明確な答えを期待したが、(大臣の)勉強不足。障害者自立支援法案の中に、付則で精神保健福祉法がある。これはおかしいと、先の国会で指摘した。今回の改正案で、精神保健の一部改正として、固有の改正項目が10項目ある。平成12年の精神保健福祉法の改正で不十分だったから、5年後の見直し規定を設けた。精神保健福祉法、固有の問題だったわけだが、今回、それがいっしょくたになっていて、精神保健福祉法は、付則扱いになっている。今回の精神保健福祉法の改正の性格は?5年前の見直し約束の答えか?宿題の医療保護入院の答えは、でていない。宿題の答えは、いつ出す予定か?次の改正はいつか?障害者自立支援法案で提案されている精神保健福祉法の一部改正の性質、位置づけは?お伺いしたい。
【尾辻大臣】 ご指摘のとおり、平成12年の見直しをふまえて、今回とりまとめた。改革ビジョン、グランドデザイン、在宅、改善に従わない病院の公表措置などを規定している。障害者自立支援法案、改革ビジョンでは、国民???、精神保健医療の改革、地域生活の強化が重点項目だが、障害者自立支援法案では、地域生活の強化に重点的にとりくんだ。そこで、精神保健福祉に課題が残っているという認識はある。ただ、関係者の見解が分かれており、さらに、ご意見をお聞きし、検討を進めなければならない。
【朝日(民主党)】 確認したい。従来からの検討課題である、医療保護入院制度、保護者の規定の見直しなど問題が残っている。今回の障害者自立支援法案では、それらが、まだ積み残しになっているとの認識はあるのか?次の法案改正もあるか?
【尾辻大臣】 問題は残っていると認識している。具体的な内容は、ご指摘のとおり。今後の課題として、検討させていただく。
【朝日(民主党)】 精神保健福祉法の中身についてお聞きしたい。①精神障害の定義。精神障害者の規定で、「精神分裂病」ということばが残っている。関係者や、学会の中では、「統合失調症」が定着し始めている。そこで、障害者自立支援法案の中で、「統合失調症」に変えることについては、賛成する。だが、それだけでよいのか?
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の定義は、もやっとしている。「???、???依存症、知的障害、精神病者…その他の…(条文)」となっていて、本当に、この定義でよいか?知的障害が入っているが、よいのか?知的障害福祉法の中では、知的障害の定義はないらしい。
また、学会で使わなくなった精神病質も残っている7/28に、定義について尋ねたとき、「障害者の定義もふくめて施行後、3年をめどに見直し」との大臣答弁があった。検討の中身は、5条もふくめて検討するという理解をしてよいか?
【尾辻大臣】 7/28の回答は、その頃、障害者自立支援法案の障害者の範囲をどうするかとの議論があり、難病、発達障害などの谷間の問題があり、念頭には、この問題をおいていたということを正直に申し上げたい。
が、今は、見直しするということは、今のご指摘がふくまれると、必然と考える。改めて、それらも含めて検討するとお答えしたい。
【朝日(民主党)】 是非、検討をお願いしたい。ただ、(検討は)大変難しく、関係者と十分意見交換をした上で判断してほしい。先の7/28の委員会での部長答弁だったと思うが、坂本委員に「高次機能障害は精神障害の範囲にふくまれ、精神保健福祉法の対象」との答弁があった。発達障害も、概念的には対象になるので、障害者自立支援法案のサービスの対象との答弁あった。高次機能障害、発達障害は、概念的には、精神保健福祉法の対象、との答弁だったかということを、改めて確認したい。
もし、そうなら、このことについての、専門家、関係者の了解は得ているのか?あえてお聞きするのは、精神障害の範囲としてほしくないという気持ちもある。
【中谷?】 (そういう内容の答弁だったと)確認いたします。当事者のかたがたの希望はさまざまであり、ご意見をお聞きして、対応したい。
【朝日(民主党)】 ということは、これまではうかがっていないということか?
【中谷?】 発達障害の方は、特に問題と思い説明をし、それなりに理解を得ているところ。
【朝日(民主党)】 私の知っている方から、「きちんと説明受けてないし、納得していない」という意見を聞いている。対象になることは意味があると言うことは承知している。が答弁で当事者の神経をさかなでることをしてはいけないと思う。医学的にはわからないでもないが、行政としてやっていくことについては説明と同意を。インフォームドコンセントをとるように。
【中谷?】 様々な分野の方の意見をきいて対応していきたい。
【朝日(民主党)】 精神保健福祉法の第32条について2点に絞って聞きたい。医療費の公費負担制度が、規定されているが、自立支援法ではこれが条文からはずされて、新設される自立支援医療に位置づけられている。法律が移った。従来5%の負担が、10%にという提案になっている。これまで精神保健福祉法32条は福祉的意味ではなく、入院中心から通院で地域生活を支える、という政策目標があった。精神保健福祉法からはずして支援法に移したことによって。座り心地がわるい。10%にあげるということは、地域生活で支えると言う政策目標がふっとぶ、むしろ抑制されると考えるがどうか。
【尾辻大臣】 精神医療の適正医療の考え方が、今回の見直しにおいては欠いているものではなく、その通りに考えている。精神障害施策は3障害をあわせたものにしたいという認識で作った。共通認識の中で、この制度を考えるというところにしたところ。これまで1割負担に変化した。5%から10%になることでどういう影響があるかということについて、推進することから逆行するのではないかと言う話だったが、確かに5%あがったともいえるが、10%という全体の整合性の中で、社会保障が1割負担と言っているので、全体の整合性ということから決めた。5%でも上限を決めていないので、5%といっても大きな額になっている人もあったと思う。今回は上限をいろいろ設定しているので、低くなる方もある。増える、減る、の両方があると考える。みんなで支えあう仕組みを考えていることを理解いただきたい。
【朝日(民主党)】 1点確認した。公費負担していた政策的意義は入院から通院へ、地域生活を支援しようという目標があったと理解している。そうすると、その政策目標を変えるつもりはないと言うことと、今後様々な政策を講じていく、ということについては、お答えできるか。
【尾辻大臣】 精神障害の適切な医療の推進を、という趣旨を変えるつもりは全くない。その趣旨を推進するために出来るかぎりの努力はしていきたい。
【朝日(民主党)】 専門家の意見を聞きやっておられるということなのですが、外来の通院を支えるのは大変。ほぼ毎日でも行って、なんとか入院しないでやっていこうという人にとって32条は意味があった。その意味がふっとぶことがあってはならないことを考えて今後の検討をお願いしたい。
大阪や京都などいくつかの自治体では32条に基づく5%分を県が独自で助成するという、実質的に無料化を実施している自治体が、政令市レベルである。この努力について大臣はどのように認識、評価されているのか。今回の改正がどういう影響を与えるとお考えか。最終的には自治体の判断になると思うが、従来無料だったものが1割負担になる可能性もある。それをどうお考えか。それにたいして何か対策を考えられているのか
【中谷?】 地方自治体における患者負担の助成について、そのような助成があることは
認識している。影響については、費用をみなさまが支えあう形の負担とご理解いただけないかと思っている。最終的には地方自治体の判断によると考えている。厚生労働省としては、利用される方に負担いただきたいと考えている。
【朝日(民主党)】 自治体が相当悩むと考えられる。従来から5%分は予算化してきたからなんとか対応できるが、プラス5%分は難しいという意見をきいている。地方自治体も財政が厳しいから、このさい補助をやめようと言う議論がでてきている。10%を負担しようという意見はなくて、5%はなんとか見ていこうという意見と、これを機に0にしようという議論がある。そうすると、従来事実上無料だった負担がいっきに10%になるところがでてくる。結局はこれに対して自治体任せか、国は何もしないのか。
【中谷?】 自治体の判断による。減免制度などもあるので、理解して欲しい。
【朝日(民主党)】 大臣にお答え頂いても同じか。
【尾辻大臣】 同じ答えになる。
【朝日(民主党)】 明日大阪に行くので、関西の関係者の意見を聴いて生かしたいと思っている。
別の課題。課題山ほどあって時間足りない。
都道府県設置の精神医療審査会がある。この委員構成の見直しというのが改正ポイントになっている。この審査会がどういう機能・役割を持っている審査会なのかということと、気になっているのは、この審査会が、法改正で規定されたが、期待された役割を果たしていないのではないかと危惧している。自治体によっては、多くの件数を取り扱って活発にうごいているところと、開店休業中というところがある。現状を厚生労働省は把握していると思うが。その審査会はそもそもどういう役割を期待されているのか。活動状況に地域格差があるのではないか。それについて今後どう取り組むつもりか、聞きたい。
【中谷?】 精神保健福祉法第12条で都道府県が設置するものと規定されている。医療保護入院の患者の入院状況の報告を受ける。医療保護入院の退院請求、入院中の患者の処遇改善請求をきいて、その必要性・妥当性を検討する業務を担っている。活動状況については、平成15年は19万をこえる定期報告を受けている。2103件が退院請求、136件が処遇改善に関するもの。これらを都道府県で審議してきた。退院請求と処遇請求の件数については都道府県によって差がある。機能の充実に努めていく所存である。
【尾辻大臣】 精神障害の見直しが必要と思い、法案つくったが、わが国の精神障害者対策は、精神障害者福祉は入院中心だった。医療の質の向上、社会復帰と、近年、方向転換がなされてきたが、成果は十分でないという認識のもとで、法案改正の作業始めた。
【朝日(民主党)】 精神障害者の医療保健でいわねばならないのは、現在、約35万人が入院しており、諸外国と比べて入院中心主義であること。そこで、これを、地域で生活できるよう、保健医療と福祉の領域をとっぱらうことが基本では?という認識をもって、改革にあたってほしかった。改めて、お伺いしたいが、今回の法改正で、地域生活ができるようもっていけるのか?
【尾辻大臣】 そう申し上げたつもり。不十分だった。そう申し上げたいと思ってお答えした。入院から在宅への方向転換がなされてはいるが、成果は十分でないということを申し上げたつもり。推進するため、この法をつくるということ。
【朝日(民主党)】 昨年9月にまとめた精神保健医療の改革ビジョンでは、?????、診療報酬の改定で検討もらえると思うが、少なくとも、精神障害者のことも障害者自立支援法案の中でとりまとめをしたと思ってよいか?
【尾辻大臣】そのとおりでございます。
【朝日(民主党)】 大臣の明確な答えを期待したが、(大臣の)勉強不足。障害者自立支援法案の中に、付則で精神保健福祉法がある。これはおかしいと、先の国会で指摘した。今回の改正案で、精神保健の一部改正として、固有の改正項目が10項目ある。平成12年の精神保健福祉法の改正で不十分だったから、5年後の見直し規定を設けた。精神保健福祉法、固有の問題だったわけだが、今回、それがいっしょくたになっていて、精神保健福祉法は、付則扱いになっている。今回の精神保健福祉法の改正の性格は?5年前の見直し約束の答えか?宿題の医療保護入院の答えは、でていない。宿題の答えは、いつ出す予定か?次の改正はいつか?障害者自立支援法案で提案されている精神保健福祉法の一部改正の性質、位置づけは?お伺いしたい。
【尾辻大臣】 ご指摘のとおり、平成12年の見直しをふまえて、今回とりまとめた。改革ビジョン、グランドデザイン、在宅、改善に従わない病院の公表措置などを規定している。障害者自立支援法案、改革ビジョンでは、国民???、精神保健医療の改革、地域生活の強化が重点項目だが、障害者自立支援法案では、地域生活の強化に重点的にとりくんだ。そこで、精神保健福祉に課題が残っているという認識はある。ただ、関係者の見解が分かれており、さらに、ご意見をお聞きし、検討を進めなければならない。
【朝日(民主党)】 確認したい。従来からの検討課題である、医療保護入院制度、保護者の規定の見直しなど問題が残っている。今回の障害者自立支援法案では、それらが、まだ積み残しになっているとの認識はあるのか?次の法案改正もあるか?
【尾辻大臣】 問題は残っていると認識している。具体的な内容は、ご指摘のとおり。今後の課題として、検討させていただく。
【朝日(民主党)】 精神保健福祉法の中身についてお聞きしたい。①精神障害の定義。精神障害者の規定で、「精神分裂病」ということばが残っている。関係者や、学会の中では、「統合失調症」が定着し始めている。そこで、障害者自立支援法案の中で、「統合失調症」に変えることについては、賛成する。だが、それだけでよいのか?
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の定義は、もやっとしている。「???、???依存症、知的障害、精神病者…その他の…(条文)」となっていて、本当に、この定義でよいか?知的障害が入っているが、よいのか?知的障害福祉法の中では、知的障害の定義はないらしい。
また、学会で使わなくなった精神病質も残っている7/28に、定義について尋ねたとき、「障害者の定義もふくめて施行後、3年をめどに見直し」との大臣答弁があった。検討の中身は、5条もふくめて検討するという理解をしてよいか?
【尾辻大臣】 7/28の回答は、その頃、障害者自立支援法案の障害者の範囲をどうするかとの議論があり、難病、発達障害などの谷間の問題があり、念頭には、この問題をおいていたということを正直に申し上げたい。
が、今は、見直しするということは、今のご指摘がふくまれると、必然と考える。改めて、それらも含めて検討するとお答えしたい。
【朝日(民主党)】 是非、検討をお願いしたい。ただ、(検討は)大変難しく、関係者と十分意見交換をした上で判断してほしい。先の7/28の委員会での部長答弁だったと思うが、坂本委員に「高次機能障害は精神障害の範囲にふくまれ、精神保健福祉法の対象」との答弁があった。発達障害も、概念的には対象になるので、障害者自立支援法案のサービスの対象との答弁あった。高次機能障害、発達障害は、概念的には、精神保健福祉法の対象、との答弁だったかということを、改めて確認したい。
もし、そうなら、このことについての、専門家、関係者の了解は得ているのか?あえてお聞きするのは、精神障害の範囲としてほしくないという気持ちもある。
【中谷?】 (そういう内容の答弁だったと)確認いたします。当事者のかたがたの希望はさまざまであり、ご意見をお聞きして、対応したい。
【朝日(民主党)】 ということは、これまではうかがっていないということか?
【中谷?】 発達障害の方は、特に問題と思い説明をし、それなりに理解を得ているところ。
【朝日(民主党)】 私の知っている方から、「きちんと説明受けてないし、納得していない」という意見を聞いている。対象になることは意味があると言うことは承知している。が答弁で当事者の神経をさかなでることをしてはいけないと思う。医学的にはわからないでもないが、行政としてやっていくことについては説明と同意を。インフォームドコンセントをとるように。
【中谷?】 様々な分野の方の意見をきいて対応していきたい。
【朝日(民主党)】 精神保健福祉法の第32条について2点に絞って聞きたい。医療費の公費負担制度が、規定されているが、自立支援法ではこれが条文からはずされて、新設される自立支援医療に位置づけられている。法律が移った。従来5%の負担が、10%にという提案になっている。これまで精神保健福祉法32条は福祉的意味ではなく、入院中心から通院で地域生活を支える、という政策目標があった。精神保健福祉法からはずして支援法に移したことによって。座り心地がわるい。10%にあげるということは、地域生活で支えると言う政策目標がふっとぶ、むしろ抑制されると考えるがどうか。
【尾辻大臣】 精神医療の適正医療の考え方が、今回の見直しにおいては欠いているものではなく、その通りに考えている。精神障害施策は3障害をあわせたものにしたいという認識で作った。共通認識の中で、この制度を考えるというところにしたところ。これまで1割負担に変化した。5%から10%になることでどういう影響があるかということについて、推進することから逆行するのではないかと言う話だったが、確かに5%あがったともいえるが、10%という全体の整合性の中で、社会保障が1割負担と言っているので、全体の整合性ということから決めた。5%でも上限を決めていないので、5%といっても大きな額になっている人もあったと思う。今回は上限をいろいろ設定しているので、低くなる方もある。増える、減る、の両方があると考える。みんなで支えあう仕組みを考えていることを理解いただきたい。
【朝日(民主党)】 1点確認した。公費負担していた政策的意義は入院から通院へ、地域生活を支援しようという目標があったと理解している。そうすると、その政策目標を変えるつもりはないと言うことと、今後様々な政策を講じていく、ということについては、お答えできるか。
【尾辻大臣】 精神障害の適切な医療の推進を、という趣旨を変えるつもりは全くない。その趣旨を推進するために出来るかぎりの努力はしていきたい。
【朝日(民主党)】 専門家の意見を聞きやっておられるということなのですが、外来の通院を支えるのは大変。ほぼ毎日でも行って、なんとか入院しないでやっていこうという人にとって32条は意味があった。その意味がふっとぶことがあってはならないことを考えて今後の検討をお願いしたい。
大阪や京都などいくつかの自治体では32条に基づく5%分を県が独自で助成するという、実質的に無料化を実施している自治体が、政令市レベルである。この努力について大臣はどのように認識、評価されているのか。今回の改正がどういう影響を与えるとお考えか。最終的には自治体の判断になると思うが、従来無料だったものが1割負担になる可能性もある。それをどうお考えか。それにたいして何か対策を考えられているのか
【中谷?】 地方自治体における患者負担の助成について、そのような助成があることは
認識している。影響については、費用をみなさまが支えあう形の負担とご理解いただけないかと思っている。最終的には地方自治体の判断によると考えている。厚生労働省としては、利用される方に負担いただきたいと考えている。
【朝日(民主党)】 自治体が相当悩むと考えられる。従来から5%分は予算化してきたからなんとか対応できるが、プラス5%分は難しいという意見をきいている。地方自治体も財政が厳しいから、このさい補助をやめようと言う議論がでてきている。10%を負担しようという意見はなくて、5%はなんとか見ていこうという意見と、これを機に0にしようという議論がある。そうすると、従来事実上無料だった負担がいっきに10%になるところがでてくる。結局はこれに対して自治体任せか、国は何もしないのか。
【中谷?】 自治体の判断による。減免制度などもあるので、理解して欲しい。
【朝日(民主党)】 大臣にお答え頂いても同じか。
【尾辻大臣】 同じ答えになる。
【朝日(民主党)】 明日大阪に行くので、関西の関係者の意見を聴いて生かしたいと思っている。
別の課題。課題山ほどあって時間足りない。
都道府県設置の精神医療審査会がある。この委員構成の見直しというのが改正ポイントになっている。この審査会がどういう機能・役割を持っている審査会なのかということと、気になっているのは、この審査会が、法改正で規定されたが、期待された役割を果たしていないのではないかと危惧している。自治体によっては、多くの件数を取り扱って活発にうごいているところと、開店休業中というところがある。現状を厚生労働省は把握していると思うが。その審査会はそもそもどういう役割を期待されているのか。活動状況に地域格差があるのではないか。それについて今後どう取り組むつもりか、聞きたい。
【中谷?】 精神保健福祉法第12条で都道府県が設置するものと規定されている。医療保護入院の患者の入院状況の報告を受ける。医療保護入院の退院請求、入院中の患者の処遇改善請求をきいて、その必要性・妥当性を検討する業務を担っている。活動状況については、平成15年は19万をこえる定期報告を受けている。2103件が退院請求、136件が処遇改善に関するもの。これらを都道府県で審議してきた。退院請求と処遇請求の件数については都道府県によって差がある。機能の充実に努めていく所存である。