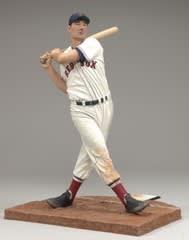
(最後の2試合に堂々出場して「最後の4割打者」となったテッド・ウィリアムズ)
競技を問わず、スポーツをしていて、誰もが「あれだけはやりたくない」「やってしまってとても恥ずかしい」プレーというものがある。
野球なら三振した打者にバッテリーが「振り逃げ」を許したり、内野手が真正面に飛んできた凡ゴロをトンネルしたり、宇野勝選手のように内野フライを“ヘッディング”しちゃったり、バスケットボールなら保持していたボールを相手にスティールされたり、陸上競技ならリレーでバトンを相手に渡しそこなったり、マラソン谷口浩美選手のように「こけちゃった」り……などなど。相撲の「勇み足」などもその部類に入るだろう。
サッカーではやはり「オウンゴール」だ。守備側の選手が味方のゴールにボールを蹴り込んで相手に得点を与えてしまうことで、Jリーグの発足直後までは「自殺点」と呼ばれていた。ただし、試合がディフェンシブになればなるほど、ディフェンダーはゴール前で「紙一重」の守りを間断なく強いられるし、相手の放ったボレーシュートをクリアしたつもりが不運にもゴールに方向転換してしまうケースもあるから、全部が全部「恥ずかし」かったり、「凡プレー、ミス」というわけではない。
しかし、それを1試合に6回も、しかも故意に、指導者の「命令」でやってしまえば話は別だ。
すでにご存じの方も多いと思うが、日本サッカー協会は、9日の理事会で、1月に新潟県で開催されたフットサル大会で、決勝トーナメントの組み合わせで強豪チームとの対戦を避けるために、選手に故意に6回のオウンゴールを指示したとして、チームのコーチを務める中学校教頭に対し、1年間のサッカー指導活動停止の処分を科した。
(asahi.comの関連記事)
http://www.asahi.com/sports/fb/TKY200904090260.html
いやしくも教育者、しかも教頭の地位にある人物が、自分の教え子でもある中学生の選手たちに対して、敗退行為を命じるとは、もはや論評にすら値しない。
敗退行為そのものも許し難いが、さらに問題なのはその動機だ。決勝トーナメントで「強豪と対戦したくない」とは、いったいどういう考え方なのか?
ゴルフコースを一人で回るなどのケースを除けば、スポーツには対戦相手があり、基本的に試合で「勝敗」「優劣」を決さなければならない。誰も試合に「負けたい」「負けよう」と思って臨むことはないが、タイムアップになったり、ゲームセットが告げられた瞬間、両者は「勝者」と「敗者」に分かれる。だが、勝者は勝ちに驕ってはいけないし、敗者も相手の強さをたたえ、敗戦から学び、次の試合の準備に備えなければならない。
過日のWBCで日本代表は連覇を果たしたが、多分に「運のよさ」に恵まれて決勝トーナメント進出が「転がり込んできた」前回よりも、決勝まで5回にわたる死闘を繰り広げた韓国代表をはじめ、前回「疑惑の判定」がらみで苦杯をなめたアメリカにもリベンジを果たし、有り余る才能をフルに生かすメンタリティーやチームワークが欠如していたキューバにも「力の差」を見せ付けるなど、「強い相手」と「いい試合」をして、今回も栄冠をつかんだ。
1941年、打率.406をマークし、メジャーリーグにおける「最後の4割打者」となったテッド・ウィリアムズは、公式戦最終2試合を残して、四捨五入切り上げながらすでに4割(.3995)をマークしており、監督のジョー・クローニンは欠場を進めたが、ウィリアムズは出場を直訴し、ダブルヘッダーで8打数6安打を放って、打率を.406にアップさせ、正真正銘の「4割打者」となった。
なぜ件の教頭は選手たちに、「この試合で堂々と勝って、強い相手の胸を借りよう」といえなかったのか。また選手たちも教頭の理不尽な命令(指示)にどうして抵抗しなかったのか。
この一件から思い出すのは、ここ数年日本のスポーツ界で起こった数々の「いやな出来事」「不祥事」あるいは「悲劇」だ。教頭による選手たちへの「敗退行為」の指示は、時津風部屋で起こった親方・兄弟子たち(いずれも当時)による新弟子リンチ事件や、京都の少年野球チームで試合に敗れた選手たちに「ペナルティー」として炎天下での過酷な練習を科した挙句、中学生選手を熱中症死に追い込んだ総監督の行為を連想させる。
また「強い相手」との対戦を避けようとした姿勢は、ボクシング亀田一家のマッチメイクとなんら変わらないものだ。
そもそも、こうした行為を教育者・指導者が率先して、チームぐるみで行なったことじたい、規範意識や順法精神の希薄さが根底にあり、最近大学運動部で頻発している大麻事件にも通じるものがあるといえるだろう。
このフットサルチームには監督がいたが、学校の非常勤講師という立場から、職場での上下関係ゆえに、教頭の指示に異論を唱えられなかったという。競技の底辺のレベルでも根深くはびこり、スポーツの尊厳をゆがめる日本社会独特の「体育会系体質」弊害に、ただただ嘆息するばかりだ。
スポーツの名誉と選手の尊厳を傷つけ、汚し、ゆがめる理不尽な命令を行なった教頭、それに抵抗することもなく、命令そのままに競技を汚す行為を実行した監督と選手たち──6個のオウンゴールは、強い相手と戦い、自分たちのプレーを向上させよう、負けてなお学ぶものがあるはずだという「勇気」を持つことのできなかった弱虫たちの“共同不法行為”そのものだったといえるだろう。
 |
少年スポーツ ダメな指導者 バカな親 永井 洋一 合同出版 このアイテムの詳細を見る |
 |
スポーツは「良い子」を育てるか (生活人新書) 永井 洋一 NHK出版 このアイテムの詳細を見る |
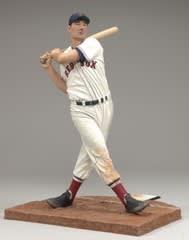 |
大打者の栄光と生活―テッド・ウィリアムズ自伝 (SUPER STAR STORY) テッド・ウィリアムズ ベースボール・マガジン社 このアイテムの詳細を見る |



















