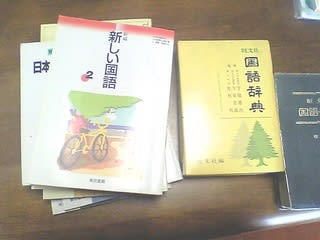
誰でも不得意科目というのがあったと思う。小学校の時は、体育と図工、音楽以外は不得意科目。中学校になってからは、国語が不得意科目であった。
幼かったころ、内弁慶で感情は激しく、しかしそれをうまく言葉で表現できない子供であった。本を読んだりするのは好きであったが、小中と国語の成績は芳しくなかった。特に書道は嫌いで、その時の国語の成績は最悪であった。
国語の試験問題を見ると、話の筋の面白さに気をとられ、時間配分まで頭が回らなかった。また、4択問題などでは、いろいろ考えて決断できなかったりした。幸か不幸か、中学校3年の時に公立高校の入試選抜の方法が大幅に変わった。9科目が3科目になった。そして国語の比重は俄然高まった。
夏休みに、1冊の国語の問題集を解き、秋以降成績は上昇した。真の国語の能力は高まったかよく判らないが、問題の解き方が上手になったのだと思う。そして、何とか入試を克服していった。
受験はともかく、不得意科目は自分の盲点を成育史の中から炙り出すのに重要だなと思う。抑圧された、根の深い劣等感や両親の影響が垣間見えてくる。
愛すべき幼少のころの、微かな記憶は幸福の鍵かもしれない!
 人気blogランキングへ <--(1クリック応援お願いしますね!)
人気blogランキングへ <--(1クリック応援お願いしますね!)











でもいま振り返ると、それには理由があったように思います。
ぼくの父は女性問題で母をずっと裏切ってきました。小さな頃から悲しむ母を見てきたので、以来、ぼくは父を憎みました。父は英語がよくでき、当時、東京オリンピックの公式通訳にもなった人ですが、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」で、英語にはコンプレックスを持ち続けました。
ぼくの父嫌いは、ぼく自身が子供を持ち、育てるようになるまで続きました。そして父を、人生の重荷を負った一人の人間として見れるようになったとき、ぼくは父を許すことが来ました。
でも、未だに英語は嫌いです。
不得意科目は、その人の素質というより、いろいろな体験の要素が強いのでしょうか。不思議です。
尚、私は今でも国語は自信がありません。